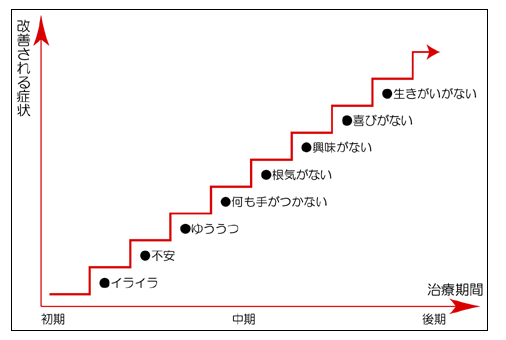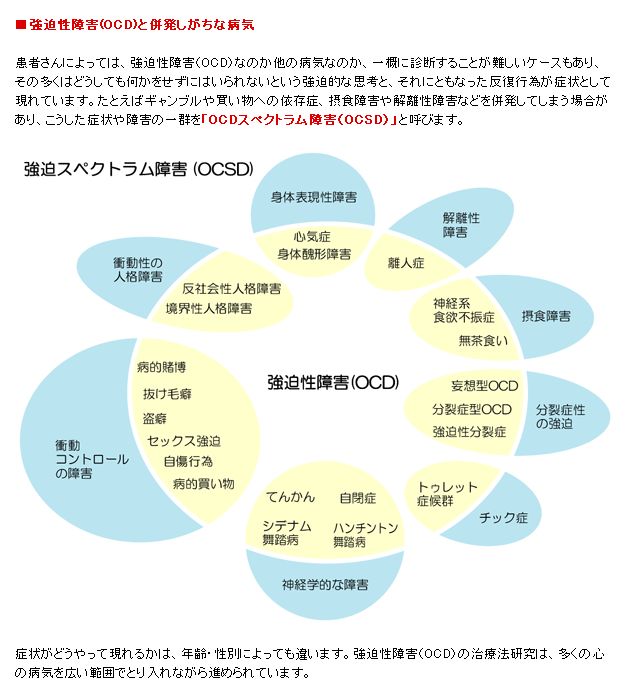managed care formularies
A study of product and policy data reveals a lack of standardization
among managed care formularies.
という副題の付いた文章。
http://www.amcp.org/data/jmcp/feature_v4_289-295.pdf
Table.1にはSSRI、2はStatin、3はAntihistamineが並んでいて、
1999年のものだが、現在日本で使われている薬の名前が多く見えている。
文章の内容としては、どの薬を選べばいいか、
その基準はどうするかといったような概論的な話で、
個別の薬剤についてではない。
例としてあげられているだけ。
それにしても、製薬会社としては気になる数字だろう。
本文でも述べられているが、
「選ぶ基準」として、「症状が消える」、「QOL」、「副作用が少ない」、「安い」など、
どのあたりで考えるかということが問題のひとつ。
このところ日本でも、個別の症状ばかりではなく、
QOLを大切に考えようじゃないかとの話題は聞く。
SSRIについていえば、
症状改善を数字で表すとして、
その症状の内容はどういうものなのか、
実は問題がある。
QOLに至っては、なおさら難しい。
そもそも、「major depression にはSSRI」という公式の、
major depression という判別がどうかという問題がまずある。
非定型うつ病の症例研究
こうした論文を読むと、comobidityの問題はやはり大きいと思う。
くっきりとしたclinical entityを立てきれない現状では、記載を精密にしていくしかないのだろう。
*****
非定型うつ病の症例研究
多田幸司,山吉佳代子,松崎大和,小島卓也
Koji Tada,Kayoko Yamayoshi,Yamato Matsuzaki,Takuya Kojima:
Atypical Depression in Japan-39 case series-
目的と方法: Columbia大学の研究グループによれば,非定型うつ病とは気分の反応性のある抑うつ気分に加えて,過眠,過食,鉛様の麻痺,拒絶に対する過敏性の4項目のうち2項目を満たすものである.本邦における非定型うつ病の臨床特徴を捉える目的で非定型うつ病の診断基準を満たす外来患者39名(男性10,女性29)について発症年齢,合併精神障害について調べ,各々の非定型症状について症例ごとに検討した.さらに,対人過敏性と非定型症状の関連,うつ病発症前のライフイペント,心理的ストレスの有無についても調べた.
*
結果:平均発症年齢は22±6歳と比較的若く,合併精神障害では社会恐怖が20例と最も多かった.過食症状は30例に認めそのうち25例が女性と性差が際立っていた.過眠症状は29例に認めたが眠気を訴えるものは7例と少なく,多くは気力がなくて起きていられないと訴えた.鉛様の麻痺を認めたものは19例と比較的少なかった.拒絶に対する過敏性を認めたものは32例であり,この症状はFNE,LSASおよびBSPSのスコアと相関していた.過眠は対人過敏と関連した症状であるとのParkerらの研究をふまえて対人過敏と過眠,過食との関連を調べたが有意な相関は得られなかった.うつ病発症の誘因としては異性との別れが7例と目立ち,社会恐怖を合併しているものでは,恐怖症状のため社会生活で自信をなくし絶望することが心理的ストレスとして重要であった.双極性障害を合併しているものは7例であり,そのうち6例が全般型の社会恐怖を合併していた.
*
考察:これまで海外で報告されていた非定型うつ病の特徴が今回の研究でも一部確認された.また,非定型症状の特徴についても明らかになった.合併精神障害ではとりわけ社会恐怖の意義が大きく,拒絶に対する過敏性は,合併する社会恐怖と関係があることが明らかになった.また,社会恐怖全般型では非定型うつ病の経過中に双極性障害へ発展する可能性があること,恐怖症状により自信をなくし絶望することがうつ病の背景にあるストレスとして重要であることなどが明らかになった.予後については合併精神障害のないものや非全般性社会恐怖を合併しているものでは比較的良いが,全般性社会恐怖や人格障害,双極性障害を合併しているものでは不良であった.<索引用語:非定型うつ病,社会恐怖,過眠,過食,拒絶に対する過敏性>
*
はじめに
1950年代に,英国の医師WestとDallyはモノアミン酸化酵素阻害薬(MAOI)に反応するうつ病の特徴について報告し,非定型うつ病という名称を初めて用いた.MAOI反応群は非反応群に比較して自責の念,早朝覚醒,午前中の抑うつ気分の悪化を訴えることが少なく,電気治療に対する反応性が悪かった.また,MAOI反応群では極度の疲労感,恐怖症や転換ヒステリーの既往,周囲の出来事に対する過剰な反応などの特徴が観察された.その後,Sargant,HordernもMAOIに反応するうつ病の患者群についてほぼ同様の臨床特徴を認め報告した.KleinとDevis,LiebowitzとKleinは自己顕示性人格,非抑うつ時の活動とエネルギー水準の亢進,拒絶時の抑うつ状態へのなり易さ,過食,過眠,極端な疲労感,抑うつ時の気分の反応性で特徴付けられるうつ病の亜型についてhysteroid dysphoricsと命名しMAOIに特異的に反応すると報告した.その後,Columbia大学の研究グループによって非定型うつ病の操作的診断基準が提案された.彼らは診断基準に沿って診断された非定型うつ病の患者群について,MAOI(phenelzine),imipramine,プラセポの3群間の治療反応性を比較した.その結果,非定型うつ病の患者ではimipramineに比較してphenelzineによる治療を受けた方が有意に改善することがわかった.
*
本邦ではMAOIがうつ病の治療薬として用いられてこなかったためか,MAOIに特異的に反応するうつ病群に関する研究に注意が向けられることはほとんどなかった.わずかに過眠をきたすうつ病に関する報告があり,記載された症例には過食など非定型うつ病の他の特徴が見出せる.DSM-IVではColumbia大学グループの診断基準が取り入れられているが,本邦では非定型うつ病は十分に認知されているとは言いがたい.今回の研究では,非定型うつ病の臨床特徴を捉える目的で非定型うつ病の診断基準を満たす外来患者について発症年齢,合併精神障害について調べ,各々の非定型症状について症例ごとに検討した.さらに,対人過敏性と非定型症状の関連,うつ病発症前のライフイペント,背景にある心理的ストレスの有無についても調べた.
*
対象と方法
対象は1994年から2003年の間に日大板橋病院ないし駿河台日大病院精神科外来において筆者が担当した初診患者(約2700名)の中で非定型うつ病と診断した39名である.診断はColumbia大学の研究グループによって作成された非定型うつ病評価スケール(atypical depressive disorder scale(ADDS))を用いた.1996年以降は初診時に非定型うつ病が疑われる症例ないし,社会恐怖や強迫性障害の診断で経過中に非定型うつ病の症状が出現した症例についてADDSを施行した.それ以外の症例(症例18,35)についてはADDSを用いてあらためて評価した.表1にADDSの邦訳を示した.なお,邦訳にあたっては横山らの文献を参考にした.合併精神障害はDSM-III-RまたはDSM-IVを用いて診断した.
*
過眠症状は鎮静作用のある薬物を投与されている場合は評価できないため,睡眠薬や他の鎮静作用のある薬物による治療を受けているものは除外した.また,過剰診断を避けるためここでは非定型うつ病発症以前に大食症の既往が認められる場合には鉛様の麻痺あるいは過眠が認められるものについてのみ非定型うつ病と診断した.また,拒絶に対する過敏性が非定型うつ病の中心的な症状であるとのParkerらの指摘を参考にして,拒絶に対する過敏性と関連が深い批判的評価に対する恐れの尺度(fears of negative evaluation(FNE)),社会状況からの回避と苦悩の尺度(social avoidance and distress(SAD))を用いて患者を評価し,得られた得点と非定型症状の関係について回帰分析を用いて調べた.また,非定型うつ病は社会恐怖との合併が多いことが知られているためLSAS(Liebowitz social anxiety scale)およびBSPS(Brief social phobia scale)を試行し得点を求め,非定型症状との関係を求めた.LSASとBSPSは社会恐怖の診断スケールではないが,重症度や治療効果を反映する尺度であり今回は社会恐怖の診断がつかない症例に対してもLSASとBSPSを施行した.個々のLSAS得点の評価を行う時は朝倉らの論文を参考にし,44点以上を高値とした.BSPSはLSASが利用出来る以前は社会恐怖の尺度として用いていたため引き続き利用した.しかし,LSASは北大グループによりカットオフ値など詳細な研究がなされているが,BSPSは本邦ではほとんど検討されていない.そこで,個々の症例のBSPS得点の評価は行わなかった.統計解析は,SPSS12.0Jを用いた.
*
表1
非定型うつ病評価スケール(atypical depressive disorder scale(ADDS))
Ⅰ 気分の反応性
何かよい出来事がまわりにあった時気分が持ち上がるかどうか,その程度について質問する.
質問例;この3ヵ月間に,もし誰かがあなたに親切にしてくれたり,なにか素敵なことが起こったり,誰かがあなたを励まそうとしてくれた時,あなたは一時的にでも元気になりますか?100は全く落ち込みのない気分,0はこの3ヵ月間の全体的気分として,上記のことがあった時あなたがどの程度反応するか教えてください.誰かが,あなたやあなたの子供を誉めたらどうなりますか?誰かが,あなたが本当に行きたいと思っていた場所に招待してくれたらどうなりますか?金銭的に成功したり,経済上の業績が上がった時,あるいはその他の好ましい事柄が起こった時,仲の良い友人や,子供があなたをに励まそうとした時はどうですか?
あなたは少なくとも一時的にせよこれらのことに反応することが出来ますか?
特別なテレビ番組,音楽,好きな本によってはどうですか?
あなたの通常の,あるいは最も典型的な反応はどうですか,最大の反応はどうですか?
(通常の反応a.__%,最大の反応b.__%とし
bが50%以上の時反応ありとする)
Ⅱ 関連症状(陽性と判定するにはA-Dのうち2つを必要とする)
A 睡眠
過剰に睡眠をとるか質問する.
質問例;この3ヵ月間の睡眠はいかがでしたか?1日に何時間睡眠をとりましたか?
(1日に10時間以上眠る日が週に3日以上あれば陽性とする)
B 鉛様の麻痺
重い,鉛のような,重りをつけられたような身体の感覚について質問する.
質問例;この3ヵ月間における,興味や意欲といった精神エネルギーではなく身体のエネルギーについての質問です.どれだけエネルギーがないか教えてください?全くエネルギーがないのか?手足が鉛でできているように重く感じる時があるか?階段を登ったり,椅子から立ち上がるのに身体的な努力が必要だったことがあるか?あるとすればどれくらいの頻度であるか?どのくらい持続するか?1週間のうち少なくとも1時間以上,鉛のような感覚がする日は何日くらいあるかについて教えてください?
(明らかなエネルギーの低下があり,1週間のうち少なくとも1時間以上,抑うつ状態に伴って鉛のような感覚がする日が週3日以上あれば陽性とする)
C 食欲/体重(下記の1),2),3))のどれかが陽性であればCは陽性と判定する.
1)食欲
食べたいという強い衝動について質問する.食べる量とは無関係である.
質問例:この3ヵ月間の食欲はいかがでしたか?実際に食べた量ではなく,食べ物に対する強い要求があったか教えてください?それが過剰かどうか,その頻度は?過食衝動があったか,1日のうちどのくらい考えていたか?
(週に3回以上過食したいと思う,あるいは週のうち5日以上食べたいという強い衝動があれば陽性とする)
2)食事量
食事の過剰摂取について質問する.
質問例:食欲とは無関係に,この3ヵ月間にどれだけ食べたか教えてください?
(落ち込んだ時,週に2回以上むちゃ食いする,ほとんど一日中なにか口にしている,1日に何回も軽食をとる日が週3日以上あれば陽性とする)
3)体重
質問例;この3ヵ月間の体重の変化について教えてください?体重は減りましたか?あるいは増えましたか?どのくらいの期間でそうなりました?
(10ポンド(3.73kg)以上の体重増加があれば陽性とする)
D 拒絶に対する過敏性
対人関係の過敏性によってどの程度,機能が障害されるか質問する.この場合,任意の2年間について問う.
1)対人関係の過敏さ(拒絶や批判に対する情緒的過剰反応)
質問例;あなたの人生をふりかえって,他人のあなたに対する接し方に対しどれほど敏感だったか教えてください?普通の人と比べて容易に拒絶された,あるいは馬鹿にされたと感じる人間だと思いますか?もしも,あなたが拒絶,批判あるいは馬鹿にされた時,落ち込むか,激怒するか,そしてそれはどの程度か教えてください?にこでは恋愛関係,友人関係,職場の人間関係,偶然の出会いなどについて尋ねる.明らかに過剰に落ち込む,怒る場合を陽性とする)
2)対人関係の質(拒絶や批判に対し過剰に反応することによって生じる激しく不安定な対人関係)
質問例;一般に他人とどう付き合っていますか?かなりうまく付き合っていますか?批判や拒絶に対して過敏なため,しばしば喧嘩,言い争い,誤解が生じますか?あなたにとって重要な人物に突然,ぷんと怒って仲たがいして,その後,元通りの間柄になったりする傾向はありますか?上司と頻繁に言い争うことはありますか?店員,管理人,あるいはあなたの手助けになるべき人と頻繁に言い争っている自分に気付くことはありませんか?(嫉妬や批判に対する過敏さのため対人関係は不安定となり,仕事や家事を続けることも困難となる,また,喧嘩,誤解,議論となる,あるいは過敏さのため,対人関係がほとんどもてないようであれば陽性とする)
3)機能の障害(批判や拒絶に対する過剰な反応によって生じる仕事,学校における障害)
質問例;仕事や学校を辞めたり,行かなかったりしましたか?約束をすっぽかしたり,重要な家事ができなくなったり,酒におぼれたり,薬に走ったりしたことがありますか?あったとすればこの2年間にどのくらいありましたか?(この2年間に4回以上批判や拒絶に反応してすぐに職を辞める,重要な家事ができなくなる,酒におぼれるようなことがあれば陽性とする)
4)関係の回避(拒絶を恐れて人間関係を作らない)
質問例;現在恋愛関係にありますか?2年間恋人がいませんか?それはどうしてですか?何が障害になっているのですか?人との関係を避けているのではありませんか?それはあなたがとても傷つきやすいからですか?どのくらい拒絶されることを避けようとするか教えてください?
(人との表面的関係は保っているが,拒絶を恐れて親しい関係を作らないようであれば陽性とする)
5)その他の拒絶の回避(拒絶を避けようとして,生活上の重要な課題を回避する)
質問例;拒絶されるかも知れないと心配しすぎてその他の活動が出来なくなることがありますか?例えば,面接で断られるのではと考えて就職の面接に行かない,契約が取れないと思って約束をすっぽかす,学校の先生に批判されるから授業に出席しない,配偶者に批判されると恐れて料理をしないなどです.これはなんらかの方法であなたの機能を障害しましたか?あるとすればどの程度ですか?そのため,2年間以上仕事を離れているということはありますか?そのため,結婚生活がかなり悪化していますか?2年間に何回か解雇されましたか?退学させられましたか?
(拒絶を回避するため重要な機能の障害があれば陽性とする)
III 判定
1 気分の反応性のないうつ病(lbが50%以下)
2 単なる気分反応性うつ病(lbが50%以上でIIのA-Dは陰性)
3 非定型うつ病の疑い(lbが50%以上でIIのA-Dのうち1つか陽性)
4 明らかな非定型うつ病(lbが50%以上でHのA-Dのうち2つ以上が陽性)
補足:通常4の「明らかな非定型うつ病」を非定型うつ病と診断する.
*
結果
症例呈示
合併精神障害のない男性症例(症例12)
初診時19歳の男性,大学1年生.家族歴,既往歴に特記すべきものはない.同胞はいない.母は知的で患者に対して理解がある.元来人と喋るのが苦手,対人場面で緊張し易い.小学生の頃から人前での発表や実技のテストなどとても嫌だった.批判されるといつまでも気にしてくよくよ考え込んでしまう性格だと言う.平成X年2月頃より夜十分に寝ているのに昼間も眠い,だるい,すぐに横になりたくなると感じるようになった.友人に誘われても億劫で断ってしまう.内科で血液検査等を施行したが異常はなかった.気力もなく,なんとなく物悲しいように感じる.クラブ活動で剣道をしている時は楽しめるが,以前ほどではない.生きていくのも辛いと考えることもあるが自殺したいとは思わない.こうなってから睡眠時間は12時間ほどに延びた.食欲はやや減ったように思うが体重は変わらない.だるくて辛いが手足が重い,体が重いとは思わない.ADDSでは,気分の反応性に加えて過眠,拒絶への過敏性があると思われた.食欲はやや低下しており体重増加はなく,鉛様の麻痺を示唆する所見は認められなかった.なお,社会恐怖に限りなく近い性格傾向を有しているが,程度は軽くかつそれによる機能障害を認めないことから合併精神障害はなしとした.治療経過;平成X年3月29日fluvoxamine50mgより開始,4月12日より100mgに増量した.5月頃より元気になった.クラブ活動中は眠くなることもなく,睡眠時間も8時間ほどに戻った.洋服を買いに出かけたり,友人と外出するようにもなった.6月頃よりほぽ以前の自分に戻った感じがすると言うようになった.
*
合併精神障害のない女性症例(症例8)
初診時22歳の女性,大学生.家族歴,既往歴に特記すべきものはない.両親は地方で生活し本人は東京で独り暮らしをしている.同胞はいない.性格は本人や母親からの陳述ではまじめ,几帳面,がんばり屋,親切,人前に出るのが好きとのことである.17歳,高校2年の頃から,朝起きても体が重く,再び寝てしまうようになった.神経科病院受診,服薬するが改善せず高校3年はほとんど登校できなかった.高卒後2年間浪人したが19歳時,抑うつ気分が悪化し6ヵ月間神経科病院に入院した.20歳で大学に合格し登校するようになったが,1年に数回2週間から1ヵ月ほど気分が落ち込み登校できなくなった.気分が落ち込むと食欲が出て体重が増え,睡眠時間が14時間ほどになるというパターンを繰り返していた.気分の日内変動はなく落ち込んでいる時でも友人と会うと気分が軽くなる,しかし自宅に戻るとどっと疲れが出るとのことであった.両親ともに保護的であるが,本人の意思を尊重し自由に行動させたいと考えている.母はうつ病の既往があるが現在は寛解している.ADDSでは気分の反応性に加えて過眠,鉛様の麻痺,食欲の増加が認められたが拒絶への過敏性は見られなかった.治療経過;平成X年10月22日nuvoxamine50mgより開始,11月13日より100mgに増量,11月20日頃から気分も良くなり,だるさもとれてきた.友人と映画や遊園地に行くなど活動的になった.しかし,増加した体重に変化はなく,睡眠時間も平均14時間と過眠状態は続いていた.12月からnuvoxamine150mgに増加したがやはり過眠状態は変わらず,元気にアルバイトをして,友人と楽しく遊んだかと思うと些細なことで落ち込んで登校できなくなるという状態が続いた.治療開始後2年6ヵ月経過,治療薬はparoxetine,milnacipran,amoxapineなどに変更したが症状は変動し安定しない.うつ状態になるため生活が制限されることが一番のストレスと言う.
*
社会恐怖と非定型うつ病の合併例(症例16)
初診時20歳の女性,看護学生.家族歴,既往歴に特記すべきものはない.両親と妹との4人暮らし,父は厳格で批判的,あまり誉められた記憶はないという.母と妹とは仲がよい.性格は本人によると心配性,他人に言われたことをくよくよ考える,新しい場面では緊張し易いという.高校生の頃から人前で喋ると緊張し動悸がした.しかし,そういった状況を避けるようなことはなく,我慢していたという.学校での実習が始まる1週間ほど前から不安感が強くなった,実習で患者さんに嫌な思いをさせたらどうしよう,指導教官に怒られたらどうしようと考え不安になっていた.実習が始まり教官に質問されたが緊張してしまい声が出なくなったり,どもったりした.緊張しているところを見られると思うとますます声が出なくなるという.
*
治療経過;社会恐怖(非全般性)と診断し,平成X年2月14日よりethyl lonazepate 1mgを投与した.抗不安薬投与後不安は和らぎ実習も比較的緊張せず終えることが出来た.しかし,初診から1ヵ月たって留年が決まったことから抑うつ的となり,気力もなくなった.集中力もなく勉強も手につかない.自殺する人の気持ちがよくわかるようになった.テレビを見ても楽しめないが,友人に誘われてスポーツをすると気分がよくなると言う.身体もだるく手足がとても重い.こうなってから甘いものが好きになり1週間で3kg以上太ってしまった.不眠はなく休日には10時間以上眠るが平均睡眠時間は8-9時間であるという.この時点で診断を社会恐怖と非定型うつ病(ADDSでは気分の反応性に加えて鉛様の麻痺,食欲の増加,拒絶への過敏性があるが過眠症状はなし)の合併と考えた.3月7日よりnuvoxamine50mgを投与したところ2週間ほどで気分の暗さがとれ,だるさや手足の重い感じもなくなり,甘いものも我慢できるようになった.4月には,学校に行っても以前よりリラックスして教師と話ができるようになったと言う.
*
社会恐怖と双極性II型障害の合併例,大うつ病エピソードは非定型の特徴を伴う女性例(症例13)
初診時19歳の女性,大学2年生.家族歴,既往歴に特記すべきものはない.両親は患者が3歳のとき別居,その後母と姉との3人で暮らした.小学校6年の頃から人前で話をすると緊張してしまい,顔が赤くなるようになった.中学時代は部活の友人と気まずくなり登校出来なくなった.高校時代は勉強が嫌になり机に座っているのもつらくなり2ヵ月ほど不登校になった.平成X年4月大学に入り東京で一人暮らしするようになったが10月頃から学校や駅で他人から見られているように感じ怖いと思うようになった.他人と一緒だと緊張するが自宅ではリラックス出来た.12月頃より気分か落ち込み,体が重く,動くのもやっとで睡眠時間も10-12時間に延びた.大学には行けず,自宅で菓子類を過食するようになり体重も2-3kg増えた.しかし,友人に誘われて外出すると楽しむことが出来た.平成X+1年5月抑うつ気分悪化し,自宅で泣いてばかりいるため当院受診した.ADDSでは気分の反応性に加えて過眠,過食,拒絶に対する過敏性が認められた.この時点では社会恐怖(全般性)と非定型うつ病の合併と診断した.
*
治療経過:fluvoxamine50mgより開始,6月24日には200mgまで増量した.症状が改善しないため7月8日よりnuvoxamine100mg,paroxetine20mgに処方を変更した.7月10日頃から気分が良くなり,今すぐ必要ではない衣類,ハンドバッグ,小物などを店員に勧められるままに一度に買ってしまった.店員とも仲良くなれてすごく嬉しくなった.食欲は低下し,睡眠も短くなり朝早く目覚めて朝市に行き野菜をたくさん買った.しかし,自宅に帰ると急に悲しくなり包丁で手首を傷つけた.7月14日よりFluvoxamineとparoxetineは中止し,炭酸リチウム200mg,sodium valproate 200mg,trazodone 25mg,nitrazepam 5mgを投与した.爽快気分はなくなり,買い物もしなくなった.過去に友人に意地悪されたことを思い出し泣いたり,腹を立て訴えると言い出した.8月5日より炭酸リチウム600mg,nitrazepam5mgとしたところ8月中旬より落ち着きを取り戻した.しかし,再び抑うつ気分,無気力,過食,過眠が出現した.その後,nuvoxamine, paroxetine, milnacipran などの抗うつ薬を用いたが平成X+1年6月の時点で抑うつ症状は改善せず,時に軽躁状態となるエピソードを繰り返している.この時点では双極Ⅱ型障害と考えた.
*
強迫I生障害,境界性人格障害と非定型うつ病の合併例(症例9)
初診時23歳の女性,大学生.家族歴,既往歴に特記すべきものはない.両親と弟の4人暮らし.両親ともに過保護,過干渉である.小学生の頃から汚いものが苦手で雑巾をバケツで洗うことが出来なかった.自宅でも何か触ると手洗いを繰り返し,入浴も一番でなければ気がすまなかった.高校2年生(17歳)の頃から特に理由なくイライラするようになった.自分ばかり教師に叱られるように思い登校できなくなり高校は中退した.その後浪人して大学に入学したが志望校ではなくそれがコンプレックスになっていたと言う.19歳頃から心療内科外来に不規則に通院するようになったが詳細は不明である.この頃から手を消毒するため外出時アルコールスプレーを持ち歩くようになった.23歳時当院初診,その2-3ヵ月前から抑うつ気分,希死念慮,イライラ,過食嘔吐(一日中何か食べている)が目立つようになり,無気力になり自宅で一日中寝ているようになった(睡眠時間はおよそ14-15時間,本人は寝逃げしていると言う).体もだるく指一本動かすのも大変だと感じるようになった.気の合う友人に誘われてカラオケに行くとその時は元気になった.ADDSでは気分の反応性に加えて過眠,過食,拒絶に対する過敏性が認められた.この時点では強迫性障害と非定型うつ病の合併と診断した.
*
治療経過;平成X年6月7日nuvoxamine50nlgより開始,6月17日には100mgまで増量した.過食はなくなり,睡眠時間も8-9時間に減少し,だるさも多少改善した.この頃から多弁になり,踊りに行きたい,買い物をしたいと母親にせがむようになった.しかし,思うようにならないとまた寝込み,死にたいと訴えた.はっきりした躁病エピソードは認めなかったが気分の安定化をはかる目的でsodium valproateを600mg投与した.その後も抑うつ気分,希死念慮強くイライラすると床に水をまく,壁を蹴るなどの行動が続いた.何が一番辛いのかと聞くと「卒業後の就職が決まっていないこと」と答えた.どうなればいいのかと尋ねると「学者か,一流テレピ局のアナウンサー,歌手」と答え,納得できない就職は考えられないと自己愛的な側面も窺えた.11月中旬よりcarbamazepine 400mg を追加投与したところイライラは多少改善し,抑うつ気分も和らいできた.しかし,将来に対する不安は強く,些細なことで落ち込み寝てしまう状況は続いている.
*
強迫性障害と双極I型障害の合併例,大うつ病エピソードは非定型の特徴を伴う女性例(症例37)
初診時30歳の女性,両親と弟の4人暮らし,家族に精神科治療歴はないが,母は患者が仕事をやめて自宅にいるようになってから夫と患者間に男女関係があると疑うようになった.既往歴として甲状腺機能亢進症を認める.性格は極端な恥ずかしがり,人前に出ると何も話すことが出来ず,まっ赤になったと言う.5歳頃から忘れ物がないか何回も確認する,水道の蛇口を力いっぱい閉めるなどの強迫的傾向があった.22歳頃より,自分の大切なものを落としてしまうのではと考え不安になり,外出する際には衣類に大切なものがついてないかどうか確認するようになった.事務職をしていたが書類を捨てる際,確認に時間がかかり仕事が続けられなくなり24歳で会社を辞めた.なお,23歳時会社の診療所で強迫神経症と診断されている.27歳頃より動悸,労作時呼吸困難,発汗,頚部腫脹などの症状が出現するようになったが外出時の確認に時間がかかるため放置していた.30歳時,呼吸困難が強くなり甲状腺機能亢進症及び心不全の診断で著者らの勤務する病院に緊急入院した.入院後確認がひどく内科病棟での治療が困難となったため精神科病棟に転棟した.入院後.甲状腺機能,心機能は正常化したが確認行為は改善せず1年10ヵ月に及ぶ入院後,強迫症状不変のまま退院した.退院後,不規則に外来通院していたが,32歳頃より抑うつ気分,過眠,過食などの症状が出現するようになった.35歳よりは一過性の軽躁状態がときに出現(高価な買い物,気分の高揚,不眠)するようになった.しかし,すぐにうつ状態となり,外来通院も出来なくなり,自宅で寝てばかりいて入浴もしなくなった.確認もひどく自宅はゴミだらけになっているとのことであった.38歳時急に多弁になり「この病院の総長になる,私がほしいのは世界jなど誇大的言動がみられるようになった.「楽しくて仕方ない,確認も楽になった.今まで出来なかった入浴もできる」と爽快気分とともに強迫行為が軽減していることも明らかになった.なお,この時点で双極I型障害と診断した.薬物療法としてはclomipramine150mg,trazodone150mg,tandospirone60mg,炭酸lithium600mg,alprazolam2.4mg,thiamazole10mgを服用していたが,躁状態になる2日前から服薬を中止していたとのことであった.無銭飲食をするなど逸脱行為も激しくA県の精神科病院に紹介入院となった.6ヵ月後に退院し著者の勤務する病院の外来に再び通院を開始したが,強迫行為は以前と同様であり,時に抑うつ的,過眠,過食となり自宅にこもり何週間も通院出来なくなるというエピソードを繰り返している.なお,甲状腺機能異常を示唆する症状や内分泌機能障害は観察されなかった.
*
神経性大食症と非定型うつ病の合併例(症例22)
初診時22歳の女性,両親と妹との4人暮らし.母は過保護で帰宅時間にきびしい.父は物静かで子供のことに口を出さない.性格は明るく,生真面目,友人は多いが他人に気を使い疲れてしまうこともあるという.20歳時,宴会が続いて体重が増えたため自分で嘔吐するようになった.21歳時,彼氏から別に好きな女性がいると告白された.その人はやせている人だと言われショックを受けた.この頃から食後に菓子パンを5-6個,おにぎり2個,1リットルほ330どの飲料を30分ほどで食べ,その後自分で嘔吐するようになった.また,一時期自分でも知らない間に彼氏との写真を破る,石を叩いて手から血が出ていたというエピソードもある.某大学病院で神経性大食症と診断され45日ほど入院したが改善しないため治療は中断した.その後も過食,自己誘発性嘔吐は続き,22歳時,抑うつ気分,意欲の低下(何もやる気がおこらず一日中横になっている),希死念慮,過眠(1日13時間以上眠った),倦怠感,手足のだるさを訴え当院初診した.抑うつ気分は過食の後強くなり,友人と外出する時はほぼ消失し楽しむことができた.初診時診断は神経性大食症,非定型うつ病(ADDSでは気分の反応性に加えて過眠,過食,鉛様麻痺が認められた)とし解離性障害の既往があると考えた.
*
治療経過;nuvoxamine(50-150mg),domperidone投与3週間後からは驚くほどだるさがとれた,過食も若干減った(朝からしていた過食が昼と夜のみになった),気分も楽になり,テレビを見ても楽しめる,気力はないが編物をするようになった.睡眠時間は6時間になり昼間は横にならないですむようになったという.その後,過食は週に3回ほどになり,意欲もでて初診から6ヵ月後には仕事も始めた.気分もよく友人と旅行をするがやはり遊んだ後はかなり疲れると訴える.事務員として働いているが過食,嘔吐はほぼ毎日続いている.
*
症例のまとめ;症例のまとめを表2に示した.非定型うつ病初発エピソードの平均年齢は22±6歳であった.また,合併精神障害の初発年齢は17±4歳であった.男女比はほぽ1対3と女性が男性のおよそ3倍であった.
*
合併精神障害;合併障害で最も多いのは社会恐怖であり39名中20例(51%)に合併していた.また,そのうちの10名は全般性の社会恐怖,10名が非全般性の社会恐怖であった.また,社会恐怖症状は自発的に語られることはなく,症例16を除き,ほとんどがうつ病エピソード発症前に社会恐怖症状による精神科受診歴はなかった.また,社会恐怖と診断できない症例の中にも社会恐怖心性(対人恐怖心性)が観察されるものやLSASの得点が高いものが5例認められた(症例39;人前にでるのはどちらかというと苦手.LSAS48.症例7;自発的に語られる社会恐怖症状は認めず,問診では社会恐怖と診断できなかったが,LSASは70と高得点であった.症例23;問診では社会恐怖と診断できないが,LSAS54と高値.症例21;同様にLSAS45.症例37;18歳までは極端な恥ずかしがり屋,人前に出ると真っ赤になった.その後強迫症状出現し,社会恐怖症状は目立たなくなった.LSAS未施行).強迫性障害は4例(症例1,9,17,37)でこのうち2例(症例1,37)は双極性障害の診断であった.このうち1例(症例1)は全般性の社会恐怖を合併しており,もう1例(症例37)は「強迫症状出現以前は人前にでると真っ赤になる,人前では何も話すことができなかった」と社会恐怖症状の既往があると思われた.残る2例(症例9,17)は思春期から強迫症状と過食症状を認め性格傾向としての強迫性と自己愛的傾向を認めた.図1に合併精神障害とその数を示した.
*
過食症状;過食または体重の増加を示したものは30例(男性5例,女性25例)であり,そのうち18例(男性1例,女性17例;症例3,4,5,9,10,13,14,17,18,19,21,22,23,27,29,30,37,38)がむちゃ食いエピソードを経験し,そのうち4例(症例4,17,21,22すべて女性)に過食の後,自己誘発性嘔吐を認めた.過食後に嘔吐するものを除いて多くは過食のため体重が増加した.むちゃ食いエピソードがみられる症例の多くは憂うつ感を紛らわすために過食すると訴えていた.また,神経性無食欲症の診断基準を満たすものはいなかった.
*
過眠症状;過眠症状は29例に認めた.過眠症状が認められないものでも不眠を訴えるものはほとんどいなかった(症例39に軽い不眠を認め,一時的に睡眠薬が使用された).眠気を訴えたものは7例(症例2,10,12,17,26,32,37)と比較的少なかった.多くはだるくて,気力がなくて,疲れて起きていられないと訴えた.眠って逃げていると説明したものも3例(症例7,9,26)いた,昼夜逆転したものは2例(症例2,10)みられた.
*
鉛様の麻痺;「体が重く,まるで鉛のようですか?」と尋ねると,「鉛?そういうことはないですね」と答えるものが多い.ADDSの質問帳のように「手足が時に鉛のように感じますか?あるいは階段を上る時,または椅子から立ち上がるのに努力を要することはありましたか?」と尋ねると「体が重くて動くのも大変です」と答える場合が多い.鉛にこだわっているとこの項目は否定されてしまうように思えた.この症状があると判断されたものは19例いた.
*
対人関係における拒絶に対する過敏性;32例に対人過敏性が認められた.ADDSでは対人関係の過敏さに関する項目で「拒絶,批判あるいは馬鹿にされた時,落ち込むか?激怒するか?」と質問する.また,関係の質の項目では拒絶や批判に対する過敏性のために激しい,不安定な対人関係になるかどうか質問する.今回,我々が経験した症例は拒絶や批判された時に傷付き,落ち込むものがほとんどであり,激怒あるいは激しい不安定な対人関係となるものは稀であった.ただし2例は過剰な怒りの感情のため対人関係が損なわれていると考えられた.
*
発症の誘因;個々の症例をみるとうつ病発症前に特定の急性ないし慢性ストレスが見出せる症例が見受けられた.7名が異性との別れを契機に抑うつ状態が出現していた.
*
社会恐怖を合併している症例の中には,対人緊張が強いため,不登校,外出困難,仕事が長続きしないなど社会生活が著しく制限されてしまい,その結果自信をなくし絶望的になったと訴えるものが8名いた(症例1,10,11,13,15,16,20,38).また,この8名のうち6名は全般性社会恐怖であった.
*
FNE,SAD,LSAS,BSPSの得点と非定型の症状との関連を表3に示した.FNE,LSAS,BSPSの得点は拒絶に対する過敏性の項目との間でのみ関連が認められた.FNEは批判的評価に対する恐れの強さを表す尺度であり,ADDSで評価した拒絶に対する過敏性と相関するのは当然といえる.LSASおよびBSPSは社会恐怖の重症度や治療効果を反映する尺度であり,LSASおよびBSPSが共に拒絶に対する過敏性と相関することはADDSで拒絶に対する過敏性が陽性となる原因として,合併する社会恐怖症状が寄与していると考えることができる.
治療経過のまとめ;抗うつ薬としては主としてnuvoxamineを使用したが,その他三環系抗うつ薬も用いた.抗うつ薬に対する反応性は主に合併精神障害に左右されているように思われた.合併のない11例(症例7,8,12,19,23,30,31,32,33,34,39)では,そのうち8例がおよそ2ヵ月程度で軽快し,経過観察期間中に再発することはなかった.しかし,残りの3例(症例8,23,33)は治療に反応しないか,一時的に反応してもすぐに抑うつ状態となり,抗うつ薬の変更によっても抑うつ症状が改善しなかった.主として非全般性社会恐怖を合併している8例(症例14,15,16,24,25,26,28,36)では6例が治療により2ヵ月以内に軽快した.なお1例(症例26)は治療中断している.恐慌性障害も合併している例(症例14)はimipramineとalprazolamを用いたが,症状が一時的に軽快するもののすぐに抑うつ状態となった.また,発病以前には人格障害と診断することは出来ないが,自己愛傾向をもつ症例23はnuvoxamineにより一時的に抑うつ気分が軽快するも,就職の失敗や男友達との喧嘩で容易にうつ状態となり安定した状態が得られなかった.主として全般性社会恐怖を合併している例(症例2,3,10,11,38)では薬物療法に反応したのは2例(症例11,38)で,服薬を拒否するものが1例(症例3;6ヵ月ほどで自然に軽快),一時的に改善しても些細なストレスで抑うつ的となり1年以上の長期にわたり自宅に引きこもるものが2例(症例2,10)であった.全般性社会恐怖を合併している症例では対人緊張が強いため,生活上のストレスが多く一時的に軽快しても容易にうつ状態へ逆戻りするように思われた.
*
うつ病エピソード発症以前から主として大食症を合併している例(症例4,17,21,22)では薬物治療により2ヵ月以内に抑うつ症状が消失し,過食症状も消失したものが1例(症例4),治療により症状は経過するが些細なストレスで抑うつ的となり,軽快と抑うつ状態を繰り返すものが3例(症例17,21,22)であった.境界性人格障害を合併している2例(症例9,27)はいずれも抗うつ薬の効果が乏しく,精神症状は不安定であった.躁病および軽躁病エピソードを伴うものは7例(症例1,5,6,13,18,20,37)であった.このうち1名は精神病性の特徴を伴い(症例1),もう1名は重症で,精神病性の特徴を伴わないものと診断された(症例37).どちらも重症の強迫性障害を伴い,抗うつ薬投与中に躁病エピソードが発症したため入院が必要となった.7名中5名が全般性社会恐怖を合併し,1名が非全般性社会恐怖を合併していた.軽躁病エピソードを伴う5名は抗うつ薬の減量ないし炭酸リチウムの併用により躁状態が軽快した.躁病および軽躁病エピソードを伴う7名は1年以上観察している症例がほとんどであるが,薬物により軽躁状態を呈した症例6を除き,抑うつ状態のため自宅に引きこもり睡眠時間が長くなるというエピソードを繰り返すため安定した精神状態を保てず,予後は不良であった.
*
考察
今回の研究で欧米の研究と同様本邦でも非定型うつ病と診断される症例は,発症年齢が若いこと,女性に多いこと,社会恐怖や強迫性障害の合併が多いことが確認できた.非定型うつ病の診断妥当性を検討したこれまでの研究では,主としてメランコリー型のうつ病と比較されることが多かった.しかし,非定型うつ病の診断にはメランコリー型の特徴を有するものは除くという除外基準があるため,得られた結果は非定型うつ病の特徴なのか,メランコリー型以外のうづ病の特徴なのか不明であった.こうした点を考慮してParkerらは270名の大うつ病の患者から精神病像を伴う群とメランコリーの特徴を有する群110名を除いた160名について非定型の特徴の有無を調べ,そのおよそ16%を非定型うつ病と診断し,非定型の特徴間の関連性を調べた.その結果,拒絶に対する過敏性は過眠,過食,鉛様麻痺と弱く関連し,気分の反応性を認める群とそうでない群間で基準B(非定型症状)の特徴の出現率に差異はないことを見出した.この結果から彼らは精神病性ないしメランコリー型のうつ病を除いた場合には気分の反応性は非定型うつ病の診断基準として重要性がないと結論した.彼らは拒絶に対する過敏性の認められる83名と認められない77例について他の非定型症状の有無を比較した.その結果,過眠症状の頻度は拒絶に対する過敏性の認められる群で有意に高かった.また,過去にパニック障害を経験した群とそうでない群を比較すると体重増加はパニック障害経験群で有意に頻度が高かった.彼らはこれらの事実から非定型うつ病で最も重要なものは拒絶に対する過敏性であり,これに何らかのストレスが加わるとうつ状態を引き起こし,その結果,自己治癒的な過眠や過食が生じると考えた.しかし,今回の統計学的検討では拒絶に対する過敏性と過眠の関係は見出せず,過眠はうつ状態の自己治癒的現象であるというParkerらの説明は,我々の経験した症例には必ずしも当てはまらないように思えた.また,拒絶に対する過敏性が目立だない症例も7名(18%)と少なからず混じっており,非定型うつ病を対人過敏に伴う二次的うつ状態と考えることには限界があると思われた.今回の研究では,非定型症状のうち拒絶に対する過敏の説明として,合併する社会恐怖が重要であることが明らかになった.非定型うつ病は社会恐怖と合併することが多く,そのため社会恐怖者の性格特徴である批判に対する過敏性と重複するような形で拒絶に対する過敏性の項目が陽性となると思われた.
*
過眠と過食は非定型うつ病の特徴的な症状であるが,鑑別を要する疾患として季節性うつ病,反復性過眠症,摂食障害などがある.季節性うつ病ではうつ状態は比較的軽度で疲労感を強く訴え,過眠,過食,体重増加,炭水化物を食べたがる,三環系抗うつ薬は効果が乏しいなど非定型うつ病に近い特徴を有している.決定的な違いは季節性うつ病では大うつ病エピソードの発症時期と1年の特定の時期(秋か冬に多い)との間に時間的な関係があることである.また批判に対する過敏性といった性格特徴は季節性うつ病の診断に重要ではない.53名の季節性感情障害について調べた日本の研究では,非定型の植物性症状は季節性感情障害の20から30%と比較的低いことも明らかになっている.我々が経験した症例は季節性に乏しく,この疾患の診断基準を満たさなかった.
*
反復性過眠症は1週間前後持続する過眠状態を繰り返し,間歇期は全く異常を示さない稀な疾患である.男性に多く思春期に発症するが傾眠期に過食を示すものはKleine-Levin症候群と呼ばれている.傾眠期に意欲の低下,抑うつ気分を呈することもあるが,この場合非定型うつ病との鑑別が必要になる.鑑別点は非定型うつ病ではうつ病相の期間が明らかに反復性過眠症より長いこと,非定型うつ病は女性に多いが反復性過眠症は男子に多く,特にKleine-Levin症候群はほとんどが男性であることなども,鑑別点として重要である.我々が経験した症例はうつ病相が短いものは含まれておらず,さらに眠気を訴えるものも7例と比較的少なく,過眠は眠気というよりは疲労感や気力のなさと関連しているようであった.逃避型抑うつは抑制が主体の逃避的色彩の濃い抑うつ状態を呈するが,うつ病エピソードの時期に睡眠時間が長くなる症例が含まれている点で,非定型うつ病と似通っている.しかし,女性に多い非定型うつ病と比べ,逃避型抑うつはこれまで挫折を知らないエリート男性であることなど相違点も認められる.また,我々が経験した症例にエリートといえる男性はいなかった.本邦で報告された過眠を伴ううつ病の症例検討においても,過食や体重増加を呈する症例が含まれるなど,非定型うつ病と共通する特徴がみうけられる.しかし,温和で社交的な性格が病前性格として特徴的であると報告されており,拒絶に対する過敏さや社会恐怖との合併が多い非定型うつ病とは若干異なっている.しかし,我々が経験した症例の中にも温和で社交的な症例も少数ながら混じっており,臼井ら,笠原らの報告例は非定型うつ病には含まれるが,どちらかといえばその中では例外的な症例といえるのかも知れない.
*
神経性大食症では過食の後にしばしば抑うつ的となる.また体重が増加するとやはりうつ状態となる.また摂食障害患者全般に対人関係の過敏さが稀ならず認められる.こうなると神経性大食症患者は非定型うつ病の罹患率が著しく高くなってしまう.ADDSは大食症の既往は除外診断としていないため,過剰診断してしまう可能性は否定できない.今回,我々が経験した症例のうち5例に神経性大食症がうつ病相発症以前から認められたがそのうちの3例はうつ病相が軽減すると過食エピソードもほとんど目立たなくなった.非定型うつ病は元来薬物療法に対する反応性の違いから提唱された概念であり,神経性大食症に伴ううつ病が三環系に比較しMAOIによく反応するという報告もある。今回経験した神経性大食症と非定型うつ病の合併例5例のうち3例はうつ病相に一致して過眠症状がみられたこと,1例は躁病エピソードを過去に経験していたことなどを考慮すると,我々が経験した症例は,大食症の二次的抑うつだけでは説明できないと思われた.
*
我々が経験した非定型うつ病発症前の発症状況をみると,異性との別れによる急性ストレスを認めたものが7名いた.Kleinらは恋愛関係で拒絶された際,無気力,過眠,過食で特徴づけられるうつ病エピソードに発展する女性患者について言及し,これら一群の患者をhysteroid dysphoric patientと名づけた.これらの患者は三環系抗うつ薬に比べMAOIに比較的良く反応することから,その後の研究で非定型うつ病に組み入れられた.我々が経験した恋愛破綻を契機に発症した7名のうち6名は女性であり,これらの患者はKleinらが述べたhysteroid dysphoric patientに当てはまるものと考えられた.社会恐怖を合併している患者では恐怖症状のため社会生活が著しく制限され,絶望的になり抑うつ状態になったと考えられる症例も少なからず混じっていた.Van Ameringenらは不安性障害専門の診療所を受診した社会恐怖患者について,社会恐怖の罹病期間とうつ病の関連を調べた.その結果,社会恐怖の罹病期間が短いものほどうつ病の罹患率が低いことから,うつ病は慢性の不安や恐怖症状による機能低下の結果引き起こされたと推測した.Steinらは社会恐怖群と恐慌性障害群の後ろ向き研究において,社会恐怖群ではその35%に,恐慌性障害群では63%に大うつ病の既往があったと報告した.彼らは不安性障害患者では慢性の不安と恐怖症による生活上の制限により意気消沈した結果うつ病になるとの説を紹介し,不安のコントロールが出来ないと抑うつ状態へ発展すると考えた.非定型うつ病では社会恐怖の合併が多いため,うつ病発症前に先立って存在する不安症状の結果としての挫折感や絶望感に注目する必要がある.また,こうした非定型うつ病の発症状況は,職場で過剰適応していた人が少なからず含まれている内因性うつ病とは対照的であるといえる.
*
これまでの研究と同様に合併精神障害としてはやはり社会恐怖の頻度が高いことが際立っていた.したがって,非定型うつ病を疑った場合には社会恐怖症状に注意して問診していく必要があるといえる.社会恐怖に注目することは,それ自体をストレス因子と考えることにより症例の理解が深まること,薬物治療に際しては社会恐怖に対する効果も有するSSRIを第一選択薬として用いる根拠となること,うつ病症状改善後の再発防止や,残存する社会恐怖症状の長期的治療計画を治療の早期に立てることができるなどの治療的意義がある.
*
強迫性障害を合併しているものは4例であったが,そのうち2例は社会恐怖症状をともなっており,やはり合併精神障害として社会恐怖がとりわけ重要であると思われた.社会恐怖症状がみられず強迫性と同一性の障害を認める2例は,「自分で納得できる容姿,ファッションでないと外出できない,親からの期待が大きく,それに相応しくない今の自分にも罪悪感がある」,「望んだ高校に入学できなかったことと関係あると思う.今の自分にどうしても納得できない」と,自己評価の低下や強迫的こだわりの破綻がうつ状態の背景にあると思われた.
*
これまでの研究ではパニック障害の合併が多いことが報告されているが,今回の研究ではパニック障害を合併しているのは2例で,このうち1例は社会恐怖とパニック障害の合併であった.なぜ我々の経験した症例にパニック障害が少ないか不明であるが,一つの理由として症例数が39例と比較的少なく,かつパニック障害では既に催眠作用のある抗不安薬や抗うつ薬が処方されているため,今回の研究対象に含まれなかったせいかも知れない.今後は症例を増やし合併精神障害を正確に把握していきたい.
*
Perugiらは重症でかつ全般化している社会恐怖症状,複数の精神障害の合併などは社会恐怖と双極性障害の併存症にもっとも関連があると述べている.双極性障害と診断された7例のうち5例が全般型の社会恐怖を合併していたこと,強迫性障害を伴う2例も重症の強迫行為を伴っていたことなどはPerugiらの報告と矛盾せず,非定型うつ病の診断基準を満たすもので全般性の社会恐怖や重篤な強迫症状を有するものは,双極性障害の診断を視野に入れ治療計画を立てていく必要があると言える.
*
薬物療法については本来MAOIを用いるべきであるが,本邦では副作用の問題からうつ病治療に対しMAOIがほとんど使われてこなかった.したがって,非定型うつ病に対しても習慣的に通常の抗うつ薬を用いてきた.すでに述べたように,非定型うつ病は社会恐怖の合併が多く,社会恐怖に対する有効性も認められているSSRIを用いることは理にかなっている.さらに,SSRIは三環系抗うつ薬のように鎮静作用と関連のある抗ヒスタミン作用や抗α1作用がないため,過眠症状を認める非定型うつ病に対して用いることは合理的なことであろう.
*
結語
非定型うつ病の診断基準を満たす外来患者39名について発症年齢,合併精神障害について調べ,各々の非定型症状について症例ごとに検討した.さらに,対人過敏性と非定型症状の関連,うつ病発症の誘因,心理的ストレスの有無についても調べた.
*
発症年齢の平均は22±6歳と比較的若く,男女比はほぽ1:3と女性に多かった.合併精神障害では51%と社会恐怖が最も多かった.過食は77%,過眠は74%,鉛様の麻痺は49%,拒絶に対する過敏性は82%に認めた.拒絶に対する過敏はLSASおよびBSPSの得点と相関したことから合併する社会恐怖と関連した症状であると思われた.過眠は対人過敏と関連した症状であるとのParkerらの研究をふまえて対人過敏と過眠,過食との関連を調べたが,有意な相関は得られなかった.うつ病発症の誘因としては異性との別れが7例と目立った.また,社会恐怖を合併しているものでは,恐怖症状のため社会生活で自信をなくし絶望することが心理的ストレスとして重要であると考えた.双極性障害を合併しているものは7例であり,そのうち5例が全般型の社会恐怖を合併していた.今回の研究で非定型うつ病の特徴として海外の研究で指摘されている発症年齢が若いこと,女性に多いこと,社会恐怖の合併が多いことが確認された.合併精神障害としては社会恐怖が重要であり,全般性社会恐怖や重症の強迫性障害の合併例では,双極性障害へ発展する可能性があることが示唆された.恐怖症状により自信をなくし絶望することが,うつ病の背景にあるストレスとして重要であることも明らかになった.予後については,合併精神障害のないものや非全般性社会恐怖を合併しているものでは抗うつ薬に対する反応も良く,予後も比較的良いと言えるが,全般性社会恐怖や人格障害,双極性障害を合併しているものでは,予後不良であった.
*
文献
1)American Psychiatric Association:Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,(3rd edition-revised).American Psychiatric Association,Washington DC,1987
2)American Psychiatric Assodation:Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,(4th edition).American Psychiatric Association,Washington DC,1994
3)Angst,J.Gamma,A.,Senaro,R,etal.:Toward validation of atypical depression in the community:results of the Zurich cohort study.J.Afiect.Disord.,72;125-138,2002
4)朝倉聡,井上誠士郎,佐々木史ほか:Liebowitz social anxiety scale(LSAS)日本語版の信頼性および妥当性の検討。精神医学,44;1077-1084,2002
5)Benazzi,F.:Prevalence and clinical features of atypical depression in depressed outpatients:a 467-case study.Psychiatry Res.,86;259-265,1999
6)Davidson,J.R.T.,Miller,R.D.,Turnbull,C.D.et al.:Atypical depression.Arch.Gen.Psychiatry,39;527-534,1982
7)Davidson,J.R.T.,Potts,N.L.S.,Richichi,E.A.et al.:The brief social phobia scale.J.Clin.Psychiatry,52(11,suppl);48̃ 51,1991
8)広瀬徹也:逃避型抑うつについて,繰うつ病の精神病理2(宮本忠雄編),弘文堂,東京,1977
9)Hordern,A.:Theantidepressantdrugs.NewEng.J.Med.,272;1159-1169,1965
10)飯島壽佐美:反復性過眠症(周期性傾眠症)。睡眠学ハンドブック(日本睡眠学会編),朝倉書店,東京,187-193,1994
n)笠原敏彦,加沢鉄士,三好直基ほか:睡眠過剰を伴ううつ病の臨床的検討(第一報)一症候論的特徴についてー。精神医学,26;465-475,1984
12)Klein,D.F.,Davis,J.M.:Diagnosis and drug treatment of psychiatric disorders.Williams&Wilkins,Baltimore,1969
13)Liebowitz,M.R.,Klein,D.F.:Hysteroid dysphoria.Psychiatr.Clin.North Am.2;555-575,1979
14)Ljebowjtz,M.R.,Qujtkin,F.MoMcGrath,P.J.et al.:Antidepressant specificity in atypical depression.Arch.Gen.Psychiatry,45;129-137,1988
15)Ljebowjtz,M.R.,Quitkjn,F.M.Stewart,J.W.et al.:Phenelzine vs imipramine in atypicaldepression:a preliminary report.Arch.Gen.Psychiatry,36;749-760,1979
16)Matza,L.S.Revicki,D.A.,Davidson,J.R.et al.:Depression with atypical features in the national comorbidity survey.Arch.Gen.Psycbiatry,60;817-826,2003
17)Parker,G.,Roy,K.,Mitchel,P.et al.:Atypical depresion:A reappraisal.Am.J.Psychiatry,159;1470-1479,2002
18)Perugi,G.,Frare,F.,Toni,C.:BipolarⅡ and unipolar comorbidity in 153 outpatients with social phobia.Compr.Psychiatry,42;375-381,2001
19)Posternak,M.A.,Zimmerman,M.:Partial validation of the atypjcal features subtype of major depressive disorder.Arch.Gen.Psychiatry,59;70-76,2002
20)Quitkin,F.M.Stewart,J.W.McGrath,P.J.et al.:Columbia atypical depression.A subgroup of depressives with better response to MAOl than to tricyclic antidepressant or pracebo,Br.J.Psychjatry,163(suppl.21);30-34,1993
21)Rothschild,R.,Quitkin,H.M.Quitkin,F.M.etal.:Adouble-blind placebo-controlled comparisn of benelzine and imipramine in the treatment of bulimia in atypical depressives.lnt.J.Eat.Disord.,15;1一9,1994
22)Sakamoto,K.,Nakadaira,S.,Kamo,K,etal:A longitudinal fonow-up study of seasonal affective disorder,Am.J.Psychiatry,152;862-868,1995
23)Sargant,W.:Drugs in the treatment of depression.Br.Med.J,225-227,1961
24)下坂幸三:摂食障害治療のこつ。金剛出版,東京,2001
25)Stein,M.B.Shea,C.A.,Uhde,T.W.:Social phobic symptoms in patients with panic disorder:Practical and theoretical implications.Am.J.Psychiatry,146;235-238,1989
26)Stewart,J.W.McGrath,P.JoRabkin,J.G.et al.:Atypical depression;a valid clinical entity?Psychiatr.Clin.North Am.16;479̃ 495,1993
27)臼井宏,永井久之,後藤多樹子ほか:睡眠過多を伴ううつ病について。精神医学,20;853-862,1978
28)Van Ameringen,M.,Styan,M.G.,Donison,D.:Relationship of social phobia with other psychiatric illness.J.Affed.Disord.,21;93-99,1991
29)Watson,D.,Friend,R.:Measurement of social evaluative anxiety.J.Consult.Clin,Psychology,33;448-457,1969
30)West,E.D.,DaUy,P.J.:Elfects of iproniazid in depressive syndromes.Br.Med.J.1;1491-1494,1959
31)横山知行,飯田真:非定型うつ病。臨床精神医学講座,第4巻気分障害(広瀬徹也,樋口輝彦編),中山書店,東京,291-304,1998
---<2005.2.5受理>---
Atypical Depression in Japan-39caseseries-
Koji TADA,Kayoko YAMAYOSHI,Yamato MATSUZAAKI,Takuya KOJIMA
ln Japan,relatively little attention has been paid to atypical depression,which is defined as the presence of mood reactivity and two of four associated features:hyperphagia,hypersomnia,leaden paralysis,rejection sensitivity.The present study was undertaken to obtain detailed clinical information from patients with a diagnosis of atypical depression.We assessed clinical characteristics of each atypical feature,comorbidity of other psychiatric disorders,presence of a stressful life event,and underlying psychological stress in 39 psychiatric outpatients.We also examined the relationship of interpersonal sensitivity to each atypical feature.
Results and Discussion:Mean age of onset was 22土6,74%were female,20 patients(51%) had comorbid socialphobia.Thirty(77%)had hyperphagia and 25 of these were women.Twenty(74%)had hypersomnia.Only seven patients reported daytime sleepiness and others(13)reported difnculty in staying awake due to lack of energy.Nineteen(49%) had leaden paralysis.Thirtytwo patients(82%) had rejection sensitivity and this symptom correlated with scores of FNE(fears of negative evaluation),LSAS(Liebowits social anxiety scale) and Brief social phobia scale(BSPA).Seven patients reported disappointment in love as a stressful life event preceding the depressive episode.
ln patients with comorbid socialphobia,loss of confidence due to hypersensitivity to rejection or criticism seemed to be the most important factor as a chronic psychological stress.Seven patients met criteria for bipolar disorder and five out of seven had comorbid generalized socialphobia.The clinical and theoretical implications of these findings were discussed.
(Authors’abstract)
くKeywords:Atypicaldepression,sodalphobia,hypersomnia,hyperphasia,rejedion sensitivity> .
*
-「うつ状態」の症例定式化(フォーミュレーション)- 準了解性
本論文は、従来からの非常に重要な視点である、了解可能性の問題を土台として、準了解性という言葉を用いながら、現代的状況における了解性の問題を扱っていて、非常に重要であるとわたしには思われる。
『「うつ病」症状の中核的特徴は理論上,非了解的なものでなければならないのだが,その一般的特徴は健常者に理解されやすい,つまり素朴心理学の範囲内で理解されうるという外観を有している』
また
『「うつ病」の準了解性と神経症圏の病態の「了解性」を識別する努力が重要であり』
上のような指摘があり、さらに本文で詳細に述べられている。
了解的・共感的視点は常に必要であるが、うつ病診断のためには、病理構造の理解が不可欠である。それは了解は出来ないが、説明は可能である何ものかである。
*****
本やネットで、DSMで提示されている項目をチェックして、自分はいわいる「うつ」だと自覚して、病院に行く。このことで、精神科受診率は増加しているが、一方で、自殺者は減少していない。中核的うつ病者は、「不調を自覚して、うつチェックを自分で行い、クリニックに行く」のとは別の行動をとっている可能性がある。
*****
臨床精神医学34(5):593-604,2005
「うつ状態」の精神医学診
「うつ状態」の診立て方
-「うつ状態」の症例定式化(フォーミュレーション)-
松浪克文
1.はじめに
*
精神科診療においては,患者の訴える精神的苦痛を「症状」として明確に把握することが常に可能ではなく,特に治療初期には,明確な診断が決まらないことが少なくない。1つには精神的苦痛が多様な表現をとって訴えられ,あるいはその表現が不十分だからであるが,受診経緯,診療施設のあり方,診療室の雰囲気,同伴者の有無,など実にさまざまな要因が患者の表出に影響するからでもある。特に初診時には,医師が患者の訴えのどの点に疑問を感じ,どのように尋ねるかによっても,その後の患者の表出は変化し,どの訴えが重要であるかも変わりうる。このような診療の場の相互的コミュニケーションにおける動的な意味のあり方を考慮すれば,診断に至るまでには少なくとも,治療者と患者が患者の訴えをめぐる諸事実を確認し共有するという作業が不可欠だといえるだろう。ほぼ妥当な診断はこの確認された情報が漸進的に蓄積していき,一定の量と質に達した段階で可能となるのである。その際,蓄積されるべき情報には,身体疾患や常用薬物(物質)の影響,意識状態,生活史的諸情報,病前のパーソナリティや能力の程度,病前の適応状況,病前の家族状況,サポートシステムのあり方,症状の発生過程および,誘因,症状の持つ状況的意味などの諸事実だけでなく,治療的コミュニケーションにおいて認められた患者の反応や行動様式,薬物の反応性,身体的および心理的諸検査の結果など診療が進行するにつれて得られる知見も含まれる。もっとも,このような意味での「診断」は単に疾患分類における位置を決定することではなく,発症と症状の治療可能性に関連する多重な要因をそれぞれの評価付けや各要因間の力学とともに認識することであるから,この目的のためには,患者の精神的苦痛を当面,「状態像」として把握しておき,疾患分類学が要請する要素的観察や症状学が背景とする仮説から自由でいる方が都合がよいともいえよう。あるいはまた,患者の抱える問題の特定の側面を明示的に「症状」として言語化し,それを治療契約を取り結ぶ足がかりにするようなケースでは,当面,状態像把握で十分だともいえるだろう。いずれにしても,「状態像」診断は精神科臨床のこのような特殊性の中で,確定診断が決まるまでの判断保留の時期に行われる暫定的診断として機能しているものと思われる。
*
2.「うつ状態」診断が含意すること
*
「うつ状態」診断を下した診断者の判断保留の理由は当然のことながら,〈「うつ病のようである」が「うつ病ではないようだ」〉と考えているため,つまり肯定と否定の,2つの漠然とした判断が下されているためである。前者の肯定的判断において診断者が当該の精神状態を「うつ(状態)」と特定する理由は何であろうか。それは,おおむね「憂うつである」「やる気がでない」「意欲がでない」などのような,臨床の場で遭遇する「うつ病」患者の訴えや言動のいくつかが認められるという事実と,診断者を含めた誰もが日常生活において経験的に知っている,憂うつな人間が表す表情や行動が認められるという常識的判断であるにの時点で,「うつ病」の可能性は否定されていない。前段の「うつ病の代表的訴え」の存否を経験科学的に確認するのにDSMやICDのような国際的診断基準を用いることが現今の精神科診断学の定石だが,その場合でも,前段と後段の判断はほぽ同質の判断になる。というのは,DSMおよびICD的診断における諸項目も後段の常識的判断も,いわゆる素朴心理学folk psychology(心的状態を用いて行動を合理的に説明するわれわれの日常的心理学)に依拠しているという点で同質だからである。
*
素朴心理学を診断の道具の1つとすること自体には,その一貫性を保つ限り,さしあたり分類学的整合性にとっての問題はない。しかし,ここには了解性をめぐるうつ病特有の錯綜した事情が潜在しているように思われる。後に述べるように「うつ病」症状の中核的特徴は理論上,非了解的なものでなければならないのだが,その一般的特徴は健常者に理解されやすい,つまり素朴心理学の範囲内で理解されうるという外観を有しているためである。このように「素朴心理学的には了解できる外観を持ちながら,症状学的には了解不能である」ことを「偽了解性」あるいは「準了解性」とでも呼ぶことにすると,「偽(準)了解性」は素朴心理学による症状把握の限界を示しているように思われる。つまり,うつ病の訴えの性質は患者の述べた言葉から引き出される命題的内容だけからは正確に推論できないのであり,本来,「うつ病」診断は,患者の表出全体を対象にした症状学によって「偽(準)了解性」が否定され,了解不能な病態であると判断されて成立するのである。こう考えると,「うつ状態」診断に含まれる「うつ病のようである」という判断は素朴心理学的判断にとどまっており,「偽(準)了解性」についての吟味を経ずに成立した不完全な判断だということになる。この判断はまた,素朴心理学的である以上,明らかに非了解性を有する病態だという可能性を敏感に排除するが,一方,「うつ」と特定する意味でそれ以外の病態を否定していながら,了解的であることを暗黙に容認している点で,明らかに了解性を有する病態の可能性を排除してはいない。
*
後者の「うつ病のようではない」という否定的判断の方は症状学の知識や臨床経験を背景にした専門的判断だといえる。というのは,「うつ病のようである」という素朴心理学的判断を否定するためには,素朴心理学に依拠しない基準を用いなければならないはずであって,そのような基準は何らかの専門的仮説あるいは理論によるものと考えざるを得ないからである。また,この判断は,「うつ病」診断を否定するほどの拘束性を持たないという点で「弱い意味で」否定しているといわなければならないが,それは,診断者が疑いのかかる程度の微細な差異や微弱な兆候soft signsによって消極的に「うつ病」診断を否定しようとしているからである。このような微妙な判断が可能であるという点でも,この判断にはやはりある種の専門性が要請されているはずである。
*
表1 「うつ病ではない」という判断
専門的仮説あるいは理論による素朴心理学的判断の吟味
1.「うつ病」を「弱い意味で」否定
2.他の精神疾患を「弱い意味で」肯定(soft signsの存在)
*
要するに,「うつ状態」診断は,素朴心理学的な「偽(準)了解性」という不完全な判断について何らかの専門的仮説あるいは理論を基準にした吟味が行われ,「うつ病」であることが「弱い意味で」否定される可能性と他の精神疾患であることが「弱い意味で」示唆される可能性を含意しているのである(表1)(なお,本稿では,治療初期から明らかにうつ病が否定され,他の精神疾患が容易に診断されうるようなケースはことさら「うつ状態」診断が用いられないと思われるので,問題にしないこととする)。
*
3.「うつ病」症状の中核的特徴
*
うつ病症状の中核的特徴についての緒論は,かつては大部分の精神科医が用いていた常に実践的仮説に基づいており,診療の現場では一種の暗黙の知識tacit knowledge的機能を果たしていたものと思われる。以下に,筆者自身が臨床経験上,うつ病診断について反省,自戒した事例を省みながら,改めてまとめてみたい。以下の項目のどれかの存在に(微かな)疑いがかかり,「うつ病」診断が消極的に否定されるときに「うつ状態」診断が下されているものと思われる。
*
1.症状
医学において「症状」としてとらえられる現象は個体差を越えた普遍性と同一個体における反復性を備えていなければならない。例えば,炎症の腫脹,発赤,疼痛という性質は個体差を越えて普遍的であり,同一個体内において反復される。むしろ,個体差を越えた普遍性と同一個体内での反復性を有する身体的(心理的)現象でなければわれわれは「症状」としてとらえることはできない,といった方がより正確だろう。このことは,「症状」には,個人の固有性が現れないということを意味している。すなわち,「症状」には患者の人柄や発病までの人生のあり方や心理・社会的背景などに左右されない性質が含まれており,また,その性質は多くの患者が呈する症状に共通に含まれている不変項だということである。このような不変項が「うつ病」診断の根拠となる症状把握にも要請されていると考えなければならない(当然のことながら,これは症状の性質について言えることであり,症状とともに訴えられる患者の背景事情や心理的苦境,ストレスヘの対処法などについてのことではなく,また筆者はそれらの情報を吟味して発症をめぐる力学を考慮することの重要性を否定するつもりは全くない)。
*
1)形式的特徴
うつ病は気分障害であり,かつ相性の病態であるから,定義上,症状の生起や消退に比較的,時日を要するものとされている(周知のように,国際診断ではこの持続時間が2週間以上と特定され,診断に要請されている)。一部の特異な変種をのぞいて,変動が短時日うちに起こり消退する精神状態はうつ病症状とは形式において質的に異なる。この時間的形式は反応性の病態や意識障害とは明確に異なる点である。
*
2)非了解性
上記した「症状」の原理的性格を考慮すれば,「うつ病」の症状は「十分な」心理了解性を有していてはならない。つまり,うつ病「症状」には,個人の有する固有な心情や個別的意味関連とは独立した性質が含まれていなければならない。表2に筆者なりのうつ病症状の概観を示した(うつ病症状の診断基準のつもりではない。また,このように個々の症状別に分けて論じることには精神疾患の全体論的性質から見て問題がなくはないが,現時点ではこれ以外に方法はない。この難点は,DSM診断における症状群familial resemblance的把握によっても解消されてはいない)。
*
表2 うつ病の症状の特徴,まとめ
Ⅰ(生気的)悲哀
Ⅱ(生気的)制止
Ⅲ自律神経機能の低下
Ⅳ三大妄想および関係妄想
Ⅴ希死念慮
Ⅵ日内変動
*
このうち,うつ病の三大妄想や関係妄想(Ⅳ)は明らかに了解不能な現象であり,診断保留とする理由にはなり得ない。自罰的理由を有する希死念慮(Ⅴ)はうつ病特有の「症状」としての性質を備えているが,自我感情の低下に由来しない他罰的な考えから生じる希死念慮は,死ぬことを望む理由が背景心理と了解的につながっている点で「うつ病」に特有のものではなく,「うつ状態」診断が採用される可能性がある。日内変動(Ⅵ)は何らかの実体的症状の付帯的性質であって,表中の他の症状と同一レベルの現象ではなく,またそもそも心理的了解の対象ではない(その病態を理解することの重要性についてはここでは論じない)。また,睡眠や食欲の変化,頭重感などの自律神経支配の領域における症状(Ⅲ)はうつ病診断の必要条件とはいえるが十分条件ではなく,単独で診断的意義を有することはない。
*
うつ病診断上問題になるのは(Ⅰ)と(Ⅱ)であり,「やる気が出ない」「憂うつである」などの趣旨の自発的訴え,特にその言語表現あるいは「文」の意味だけを判断の根拠とする視点からは,了解可能/不能の区別が困難だという点である。DSMIVやICD-10における(大)うつ病エピソードの診断基準の項目を注意深く考量しても,この点は十分には明らかにならない。(これらの診断基準は精神症状を量化して表現しているために,症状項目としてとらえられた精神現象の文脈的意義や,おのおのの項目の診断にとっての重要度の差異が捨象されている。端的に,現実には,これらの診断項目を満たしてもなお,「うつ状態」の診断が下される可能性がある)。
*
筆者の考えでは診断学上のこの困難を救済する道は,今日では実証的でないとして参照されることの少なくなった「内因性」うつ病に関する症状学で論じられた,抑うつ感の①生気性,②非反応性,③非共鳴性などの性質を判断の指標とすることにあると思われる(ただし,これらの特徴の一部はDSM診断においても,melancholic features specifierにおいて言及されている)。本稿では詳述は避け,うつ病の抑うつ気分の非了解性にだけ触れておく。
*
うつ病の症状について,健常人の有する意味での「憂うつ」という言葉のニュアンスが患者には通じないことが意外に多いという臨床経験はこれまでにも指摘されてきた。健常人がうつ病の抑うつ気分を理解する方法としては,各人が体験し,あるいは見聞した「憂うつさ」を参照するしかないのではあるが,そのような視点から〈どんな気分ですか?/何にお困りですか?〉と問いかけた時に,誘導されることなく端的に「憂うつ」という言葉を用いて答えるうつ病患者は意外に少なく,他の「寂しい」「悲しい」「むなしい」などの複数の陰性感情の表現がとられたり,質問と対応しない身体的愁訴が返ってくることが多い。あるいは,首を傾げ,表現に困り「何と言ったらいいのか……」と表現に困難を感じているような態度が認められる。つまり,患者当人にとってもうつ病の抑うつ感を表現する言葉はなかなか見いだしにくいのであり,われわれの日常言語の中にはこの病理的な気持ちをぴったりと言い当てる言葉が存在しないのである。そして,この不可解さ,把握の難しさとそのための当惑こそ治療者が共感しうるポイントである(診察の過程で治療者が「優うつ」という表現を用いて質問したために,患者の方が「優うつ」の語を受け身的に選択してしまうということさえありうる)。このことこそ,この症状が端的に了解不能であることを物語っている。このことから,筆者の考えでは,うつ病性の感情は喜怒哀楽の感情すべてにわたって,それらを十分に体験できないことであるという仮説は現時点でも十分,妥当な解釈であると思われる。「うつ病」のこのような性質は,DSM上はlack of reactivityという表現で一部提示されており,また欧米の教科書のケーススタディにおいても,患者の感情面の特徴を表すのにapatheticという言葉がときに用いられることがある。この症状が特に喜びや快楽の享受という体験面で最も深刻な問題になるのは,うつ病の症状が本来的にそのような快楽の喪失であるからというよりも,本来喜怒哀楽の感情の中で喜びや楽しみが生きていくうえで不可欠な感情だという初期条件のためだと考えることも可能であろう。
*
一方,制止症状の方は,確実に行動面に露呈している点で比較的明白に把握できる。患者当人には能率や理解力の低下,物忘れ,失策,遅滞などとして自覚されるが,当初はこの自分の精神的機能の遅鈍化が自覚されていることは少ないのではないだろうか。うつ病の制止はむしろ診察場面の患者の行動において確認できる。例えば制止は話すスピードに端的に現れており,また話題に応じて表情が変化し,問いに適切に対応した応答が可能な場合,憂うつという訴えがあっても制止症状の存在は疑わしい。このように,制止症状は生理的機能の低下からも推し量られるが,本来的には生活行動のレペルで,すなわち衣食住と基本的な社会的行動のレベルで確認されるべきである。生活行動はスムーズに行えているのに仕事がはかどらない,能率が上がらないという場合は,少なくともfun-fledgedな制止症状とはいえないだろう。
*
3)発症過程の非了解性
うつ病の発症過程は,少なくとも個人の背景的諸条件(病前の人格,個別的な心理的,社会的背景,固有の体質)から心理了解的には理解できないという性質を持つはずである。ただし,ここで臨床的に有用性を発揮する「了解可能」とは,特定の心理的事態の推移が,医師,患者を問わず,われわれが平均的社会人として共同体の他の成員と共有している感情や思考の変化可能性の範囲内にある,という直感的かつ素朴な常識的判断のことだと考えるべきである。したがって,昨今,十分に人口に膾炙した感のある発病状況論的理解朗や精神分析的解釈も,仮説による理解であって「了解的」な理解ではないことに留意しなければならない。臨床的によく遭遇する発症パターンであることは了解可能であることとは別の事柄である。臨床的には,患者自身が憂うつになった心理的な事情を明確に述べ立て,かつその訴えが医師にとっても十分あり得ることだと思える場合には了解可能な病態である可能性が高く,少なくとも中核的うつ病とはいえないだろう。反対に,昇進うつ病や引っ越しうつ病などの状況論的把握が可能であることが了解可能な発症を意味するわけではない。
*
4)身体性
うつ病の気分状態が健常人の「憂うつ」な心理とは異なり,両者の差異は何らかの意味での身体性の関与にあることに異論はないだろう。上述したうつ病の体験構造的理解が妥当だとすれば,うつ病の「抑うつ気分」は患者には純粋な心理的事態とは体験されてはいないはずである。つまり,当人の背景事情や心理的体験の流れの中に十分に位置づけられない異質性を持っており,当人の精神の作用域にとってはどこか外来性のものとして,多くは,精神作用には外的な身体的機能の変質として体験されている可能性がある。これは能率低下や疲労感,倦怠感,各種自律神経症状の訴えと抑うつ気分がともに,Koerperとしての障害であり,かつLeibとしての病理であるととらえられなければならないことを意味している。患者が自分の「憂うつな気持ち」をあくまで純粋に心理的な事情を伴った心理的な苦痛として物語ることが可能な例では,抑うつ気分自体も純粋に心理的な体験として語られ,悲しみやむなしさなどの具体的感情が十分に説得性を持って表現されることが多い。
*
2.心理の特徴
うつ病の心理学的な意味での特徴は「症状」としての資格を十分に備えているとは必ずしもいえない。というのは,強迫性や依存性などの用語は人間の心理についての抽象的な解釈概念であって,個々の症例において具体的に(症状としてとらえるための具体的対象というレベルで)どのように現れうるのかを予測,指示しないからである。また,多くのうつ病患者にこれらの心理傾向が確認されるということは,必ずしもこの心理的傾向を持つ人がうつ病であることを意味しないので診断的価値は大きくはない。しかし,これまで諸家によって提唱されてきたこれらの心理傾向は経験科学的判断における傍証として十分機能し,うつ病の病態を理解する仮説として多くの支持を集めているものと思われる。これらの特徴自身が「うつ状態」の病態把握や診断にとってのsoft signsとして重要な位置を占めてきたものと思われる(したがって,これらの特徴の否定もまた,「うつ病のようではない」ことを示すsoft signsとなりうるわけである)。
*
1)強迫性
メランコリー型のような病前性格の理解に見られるように,従来,うつ病の心理の特徴として強迫性が指摘されてきたが,強迫性の現れをいわゆる几帳面であることとして理解すると,近年の几帳面なうつ病患者の減少傾向を理解できなくなる。しかし臨床経験上,一般に,うつ病の人がいったん受け入れたルールや習慣に違反することが少ないとはいえるのではないだろうか。むしろ,いったん決められた,あるいは習慣となった行動パターンを変化させることが難しいことや,自分の恣意的判断に左右されない固定されたルールを求める傾向はあり,これらはひとまず,一種の変化可能性の低下としてだけ理解しておいた方が実状にあうように思われる。近年のうつ病が私的領域で決まった行動パターンを持つこと,あるいは特定のライフスタイルを維持しようとする傾向があることは強迫性の顕現様態の変種として理解できるだろう。
*
2)依存性
うつ病の患者が家族成員,ときに緊密な治療関係を持つ治療者に示す依存的態度も「うつ病」の心理の特徴といえるだろう。従来,遷延化した症例で確認されてきた点である。もっとも,近年はうつ病患者の早期受診傾向,薬物療法の進歩などにより治療関係が医学モデル的になり,精神療法に重心をおいてアプローチする治療者は多くはないものと思われる。しかし,若年のうつ状態患者には,初診時からこのような依存性を顕わに示すケースが増えている。そして,依存性に関連して論じられるのが,うつ病患者の自己愛の問題である。いわゆるnarcissistic supplyを常に必要とする傾向,dominant otherの存在,などとしてあくまでうつ病の心理という枠内で論じられてきた。近年の若年者のうつ病には当てはまることの多い視点だが,うつ病患者の典型例における自己愛は他人にそのまま表現されることはなく,社会的な配慮つまり対人状況への配慮という形で,つまり強迫的な防衛によって対人戦略的に加工されている。むしろ,明らかな自己愛性の病理が前景に立つ病像は「うつ病」症状を発症する心理的準備性が十分に形成されていないという認識で臨んだ方がよいものと思われる。
*
3)同調性
「うつ病」患者が社会的環境との間に軋轢を招こうとすることは少ない。少なくとも,争いを好まないという傾向,自他を明確に分離することに抵抗する傾向を持つことは否定できない。職場に苦手な人がいるという場合でも,嫌いながらもなんとか協調の努力をするのがうつ病の人の基本的な姿勢と思われる。同調性の傾向は協調的態度,一体化希求などとして現れる場合が多い。同調性は,一般に社会人が多かれ少なかれ組織や共同体の中で要請されている性質なので,うつ病心理の「準了解性」と最も密接に関係しているものと思われる。すなわち,「症状」の非了解性にもかかわらず,症状をめぐる心理的布置や病前の適応的同調性が了解可能なのである。
*
4)いわゆる攻撃性の内向
うつ病の心理についてはフロイト以来,攻撃性の内向という図式が用いられてきた。事実,例えばうつ病における希死念慮は自罰的性質のものであることが多いし,他人への迷惑を悔い,自分を責めるうつ病患者は多い。やはり,他罰傾向を前面に表現したり,具体的な攻撃対象を述べ立てるうつ病患者は少ないように思われる。
*
5)発病状況と好発年齢層
うつ病は社会化の努力や自律性の維持と密接に関連した中年期発症の病態とされ,臨床的にも典型的な発病状況がほぼ診断の傍証として機能するまでにパターン化されて認識されている。しかし,DSM診断によってこのような仮説が排除されてから,また社会的状況の変化の影響もあり,うつ病はかならずしも中年期の病理とは考えられず,若年層におけるうつ病症例数が数多く報告されるようになっている。しかし,私見によれば,うつ病の発病状況を成長と衰退,強壮化と弱体化,拡大と縮小などの生の相反する運動が措抗する臨界状況であると考えれば,いわばこの中年期的状況は若年層にも起こりうる。ただし,これは環境への適応の努力や自律性や責任の維持といった社会的な課題を志向している人に当てはまることであり,この点は除外することができないだろう。したがって,より若年(10代,20代)に起こるうつ病については妥当しない。一般的に,より若年の抑うつの訴えはパーソナリティ形成の途上での困難である場合,自生的な双極性障害の初発,抵抗障害などであることが多いのではないだろうか。
*
6)いわゆる基礎性格
メランコリー型や執着性格などの病前性格は少なくなったと言われて久しいが,まだ臨床的にはよく遭遇する。これらは強迫性の対社会防衛としての意味あいが強く,その分,社会的状況に影響を受けてさまざまな変種が生まれる可能性を持っているのだが,しかし,強迫性が倫理的審級にまで浸透していることはやはりうつ病になりやすい人々の特徴ではないだろうか。また,循環気質の人のうつ病親和性も重要である。すでに述べたが,循環器質的同調性や協調性,あるいは感情の豊かさ,エネルギーレペルの高さは,統合失調症的な疎遠な個人主義的雰囲気とは質的にことなり,これらも診断のためのsoft signsとしては十分機能しうるものと思われる。
4.「うつ病」診断を「弱い意味で」否定する因子
1.軽症うつ病の判断
「うつ病」診断を(弱く)否定する因子としてまず考えられるのは,軽症の病態である。一般に,重症度の判断は個人の社会的機能の障害程度や苦痛の程度によって素朴心理学的に行われうるが,軽症であることが「うつ病」診断を妨げるのかどうかについては微妙な問題がある。わが国における軽症うつ病概念やいわゆる逃避型抑うつとDSMにおけるDysthymia,Subsyndromal Symptomatic Depression(SSD)などの軽症のうつ病概念とは質的に異なる概念だからである。前者が提唱された意義は,素朴心理学的に軽症である病態が専門的判断によっては内因性うつ病と診断されうるという逆説にあるのに対し,後者は,DSM上のうつ病エピソード診断に要請されている症状項目数や持続時間が満たされないという意昧での軽度な症状が,素朴心理学的な重症度の判断によっては軽症ではなく,深刻な社会的機能の障害を招くという点で重要視されている。「うつ状態」の診断が行われている可能性が高いのは前者であり,後者は診断学上の量的差異によって早期に特定されうる病型であって,「うつ状態」と診断保留にされている可能性は少ないだろう。
*
2.他の精神疾患を示すsoft signs
次に,「うつ状態」診断が含意する他の精神疾患あるいは病態を整理してみたい。「うつ状態」という診断を選択するという判断に含まれているはずの,他の精神疾患を想定させる因子を①器質性因子,②精神病性因子,③心理的反応性因子,に分けて概観してみよう(表3)。ただし,ここで「器質性」とは精神的異常に対して因果的効力を有する身体疾患や身体的現象によるものを指し,「精神病性」とは明らかに非了解性を有する精神疾患によるものを指し,「神経症性因子」とは(了解可能,不能を問わず)心理的反応として生起する心理状態を指すこととする。表4はうつ病発症と関連する薬物と身体疾患のまとめである。
*
表3「うつ状態」診断が含意する他の精神疾患・精神状態
1)器質性因子
(1)症状性精神病
(2)認知症
(3)薬物(物質)の影響
2)精神病性因子
(1)統合失調症
(2)躁うつ病
(3)てんかん
(4)非定型精神病
3)心理的反応性因子
(1)神経症性障害
(2)パーソナリティ障害
表4うつ病発症に関連する薬理学的因子と身体疾患
Pharmacological
Steroidal contraceptives
Reserpine;a-methyldopa
Anticholinesterase insecticides
Amphetamine or cocaine withdrawal
Alcohol or sedative-hypnotic withdrawal
Cimetidine;indomethacin
Phenothiazine antipsychotic drugs
Thallium;mercury
Cycloserine
Vincristine;vinblastine
Endocrine
Hypothyroidism and hypertbyroidism
Hyperparathyroidism
Hypopituitarism
Addison’s disease
Cushing’sdisease
Diabetes melltus
General paresis(tertiary syphilis)
Toxoplasmosis
Influenza;viral pneumonia
Viral hepatitis
Infectious mononudeosis
AIDS
Collagen
Rheumatoid arthritis
Lupus erythematosus
Nutritional
Pellagra
Pernicious anemia
Neurological
Multiple sclerosis
Parkinson’s disease
Head trauma
Complex partial seizures
Sleep apnea
Cerebral tumors
Cerebrovascular disorder
Neoplastic
Abdominal malignancies
Disseminated carcinomatosis(文献23より)
1)器質性因子
何らかの器質的疾患で治療中の患者が「うつ病の疑い」で精神科に紹介された場合,あるいは何らかのうつ病的な訴えや身体的愁訴で受診した患者に身体疾患がすでに存在した場合に想定される事態として,
①すでに存在する身体疾患がうつ病の外因として特定されるもの(内分泌疾患,感染症,膠原病,神経内科的疾患,腫瘍,手術後の疲弊など)
②すでに存在する身体疾患の治療薬,あるいは常用物質にうつ病誘発性の作用がある場合(C型肝炎のインターフェロン治療,アルコール,ステロイドなど)
③すでに存在する身体疾患の闘病過程が発病状況として働き,発病を誘発したもの
④すでに存在する身体疾患の苦痛や闘病過程が重大なストレスとはなっていないもの
⑤精神的訴えに対するexaminationの過程で,精神障害に対して因果的効力を有する身体疾患が発見される場合,などが想定される。
①②は,症状性精神病(DSMでは器質性精神症候群,ICDでは症状性を含む器質的精神障害)のカテゴリーに入り,その部分症として「うつ状態」という診断が下されている場合である。もちろん,身体疾患が当初明確でなく精神的訴えで来院した患者に身体疾患が認められる場合もあるだろう(⑤)。リエゾン精神医学における事例化ではなく,憂うつであることを主訴とする患者で,かすかな物忘れ傾向や理解度の悪さ,情動の不安定さなどが併存するなどのsoft signsがある場合には,器質的疾患特に認知症の可能性がある。認知症初期のうつ状態とうつ病の鑑別は難しく,「うつ状態」と診断され判断が保留されるだろう。うつ病性の偽痴呆という診断カテゴリーもあるが,irreversible dementiaがうつ病を伴うreversible dementiaの43%に(うつ病のみ症例では12%)に見られるという報告もあり,抗うつ薬で治癒したかに見える偽痴呆の症例でもその後認知症に至る可能性は常に念頭においてよいだろう。
③④は治療過程に被る苦痛や不安,治療そのもののストレスなどに引き続きうつ状態が出現する場合である。総じて器質的疾患に引き続いて起こるうつ状態では,うつ病のようにみえる言動の出現が比較的短時日のうちに現れることが多く,また,そのような場合には,軽微な意識混濁が共存し,微弱なせん妄が疑われる場合が少なくない。うつ病の制止症状のように見えて実は周囲の状況を認識できていないこと,短期記憶のかすかな障害,当人が行動の現象を深刻には悩んでいないこと,症状の動揺などがチェックポイントであろう。ただし,闘病生活が持続的な誘発状況どなっている可能性も十分にある。しかし,④の場合は原疾患による誘発というよりは,家族などからのサポートが不十分であること,不安閾値の低さ/依存性の強さなど患者の元来のパーソナリティから十分な了解性を持ってあり得る事態だと考えられ,ストレス関連障害やパーソナリティの病理が想定されて「うつ状態」とされていることが多いだろう。
*
2)精神病性因子
「うつ状態」診断の背景には,統合失調症,蹄うつ病,てんかん,非定型精神病などあらゆる精神病性の疾患が存在しうる。「偽(準)了解的」な訴えの中に,不協和音のように,「微かに」認められるより明確な了解不能性を有する言葉や行動,感情状態の性質が精神病性の否定因子として問題になる。てんかんに見られる不機嫌状態やいわゆる非定型精神病に含まれる気分の病理がそれぞれの疾患の特徴を確認するまでの間,「うつ状態」して診断が保留されているであろう。ここでは,特に微妙な症候soft signsによって「うつ病」との差異が問題となる統合失調症と躁うつ病についてだけ言及する。
*
①統合失調症:いわゆる発動性の低下や自明性の喪失と言われているような病態がごく微かに疑われるときに「うつ状態」診断が用いられているものと思われる。より明確な了解不能性を有する言動や妄想性,幻覚性の病理ならば微かなものでも,現実には統合失調症が疑われ警戒されているだろう。しかし,診断者がこの重大な診断を下すのは時期尚早だと考えている場合も多く,むしろ「うつ状態」診断は社会的配慮という次元の問題かもしれないが,多かれ少なかれ,断定できないという診断学上の困難はあるだろう。そのような場合,診断者が統合失調症を疑う根拠はなんだろうか。実は,ここでも「統合失調症らしさ」という穏れた診断基準,むしろわが国では周知のpraecoxgefuehlや気質診断が傍証すなわちsoft signとして用いられている可能性がある。従来わが国で行われてきた統合失調気質の存在は実証的に証明されてはいないのだろうが,臨床的にはこのような気質判断も有用性を発揮するときがある。私見によれば,統合失調気質の人がうつ病圏の人々に見られる同調性という標識を有していないことは臨床的には明らかで,このことは,「うつ病」診断を否定する唯一の根拠とはならなくても,重要なsoft signとはなっているものと思われる。特に,統合失調器質の人が厳しい職場状況や複雑な人間関係の中で適応障害に陥り,不活発,無感情となっている場合には,当面「うつ状態」という診断が妥当な場合がある(統合失調気質の適応障害)。しかし,この点で診断上,優先されているのは,従来,行われてきた統合失調気質についての病理学的仮説よりもむしろ冒頭に述べた「うつ病のようである」という素朴心理学的了解性の判断である。実際,DSM診断上の大うつ病性エピソード患者の中には統合失調気質の人も数多く含まれ,将来,統合失調症を発病する危険性を有する一群も存在するものと思われる。国際的診断基準にはこの点を識別する診断力はない,というよりもむしろ,そのような診断変更の可能性を否定しない,という構想で作られているのだと理解しておくべきであろう。
*
②躁うつ病:うつ状態に躁性の成分が混入しているという判断つまり,可能性として双極性障害を想定することは,気分障害の治療論にとって重要である。気分障害のすべての病態を躁とうつの混合様態としてとらえる視点もあり,それ自体は理論上,重要な示唆を含んでいる。実際,臨床的に「うつ病」診断はほぼ確実でも単極性,双極性の判断は明確に行えないことも多い。a)強い焦燥,興奮,不安,b)強力性を含んだ人格,c)感情状態の急速な変化,d)病前性格が循環気質やマニー型である,などは「躁うつ病」の可能性を考慮するsoft signとして重要であろう。特に,病前にマニー型であった人が重篤な身体疾患や深刻な挫折ののちに疲弊し「うつ状態」となる場合などは,患者本人が訴える抑うつ的な不調自体がマニー型に特有の活動レペルを維持できないという現状への批判あるいは嫌悪が病像心理の中心となっていることが多い(マニー型の疲弊)。さらには,うつ病症例の病前性格に循環気質的な同調性や常識的態度,協調性が十分に認められている場合には,一応躁転の可能性を念頭に置くべきだろう。
*
3)心理反応性因子
①神経症性障害:明確な恐怖症性障害や強迫性障害が存在するときには,「うつ病」よりも「うつ状態」の診断が選択されるだろうが,周知のように,昨今のcomorbidityという視点からは「うつ病」診断は否定されてはいないことになる。特に,恐怖症については,パニック障害の並存やうつ病の社会復帰の時期になって現れる職場状況への恐怖症的心理が代表的なものだが,どちらも「うつ病」の診断と並存しうる。強迫性障害の場合は,明らかな強迫行動や強迫表象が存在し生活の障害となっていれば「うつ病」診断が保留されるだろう。上述したように,うつ病に特有の強迫性は社会的機能として患者の人格の中に浸透し,患者の手順や手法あるいはライフスタイルと融合していることが多く,いわぱ自我親和的かつかろうじて適応的であるのに対し,強迫性障害の強迫性は自我違和的であり社会的機能を妨げる方向性をとっていることが多い。
*
ストレス反応や適応障害とうつ病との異同は常に問題となるところである。上述したように,これらの病態における症状には了解性があり,この点で「うつ病」症状と区別されるべきである。この意味でも,「うつ病」の準了解性と神経症圏の病態の「了解性」を識別する努力が重要であり,またこのことは,治療初期には的確に行えないものである。
*
②パーソナリティ障害:いわゆるclusterC(回避性,依存性,強迫性)の障害はそれぞれの病理がうつ病の病理の中に含めて考えられうることもあり,また現実に,これらの病態が「うつ病」による障害度を超える重篤さを呈して病像の前景に立つことは少ないので,軽症の場合には「うつ病」診断を否定するsoft signとして機能することは少ない(もちろん,そもそも「うつ病」の症状が明確でないときにはパーソナリティ障害の診断だけが採用されるだろう)。clusterA(妄想性,シソイドパーソナリティ,失調性)とclusterB(反社会性,境界性,演技性,自己愛性)が明らかに認められる場合には,むしろうつ病症状よりもパーソナリティ障害こそが生活にとっての主要な障害となっていることが多い。また「うつ病」がパーソナリティ障害の生む軋轢やストレスとは独立に出現することは少ないので,挿間的に出現する「うつ状態」という認識で治療されていることが多いだろう。この場合にも,DSM的診断学に従う限り,うつ病の診断は可能であって,多くはパーソナリティ障害とのcomorbidityと認識されて「うつ病」診断は維持されうる。特に微妙な問題となるのは,自己愛性の場合で,この障害を持つ人はまさに「うつ状態」に陥ったことで事例化し,初診時には抑うつ的であることを主訴とする場合が多い。「うつ病」にも自己愛の病理が想定され議論されてきたのだが,上述したように,うつ病症状の中核的特徴と強迫性の質に注目することによってこの2つを識別することが可能だと思われる。
*
5.おわりに;「うつ状態」をめぐる症状間の治療論的ヒエラルキーの視点
以上述べてきたことを,概観するために表にまとめておいた(表5)。冒頭に述べたように,状態像診断は原理的には,診断学,疾病分類学,病態仮説から自由な把握法なのだが,治療論的視点に立てば,むしろ標的となる治療対象を選択する点でも有利でもある。特に,複数の病態のcomorbidityが問題となる症例においては,疾病学的に「うつ病」よりヒエラルキーの高い疾患の存在が強く疑われても,当面は「うつ状態」の治療を優先させ,あるいはその逆の治療方針をとるべきケースが往々にしてある。2,3例を挙げておくと,インターフェロンやステロイドによって治療中の「うつ状態」で,原疾患である肝炎の治療とうつ病の治療のどちらを優先させるかは,それぞれの症状の重篤度や治療局面の差など多要因によって決定され,必ずしも原疾患の治療が優先されなければならないわけではない。反対に,一過性の病的な対人過敏性や状況とそぐわない被害念慮や恐怖が見られる統合失調気質の人の適応障害の症例では,現に抗うつ剤が奏功し気分状態としては復調したとしても,うつ病患者の心性を基礎理解として環境適応のアドバイスを行うのでは長期に見て治療的にはならず,やはり統合失調症的心性を念頭に助言していく必要がある。あるいは,マニー型の生き様を続けられないことが持続的な閉塞感を招いて「うつ状態」診断が下された症例では,長期的には,当面の治療対象であった「うつ病」の治療原則として休養の勧めを説いても安定は得られず,むしろ病前性格に含まれる病理を重視して,自由度を求めるマニー型の動きそのものはある程度容認しなければならない。さらには,境界型や自己愛型のパーソナリティ障害にみられる「うつ状態」では,むしろうつ病よりもパーソナリティ障害の方が患者の生活を障害する程度が甚大で,治療の標的となるのはパーソナリティ障害の方である。
*
表5「うつ状態」診断に含まれる諸判断
1.「うつ病のようである」という判断=「偽(準)了解性」の容認
素朴心理学的判断
①うつ病に見られる代表的な症状のいくつかを確認
②常識的な「憂うつ」の判断
2.「うつ病のようではない」という判断=1.の判断を吟味
①「うつ病」を「弱い意味で」否定
a.「うつ病」の中核的特徴が不十分
b.「うつ病」心理の特徴か不十分
②他の精神疾患を「弱い意味で」肯定;soft signsの存在
a. 器質性因子
意識障害の有無の確認
身体疾患の存在
薬物ないし物質摂取の影響
b. 精神病性因子
統合失調症;同調性の否定・気質診断
躁うつ病;躁性成分の混入,マニー型の診断
c. 心理反応性因子
神経症(強迫性障害,恐怖症,ストレス反応,適応障害抑うつ反応型など)
パーソナリティ障害(境界型,自己愛型など)
*
このように,「うつ状態」という診断の背景にある疾患や精神病理をふまえて,実際にどのような症状や行動を治療の課題とするのかは,診断分類学上のヒエラルキーによらず,現実に患者のどのような苦痛や障害が患者の固有性を障害しているのかという視点,許されている期間内でどの症状に最も治療可能性があるかなどの治療戦略的視点から決定されるべきものだと思われる。しかし,治療論的な症状ヒエラルキーは分類学上のヒエラルキーと全面的に対立するものではもちろんない。社会適応という目的のためには,疾患分類の整合性を重要視するtop downの視点だけではなく,実践の中に法則性を見いだすbottom upの視点をも加味して総合的に判断することが重要だということである。
*
文献
1)Akiskal HS:Dysthymic Disorder:Psychopathology of Proposed Chronic Depression Subtypes.Am J Psychiatry 140:11-20,1983
2)Alexopoulos GS,Meyers BS,Young RC et al:The course of geriatric depression with “reversible dementia” :A controlled study.Am J Psychiatry 150:1593-1699,1993
3)American Psychjatric Diagnostic and Statjstical Manual of Mental Disorders,4th ed(DM4V).American Psychiatric Association Press,Washington DC,1994(高橋三郎,大野裕,染谷俊幸訳:DSM-IV精神疾患の分類と診断の手引.医学書院,東京,1995)
4)Arieti S:Affective disorders;Manic-depressive psydosis and pschotic depression;Manifest symptomatology,psychodynalnics,sociological factors,and psychotherapy.American Handbook of Psychiatry.Arieti(ed),vol.3,Basicbooks,NewYork,1974
5)Arieti S,Bempord J:Severe and mild depression:The psychotherapeutic approach.Basic Books,NewYork,1978(水上忠臣,横山和子,平井富雄訳:うつ病の心理一精神療法的アプローチ.誠心書房,東京,1989)
6)FreudS:Morningandmelancholia.Standard Edition 14;Hogarth Press,London,pp243-258,(1957/arig,1917)
7)原田憲一:器質性精神病.医学図書出版,東京,1975
8)広瀬徹也:「逃避型抑うつ」について.宮本忠雄編:繰うつ病の精神病理2,弘文堂,東京,1977
9)広瀬徹也:精神疾患におけるcomobidity概念の成立.精神経誌99:942-949,1997
10)飯田眞,松浪克文,林直樹:うつ病の状況論.大熊輝雄編:躁うつ病の臨床と理論.医学書院 東京 1990
11)Judd LL,Rapaport MH,Paulus MP et al:Subsyndromal Symptomatic Depression:A New Mood Disorder ? J Clin Psychiatry 55(suppl 4);18-28-1994
12)金杉武司:フォークサイコロジーと消去主義.2000信原幸弘編:シリーズ心の哲学一人篇.勁草書房,東京,2004
13)笠原嘉:各科を訪れる可能性のあるデプレッション.心身医24:6-12,1984
14)松浪克文:秩序指向性と反復,imago2.青土社 東京 pp67-75,1991
15)松浪克文,大前晋,飯田眞:心理,病態.臨床精神医学講座4,気分障害.中山書店,東京 pp61-88,1998
16)松浪克文,大前晋:内因性うつ病とパーソナリティー現代型うつ病(恐怖症型うつ病)と分裂気質者の呈する内因性うつ病像-.精神科治療学14:729-738,1999
17)松浪克文,大前晋:気分障害の精神病理一最新の知見-.臨床精神医学29:843-852,2000
18)松浪克文,熊崎努:現代の中年像.精神療法27:107-117,2001
19)松浪克文:うつ病の概念を考える:「神経症性うつ病」という概念の行方.精神科治療学17:1975969-978,2002
20)松浪克文:精神病理学の立場から.うつ病研究の方向を求めて.上島国利,樋口輝彦・野村総一郎編:今日のうつ病一治療と研究への最新アプローチ.アルタ社,2004
21)宮本忠雄:噪うつ病における混合状態の意義.臨床精神医学21:1433-1439,1992書院,東京,1990
22)西園昌久:精神分析理論.飯田眞編:躁うつ病.国際医書出版,東京,pp531-544,1983
23)Sadock BJ,Sadockv A:Kaplan&Sadock’s Comprehensive Textbook of Psyehiatry seventh 28,1994 edition on CD-ROM.Lippincott Williams&WilkiDs,2000
24)Schulte W:Studien zur Heutigen Psychothepie.Quelle&Meyer,Heidelbeg,1964(飯田真,中井久夫訳:精神療法研究.岩崎学術出版社,東京 1994
25)World Health organization:The ICD-10 Classication of Mental and Behavioural Disorders.Clinical description and diagnostic guide lines,1992(融道男,中根よし文,小見山実:ICD-10pp61-88,1998精神および行動の障害.臨床記述と診断ガイドライン,医学書院,1993)
「意識の探求」第一章-2
アリゾナ大学ツーソン校の、哲学者デービッド・チャルマーズ(David Chalmers)は、意識についてまた別の説を唱えている。チャルマーズは、情報には二つの側面があると主張している。
一つは、コンピューターの中で見られるような、物質的、物理的に実現可能で、外部から観測可能な側面。
もう一つは、現象論的、経験的な、外部から観測することができない側面である。
チャルマーズの世界観では、自動温度調節器から人間の脳に至るまで、どんな情報処理システムも、少なくともある基本的な意味で意識を持っていると考える。たとえ自動温度調節器になることができたとしても、たいした意識を持つことはできないだろうと、チャルマーズ自身認めているが。情報の二面性を考えることで、自動温度調節器から人間の脳に至るまで、情報を表わすシステムすべてに意識があると考えることができる、という彼の大胆な提案は、すばらしく簡潔で格好いい理論であり、私自身、非常に惹かれるものがあるのを認めている。しかし、どうやったら、チャルマーズの仮説を科学実験によってテストできるか、私には見当もつかない。今のところ、この現代版「汎心論(pan-psychism)」は実験によって反証されることがないため、単なる信仰の問題、信じるか信じないかのお話になってしまっている。しかし、時間が経てば、確率論や情報理論を基礎にしたチャルマーズの理論のようなものが、意識を理解するのに必要であったということが明らかになるかもしれない。仮に、チャルマーズの定性的な枠組みが受け入れられたとしても、より定量的な枠組みが作られなければならない。具体的で重要な疑問としては、次にあげるようなものがあるだろう。同時平行(パラレル、parallel)に情報処理する脳のようなシステムと、系列的(シリアル、serial)に情報処理をするコンピューターのようなシステムでは、それぞれのシステムが持つとされる意識はどちらが高度なのか。主観的経験の豊富さは、記憶、メモリの容量の大きさに関係するのか。脳のように、いろいろな場所に分けて情報を保存する形式ほうが、一カ所に集中させるより、経験は豊富になるのか。普段我々がものごとを思い出すときのように、一つのことを思い出すとそれに関連したことが自動的に思い出されるシステムでは、意識はより鮮明になるのか。いくつかの情報処理システムが記憶情報を共有したほうがいいのか。記憶は階層的な処理や保存がなされたほうがいいのか。また、記憶の担い手は安定した物質的実体を持つもの(コンピューターで言えばハードディスク、脳で言えばシナプスの形や細胞のつながり具合)と、一時的だがアクセスの早いもの(RAMや神経の活動電位のようなもの)とでは、どちらがより意識を生み出すのだろうか。
*現代版「汎心論(pan-psychism)」には反証可能性がない。
意識が脳から生まれてくる過程を説明するために、今まで発見されている物理法則以上の、根本的に新しい法則が要求される可能性はなきにしもあらずといえよう。しかし、私はそのような一歩を今すぐ踏出さねばならないとは思わない。
*踏み出した人たちはあまりスマートではないのが残念ながら現状である。
意識を持つには行動が必要だ現実には、神経系を肉体から切り離すことができないという事実を強調するのが、意識の行動説(enactive account、別名、感覚運動説 sensorimotor account)を唱える学者達である。ある場所に適応して住みついた動物種の身体の一部に神経系が存在する。そして、生きている間に起こる感覚入力から運動出力までの無数の相互作用を経験していく中で、自分の身体を含んで、世界がどう成り立っているのかを脳は学んでいく。こうして学んだ知識は、生きているうちにぶつかる様々な困難を乗り越え、種を保存するのに役立っている。意識の行動説の主張者たちは、脳が知覚をサポートすることを認めるが、神経の活動だけで意識が生じるわけではない、神経活動は意識が生じるためには十分でないと主張する。さらに、意識の物質的な原因や相関を捜す研究は役立たないとまで主張する。そのような脳中心の見方ではなく、特定の環境に適応して行動をとっている動物種に生じる「感覚」というものが重要だとしている。
*enactive accountは、かなり正しいが、意識の問題までは届かない。
知覚が生じるのは、一般に、動物が何らかの行動をとる時である、と行動説を唱える人々は強調している。そのこと自体は非常に的を射たものではある。しかし、彼らの、知覚がどのように脳内の神経活動から生まれてくるのかという問題を軽視している態度には、私は全く共感することができない。ある生物が意識を持つためには、その生物の脳内にある種の神経活動が起こらなければならないし、逆にそのような活動が起これば、生物は意識を持つに至る、というのは科学者が合理的な確信をもって言えることである。ある種の脳内活動さえあれば意識が生じるということは、実証的に支持されている。例えば、夢を見ている間、主観的には、起きて活動しているときのように、物を見たり感じたりするという意味での意識があるわけだが、それでもほぼすべての髄意筋が抑制され動かなくなっている。すなわち、毎晩、ほとんどの人は、動くことができないにもかかわらず、脳の活動だけによって、現象論的な(phenomenal)感覚を経験している。また、電気的もしくは磁気的なパルスを使って、脳のニューロン群を直接に刺激すると、もちろん、被験者は全く動いていないにも関わらず、色のついた光のフラッシュなどの単純な知覚が感じられる。この現象を基に、外部の視覚情報を電気刺激のパターンに変えることで、目の不自由な人に視覚経験を直接引き起こす、神経補助具(neuroprosthetic devices)の研究が盛んに行われている。さらに、神経疾患のせいで全く動けなくなってしまったたくさんの不運な患者たちも、どうやら我々と変わらない意識を持っていることも挙げられる。神経疾患の1つ、睡眠発作(narcolepsy、ナルコレプシー)の患者は、一過性の全身麻痺に掛かることがある。極度の笑いや当惑、怒りや興奮などの感情が引き金となって、患者は急に骨格筋の緊張を失って全身麻痺の状況におちいるが、このとき意識を失わない。また、数分間も続く極度の脱力発作(cataplexy、カタプレクシー)におちいると、患者は床に倒れたまま全く動けず、周囲に発作を知らせることもできないが、患者は周囲の状況を完全に把握し、意識をしっかりと持ち続ける。このような、一時的に全く動けなくなってしまった患者だけでなく、一生動けなくなってしまった患者もまた意識を持ち続ける。最もドラマティックな症状は、ロックットイン・シンドローム(閉じ込め症候群、locked-in syndrome)だろう。フランスのファッション雑誌エル(Elle)の編集者、ジーン=ドミニク・ボービー(Jean- Dominique Bauby)のケースを紹介しよう。ボービーは重度の脳卒中の後、上下に目を動かす以外、全く動けなくなってしまった。彼は目の動きをモールス信号のかわりに使って、彼が何を感じ、考えているかを書き綴った本を出版した。もしも、上下の目の動きすらできなくなって、周囲の人々と交信が取れなくなってしまったら、ボービーは、完全な意識をもちながら、人々から死人とみなされるはめになっていたことだろう!彼のようなロックトイン・シンドロームの患者の系統的な研究はまだなされていないが、見ためは全く普通の人々と変わらないようだ。私が第7章でとりあげる、「凍った麻薬常用者(Frozen addicts)」もまた、長期間、全く動けなくなってしまった人の意識をしめす一例である。
*
以上のことから、外部出力としての行動は意識に必要ではない、と私は結論づける。もちろん、体、目、手足などの運動が意識を形作っていくときに重要でない、というわけではない。実際、非常に重要なものだ! しかし、上の例が示しているように、体の自由がきくことが、意識を持つために必要なわけではない。体が全く動いていない状態で、夢を見るし、直接の脳刺激によって感覚は生じるし、動けない患者も意識をもっているのである。
*自意識がどのように形成されるかということと、形成されたあと、どのように振る舞うかということとは、別のことだと思う。
意識はある種の脳内のニューロンから生じてくる特性(Emergent Property)である
この本の作業仮説は、脳内のニューロンがもつ特徴から意識が出現する(emerge)ということである。意識の物質基礎を理解するには、恐らく、今までになかった新しい物理法則を導入する必要はないだろう。むしろ、非常に多くの異なる性質を持ったニューロンが混じりあい、更に、それぞれが、相互に複雑に連結したできたニューラル・ネットなるものが、どのように作動するかについての、今現在以上の、はるかに深い洞察が求められるだろう。環境との相互作用および自己の内部の活動を基にして学習していく、ニューロンの集合体(coalition)の持ちうる機能は、通常過小評価されている。個々のニューロンそれ自身ですら、ユニークな形態を持ち、何千もの入出力を備えた、複雑な実体である。それらの相互連結、シナプス(synapses) は、非常に手の込んだ分子機械である。シナプス連結部には、長短様々な時間スケールにわたる、情報伝達効率を調整する仕組みが備わっていて、学習を可能にしている。人類はかつて、そのような何千億もの複雑な個々の要素が、何千もの入出力によって複雑な絡み合っているような組織を相手にした経験がないのだ。それ故、生物学者さえもが、神経系の特性やその最大限の力を理解するのに苦労している。
*emergeというのは、ずっと昔から、emergence theory 創発説と呼ばれているものである。上の解説でも述べられているように、新しい原理や物理法則は必要とされない。かつては、「量が質に転化する」、複雑さがある点を超えると、休息に質的変化を起こすなどと説明された。あまり説明になっていないので、見込み唯物論などと揶揄されていた。
この意識問題を巡る現在の状況は、20世紀初頭にピークを迎えていた、生気説(vitalism)および遺伝のメカニズムに関しての激論に類似している。ただの化学物質が、それぞれユニークな個人の特性を決定するために必要な情報をすべて貯蔵できるなどと、誰が想像できただろうか? 二細胞期の蛙の胚は、二つに分割されると二匹のオタマジャクシになるが、そのメカニズムが後に化学によって説明されるなどとは、誰が予想できただろうか? エルヴィン・シュレディンガー(Erwin Schrödinger)が考えていたように、これらの事柄を説明するには、ある生気説的な力(vitalistic force)、もしくは、新しい物理法則が必要なのではないかと、多くの科学者達は考えていたのではないか。個々の分子それぞれに固有の特異性が、想像を絶するレベルのものであったために、当時の研究者たちには、生命という現象が、不可解なものに映っていたのだった。この事実は、英国20世紀初期の遺伝学におけるリーダーの一人、ウィリアム・ベイトソン(William Bateson)からの引用が何より雄弁に語っている。ノーベル賞受賞者トーマス・ハント・モーガン(Thomas Hunt Morgan)および彼の共同研究者による『メンデルの法則の遺伝のメカニズム(The mechanism of Mendelian Heredity)』、についての1916年の評論のなかで、ベイトソンは次のように述べている:
*
生物の特性は、何らかの形で物質的基盤、恐らく、特に核染色質に、基づいたものだろう。しかし、どれだけ複雑であろうと、染色質や他の物質の微粒子に、我々の遺伝情報を保持する力があるとはとうてい考えられない。異なる生物同士の染色質は、互いに判別不能で似通っているし、これまでに知られている全てのテストにおいて、どの生物の染色質も化学的にほとんど均質であるということが分かっている。この似たり寄ったりの染色質に、それぞれの生物が受け継いで来た高度に特殊化した遺伝情報が備わっている、という仮説は、一般科学者に最も受け入れられている唯物論の範疇をも超越している。
*
当時の最先端の科学技術をもってしても、ベイトソンや他の科学者達には分かっていなかったことがあった。染色質、すなわち染色体は、統計的に考えた場合に限れば均質、つまり、大雑把に言って等量な4つの塩基から構成されている。だが、塩基の正確な一次元配列こそがまさに遺伝の暗号化の秘密だったのである。遺伝学者たちは、これらの塩基が巨大な量の情報を蓄えることができるなどとは思わなかった。また、当時の遺伝学者たちには、それぞれのタンパク質分子が持っている驚くべき特異性を知る由もなかった。分子生物学の発展によって、まるで「鍵」と「鍵穴」のように、それぞれのタンパク質分子はある特定の分子を認識できることがわかった。この特異性によって、シナプスでの複雑な情報伝達や免疫系などの働きが支えられている。このタンパク質の特異性は、数十億年間にわたる自然淘汰の過程で進化して生まれて来たものであり、我々の想像を絶するほど複雑かつ精緻な生物学的なシステムになっているのである。物質からどのようにして意識が生まれてくるかを探究をする上で、脳という生物システムがもつ驚くべき特異性や能力を過小に評価してはならない。我々は、同じ誤りを繰り返すべきではない。
*
私が本書で主張する仮説とは、意識は、脳の中での非常に複雑な相互作用から「生まれてくる特殊な性質」(emergent property)であるというものだ。すなわち、意識は脳の中の多数のニューロンの相互作用、あるいはニューロン内部に存在するカルシウムイオンの濃度などの相互作用さらには活動電位の相互作用といった、物理的現象が複雑に相互作用することで生まれてくるのだ。意識のメカニズムは物理学の法則と完全に両立しているものの、これらの法則から意識がどのように脳から生まれてくるかを完全に理解するのは容易ではない。
*現代版創発説のようだ。
1.3 我々のアプローチは、実用的で、経験主義的なものである。
*
細かい論争に気をとらわれることなく、困難な問題に向かって前進していくためには、十分な根拠を示さずに、いくつかの前提をもうけなければならない。暫定的な作業仮説は、頻繁に修正され、時には、後で否定されるべきものかもしれない。物理学者から転身した分子生物学者、マックス・デルブリュック(Max Delbruck)は、実験のためには、「適度ないいかげんさの原理(The Principle of Limited Sloppiness)」が効果的だと主張した。ある仮説がうまくいくどうか、急場しのぎのややいい加減なやり方で試すのがいい、という原理である。脳と意識について考える時にもこの原理を適用しよう。
*
作業(仮説的な)定義「意識」とは何を意味するか、ほとんど誰もが何らかの定義を持っている。哲学者ジョン・サール(John Searle)による意識の定義は、「意識(consciousness)は、感覚(sentience)、感情(feeling) 、気付き(awareness)から成り立つ。意識は、朝我々が夢を見ていない状態の睡眠から目覚めた時にはじまり、昏睡状態に陥ったり、死んでしまったり、再び眠りに落ちたり、その他の方法で無意識にならない限り、その日一日中続く」というものである。 「何が見えますか?」と聞かれて、ボタンを押したり、口で説明したりしてちゃんと答えられるのであれば、今のところ、我々はその人に「意識がある」とみなす。ここでの「意識がある」という状態は、サールのいう、朝から始まり眠るまで続く意識に近い。意識があるとみなされるには、なんらかの注意力(アテンション、attention)も要求されるが、それだけでは十分でない。ここで、更にもう一歩踏み込んだ、科学実験にも耐えるような定義を設けよう。その定義とは「数秒以上情報を維持することが必要とされる、普段慣れていないことを行うことができること」である。そのためには、『意識』が必ず必要である。例えば、読書したり、喋ったりするときには、短期的に何が話題になっているかが頭になければならない、意識しなければならない。この命題が正しいか間違っているかは、科学的な実験を通して、これから検証していくべきものである。
*ジョン・サール(John Searle)による意識の定義なんか考えてみても、あまり意味はない。意識の中身として、attentionやvigilanceがいわれるが、まあ、そうですかというだけでいいだろう。
かなり曖昧であるとはいえ、この仮の定義は、研究を始めるには十分なものである。実験に基づいて、意識の理解が進むにつれて、意識の定義は、新たな知見をとりいれて、より精密な表現へと洗練されていくべきだろう。例えば、意識とは、ある特別なニューロンの集合体が、なんらかの発火パターンを示したときに生じるものだ、など、現時点では想像もつかないような意識の定義になるかもしれない。ところが、現時点で形式的で厳密な意識の定義を作ろうとすることには意味がない。むしろ、誤解を招いたり、必要以上に厳しい定義のせいで、意識の問題の本質を見失ってしまう恐れさえある。例えば、生命とは何か、という問題に対して、ウイルスを生命とみなすべきかどうかにこだわっていたならば、DNAという生命の本質に近付けなかっただろう。それでもまだ、厳密な定義にこだわらないという我々の姿勢が「ごまかし」のように思えるのであれば、「遺伝子(gene)」という語を厳密に定義しようとしていただきたい。実は、遺伝子の定義はいまだに非常に困難なのである。遺伝要素を伝えるひとかたまりのDNAが遺伝子であるという定義で十分だろうか? 単一の酵素を暗号化しているものが遺伝子なのか? 構造遺伝子(structural genes) や、制限遺伝子(regulatory genes)は、どう扱われるべきか?核酸の1つの連続している部分(segment、セグメント)に相当するものを遺伝子とするべきだろうか? イントロン(無意味な塩基配列。その機能が本当に無意味かどうか、現在も分子生物学では議論が分かれている)は遺伝子なのだろうか? ひょっとすると、DNAからメッセンジャー RNAまでに至る、すべての分子編集作業とスプライシングが終わった後の、成熟した状態のものを、遺伝子と定義したほうがいいのではないか? 非常に多くのことがわかってきている今でさえ、単純に遺伝子を定義しようとしても、どうしても不十分なものになってしまう。我々が現在理解している範囲で、意識のような捉えがたいものを定義すれば、もっと不十分なものになってしまうだろうということは火を見るよりも明らかである。
*厳密な意識の定義はたしかに、今のところ、不必要である。たとえば、生命とは何かなんて定義しても、あまり意味はないのと同じである。中身を研究した方がいい。中身の研究が出来ないから、意識とは何かなどと言って、報告しようとするのだろう。
歴史を振り返ってみれば、重要な科学の進展が起こるときには、往々にして、格式ばった厳密な定義がないことが多い。例えば、オーム、アンペールおよびボルタによって、電流現象についての法則は公式化されていたが、それは、トムプソン(Thompson)が1892年に電子を発見するずっと前の話である。したがって、当分の間、私は、上で述べたような一応の定義を使って、意識の研究を行なっていくことにする。この定義がどこまで通用するのか、科学的に検証していくとしよう。
*
意識は人間に特有ではないある種の動物、特に哺乳類には、意識があると考えるのは妥当だろう。ただ、我々が持つ意識の全ての特徴を兼ね揃えているわけではないだろう。他の動物にも、人間とあまりかわらない、視覚、聴覚、嗅覚、その他の知覚経験があるだろう。もちろん、それぞれの動物種は、生態的地位(ニッチ、niche)に適応した、特別な知覚感覚器官を持っており、コウモリなどは超音波を感じる器官を持っている。そういう特殊な感覚も含めて、実際には様々な動物がどんな感覚、クオリアをもっているか、我々には直接知るすべがないことは認める。しかし、私は動物が感覚を持ち、それ相応の主観を持っていることは明らかだと仮定する。動物の感覚や意識を認めないという立場は、思慮の足りない推測にすぎないし、様々な実験事実に反している。ネズミからサル、そして類人猿、人間までの動物種の間には、進化やDNAという証拠や行動学的な研究によって、つながりがあることがわかっている。我々人間を含めた動物は、共通の祖先をもち、進化の過程を経て大自然の中で生き残ってきたのであって、人間だけが意識や感覚を持っているという考えは間違っている。
*こんなことをくどく言うのは、聖書との関係があるから。
猿や類人猿と人間は、行動や発育過程が非常に似ており、脳構造については、非常に類似している。その道の専門家でなければ、1ミリ立方メートルの脳組織が、サルのものか人間のものか区別できない程だ。実際、最先端の脳科学では、入力刺激と意識の関係を調べるときには猿を使っている。覚醒し行動している猿の脳に、電極を埋め込み、ニューロンの活動と猿の意識の関係が調べられている。こういった研究を行う場合には、もちろん猿と人間との類似性に留意して、倫理的な配慮がなされている。猿を使った適切な動物実験は、意識の基礎となるニューロンメカニズムを発見するのに不可欠である。
*
もちろん、動物と人間との言語能力の違いは明らかである。言語によって、人間は、非常に複雑な概念を表現し、他者に自分の意図を伝えられるようになった。書物、デモクラシー、一般相対性理論、マッキントッシュコンピューターなどは、言語を用いて作られたものだ。他の動物にはこのような発明ができない。文明生活においては、常に言語が生活の中心となっているため、哲学者や言語学者、また他の分野の人々は、「言語の無い動物には意識を持つことができず、人間だけが、感覚を持ち自分に意識をむけることができる」と信じてきた。自意識、つまり、「私が赤い色を見ていることを、『私』が知っている」、というときの『私』のようなものについては、言語無しでは、たしかに成り立たないかもしれない。しかし、言語を持たない哺乳動物にも、見たり聴いたりするときのクオリアがあるとする説は、分断脳(split-brain)患者や自閉症の子供の臨床研究、進化論的な比較研究、動物行動学などから導かれる結論と合致している。動物が何らかの感覚を持っていても不思議ではないが、すべての動物に共有されている意識的な知覚は、どの程度のものものなのか現在わかっていない。のどの渇きのような比較的簡単な感覚だけは他の動物も同じように感じているのだろうか? 自意識のような高度な意識を他の動物は持っているのだろうか? ただ、神経系の複雑さと、その種の持つであろう意識レベルはある程度相関があると思われる。イカ、ハチ、ハエ、線虫ですら、非常に複雑な行動を取る。恐らく、これらの種にも、ある程度の意識があって、苦痛も感じれば、快楽をむさぼったり、何かを見たりしているのだろう。
*「言語を持たない哺乳動物にも、見たり聴いたりするときのクオリアがあるとする説は、分断脳(split-brain)患者や自閉症の子供の臨床研究、進化論的な比較研究、動物行動学などから導かれる結論と合致している。」そんなはずはないのであって、「クオリアがある」ことを、外側からの観察で証明することは無理だといっていたはず。
*この人は、一般人の質問しそうなことに答えすぎている。
どうやって意識を科学的に研究するのか?一口に意識と言っても、意識には多様な種類があるが、最も取り組みやすい意識、視覚的意識から研究を始めるのが最善だろう。意識がどう脳から生じるかを実験によって探究していく上で、視覚研究は、他の感覚を研究するときと比べて、少なくとも四つほど有利な点がある。
*
第一に、人間は視覚的な動物であるということがあげられる。視覚イメージの分析には大量の脳組織が割り当てられており、人間の生活において視覚は非常に重要である。他の感覚と比較してみよう。例えば、あなたが風邪をひいたら、鼻が詰まって、嗅覚を失ってしまうかもしれないが、被害は限られている。ところが、雪盲になるなどして、たとえ一時的にでも視覚を失えば被害が甚大なのは明らかだろう。第二に、視覚は他の感覚に比べ、鮮明でかつ情報が豊富であることがあげられる。絵や映画などの入力刺激は、コンピュータ・グラフィックスを使うことで、操作したり、高度に洗練したりしていくことが容易である。第三に、無限と言ってもよいほどに、次々と発見され、報告されてくる新しい錯覚を使うことで、直接に視覚経験を操作することができる。Motion-Induced Blindness(運動よって引き起こされる消失錯覚, 略してMIB)を例に取ろう。 http://questforconsciousness.com/conscious.html を参照画面上には、三つの非常に目立つ静止した黄色い点がある。その周りをたくさんの青い小さな光点がでたらめに動いている。画面上のどこでもいいから目を動かさないようにして見つめてみよう...しばらくすると、1つ、2つ、あるいは、3つの黄色い点すべてが消えてしまうはずだ。なんと! あなたはこれをみたら絶対に驚くだろう。まるで、青い点からなる雲が動くにつれて、黄色の点を本当に拭きとりさってしまうかのように意識から消えてしまうのである。黄色い点は網膜を刺激し続けているにも関わらず...ちょっと目を動かすと、黄色い点は再び現われる。こういう視覚現象は、哲学者が重要視している「意志 (intentionality)」や、「志向性(aboutness of consciousness))、「自由意志(free will)」、またその他の哲学上の重要概念に、直接関係はないかもしれない。しかし、このような錯覚が、どのように脳内のニューロン活動によって引き起こされるのかが理解できたならば、意識一般が、物質である脳からどのように生じてくるかについて多くのことが分かるようになるかもしれない。分子生物学の初期に、マックス・デルブリュック(Max Delbruck)は、ファージという、バクテリアを捕食する単純なウィルスの遺伝子に注目していた。もしも、あなたが、当時の科学者であったなら、単純なファージの遺伝メカニズムなど、複雑な人間の遺伝と無関係だと思っただろう。しかし、大方の予想とは裏腹に、ファージの研究は、生物一般の遺伝メカニズムを解明するに当たって、重要な鍵となったのである。同じ様なことが、記憶のメカニズムを探る脳科学においても近年確認された。エリック・カンデル(Eric Kandel)は、進化レベルの低い、簡単な生物が記憶する仕組みを研究することで、人間の記憶を支える分子メカニズム、細胞メカニズムについて多くのことがわかるのでははないか、と長年信じていた。カンデルは 、アプリシア(Aplysia)という海カタツムリの記憶の仕組みを明らかにしたのだが、その後の研究により、確かに、より高度な動物における記憶の仕組みについても同じ原理が成り立っていることがかってきたのである。つまり彼の確信は正しかったのだ。
*optical illusionで検索すると、錯視がいくつも見られる。不思議。
最後に、多くの視覚現象や錯視を引き起こすニューロン活動研究が様々な動物種を使ってなされてきた、ということが視覚の研究が意識を解明するためのアプローチとして有効である理由である。このような幅広いニューロンレベルでの研究の蓄積があるおかげで、視覚神経科学は非常に進んでおり、どの実験をすべきか決めたり、データを要約したりする際に、非常に役立つ精巧な計算モデルが構築されている。
*
これら四点の有利さを考慮して、私は視覚研究に専念することを選んだ。ところで、アイオワの大学の優れた神経学者,アントニオ・ダマシオ(Antonio Damasio)は、意識の中でも、感覚的な意識のことを中核意識(core consciousness)と呼び、これらを拡張意識(extended consciousness)と区別している。 中核意識とは、「今/ここ」での意識のことを指している。一方、拡張意識には、多くの人が普段「意識」と呼ぶものにあたり、自分のことを客観的に見る視点を持った自意識と、過去と未来に関する意識的感覚とが要求される。
*
私の研究計画は今のところ、自意識や過去未来の感覚をともなう拡張意識、および言語、感情といった意識の一面は捨象している。だからといって、これらが人間にとって決定的に重要でない、というわけではない。それどころか、大変重要である。失語症患者、重度の自閉症の子供、自己喪失患者などは、拡張意識に重大な障害を持つため、病院や老人ホームに閉じ込められている。しかし、こういった障害にもかかわらず、彼らは大概、苦痛を感じたり、ものを見たりといった、中核意識は保っている。中核意識と同じく、拡張意識がどのように脳から生じているのかというのは、非常に不可解で我々にとって大事な問題であることに変わりはない。しかし、拡張意識を研究するのは、動物研究においては、中核意識よりも困難である。拡張意識を動物の行動だけを見てテストする実験を考え付いたり、実際にその実験のために動物をトレーニングすることが簡単ではないので、これらの意識を生み出しているニューロン活動を観察したり、分析するのは難しいだろう。
*
私が視覚を研究の糸口として選んだのには、また他の理由もある。匂いや苦痛、視覚や自意識、自分の行動が自分の意志に起因しているという自由意志の感覚など、一口に意識といっても様々な異なる面があるが、おそらく、これら全てに共通のニューロン活動というものが存在していると思われる。もし、この仮定が正しいならば、一種類の感覚についてのニューロン基礎が理解できると、その他の意識感覚の理解は簡単なものとなるだろう。自分の意識を振り返ってみれば、この仮説は非常にラディカルで唐突にきこえる。視覚、聴覚、嗅覚の間に共通点なんてあるのだろうか? むしろ、それぞれは全く異なっているように感じられる。しかし、三つの感覚のもとには、バチバチ、ダダダ、とアンプを通して聞こえてくるニューロンの活動があるのは事実である。主観的には全く異なる視覚、聴覚、嗅覚が、同じ様なニューロン活動や回路によって、引き起こされているのだろうか?
*
本書では視覚以外の研究も紹介していく。例えば、イナゴの嗅覚システムを使った、ニューロン同士の発火するタイミングについての研究は、多数のニューロンによる同期発火が意識を生じさせるという仮説との関係で重要だ。また、ベルと餌の関係を覚えた犬が、ベルの音を聞いただけでよだれをたらす、というパブロフの条件付けの研究も、数秒以上の情報時保持には意識が必要だという、我々の仮説を確かめるのに重要である。これらの研究は、ニューロンレベルで進んでおり、将来に期待がもてる。我々の目的は個々のニューロン発火活動と意識を関連づけることなので、動き回っている元気なマウスを使って、行動から予想される彼らの意識の状態と、ニューロンの発火活動を同時に記録するような実験が必要とされる。マウスで可能な分子生物学的手法は非常に驚くべきスピードで発展していて、その力強さはとどまるところを知らない。この技術を使えば、科学者は、マウスの脳を、計画的に、デリケートに最小限のダメージしか与えず、可逆的に、操作するができるようになるだろう。しかしながら、現在の技術ではサルなどの霊長類に対して、こういった分子生物学的な手法を使うことはできない。
*
催眠、幽体離脱、夢見ていることを自覚しながら見る明晰夢、幻覚(hallucination)、瞑想などの意識変容状態(altered state of consciousness)を、本書は扱わない。これらのケーススタディは非常に魅力的ではあるが、もととなっているニューロン活動にアクセスすることが難しい(猿は催眠術にかかるのだろうか?)。しかし、包括的な意識理論は、究極的にはこれらの異常な現象も説明できなければならないだろう。
*
1.4 意識と相関するニューロン:NCC (the Neuronal Correlates of Consciousness)
フランシス・クリックと私は、NCC(the neuronal correlates of consciousness、意識と相関しているニューロン群)の発見に全力をそそいでいる。脳に入力した情報が、NCCのニューロン群に伝わり、そこでその情報が明示的にはっきりと表現されると、必ずその情報は意識にのぼる。我々の目的は、「ある特定の意識知覚を生じさせるために、最小限必要でかつ十分なニューロンの活動形式とメカニズムを含んだ最小のニューロン群を明らかにすること」である(図1.1)。NCCは前脳部のニューロン発火活動を含む。次の章で詳述されるように、「発火活動」とは、連続的なひと固まりのパルス状の活動電位のことを指している。1パルスは、約0.1V(ボルト)の電圧を持ち、0.5msec、1秒の1000分の1から2000分の1の長さにわたる。これらの2進法の活動電位(action potential 。スパイク(spike)と呼ばれることもある)は前脳部ニューロンの主な出力と考えられる。将来、ニューロンを刺激する技術が進めば、適切にニューロンを選び、正確なタイミングで、多数のニューロンのスパイクを制御するできるようになるかもしれない。もしそのような技術が実用化されれば、普段の生活の中で見る映像、聞く音、嗅ぐ匂いによって引き起こされる、多数のニューロンのスパイクのパターンを、それぞれタイミングも正確に、再現することができるはずである。その場合、人工的な直接の脳刺激による意識と、自然な入力による意識の区別はつかないはずである。この推論は、数ページ前に強調した通り、私たちのアプローチは、意識は頭の内部のものに依存し、必ずしも行動出力には依存しない、ということを前提としている。
*なるほどね。
NCCという概念は、ここで図示されているよりも相当微妙なものである。被験者の目が覚めている時に限って、相関関係が成り立てばいいのだろうか? 夢を見ている時は起きている時と同じNCCが意識を生み出しているのだろうか? 様々な病理に侵されていたり、脳に損傷があるときにも同じ原理は成り立たなければならないのだろうか? 相関関係はすべての動物に対して同じように成り立たなければならないのだろうか? このように、被験者の状況や集められたデータの精度を細かく指定した上で、ニューロンの活動形式と意識知覚の間の相関性を我々は論じなければならない。これらの複雑な問題は第5章で取り上げるとしよう。
*
私がある出来事を意識的に経験しているとき、私の頭の中のNCCが直接これを表現していなければならない、ということを「NCC」という語は暗示している。どのような精神上の出来事にも、それに相互関連したニューロン群の活動との間には、明示的な一致がなければならない。言い換えれば、どのような主観的状態の変化も、ニューロン群の状態の変化が伴っていなければならないということだ。 しかし、逆は必ずしも真であるとは限らない。すなわち、脳内のニューロンの二つの異なる状態が、主観的には判別不能なことがあるかもしれない。 NCCが、ニューロン群のスパイク活動によって表されていないという可能性もある。ニューロンが出力している先のシナプス後部樹状突起の中にある細胞内カルシウムイオンの濃度が NCCである可能性もある。 あるいはニューロンの目立たないパートナー、グリア細胞(ニューロンや脳の中の環境を支援、養育、維持する細胞)が直接にNCCに関係する可能性も、もしかしたらあるかもしれない。非常にその可能性は低いが。 しかし、NCCになっているようなものは、意識との間に直接の関係を持っていなければならない。NCCの変化は直接に意識に影響を与えなければならない。NCCと意識の間になんらかのものがあってはならない。間接的な関係ではNCCとは呼べないのである。なぜなら、NCCこそが、特定の経験のために必要とされる唯一のものだからだ。
*
NCCのニューロン群には、神経細胞内成分などの薬理学的な特徴や、細胞の形などの解剖学的特徴、細胞膜の特性などの生物物理学的特徴などの共通項があるかもしれない。そして、これらの特性を兼ね備えたある種類のニューロンの特別な神経活動が、なんらかの閾(いき)値や、最小限の持続時間を保った時に、意識は生み出されるのかもしれない。
*
14章の中で議論するように、意識は単なる付随現象(epiphenomenon)であるとは非常に考えにくい。むしろ、意識をもっていると生存に有利だと考えられる。というのは、NCCの活動は、他のニューロンになんらかの影響を与えるからである。NCCの影響によって起こる二次的なニューロン活動は、最終的には、行動を引き起こすニューロンに影響を及ぼす。その活動は、さらに、NCCニューロンもしくは一段階下のレベルのニューロンにフィードバックをあたえることで、事態をひどく複雑化させている。
*付随現象(epiphenomenon)説も昔からある。この説に属するものにもいろんなタイプがあると思うが、現代的なものは、「他のニューロンになんらかの影響を与える」部分までは全部、付随的ではないものであって、影響を与えない部分で、付随的に発生しているものが意識だとしているのではないかと理解している。
NCCの発見が成功すれば、意識の最終理解に向かって大きな一歩を踏出すことになるだろう。神経科学者は薬品を使ったり、遺伝子組み換え技術で、細胞の性質を操作できるようになるだろう。NCCのニューロン群の活動のスイッチを急速にしかも安全な方法でオンにしたりオフにしたりなどということも可能になるかもしれない。そして、遺伝子組み換えによって、行動は普通のマウスと一見変わらないが、全く主観的な意識を持たないゾンビマウスも創られるかもしれない。ゾンビマウスはいったいどんな行動ができるのだろうか?本当に意識なしで、普通のマウスと全く同じ行動をとることができるのだろうか? NCCが発見されれば、精神病について理解が進むだろうし、ほとんど副作用のない強力な新麻酔薬などの臨床応用なども考えられるだろう。ある特定のニューロンの活動という客観的に測定可能な物理現象と、それによって引き起こされる感覚、すなわちクオリアという主観的な世界との間のギャップを埋める理論が、最終的には要求される(もしかすると、主観的な世界と客観的な物理現象は、次に述べるように、同じことを違う側面からみたものだ、という結論に最終的には辿り着くかもしれない)。なぜ、ある活動がその動物にとって何らかの意味を持つのか?(どうして我々は痛みを感じなければならないのか?)なぜクオリアは、それぞれの特有な質感を獲得するのだろうか? 例えば、なぜ、赤はあの「赤い感じ」であって、「青い感じ」と全く異なるのだろうか、といった疑問を、最終理論は理解可能な形で答えなければならない。
*
そこまでの理解に辿り着くまでには、物質的なニューロン群の活動と、精神的な心の中での出来事との精密な関係を取り巻く、重大でややこしい議論を解決しなければならない。物理主義(physicalism)は、この二つ、物質的側面と精神的側面は同一であると主張している。すなわち、紫の知覚表象のためのNCCこそが紫の感覚であり、何も他に必要ではないというのだ。物質的側面が微小電極によって測定されている一方で、精神的側面は脳によって経験される。例えて言うならば、空気の温度とたくさんの空気分子がもっている運動エネルギーの平均値との関係のようなものだ。前者が温度計で記録される巨視的変数である一方、後者は微視的変数である。測定には全く異なった研究道具が用いられるが、二者はあるひとつのものごとを、異なる手段で観測されるそれぞれの側面である。たとえ表面的に全く別個に見えても、温度は分子の平均の運動エネルギーと等価である。分子が速く移動するほど、温度はより高くなる。あたかも片方が原因で他方が結果であると考えるわけにはいかない。というのは、片方が他方の必要十分条件となっているからである。
*
現時点では、NCCとそれに対応した感覚に、この種の強い同一性が当てはまるかどうか、私には確信が持てない。本当に、主観的な意識と、客観的な神経活動は、異なる観点から観測される同一のものなのだろうか? 脳内で観察される物理的な現象の特徴、すなわちニューロンの電気化学的な活動と、主観的な我々の感覚、クオリアは、あまりにもかけ離れていて、関係があるのかわからないほどであり、科学法則をもって、物質から意識に至るまでを順に説明するのは、一見、不可能だとも思える。脳内のニューロンの活動と、それに対応した主観的な現象との関係は、哲学者たちが伝統的に考えていたよりもはるかに複雑なのではないだろうか。今のところ、この問題については、様々な解決法があるかもしれないという心構えで、意識と深い相関関係がある脳内ニューロン活動、NCCの正体を暴くことに専念するのが、我々のとることができる最善の心脳問題へのアプローチだろう。
*
1.5 要旨の繰り返し
意識がどうやって脳から生じるのかという問題は、心脳問題の中心であり、最重要問題である。21世紀の学者にとっても、この問題は、人類が何千年前かに初めて思いをめぐらせた時から依然として、大きな謎のままである。しかし、この問題に取り組むにあたって、人類の歴史の中で、今日の科学者は最も恵まれている状況にある。今こそ、意識の問題に科学が立ち向かうべきなのである!
*
私のアプローチは、動物にも我々と同じような意識が存在し、視覚をはじめとして、聴覚、嗅覚、自意識などはおそらく同じようなニューロン活動がもとになっているだろうと仮定するところから始まる。同僚の多くは、私のアプローチについて、素朴過ぎるとか軽率だと考えているようだ。私は主観的な経験を明白に存在するものであると認め、ある種の脳内のニューロンの活動が、地球上の生物がクオリアを感じることの必要十分条件である、と仮定している。生物の体は、実際に行動を起こして、外界に働きかける時に必要であるが、意識を持つためには一切必要ではない。我々は、ニューロンの細胞体の中、およびニューロン同士のつながり方、集団としての活動形態の中に、主観的に感じられる意識現象を生み出している仕組みを発見しようとしている。この意識を生み出す特定のニューロン活動の性質、NCC、すなわち、意識と相関があるニューロン群の活動、そしてそのNCCが何処にあり、何であるか、これらを明らかにし、そして、どの程度までNCCと、無意識に行われる行動を支えているニューロン活動とが異なるのかを決定することが我々の目指している意識研究である。
*
他の感覚よりも、視覚感覚は科学的な実験研究を行いやすいので、知覚の中でも、とりわけ視覚に焦点ををあてて研究がなされている。もちろん、感情、言語、自意識、および他の意識は、日常生活にとって重大であるが、これらの意識については将来に残して、これらがどのようにニューロンの活動から生じてくるかがよりよく理解される可能性が高まるまで待つのが良いと思われる。我々人類の遺伝の仕組みが明らかになったときと同じように、鮮明で具体的な視覚意識に対応するNCCを構成する分子のはたらきや、活動電位やカルシウムイオン濃度などの生物物理・神経生理学的な仕組みを発見し特徴を決定づけるのが重要である。恐らくそこから解決の糸口が見つかって、「ある特別な物理的システムに起こる出来事、すなわち、脳内の電気化学的活動が、どうして感覚を生み出せるのか? もしくは、脳の活動は、感覚それ自体を別の面から観測したものにすぎないのだろうか?」という心脳問題の中心的な謎を解決する方向へと一歩ずつ近付くことになるだろう。
*
人間だけが意識を持っているという信仰は、進化は徐々に進んできたものであって、我々は単独に創造されたものではないという事実に反している。人間の心と、動物の心、特に猿やマウスなどの哺乳類の心には、いくつかの根本的に共通したものがあるはずだ、と私は仮定する。また、私は意識を正確に、厳密に定義しなければならないという、こまごまとした議論や、脊髄には意識があるが私にはそれがわからないだけだ、というような意地悪な議論も無視して議論を進めていく。これらの問題はそのうち答えられなければならないが、今日の時点では、こういう議論は単に意識研究の進展を妨げるだけだろう。戦争に勝つには、最も骨の折れる戦いを最初からしてはならない。
*
歴史上、最も人類を悩ませてきたこの意識の問題を解こうという試みの中では、大失敗や、過度の単純化が起こるということも考えられるが、それは時間が経ち研究が進むにつれて分かってくることだろう。今のところ、科学はこの難問に立ち向かい、脳からどのように意識が生じてくるかを調査するべきだ。登山家の気分に喩えるならば、雪で覆われた壮麗な山頂部が見えかくれしていて、いてもたってもいられず、早く最初の一歩を踏出したい、そんな気分である。我々はこの難問の魅力に抗うことはできない。その昔、老子が言ったように、「千里の道も一歩から」。さあ、一歩目を踏出すのです!
*
わたし達の長い旅はいま始まった。この長い探究の道を導く重要な概念をまず紹介しよう。そして、明示的(explicit)VS 暗示的(implicit)なニューロンによる表象、エッセンシャルノード(essential node)、様々な形式での神経活動の概念については特に具体例と共に示していくとしよう。
*それがいい。正しい方向だと思う。
「意識の探求」第一章-1
意識の探求―神経科学からのアプローチ (上) (単行本)
クリストフ・コッホ (著), 土谷 尚嗣, 金井 良太
第1章
*
意識研究入門
*
意識の問題があるから、心脳問題(精神物質二元論、the mind-body problem)はとても難しい。しかし、意識の問題がなければ、心脳問題は全然面白くない。ところが、意識の問題は、絶望的に難しいと思われる。
トーマス・ネイジェル(Thomas Nagel)「コウモリになるとはいったいどういうことか?」より
*Nagel, T. “What is it like to be a bat?” Philosophical Rev. 83:435–450
(1974).これは懐かしい論文。しばらく机の上にあったと思う。当時は話し合う相手もいなくて、この方面では結構孤独だった。引用回数の多い論文ではないかと思う。
トーマス・マンの未完の小説「詐欺師フェーリクス・クルルの告白」に登場するカカック教授は、ヴェノスタ侯爵に対し、世界の創造における基本的で謎に満ちた三つの段階について述べている。第一段階ではなんらかの物質、すなわち宇宙そのものが「無」から創造された。第二段階では、生命が、無機物、すなわち、生命のないものから生まれてきた。第三段階では、有機物から意識(consciousness)および意識をもった動物、すなわち、自意識を持ち、自分自身について考えることができるような動物が誕生した。人間や、少なくとも何種類かの動物は、光を検知し、そちらに目を向け、それ以外の行動をとる時に、こういった行動や状況に伴って、光の「眩しさ」等の主観的な「感覚(feelings)」をもつ。我々は、この意識誕生という、驚嘆すべき謎を説明しなければならない。意識の問題は、いまでも科学に基づく世界観が直面している重要な難問のひとつである。
*三つの謎のうち、第二段階の、無機物から生命が誕生したことについては、完全ではないけれど、説明がつくようになってきた。これはやはりすごいことだ。
*第一段階については、全くの、謎。見たこともない。
*第三段階については、どうにか説明できないかなあと思うが、これも、謎。
*宇宙創造は、我々の身辺で見かけることではないけれど、赤ん坊がだんだん人間らしくなるところなら、みんな目撃している。意識のない有機物から意識のある有機物へ、連続した変化であり、我々のほぼ全員に起こる。宇宙の歴史に中で一回起こったことではなくて、毎日起こっていることなのだ。何とか説明できそうな気がする。
1.1 我々は何を説明すべきか?
*
有史以来、我々人間は、「私たちは、一体どうやって、見たり、匂いをかいだり、自分を顧みたり、記憶を蘇らせたりしているのだろう」、という疑問を持ち続けて来た。これらの感覚はどのように生まれてくるのだろうか? 意識的な精神の働きとその物質的基盤、すなわち、脳内での電気化学的な相互作用との間には、どのような関係が成り立っているのだろうか? それが心脳問題の最も根本的で中心となる問題である。 ポテトチップスのあの塩気の効いた味、ぱりぱりっとした食感。高山に登ったときに見えるあの空の濃青色。最後の安全な足場から数メートル上の絶壁で、わずかな手がかりにしがみついているときの、手の感触、ぶらりとした足の感覚、それらからくるスリル感。一体、これらの感覚は、どのようにして、ニューロン(神経細胞、neuron)のネットワークから生まれてくるのだろうか? こういった感覚、知覚の質感は西洋科学、哲学の伝統において、クオリア(qualia)と呼ばれてきた。クオリアとは普段我々が「意識」という語で指す事柄の中でも最も原始的な「感じ」、質感である。クオリアの種類やその強弱は、それを直接感じている本人にしか厳密にはわからないところがポイントである。数日間断水させられた人が、水を飲むことを遂に許されたとき、彼の喉の渇きのクオリアが弱まることは第三者にも想像できるが、実際の彼の喉の渇きのクオリアがどの程度かはわからない。普段あなたがコンピューター画面上にある黄色い点を見るときは、強烈な黄色いクオリアを感じるだろう。ところが、後で紹介するようなある種の錯覚が起こる条件下では、この黄色いクオリアを引き起こす同じ黄色い点も、クオリアを引き起こすのに失敗してしまう、つまり、黄色い点が消えてしまうことすらある! もちろん、錯覚がおこるような条件にさらされていない第三者の目には、同じ黄色い点はやはり黄色のクオリアを引き起こす。クオリアは脳によって生じているが、なぜ、どのように、こういったクオリアが脳から生まれてくるのか、それが問題なのである。
*離人症の一部は、クオリアの消失なのだろう。
更に問題なのが、なぜある種のクオリアには、それ特有の「感じ」があって、それ以外の「感じ」ではないのか、ということである。一体全体、何で、「赤い感じ」はあの赤い感じなのだろうか? どうしてあの「青い感じ」とは全く異なるのだろう? こういった「感じ」は、抽象的なものではないし、個人個人が勝手に決めたシンボルでもなく、人類にある程度は共通のものである。このような感覚は、生物にとって何か「意味」のあるものを表わしている。現代の哲学者たちは、ある事柄を表象する能力や、自分の外の世界にある何物かに「向かう」意識の能力、すなわち、「志向性」等の精神の能力について議論している。主観的な意識は、常に何か外界に存在するものについての意識である、ということを指して「志向性」という。例えば、あなたが赤いクオリアを持ったときには、それは外界の新鮮で美味そうなトマトに「向かう」、もしくは、トマトを「指し示す」。まるで、我々の主観である赤いクオリアからトマトへの矢印が出ているかのように。意識が外界の何かに向かう、この矢印のような働きのおかげで、主観者の内部にある表象が外界の何かに対し「意味」を持つことができるのだ。脳を構築する広大な神経の網目のようなつながり、ニューラル・ネットの電気的な活動から,「意味」がどのように生じてくるのかという謎は、非常にミステリアスである。ニューラル・ネットの構造や、それらの接続パターンが、確実に役割を果たすというのは分かっている。しかし、具体的にそれらがどうやって「意味」と「志向性」を生み出すのだろうか?
*「志向性」は現象学でよく言われる言葉だけれど、ここで何か関係があるかな?
人間および多くの動物が、状況や行動に応じてクオリアを経験するのはどうしてなのだろうか? なぜ人間は、全く無意識のままに生きて、子供を生んで、育てていかないのだろうか? そんな無意識のままの人生なんて、まるで、夢中歩行して人生を送るようなもので、主観的には、生きていると言えたものではないだろう。それでは、進化論的に言って、意識が存在する理由はなんだろうか? 人間という種の存続に、他人とわかちあうことのできないクオリアはどのような利点をもたらしたのだろうか?
*主観的クオリア体験がなくても、多分、立派に生きていけるでしょうね。
ハイチに伝わる伝説に、死者の蘇り、ゾンビが登場する。ゾンビは呪術師の魔力によって、操るものの意のままに動くという。哲学の世界では、「ゾンビ」というのは架空の存在として思考実験に用いられている。外見上の立ち居振る舞いは、全く普通の人と変わらないが、意識、感覚および感情が完全に欠けたもの、それが哲学用語としての「ゾンビ」である。哲学者が思考実験をするときには、全く無意識であるにもかかわらず、あたかも普通の人間のような経験があると嘘をつくように企んでいるゾンビを考えることもある。
*
そのようなゾンビを想像するのは非常に難かしいが、その事実こそが、まさに、意識が日常生活に欠かせない重要なものだということを示している。かのルネ・デカルト(Rene Descartes)も自己の存在証明時に言ったではないか。「私は、『私に意識がある』ことを疑いなく確信できる」と。我々には常に意識があるわけではない。夢を見ていない睡眠中、全身麻酔にかかっている間はもちろん無意識だ。だが、本を読んだり、喋ったり、ロッククライミングをしたり、考えたり、議論したり、単に座ってぼーっと景色の美しさに見とれたりする時などは、たいてい我々には意識がある。
*
脳の電気化学的な活動のほとんどは意識にのぼらない。この事実を認めると、単に、意識がなぜ脳から生まれてくるかという漠然とした問題が、一歩踏み込んだものになり、なぜある特定の電気化学活動だけが意識を生み出し、他の活動は無意識に処理されてしまうのか、というより具体的な疑問が湧いてくる。ものすごい数のニューロンの猛烈な活動が起こったからといって、いつも、感覚を覚えたり、何かのエピソードを思い出したりするわけではない。このことは電気生理学による実験によって証明されている。例えば、反射的に動くときなどがそうである。なんとなく、ぱっと足を振り払う。そのあとで、自分の足の上を、虫が這っていたことにに意識的に気がつくなんてこともある。つまり、視界に入った虫を発見し、そして勢いよく足を動かすという、高度な計算が無意識のうちに脳内で、まるで反射のように行われることがあるのだ。あるいは、毒蜘蛛や銃などの生命を脅かす危険のあるものが視界に入るだけで、たとえそれらを意識しなくても、身体が先に反応することもある。それらの危険物に対する恐怖が意識にのぼる前に、手のひらは汗ばみ、心臓の脈拍および血圧は増加し、アドレナリンが放出される。蜘蛛や銃の発見だけでなく、それらが危険なものであるという分析、そしてその分析に対しての反応までもが無意識のうちになされることがあることの一例である。現在のコンピューターでも手に負えない、知覚から行動までの複雑な一連のプロセスもまた、迅速にかつ無意識に起こっている。実際、サーブを返したり、パンチをよけたり、靴ひもを結んだりといった、複雑な一連の動作は、繰り返し練習をつむことで、無意識に素早く実行できるようになる。無意識の情報処理は、精神の働きのうち非常に高次のものまでも含んでいる。大人になってからの行動が、意識的な思考や判断を超えて、幼年期の経験(多くの場合、精神的外傷、トラウマなど)によって、深いところで決定されることもある、とジーグムント・フロイト(Sigmund Freud)は主張した。高次の意志決定および創造的な行動の多くが無意識のうちに生じている(この話題は18章でより深く扱う)。毎日の生活を彩る出来事の非常に多くが意識の外で起こっている。このことは、臨床研究において見られる患者の振る舞いによって、非常に強く支持されている。神経障害を持った患者、D.Fさんの奇妙なケースを紹介しよう。彼女は、形を見たり、日常生活にありふれた物の写真を認識することができない。それにもかかわらず、驚くべきことに、ボールをキャッチすることができる。郵便受けポストの入り口のような、細い横穴の向きを水平なのか垂直なのか意識的には分からず、口では「どっち向きかわからない」と答えるのに、彼女はさも簡単に、スリットへ手紙を入れることができる。このような患者の研究によって、神経心理学者は、人間の行動の中には、まるで反射のように無意識に行われるが、大脳によって高度に制御される必要がある複雑なものがあることを突き詰めた。こういった脳を介した反射のようなものを、脳の中の「ゾンビシステム」と呼ぶ。もちろん、ゾンビシステムは一般の健康な人の脳にも存在する。これらのゾンビシステムは、視線を移したり、手を置いたりといった、決まりきった行動に限られており、通常かなり急速に作動する。ゾンビシステムが作動を開始するのに必要な状況や入力、すなわちボールがこちらに投げられたり、手紙を持ってスリットに向かったり、といった状況を意識的に思い出して作動させようとしても、それはできない。例えば、D.F.さんは、ポストに向かった後、たった二秒間目隠しされてしまうだけで、手紙を投函することができなくなってしまう。意識的には、どんな角度だったか思い出せないのだ。ゾンビシステムについては、本書の12章、13章で、もう一度詳しく扱う。
*ゾンビシステムこそが基本で、自意識はその上に付加的に形成されたものだと考えることができる。
このようなゾンビシステムが脳の中に備わっていることを知れば、「なぜ、脳は高度に専門的なゾンビシステムをたくさん集めただけのものではないのか」という疑問が湧いてくるだろう。もし我々がゾンビシステムの寄せ集めだったならば、人生は退屈なものかもしれない。しかし、たくさんのゾンビシステムが簡単に、そして、素早く働くのならば、どうして意識など必要なのだろうか? 意識には生存に役立つなんらかの機能があるのだろうか? 将来の一連の行動の予定を立てたり、その予定を吟味したりするときにこそ、色々なことに応用がきき、かつ、計画的な情報処理モードである意識が必要なのだ、という主張を14章で展開することにしよう。意識は非常に個人的なものであり、他人と共有されることはない。感覚は、直接に誰か他の人に伝えることができないので、通常、他の感覚を経験するときの様子に例えたり、それと比べたりすることによってのみ、間接的に伝えられる。たとえば、あなたがどんな赤さを感じたのかを説明しようすれば、結局は、なんらかの赤の経験、つまり、「日没の時の赤」とか、「中国の国旗のような赤」とかを持ち出すことになるだろう。出生時から盲目の人にあなたが感じた赤さを説明するのは不可能に近い。二種類の異なった経験、例えば夕焼けの赤さと中国の国旗の赤さとの、類似点や細かな相違について語ることに意義はあるが、ある一つの経験について、他の経験を持ち出さずにそれだけについて話すことは不可能である。なぜ、我々はそういった手段を持たないのかもまた、意識の理解が進めば説明されるべき事柄である。
*
実はこの事実、我々が自分の体験している世界を直接他人に伝えることができないという事実を、我々の意識がどのように脳から生まれてくるかを研究するうえで、最も根本的なものとして重要視せねばならない。どのように、そして、なぜ、ある特定の意識的な感覚を支えている神経の物質的基盤(neural basis)が、それ以外の感覚を生み出したり、完全な無意識の状態をつくらないのか、この疑問に答えることが目標である。短い波長の光が青く、長い波長の光は赤く、あの青さ、あの赤さでそれぞれ全く異なる鮮やかさで感じられるように、どのようにして、それぞれの感覚に私たちが感じる独特な質感が構成されているのだろうか。また、どのようにして、自分の内部の主観的な感覚に、外界のものごとを指し示すような意味が与えられていくのか。また、なぜ感覚は個人的なもので他人と共有されないのか。どのように、また、なぜ、多くの行動は意識を伴わずに生じるのか。
*「なぜ感覚は個人的なもので他人と共有されないのか」というよりも、「感覚は個人的なものであるが、体験と神経ネットワークに共通性があるため、普遍性があり、共有できるものである。共有できない場合に、病理的現象が生じる。」と私は考えている。
1.2 どんな答えがありうるか
*
17世紀中頃に、デカルトの「人間論」(Traite de l'homme)が出版されて以来、哲学者や科学者は、現在の形の心脳問題についてあれこれと考えを巡らせて来た。しかし、1980年代まで、脳科学におけるほどんどの研究は意識の問題を完全に避けてきたのである。ここ20年間でその潮流に変化が生じ、哲学者、心理学者、認知科学者、臨床医、神経科学者、さらにはエンジニアまでもが、意識について学術論文や本を多数発表するようになった。これらの本は、現在の科学的な知見を持って、意識がなぜ脳から生じるかという問題をあらためて「発見」したり、「説明」したり、意識について「再考」し直したりすることを目的としている。本のタイトルも「意識を再考する」だったりする。これらの本は、純粋な思索だけに頼ったものが多く、ニューロンの集合体である脳から意識がどのように生じてくるのかを実際に科学的に発見するためには、どのようにして真摯な研究を行っていけばいいのか、という系統的で詳細な指針を示していない。そのため、本書で述べるような、意識が脳からどう生じてくるかの謎を解くための様々な研究のアイデアには、これらの本の内容は全く役に立っていない。
*1980年代から、ここ20年で、状況が変わったと述べている。本当に変わったと思う。20年前、Thomas Nagel「コウモリになるとはいったいどういうことか?」が提出され、エックルズとポパーが共著で「三世界」の構図を示し、一方で、唯物論者たちは、創発論でお茶を濁していたと記憶している。わたしはエックルズとポパーが好きだったが、理系の人たちには、軽蔑されただけだった。
フランシス・クリック(Francis Crick)と私がとるアプローチを紹介する前に、これまでの哲学者が考えてきた、これらの問題へのもっともらしい答えを、ざっと見渡してみよう。ただし、ここではあまり、深入りせず、それぞれの立場の単なるスケッチだけしか提供しないということを心に留めておいていただきたい。
*
意識は不死の魂に依存する西洋哲学の父、プラトン(Plato)は、人間というものを、「永遠不死の魂が、必ず死の運命にある肉体に閉じ込められた存在である」、と論じたことで広く知られている。プラトンはまた、イデア(idea)は、我々の肉体が存在しているこの世界とは別の、イデアだけの世界に存在し、それらは永遠であるとも言った。このようなプラトンの考え方(Platonic views)は、後に、新約聖書に組み込まれ、古典的ローマカトリックの魂(soul)についての教えの基となっている。意識の根源には物質世界には存在しない不死の魂がある、という信仰は、数多くの宗教に広く共有されている。
*これが一番安定した考え方なんだろう。何と言っても強力。
近代に入ると、デカルトが、「延長するもの」(res extensa)、例えば、物質としての実体を持った神経や筋肉を動かす動物精気(animal spirit)、すなわち現代科学では明らかになっている神経や筋肉の電気化学的な活動のこと、と「思惟するもの」(res cogitans)、すなわち、思考する実体、とに区別を付けた。デカルトは、res cogitans は人間に特有のもので、それが意識になるのだと唱えた。デカルトがこのように全ての存在をこのふたつのカテゴリーに分類したことが、まさに精神物質二元論(dualism)とよばれるものである。それほど厳格でない二元論は、すでにアリストテレス(Aristotle)や、トーマス・アクゥィナス(Thomas Aquinas)によって提唱されていた。現在の最も有名な二元論支援者は、哲学者カール・ポパー(Karl Popper) と、ノーベル賞を受賞した神経生理学者、ジョン・エックルス(John Eccles)だろう。
*20年前、「エックルズ先生も、歳をとって、死後のことを考えると、無神論的唯物論ではきついのだろう、歳をとればそんなものだ」、といった感じの文章さえあった。ポパーは三世界論だし、その中の意識経験についても、単純に精神世界のことを言っているのではないように思う。極端に言えば、物質世界と脳・意識と文化の三者が共進化する世界観といえばいいのだろうか。脳と意識を特に区別しているとも思えなかったけれど、私の考え違いか。物質世界と、個人精神内界と、人類が共有する文化の総体、この三者の関係といった感じのことだったように記憶している。脳と心の問題についてはどのように言っていただろうか?
二元論は、論理上一貫している一方、原理主義的で言葉どおりの二元論は、科学的な見解からすると不満が残る。特に面倒なのは、魂と脳とがどのように相互に影響をあっているのかという問題である。どうやって、どこで、その相互作用は起こるのか。おそらく、この相互作用は物理学の法則と両立していなければならないだろう。ところが、もしそのような相互作用を仮定すると、魂と脳の間でのエネルギーの交換がなくてはならないことになる。さらにそのメカニズムも説明されねばならない。これらは非常に問題である。また、二元論によると、魂の一時的な宿主である肉体が亡んだとき、すなわち、脳が機能を停止したとき、一体、何がこの不気味な存在である魂に起こるのだろうか。幽霊のように、超空間を漂うとでもいうのだろうか?
*
精神の本質としての魂という概念は、魂が不死であって、魂の存在が脳に全く依存しないと仮定すれば、矛盾が生じることはない。すなわち、魂とは、いかなる科学的方法によっても検出することのできない、ギルバート・ライルのいわゆる「機械中のゴースト」、とみなすのである。つまり、魂は科学の扱う範囲外であると考えてしまうということである。
*
科学的な手段では意識を理解することは不可能だ伝統的な哲学的態度に、ミステリアン(Mysterian)と呼ばれる流派がある。ミステリアンは、意識の問題は複雑すぎて人間の理解の範疇を越えると主張する。この流派には二種類ある。一方は、「どんな認知システムもそのシステム内部の状態を完全に理解することができない。同じように、我々の脳は、脳内部から生じる意識の状態や仕組みは理解できないのだ」という理論的な主張である。もう一方は、現実的ではあるが、悲観的な主張である。愚かな人類には、知性に限界があり、既存の概念を大きく変更することはできない。類人猿が一般相対性理論を理解できないように、意識がなぜ脳から生じるかという問題は、人類にはとても及ばない問題なのだ、というものである。
*脳は脳を理解できるかという命題がある。
*一個のニューロンが、一個のニューロンを「理解」するとすれば、あるいは、一個のシナプスの状態を、一個のシナプスで「理解」するとすれば、結局、そっくり同じものができるだけで、「理解」とはいえないだろう。脳よりももう一次元、複雑さの程度の高次なものでなければ、脳を理解できないだろうとするもの。
*なんとなく分かるけれど、でも、脳は、そのように理解しているのではなくて、抽象化したり、輪郭をつかんだりして、圧縮して理解しているのだ。海を構成する分子のすべてをひとつひとつ理解しているわけではないが、H2Oがいっぱいあって、ナトリウムと、……なんていう具合に「理解」するので、そのように、「情報圧縮」しても理解はできるのだと思う。
また別の哲学者は、「ただの物質に過ぎない脳が、意識をどのように生じさせることができるか、全く予想もつかない。ゆえに、単なる物質である脳の中に、意識が生じてくるメカニズムを科学的に研究しようとしても、絶対に失敗するに違いない」と断言している。こういった主張は、彼等の無知を晒しているにすぎない。現時点で、脳と意識にはつながりがあるということを強く支持する議論がないからといって、つながりがないことを証明することにはならない。もちろん、これらの批判に答えるためには、科学こそが、このつながりを支持するような適切な概念や証拠を提出していかねばならないのだが。
*
将来、意識を生み出す脳の仕組みを解明することは、単に技術的に難しいだけでなく、原理的に不可能だと判明することがあるかもしれないが、現時点ではそのような結論を出すのは時期尚早というものだろう。神経科学は、非常に若い科学分野である。息をのむような速度で、常により洗練された方法によって、新しい知識が蓄積してきている。神経科学の発展が翳りを見せる前に、そんなに悲観的なってしまう必要はない。意識がいかに脳から生まれてくるかを、ただ単にある学者が理解できないからといって、この問題が人類の知性の限界を越えているというわけではない!
*今のところ、原理的に不可能だと証明されてはいない。可能だと証明されてもいない。
意識は錯覚である
脳と意識の問題があまりにも難しいので、哲学者の他の流派には、一般には理解しがたいことだが、なんと、その問題自体を否定しまうものもある。この種の意識問題を否定してしまう哲学流派は、行動主義(behaviorism)に起源を持つ。現代の哲学者の中では、タフツ大学(Tufts University)の哲学者ダニエル・デネット(Daniel Dennett)が最も影響力を持っている。『解明された意識(邦題)』(Conscoiusness Explained)で、デネットは、私たちが普段持っている感覚、クオリアは、手のこんだイリュージョン、幻想、なのであると論じている。感覚入力システムと行動出力システムとが共謀し、人類の社会構造と脳の学習がその幻想をサポートしているという。デネットは、人々が、自分に意識があると言い張っていること、その事実をまず認めている。そのうえで、「私には意識がある」と人々がずっと信じ込んでいる事実には説明が必要だ、ということも認めている。但し、デネットによると、この信仰は「間違っている」。その一方で、どのように脳から生じるのか非常に理解が難しいクオリアを、どれだけ鮮明に人々が主観的に感じようとも、それは幻想なのだとデネットは言い切ってしまう。彼は、意識を研究しようとする通常のやり方は、非常に間違っていると考えている。
*わたしはこの流派に近い。
*デネットがイリュージョンと言うとき、何を意味しているのか、吟味しなければならない。吟味してみれば、納得する部分があると思う。
通常意識がどうやって脳から生じるかを考える場合、意識を持つ主体の側からみた、主観的な意識が問題になっている。この主観的な意識が、なぜその人だけにしか経験されないのか等、主観者の側からの疑問に対しての説明をしようとするのが通常のアプローチだ。このような説明の方法を、意識のファースト・パーソン・アカウント(主観者説明、First-person account)と呼ぶ。それに対して、デネットは、そのような説明ではなくて、意識を第三者の目で見たときに説明されるべき事柄(例えば、意識を持っている種はそうでない種に比べ、生存に有利な点はあるのか等)だけをターゲットにした、サード・パーソン・アカウント(第三者説明、 Third-person account)を目標にするべきだと主張する。「ある波長の光が網膜に影響を与え、被験者に『赤い光が見えた!』と叫ばせた。」という叙述は、第三者の視点でなされた客観的な叙述である。物理法則、化学法則から説きおこして、なぜ、脳の中のニューロンという単なる物質が起こす電気化学的活動が最終的に主観的な意識に至るのかまでを順を追って説明することはあまりに無謀に見える。そのため、最後の部分、すなわち脳から意識が生まれてくる部分を幻想だと見なし、科学的に存在しないものは説明できないという立場をとる。
*「すなわち脳から意識が生まれてくる部分を幻想だと見なし、科学的に存在しないものは説明できないという立場をとる。」という解説は正しいのか?
デネットによると、歯が痛いというのは、しかめっつらをしてこらえる、といった、ある行動をとること、もしくは、痛い側の口で噛まないようにしよう、とか、逃げて苦痛が去るまで隠れていたい、といった、ある行動をとりたいという欲求をもっている状態だと考える。これらの、デネットが「反応的な傾向(reactive dispositions)」と呼ぶ、外部から観察され、研究しやすいものは、現実に存在するものであり、それがどうして起こったのか、その後何が起こるのかについては、説明がなされなければならない。しかし、苦痛の不愉快さそのもの、これは幻想であって、その捉えがたい感覚は存在しないとする。
*「苦痛の不愉快さそのもの、これは幻想であって、その捉えがたい感覚は存在しない」というように、「主観的な意識」「主観的な経験」を消去してしまったら、不思議は消えてしまう。やはりここをきちんと説明したいと思うのは、著者に賛成。
日常生活において主観的な感情が中心的位置を占めていることを考えると、クオリアや感情が錯覚であると結論づけるには、相当量の実際的な証拠、科学研究を必要とする。哲学的な議論は、論理的な分析と内省(introspection)、すなわち 自分の内部を真剣に見つめることに基づいており、科学的方法に比べ 現実世界の様々な問題を取り扱うには全く力不足である。哲学的方法では、微妙な論点を決定的に論じ、定量的に決着をつけることはできない。哲学的な方法論が、最も効果を発揮するのは、問いをたてるときである。悲しいかな、長い歴史を持った哲学は、自らがたてた問いに答えたためしがほとんどないのである。私が本書でとる中心的なアプローチは、ファースト・パーソン・アカウントを、乱暴ではあるけれども、人生における明らかな事実と見なして、それを説明しようと努力するというものである。
*
意識の解明には根本的に新しい法則が必要とされる
一部の科学者たちは、脳に関しての更なる事実の積み上げや原理の発見ではなく、新しい科学法則こそが、意識にまつわる謎を解明するのに必要であると主張している。オックスフォード大学のロジャー・ペンローズ(Roger Penrose)は、名著『皇帝の新しい心(邦題)(The Emperor’ s New Mind )』の中で、「現代の物理学では、数学者の直観(大きくは一般の人々の直感も含む)がどのように生じるのかを全く説明することができない」と論じている。近い将来のうちに公式化が期待されている「量子重力論」がこの問題を解く鍵であり、どんなチューリング式 (Turing)ディジタルコンピューターもこなすことのできないプロセス、数学者の直観が、人間の意識によって、どのようにして生み出されてくるかが、「量子重力論」によって説明されるだろう、とペンローズは信じている。アリゾナ大学ツーソン校の麻酔専門医スチュアート・ハメロフ(Stuart Hameroff)とペンローズは、体中すべての細胞にある、微小管(マイクロチューブル、 microtubles)に注目している。微小管は集まると、外部の酵素の働きなどを必要とせずに、勝手に組みあがって大きくなるという性質がある。微小管が多数のニューロンをつないで、量子の共鳴状態(coherent quantum states)をつくるのに中心的な役割を担うのだ、とハメロフとペンローズは提唱している。
*ロジャー・ペンローズの本も、分厚い本で、読み始めるまで、億劫、そしてこの手の本は、大部分が既知の基礎的な事柄のⅢ確認になっているので、その点でも退屈。ペンローズ氏の確信は、とても同意できるものではない。
*おおむね、学者仲間から見放された時点で、一般向けの本を書いて、さらに失望させてしまうものである。
数学者は一体どこまで非計算論的な真実を直観的に理解できるのかという問題や、コンピューターを用いて数学者の直観を実現できるのかということに関し、ペンローズは、活発な討論を巻き起こした。しかし一方で、高度に秩序だった物質である脳の中で、ある種の動物の脳には少なくとも意識が生じてくるのはなぜか、という問題に量子重力(quantum gravity)がどう関わってくるのか、はっきりしたことを何も説明していない。確かに、意識と量子重力はそれぞれが不可解な側面を持っている。しかしだからと言って、片方がもう片方の原因なのだ、と結論付けるのは、恣意的で根拠がない。巨視的な量子力学的効果の事例が、脳内において一例も報告されていない現在、これ以上彼らの考えを追求することに意味はないと思われる。
*そうですね。トンデモ系。
うつ病の社会文化的試論-特に「ディスチミア親和型うつ病」について-
あの有名な、樽味氏の「ディスチミア親和型うつ病」のお話。分かりやすくていいですね。
原著論文日社精医誌,13:129-136,2005
うつ病の社会文化的試論-特に「ディスチミア親和型うつ病」について-
樽味伸,神庭重信
*
抄録:わが国のうつ病の気質的特徴として,几帳面で秩序を愛し,他者配慮的である点が指摘されてきた。しかし昨今の精神科臨床においては,比較的若年者を中心に上記の特徴に合致しない一群が多く現れ始めている。彼らはそれほど規範的ではなく,むしろ規範に閉じこめられることを嫌い、「仕事熱心」という時期が見られないまま,常態的にやる気のなさを訴えてうつ病を呈する。本稿では彼らを「ディスチミア親和型うつ病」と呼び,従来のメランコリー親和的なうつ病と対比させ,その臨床場面での特徴を整理した。ディスチミア親和型では,抑制よりも倦怠が強く,罪業感とともに疲弊するよりも,漠然とした万能感を保持したまま回避的行動をとる印象がある。本稿では,特に抑うつ症状としての罪業感の変容に着目し,そこに社会文化的に受け継がれてきた役割意識の希薄化と,それに代わって構築された保護的環境での個人主義が影響している可能性を指摘した。
日社精医誌13:129-136,2005
索引用語:ディスチミア親和型うつ病,メランコリー親和型うつ病,罪業感,役割意識
*
はじめに
*
わが国におけるうつ病に関しては,下田が言及した執着気質,それに近いところでTellenbachのメランコリー性格の影響がこれまで言及されてきた。
*
几帳面,仕事熱心,過剰に規範的で秩序を愛し,他者配慮的であるとされるこの気質,性格は,日本人の自己規定に近く,また確かに,わが国のうつ病者の一側面を言い当てているように思われる。
*
しかし昨今の,すそ野の広がった日本の精神科一般臨床においては,上記の特徴に合致する一群だけでなく,そうではない群が多く現れ始めたように思われる。
*
すなわち,メランコリー性格に代表されるような,几帳面で配慮的であるがゆえに疲弊,消耗してうつ病に陥る人々と,もう一群:もともとそれほど規範的ではをくむしろ規範に閉じこめられることを嫌い、「仕事熱心」という時期が見られないまま常態的にやる気のなさを訴えてうつ病を呈する人々である。後者はより若年層に見られるような印象があり,自責や悲哀よりも,輪郭のはっきりしない抑うつと倦怠を呈する。
*
ここで前者を「メランコリア親和型」,後者を「ディスチミア親和型」と呼ぶこととし,その臨床面での特徴を抜き出してみる。
*
症例呈示
以下に,両病型の典型像を症例呈示の形で略述する。なお,プライバシー保護の観点から,個人を特定できないように変更を加えている。
症例1:メランコリア親和型,45歳男性
【主訴】不眠,意欲の低下
【家族歴】特記すべきことなし。
【既往歴】これまで精神医学的疾患を指摘されたことはない。
【生活史】もともと真面目な性格で柔道に打ち込みつつ文武両道を目指していたという。大学卒業後,高校の体育教師をしている。生徒指導にも携わり,親身になってくれる教師として人望も厚かった。柔道師範の資格を持ち,勤務先の高校柔道部顧問および所属自治体の代表選手の指導をしていた。既婚,子どもが3人いる。異動も数回経験しているが,特にこれまで問題はなかった。
【現病歴】2003年4月,転勤のため,ある都市部の高校に赴任することになった。これまでの勤務地と異なり,そこは生徒数の多い大規模校であり,教員も生徒も「ビジネスライクで冷めている」ことにいらだつことが多かった。本人としては,休日出勤して部活の指導や研修の準備を進めるのは「教師として当然のこと」と思っていたが,他の同僚はそうではなく,自然に本人の仕事量が増えていった。2003年9月,夏の柔道大会と合宿が終了し,2学期に入ったが徐々に不眠が増強し,早朝覚醒が目立ち始めた。これではいけないと無理して出勤しても,終日ぼんやりしてしまい,気力が湧かなくなった。これでは生徒に申し訳ない,教師として不甲斐ない,このような自分では生徒指導をする資格がない,と悩み始めた。自宅でもため息が多く考え込んでいるため妻も心配するようになり,2003年10月,上記の症状を主訴に,近医総合病院精神科を受診した。DSM̃IVにおける大うつ病エピソードの基準を満たし,うつ病と診断された。
*
症例2:ディスチミア親和型,24歳男性
【主訴】やる気が出ない
【家族歴】特記すべきことなし。
【既往歴】これまで精神医学的疾患を指摘されたことはない。
【生活史】長男,姉が1人いる。父親は会社員,母親は専業主婦。中学,高校と特に問題となるようなことはなかったが,嫌いな教師の科目はわざと勉強しないといったことがあったという。大学ではサークル活動とアルバイトを「人並みに」こなしていた。就職活動にはそれほど熱心ではなく,公務員を目指した。大学を卒業後,1年間は公務員試験対策として専門学校に通い,「たまたま受けたら合格した」地方都市の役所に23歳から勤務している。
【現病歴】採用後配属された職場では,仕事は特に嫌ではないが,あまり興味も持てないという。ただ「うるさい上司がいて顔を見るのが嫌だったjので,時々欠勤はしていたとのことである。ただし憂うつで出勤できなかったわけではなく,欠勤中はパチンコに行ったり映画を見に行ったり買い物したりしていた。2002年6月,働き始めて1年が経ち,職場の同僚女性と恋愛結婚した。2003年5月,第1子が生まれた。仕事には相変わらずあまり身が入らず,かといって家にも居づらく,パチンコに行ったり映画を見たりしていた。育児は大変だったが,退職した妻や両家の母親が上手に切り盛りしてくれた。2003年12月,勤務態度を上司に叱責された。これまでにも数回注意はされていたが,今回は非常に厳しい口調だったという。そのあと「体調不良なので」と職場を早退した。本人によれば,その日から夜眠れなくなったという。その後はきちんと出勤したが,職場ではやる気にならず意欲が湧かずイライラし,忘年会や新年会などの職場の集まりにも出る気がしなくなった。パチンコをするときに少し元気は出るが,家に帰ると「おもしろくなくて」再び暗く沈んでしまう。そのため近医精神科クリニックを上記の主訴で受診。DSM-IVにおける大うつ病エピソードの基準を満たし,うつ病と診断された。その場で本人は診断書を希望した。ちなみに,回避性人格障害,分裂病質人格障害および自己愛性人格障害の診断基準は満たしていない。また同席した妻の情報では,早退時の「体調不良」とは異なり,今回の症候に関して特に詐病を疑わせるような所見はなかった。
注1)「ディスチミア親和型」がDSM̃IVのdysthymicdisorderをそのまま指しているわけではない。dysthymic disorderは「大うっ病性エピソードを欠き,少なくとも2年の罹病期間が存在する」ことが前提とされているが,本論で言及するrディスチミア親和型」はもう少し対象範囲は広く,主に治療初期の抑うつ症状における現象面の特徴を指している。
*
表1 メランコリア親和型うつ病およびディスチミア親和型うつ病の対比
メランコリア親和型
年齢層……中高年層
関連する気質……執着気質(下田)、メランコリー性格(Tellenbach)
病前性格……社会的役割・規範への愛着、規範に対して好意的で同一化、秩序を愛し,配慮的で几帳面、基本的に仕事熱心
症候学的特徴……焦燥と抑制、疲弊と罪業感(申し訳なさの表明)、完遂しかねない“熟慮しだ’自殺企図
治療関係と経過……初期には「うつ病」の診断に抵抗する、その後は,「うつ病」の経験から新たな認知、「無理しない生き方」を身につけ,新たな役割意識となりうる
薬物への反応……多くは良好(病み終える)
認知と行動特性……疾病による行動変化が明らか「課長としての私」から「うつを経験した課長としての私」へ(新たな役割意識の獲得)
予後と環境変化……休養と服薬で全般に軽快しやすい場・環境の変化は両価的である(時に自責的となる)
*
ディスチミア親和型
青年層
studentapathy(Walters)
退却傾向(笠原)と無気力
自己自身(役割ぬき)への愛着
規範に対して「ストレス」であると抵抗する
秩序への否定的感情と漠然とした万能感
もともと仕事熱心ではない
不全感と倦怠
回避と他罰的感情(他者への非難)
衝動的な自傷,一方で“軽やかな”自殺企図
初期から「うつ病」の診断に協力的
その後も「うつ症状」の存在確認に終始しがちとなり「うつの文脈」からの離脱が困難,慢性化
多くは部分的効果にとどまる(病み終えない)
どこまでが「生き方」でどこからが「症状経過」か不分明
「(単なる)私」から「うつの私」で固着し,新たな文脈が形成されにくい
休養と服薬のみではしばしば慢性化する
置かれた場・環境の変化で急速に改善することがある
*
病型の概括
わが国の「うつ病」の病前性格についてはこれまで,冒頭で記したようにメランコリー性格が特徴であるとされてきた。確かに,中年期以降の患者では「メランコリア親和型」が多くを占める。しかし一方,より若年層(10代から30代)を中心に,この「ディスチミア親和型」に出会う頻度が増加しているように思われる。両病型についての特徴は,表1にまとめた。「ディスチミア親和型」の特徴は,1970年代に指摘されたような退却神経症,あるいは広瀬の逃避型抑うつ引こ近い。しかし,そこで指摘されていた「高学歴の男性に多い」といった特徴は,現在においては目立たないように思われる。むしろこの症候が汎化してしまい,男女比や教育年数は偏りを消失させているような印象がある。この汎化は,生物学的な要因よりも,社会文化的変容による部分が大きいのではないかと思われるが,その点について次項において現時点での試論を呈示する。阿部らの未熟型うつ病については,その発症年齢や性格傾向,依存性と攻撃性の問題など,重なる点が多い。ただし「未熟型」の特徴のひとつとされる「(入院後の)軽躁状態」については,われわれの病型からはまだ明らかではなく,さらに検討の余地があると考える。したがって,「未熟型」の背景とされる双極性スペクトラムに「ディスチミア親和型」を含めることは,現時点では留保したい。少なくとも,われわれの「ディスチミア親和型」が一般精神科外来レベルを中心としているのに対し,阿部らの論では,より重症のレペルに力点が置かれていることは推察できる。
*
なお「ディスチミア親和型」において,なんらかの人格障害の存在を想定しうるほどには,彼らの性格的な偏りは強くはない。もちろん場合によっては自己愛的な性格傾向を指摘しうる例もあるが,少なくとも診断基準を満たしうるほどには,病理性は際たっていない。自己愛的側面については,次項後半に触れることになる。
*
考察
*
本項では,うつ病の代表的な症候である罪業感に着目し,その母体となる「役割意識」の社会文化的変容を追う。その上で,筆者らが仮定した2病型における罪業感の現れの変化を記述する。
*
1.役割意識の変容
ここで「役割意識」とは,「○○として××せねばならない」という意識を指し,自己規範とほぽ同義のものとして使用している。図1に示したように,おおまかに5種の役割意識を想定している。これは社会の成員すべてが,なんらかの形で担ってきた文化要因であり,図のような階層構造をとると仮定している。
*
図1 役割意識の階層構造
①職業的役割意識:「課長として」「教師として」「○○に勤めている以上」「これが私の仕事だから」②家族的役割意識:「長男(長女)として」「親として」「家のため」
③地域的役割意識:「先輩として」「故郷に錦を」「地域のために」
④宗教的役割意識:「仏教の教えのもとに」「キリストの名のもとに」
⑤民族的役割意識:「日本国民としてJ「アジア人として」図1役割意識の階層構造
上記の役割意識は,わが国において社会の成員が,さまざまな形で担ってきた文化要因である。役割を果たせない場合,罪業感として析出する要素でもある。わが国では,少なくとも1950年以降は④と⑤は希薄であった可能性が高く,もっぱら①~③によって保たれていたと思われる。ちなみに⑤民族的役割意識は一時的に高揚するが1945年の敗戦によって希薄化した。④宗教的役割意識はそれ以前から希薄であった。
*
この役割意識は,なんらかの事由で社仝機能が低下し役割を果たせない場合,罪業感として析出する要素であるように思われる。ちなみに②~⑤は,歴史的文化的に構成され伝達されてきた持続的因子であるのに対し(⑤が最も持続時間が長く,②は短い),①は社会・経済的に構築されるー過性の要因にすぎない(例えば退職すれば失われる)。
*
わが国における特殊性として,最基底層の⑤および④は,少なくとも20世紀後半においてすでに非常に脆弱な状態を露呈してきたと考えられる。背景には,海に囲まれた地理的特殊性,明治政府成立後の神仏合祀と第二次世界大戦による敗戦,その後の急激な社会変動の影響があげられる。

さらに図2に示したように,1950年代から図1③の地域的役割意識は徐々に衰退し,一時的に「県人会」として都市で再生をみるも,その後再び壊滅する。また同②の家族的役割意識も,核家族化の問題に限らず,父性の弱体化など家族内ヒエラルキーの解体などにより,特に都心部において1980年代までに希薄化してきたように思われる。したがって,わが国における役割意識は,①の職業的役割意識が唯一,一貫して1990年前後までわが国で存続しえたのではないだろうか。
*
しかし,その①の母体となるべき経済的成長がプラトーに達し,次第に衰えるにつれて,1990年代あたりから,その役割意識と自己規範も崩れ始めている。また家庭においては,家族内モラトリアムとでもいうべき保護の延長から,子の社会的出立はなし崩し的に遅れているのが実状であろう。社会の競争原理を良くも悪くも体現していだ“会社人間”および“教育ママ”はすべて死語と化し,平坦な無風空間が存在するに過ぎない。家庭内で次代の骨格を構成したのは,「個」の意識,「個」の尊重である。しかしそれはかなり脆弱なものであって,その「個」に当然付随しているべき「自己責任」「自己規範」が巧妙に抜け落ちたままであるように思われる。
*
注2)ここではモラトリアムの語を,本来の“猶予期間゛という意味で使用している。「社会に出るべき年齢であるにもかかわらず,家族内で養育され,しかもそれが大きな齟齬をきたさないまま家族内で是認されている状態」といった状態を指す。積極的ではないか消極的に容認しているという意味では「消極的過保護」とさえいいうるかもしれない。
*
2.不甲斐なさとしての罪業感
宗教的背景をなす“神”の存在の意識が薄いわが国では,おそらく症状としての罪業感は,図1に示した①~̃③を母体としてきたように思われる。わが国の抑うつで一般的な罪業感は,例えば父親として申し訳ない,課長として申し訳ない,そのような働きができない,といった表明となる。
*
「メランコリア親和型」が呈する罪業感は,社仝的役割・地位・役職に付随した規範意識が構築した「不甲斐ない」「申し訳ない」という表明である。それは実存的に罪の意識に苛まれるのではなく,「課長に昇進したのに,この状態では不甲斐ない」「部下に申し訳ない」という,おもに社会面の役割に関する罪の意識である。世代的には,①の職業的役割意識が残存している世代が多い印象がある。
*
一方,「ディスチミア親和型」を構成する若い世代では,社会的役割への同一化よりも,自己自身への愛着が優先している印象がある。そして役割意識を母体とした罪業感を一般に呈しにくい。その希薄な役割意識を「うつ病」の診断に補完してもらうかのように,彼らは「うつの役割と文脈」にすぐに沿い,そこからなかなか離脱しない。「がんばれといわれたら傷つく」「うつ病を家族が理解しない」と積極的に表明するのは,主として彼らである。言語化されず葛藤にもならない「いらいら」は,一方では他罰的言動となり,他方では手首への自傷や大量服薬として現出する。彼らの手首の自傷は「いらいらするので」「すっとするために」行うのであって,罪業感に苛まれた末の自殺企図ではない。大量服薬も,最初から死ぬために飲むのではなく,「いらいらするので」酩酊感を求めて過量服用するほうが多いようである。もちろん境界型人格障害の行動化ともニュアンスを異にしている。他者との関係性の問題を基盤にした当てつけではないのである。
*
この若い世代では,可能な限り競争原理が被覆された環境のもとで成長した場合が多い。前述のように,すでに競争原理の家庭内への持ち込みもなくなった世代である。その無風空間から何の備えもなく一般社会に出立したとき,実は存在していた競争原理に,彼らはいきなり直面することになる。彼らの神話であった「個の尊厳」は,彼らが期待する形ではそこには存在しない。その意味では,この世代が越えねばならないギャップとしては,この50年間で最も大きくなっているのかもしれない。それに対抗するために彼らがもっているものは,それまで試されることさえないまま保持されてきた,幼い万能感しかないのである。それを守るためには,彼らは自己愛的にならざるをえない。それはもっとも罪業感から遠い症候を構成する。
*用語は笠原先生流。
おわりに
*
本稿は,臨床場面での印象をもとにした予備的試論であり,具体的なデータを欠いたままである。しかし,両者の症候学的差異について,どのような社会的要因が関与しているのか考察することには一定の意義があると思われた。
*
抑うつ症状の時代的な変容に目を配っておくことは,時代に応じた診断行為の最適化につながるという意味で,価値のある臨床行為である。うつ病への脆弱性を構成する遺伝的素因と行動特性,その社仝文化的変容といった環境要因の相互作用を考えていくとき,おそらく「ディスチミア親和型」への着目は,慢性化した抑うつに関する研究の,重要な一部となっていくと思われる。
*
なお,このディスチミア親和型うつ病と,退却神経症や逃避型抑うつおよび未熟型うつ病との関係については,さらに厳密な論考を要すると考えている。
*
本稿は2004年10月,神戸市で開催された第18回世界社会精神医学会(同時開催:第24回日本社会精神医学会)において「うつ病の比較文化論:試論」(神庭,樽昧)として発表した内容をもとにした。
*
文献1)阿部隆明,大塚公一郎,永野満,ほか:「未熟型うつ病」の臨床精神病理学的検討一構造力動諭(W.Janzarik)からみたうつ病の病前性格と臨床像.臨床精神病理16:239-248,1995
2)広瀬徹也:「逃避型抑うつ」について.(宮本忠雄編)躁うつ病の精神病理vo12,61-86,弘文堂,東京,1977
3)神庭重信,平野雅巳,大野裕:病前性格は気分障害の発症規定因子か:性格の行動遺伝学的研究.精神医学42:481-489,2000
4)笠原嘉:現代の神経症-とくに神経症性apathy(仮称)について.臨床精神医学2(2)153-162,1973
5)笠原嘉:アパシー・シンドローム:高学歴社会の青年心理.岩波書店,東京,1984
6)下田光造:精神衛生講話.同文書院,pp.85-87,東京,1957
7)Tellenbach,H.:Melancholie(木村敏訳:メランコリー).みすず書房,東京,1985
*
葉酸不足でうつが多めに 遺伝子組換え食品 有機JASマーク
| こんな記事にコメント。 ***** 葉酸不足でうつが多めに 食習慣調査で関連判明 | ||
|
1.「うつ症状」の確認方法は妥当か。---関連判明というタイトルが不正確なんだ。最後のコメントで、「別の調査も必要」と言っているでしょう。
2.うつだったら、食事量が減るから、たったそれだけのことではないか?---他の栄養素も測定しているから大丈夫。
3.「たべたもの」と「栄養摂取」は同じではない。うつだと消化吸収も悪くなる。---そんなことは言っていないんです。いいですか、おちついて。『過去1カ月間に食べたものを詳しく聞き、各栄養成分の摂取量を算出した。同時に別の質問でうつ症状があるかどうかを調べ、摂取した各栄養素との関連を探った。』と書いてあるだけです。『その結果、葉酸の摂取が少ない人ほどうつ症状の割合が高かった。摂取が多い人では、少ない人よりうつ症状が半減していた。この傾向は女性でもうかがえたが、男性でよりはっきりしていた。』と書いてありますが、学者はこんな粗雑なことは書きません。ここは、『葉酸の摂取が少ない』は不正確だし、『うつ症状の割合が高かった』も不正確でしょう。実験もなにもしていない、ただのアンケート調査なんですよ。
因果関係は言っていないんです。ひょっとしたら、うつで葉酸摂取不足になっているのかもしれないし、ある原因Xのせいで、葉酸摂取不足とうつが両方起こっているかもしれないし。統計的に相関があったというだけで。
正確に言うと、「自己申告した食事中の葉酸量と、自己申告したうつ症状の間に負の相関が見られた」ということなんだろう。
葉酸欠乏での巨赤芽球性貧血は有名。うつと関係しているかどうか、今後の研究待ち。
4.多い少ない、割合が多いとは、どのようにして決めたものか。---統計学があります。---でも、統計学は、嘘をつくための学問だとも言われます。---望む結果が得られる検定方法を採用すればいいだけのことで。
5.JanzarikやTellnbachやAkiskalはどうなるのか?---いえいえ、うつは、人間学的な原因によっても起こり、一方、一栄養素の欠乏とも関係しているのです。---それって、哲学的。
6.そういえば、過食症で、トリプトファンを飲んでいるという患者さんがいまして、最初に吐き気がして食欲がなくなっただけで、その後はあまり効かないそうですが、思い出したのは、遺伝子組み換えトリプトファンの昭和電工。
同社によって製造されたトリプトファンからは、後になって60近くの種々の不純物が検出され、そのうちの2つは、発症を引き起こした疑いのある重要なものだった。つまり、同社が枯草菌の遺伝子を組み込んだことで予期し得ない有害物質ができ、しかも、これを濾過して取り除く精製工程を無視したことで大きな被害がもたらされたということらしい。 FADは生命工学産業の保護育成のために、真実の発表を遅らせたというスキャンダルに発展。
難しい世の中になったものです。
家に「トゥルーフード・ガイド」が届いていました。大豆はいろいろな食品に使われているのでチェックしてみたら、なかなかおもしろかった。坂本龍一と大貫 妙子が出ていて、わたしは信用してしまう。音楽関係者がなぜ遺伝子組換え食品についてコメントしているのかよく分からないが。リズムが狂ったりするのだろうか?
有機JASマークがついていれば、一応、安心らしい。
といっても、最近の嘘食品騒ぎをみれば、信用はできないけれどね。
ユルゲン・ハーバマス 自由と決定論―自由意志は幻想か?
参考文献を眺めていたら、ベンジャミン・リベットの論文がいくつかあった。
懐かしくて検索したら、こんなのが見つかった。
*****
The 2004 Kyoto Prize Workshop: Symposium of Arts and Philosophy Category
〈受賞者講演要旨〉
ユルゲン・ハーバマス 教授
フランクフルト大学 名誉教授
自由と決定論―自由意志は幻想か?
近年、神経生物学の新たな展開により、決定論の立場から人間行動を説明する是非をめぐる伝統的論争が、再燃している。きっかけは、ベンジャミン・リベットとその追随者たちによって行われた、よく知られた実験である。そこで明らかにされたのは、被験者がなんらかの行動を起こす際、いくつもある選択肢の中から、自発的にある特定の動き方を選んだのだと本人が意識するよりも前に、すでにその動き方のための特性が神経レベルで観察できるということである。著名な決定論者たちはこの結果を―リベット自身による解釈とは対照的に―、我々が自らを自由意志を持った存在だと自認することもまた幻想に過ぎない、という主張を裏付けるものとして用いているのである。
このペーパーでは、こうした主張に対する反論として主なものを三つ取り上げ、概説する。
(1) 自由意志を過度に狭い意味で概念化することは、実験の設計を不完全なものにし、それによって、まちがった操作化をもたらすと考えられる。また、不完全な実験設計は、実験結果の包括的一般化を不可能にする。
(2) 還元主義的解釈では、それぞれ一人称と三人称に定位した言語ゲームをする唯心論者と経験論者の間に広がる溝の意味するところが、十分に考慮されない。
(3) 生物進化の観点から見るなら、自らの意志でこのようにも、あのようにも自由に行為できる、という行為者の自己理解が、人間の行動の説明にいかなる因果的役割も果たさないということの方が、かえって奇妙なことに思われる。
論争のテーマをより厳密に定義するなら、脳と文化の(おそらく双方向の)相互作用に注目せざるを得なくなる。この場合、「文化」とは、規則に支配された命題内容の蓄積と象徴的保存を意味している。また発表では最後に、(自由という現象の存在可能性を認める)認識論的二元論と、(一貫した宇宙観を追求する我々を満足させてくれる)存在論的一元論を結びつけることを提案したい。すなわち、人間の認知が、「観察者」と「当事者」という二つの相互補完的視点の不可避的な相関関係に依拠するということを、進化にもとづいて説明することができれば、柔軟な、つまり科学主義的ではない自然主義を確保することができるということである。我々は社会化された諸個人という生物種である以上、我々が観察可能な出来事から成る客観的世界とのかかわり方を学ぶことができるのも、ただ、共有された象徴的意味と根拠から成る「公共空間」の中でコミュニケーションすることを通して、同時にお互いから学び取ることによってのみである。世界と人間相互の両方に同時に向けられているこの二重の視界の背後にさかのぼることは、科学者としての我々にすらできないとしても、さまざまな対象から成る世界を客観化して見ることができるのは間主観的に共有された生活世界の内部からのみであり、またそれを可能にしている文化的生活形式を生み出したのも、この同じ自然であるということは、我々は依然として認識しうるのである。
Professor Jürgen Habermas
Professor Emeritus, University of Frankfurt
Freedom and Determinism ― Is Human ‘Freedom of Will’ an Illusion?
Recent developments in neurobiology have revived an old debate about deterministic accounts of human action. It takes off from the well-known experiments of Benjamin Libet and his followers. The experiments prove that an observable neurological disposition to act in a certain way precedes the test person’s awareness of having voluntarily chosen between alternative ways of action. Contrary to Libet’s own interpretation, prominent proponents of determinism defend the conclusion that our self-attributed freedom is an illusion.
The paper summarizes three of the main counterarguments:
(1) An overly narrow conceptualisation of freedom is assumed to lead to a misleading operationalization in terms of an inadequate experimental design, that does not allow a sweeping generalization of the findings.
(2) The reductionist interpretation does not pay due attention to the implications of the gap between the mentalist and the empiricist language games, attached to a first and third person perspective respectively.
(3) From the point of view of biological evolution, it were a rather mysterious fact, if the self-understanding of actors as being free to act in one way or the other would not play any causal role in the explanation human behaviour.
A sharper definition of the controversial issue directs attention to the (supposedly two way) interaction between brain and culture, while culture is conceived as the storage and symbolic enshrinement of rule-governed propositional contents. The paper finally suggests a combination of epistemological dualism (which leaves room for the phenomenon of freedom) with ontological monism (which satisfies our quest for a coherent view of the universe). A soft, that is non-scientistic naturalism can be secured by an evolutionary explanation of the fact, that human cognition depends on the unavoidable interrelation of two complementary perspectives, that of an observer and that of a participant. A species of socialized individuals can only learn how to cope with the objective world of observable events by simultaneously learning from one another, through communication within the “public space” of shared symbolic meanings and reasons. Even if we, as scientists, were permanently impeded in our attempt to “get behind” this bifurcated view directed simultaneously at both, the world and one another, we can still know that it is just one and the same nature from which there has evolved a cultural form of life which permits an objectivating view at the world of objects only from within an intersubjectively shared life-world.
*****
これはこれで、大変な含蓄のある発言なのであるが、「ベンジャミン・リベットとその追随者たち」の仕事を軽く引用して、さらに、「著名な決定論者たちはこの結果をリベット自身による解釈とは対照的に、我々が自らを自由意志を持った存在だと自認することもまた幻想に過ぎない、という主張を裏付けるものとして用いているのである。」として、決定論に対しての反論を展開しているのだが、論点の三つはどれもすばらしく難解で、リベット先生の提示した実験の説得力に遠く及ばないものと私には思われる。
ハーバマスは「史的唯物論の再構成」なんていうマルクス的な本があり、一方で、多方面に関しての著作があるエライ人だと思っているが、「自由意志」に関しては、こんなことになってしまう。
これって、「天動説」じゃないですか?
意識の探求―神経科学からのアプローチ インタヴュー
意識の探求―神経科学からのアプローチ;岩波書店
クリストフ・コッホ (著), 土谷 尚嗣, 金井 良太(訳)
*この本の、最終章に収められた、架空の、自作自演のインタビュー。*部分はわたしのコメント。
二十章 インタヴュー
*
「ねえねえ教えてよ。それってどういう意味?」とアリスは尋ねた。「君は賢そうだから教えてあげよう。」と、ハンプティーダンプティーはとても嬉しそうにいった。「どうしてもわからないこと、ってのはしょうがないんだ。その話題はもうたくさんだっていうことだよ。だから、君がこれからどうするつもりなのか話してくれてもいいし、ほら、残りの人生ずっとここにとどまっているつもりじゃないんだろう。 」「鏡の国のアリス」ルイス・キャロル(Lewis Carroll)
*
結局、本書の主張とは何だったのだろうか。十九章をより分かりやすくするため、最終章では、架空のジャーナリストから受けたインタヴューという形式で、本書の趣旨をまとめてみたい。意識について考えていると、現在の我々の理解では答えるのが難しいが、興味深い数多くの問題に直面する。どうやって脳というシステムが意味を扱うことができるのか。動物に意識があるとすれば、動物実験は倫理的に許されるのか。我々に自由意志はあるのか。機械やロボットは最終的に意識を持つようになるのか、などなど疑問は尽きない。ここでは私の憶測を交えてこれらの疑問に答えていきたいと思う。
*
ジャーナリスト:まず最初に、コッホ教授の採る、「意識の探求」への戦略を一言でお願いします。
*
コッホ:第一に、私は、我々に意識があることは、否定しようのない事実であり、どうやって意識が脳から生じてくるのかを、我々は説明すべきだと考えています。主観、感覚、質感、クオリア、意識、現象としての経験、どんな言葉を使うかは自由ですが、そういうものを、我々は確実に事実として経験している。なんらかの脳の処理過程からこの意識は生じてくる。我々にはこういう意識的な経験があるから、人生が彩られたものになっているんです。大平洋へ沈む深い太陽の深い赤、バラの素晴らしい香り、犬が虐待されるのを見たときにこみ上げてくる激怒、スペースシャトル・チャレンジャー号が爆発したのを生中継のテレビで見たときの鮮明な記憶。こういった主観的な感覚が、どのようにして脳という物理的なシステムから生じてくるのかを説明するのが、現代科学の役割なんです。それができないようでは、科学のもたらす世界観なんて、本当に限られたものにすぎないでしょう。
*
私の第二の主張は、哲学者が論じている難しい問題は取り敢えず、おいておこう、無視しよう、ってことなんです。特に難しいのは、何故、何かを見たり聞いたりすると、それぞれに特有の感覚を我々は感じるのかということなんです。自分がいつものように自分であると感じるのはどうしてなのか、非常に難しい問題ですね。そういうことに捕らわれ過ぎずに、ひとまず、科学的に取り組める問題に集中しましょう、といっているのです。意識が変化するのにつれてぴったりと活動を変化させるようなニューロン(神経細胞)、そういう意識と相関のあるニューロン(Neural Correlates of Consciousness)をNCCと私は呼んでいますが、そういうニューロン、もしくは意識と相関するような分子を明らかにすることに集中しよう、というのが戦略なんです。具体的に言うと、ある特定の意識的知覚を引き起こすために十分な最小限のニューロン集団の仕組みとは一体何かを明らかにすることを目標としています。最近の脳科学における技術の進展には目を見張るものがあります。哺乳類における遺伝子工学、サルの脳内から何百個ものニューロンを同時に記録する技術、生きた人の脳を輪切りにして画像化するイメージング技術。これらの技術を持ってすれば、NCCの探索は現実的な目標といえるでしょう。問題の定義もはっきりしているので、一貫して、科学的な成果が出せるはずです。
*
ジャーナリスト:NCCが見つかれば、意識にまつわる謎は解決されるということですか?
*
コッホ:いやいや、そんなに事は簡単ではない。なぜ、どんな状況において、ある種の非常に複雑な生命体が、主観を持って感覚を経験するようになるのか。なぜそれぞれの感覚には特有の感じられ方が決まっているのか。こういう問いに対しても、最終的に、原理的な説明ができるようにならなければ、意識の謎は解決されたことにはならないんです。人類は二千年間もこれらの謎を解こうとして、もがいてきたんです。実に「難しい」問題ですよ、これは。NCCが見つかったとしても、それは始まりにしか過ぎないでしょうね。謎を解くには程遠い。NCCの発見が意識の探求について果たす役割という意味では、DNAの発見と生命にまつわる謎との関係がもしかすると良い例になるかもしれません。DNAが二重螺旋構造を持っていることが解明されたことで、どれくらい遺伝の仕組み、すなわち、分子がどうやって複製コピーを作っているかが明らかになったか思い出してください。糖とリン酸、そしてアミノ基でできた二本の鎖が、弱い水素結合によって相補的な螺旋構造を持っていることが発見されるとすぐに、遺伝のメカニズムが提唱されました。遺伝情報はどう表現されているか、どう複製されるのか、そしてどう次の世代へと受け継がれていくのか、一気に遺伝の謎、生命の謎を解く鍵が示されたんです。遺伝のメカニズムは、DNA分子の構造を知らなかった、それ以前の世代の化学者や生物学者には、絶対に思いもつかなかったはずです。同じようなことが、意識の謎についても起きるかもしれません。ある特定の意識的知覚が、どの脳部位にあるニューロン集団によって生成されるのか、そのニューロン集団はどの部位へ出力を送って、どこから入力を受け取るのか、どんな発火パターンを示すのか、生後から成体になるまでの発達過程ではどうなっているのか。これらが分かれば、意識の完全な理論へとつながるブレイクスルーをもたらすかもしれません。
*
ジャーナリスト:というのが、理想というか、夢ですよね。
*
コッホ:たしかに現時点では夢かもしれません。だけど、NCCを探すよりも信頼のおける代替策はないんです。論理的に議論したり、自分自身の意識経験をじっと内省したりしても無駄でしょう。二百年前までは、科学実験が無かったので、学者達はそうやって意識の謎に取り組んできたわけですが、経験から言うと、そんな方法では意識の謎にはとうてい太刀打ちできない。頭の中で哲学者のようにごちゃごちゃ考えていたって、理屈で意識の謎が解けるわけがない。椅子に座って、じっくり考えて答えが出るほど、甘くない、脳はあまりにも複雑なんです。進化の過程で起きた、ものすごい回数起きたでたらめの出来事や偶発的な出来事を通じて、現在の複雑な脳が できあがってきたから、理屈が通用しない部分すらあるんです。むしろ今は、観察事実を積み上げることが必要でしょう。ニューロンから伸びる軸索の結合パターンはどれ程精密なのか。たくさんのニューロンが同時に発火することは意識が生じるのに重要なのか。皮質と視床の間を行き来しているフィードバック経路は、意識に重要なのか。NCCを構成するニューロンは特定の種類のニューロンなのか。こういう仮説が正しいかどうかを突き止めることの方がはるかに大事なんです。
*
ジャーナリスト:なるほど。ということは、科学的に意識の理論を構築していく上で、哲学者に何か役割はあるのでしょうか?
*
コッホ:歴史を振り返ってみると、哲学が、現実世界に関する疑問に対して、白黒はっきりつけたという、目覚しい結果は見られません。宇宙はどこからきてどうなって今まであるのか、生命はどうやって生まれたのか、精神はどんな性質を持っているのか、生まれが大事なのか、それとも育ちのほうが大事なのか。これらの問題になどに哲学が明確な答えを出した試しはない。ただ、哲学が問題解決には不向きだ、と声高に指摘するような失礼な学者は滅多にいないから、そういうことこの事実をめったに耳にすることがない。一方で、哲学者が問いを立てることに秀でているというのは確かでしょう。哲学者は科学者には思いつかないような視点でものを見ています。意識の問題には「難しい・ハード」なものと「簡単・イージー」なものとがあるという観念、現象としての意識とアクセス意識の区別、意識の「内容」と意識「そのもの」の識別、意識は何故統一されているのか、意識が生じるための条件とは何か、などは科学者がもっと考えるべき重要な問題です。まとめると、哲学者の投げかける問いには注目し、彼らの提示する答えにまどわされないようにするのが一番良いってことです。そのいい例が哲学者のいう「ゾンビ」でしょう。
*
ジャーナリスト:「ゾンビ」って、腕をだらっとのばして歩き回る呪われた死人のことですか?
*
コッホ:いや、ちょっと違う。見かけ上は、私やあなたと全く変わらないが、まったく意識がない架空の生き物のことを哲学者は「ゾンビ」と呼んでいるんです。チャルマーズがこの魂のないゾンビを議論に使って、今までに知られている宇宙の物理法則からは、意識がどうして生じるのかを説明できない、と主張している。物理学、生物学、心理学の知識は、主観的経験がこの宇宙にいかにして現われてくるのか理解するのに、これっぽっちも役に立たないという主張だ。何かそれ以上のものが必要だと。この奇怪な架空の生き物、ゾンビを使った哲学的な議論が、私には非常に役に立つ概念だとは思えない。しかし、哲学者のゾンビには程遠いが、それに似たような状況が現実にもあるんです。フランシスと私はこの取っ付きやすい用語を使って、一連の、それ自体は、意識にのぼらない素早いステレオタイプの感覚と運動の連合した行動を示すことにしました。古典的な代表例は、運動を制御することです。走りたいと思えば、何も考えず、ただ単に、[走る]だけでしょう? 体制感覚器とニューロンと筋骨格系があとはなんとかしてくれる。ただそれだけであなたはどんどん進んでいく。自分がどうやってそれぞれの筋肉をどう動かしているのか内省的に振り返ろうととしても、全く見当もつかないでしょう。このように一見単純な行動に潜んだ、驚くまでに複雑な計算と運動が直接意識にのぼることはない。
*
ジャーナリスト: ではゾンビ行動というのは反射行動なのですね。ただし、より複雑な。
*
コッホ:まさにそのとおり。大脳も含めた反射ということです。水の入ったグラスに手を伸ばす。そのとき、グラスを握るため手が自動的に開く。そういった行動は一種のゾンビ行動で、腕と手を制御するために視覚入力を必要とする。これらの行動は1日に何千回と行われている。もちろん、あなたはグラスを見ることができるが、それはまた別の神経系での神経活動が意識的に知覚されるからです。
*
ジャーナリスト:ということは、健常者の中にも、無意識のゾンビ・システムと意識システムが共存しているということですか?
*
コッホ:まさにそういうことです。毎日の行動のうち、大部分がゾンビ・システムによって制御されています。仕事にいく時の運転はまさに自動的だし、目を動かすのも、歯を磨くのも、靴ひもを結ぶのも、同僚に会ったときに挨拶するのも、その他の色んな日常生活における行動は、みんなゾンビ・システムがコントロールしているのです。ロッククライミング、ダンス、空手、テニスなどの複雑な行動でも、十分に訓練を積んだ後では、意識せずに、無心でやると一番うまくいく。どれか特定のひとつのアクションについて考え過ぎると、かえって滑らかな運動に干渉してしてうまくいかない。
*ゾンビ・システムは。原則として、これまでの知識で解釈できるわけです。神経細胞で構築できると思う。またたとえば、それと等価なものをコンピューターで構築することもできそうだ。つまりは、知覚→脳・処理→運動→知覚→以下ループ、という循環をつくればよいだけで、脳・処理の部分についても、ジャクソニスム的な原則を適用すれば、だいたいは説明がつくように思う。説明がつかないのが、「主観的体験」であり、「自意識」である。「自分は今経験している」と感覚すること、これがどのようにして生成されるのかが問題である。しかし手がかりがないわけではない。病気の中には、まさに、こうした、「主観的体験」「自意識」の部分が障害を受けるものがあり、そこでは、自意識の病理が展開される。完璧なモデルはまだないが、不完全な萌芽的モデルならば、提示できる。
ジャーナリスト:そんなにゾンビ・システムが効率的ならば、そもそも、なぜ意識なんて必要なのでしょうか?どうして私はゾンビではないのでしょうか?
*こういうことも思考の上では楽しいが、必要も何も、実際にあるのだと言いたい。
コッホ:どうしてあなたがゾンビでありえないのかについて、私には論理的な理由はわかりません。でも、全く感覚のない人生というのはそうとう退屈でしょうね。(そもそも、退屈という感覚さえもゾンビにはないのだろうけど。)しかし、この惑星の進化はちがう方向へ向かったわけです。非常に単純な生物がゾンビ・システムだけから成り立っているというのはあり得る話だ。だから、カタツムリや回虫にいたっては何も感じていないかもしれない。しかし哺乳類のように、様々な種類の感覚器からの膨大な入力を受け取り、そして複雑な行動を生み出すことのできる効果器を備えた動物にとっては、あらゆる可能な入力と出力の組み合わせそれぞれに対してゾンビ・システムを用意しておくというのはあまりにコストがかかる。脳が大きくなり過ぎてしまう。実際、進化の過程では、この問題は別の方法で対処した。予測していなかった出来事に対処したり、未来の計画を立てられる、ずっと強力で融通の効くシステムを作り上げた。NCCはある環境の選択された関心のある部分、すなわち、あなたがいま現時点で認識している物事を、コンパクトに表象し、この情報を脳における計画の段階にアクセスできるようにしている。このためには、なんらかの形で、数秒にわたるような即時記憶が必要とされる。コンピュータ用語では、現在の意識の内容というのはキャッシュメモリの状態に対応する。意識の流れが、視覚知覚、記憶、いま聞こえている声へと不規則に行き来するのにあわせて、そのキャッシュメモリの内容も変動する。
*「未来の計画」には疑問。
*「進化論的には、自意識は生存可能性を高めるはずだ」なんていう議論も、意識のメカニズムそのものには関係ないのだと思う。何故その方向に進化したかを説明はするだろうが、そんなことは、事実がわかってからでいいだろう。
ジャーナリスト:なるほど。意識の機能というのは、自動的な対応方法を用意するのが難しいような状況を扱うことだということですね。もっともらしく聞こえますが、なぜこれが主観的感覚を伴うことになるのでしょうか?
*
コッホ:確かに難しい問題はそこだ。現時点では、なぜ神経活動が感覚を引き起こすのかを説明できる合理的な仮説はない。もっと正確に言うと、色々な提案はあるけれども、どれも納得がいくものではないし、広く支持されているものもない。しかし、フランシスと私は「意味」というものが決定的に重要な役割を果たしているのではないかと思っている。
*
ジャーナリスト:言葉の「意味」ですか?
*
コッホ:いや、言語的な意味ではない。私が感じたり、見たり、聞いたりする世界にある物体は意味のないシンボルではなく、豊富な連想を伴っている。磁器のカップの青の色合いは子供の頃の記憶を喚び起こす。そのカップを掴んだり、その中にお茶をそそいだりすることができるということを私は知っている。落としたら、粉々に壊れてしまうこと。これらの連想が明示的である必要はない。それらの連想は、生きてきた期間の経験を通じて行われてきた、外世界との数えきれないほど感覚̶運動の相互作用から成り立っている。こういった捉えどころのない「意味」は、磁器のコップを表象しているニューロンと、他の概念を表しているニューロンとの間の、入力と出力両方においての、シナプスの相互作用に対応している。このような膨大な量の情報が、コップを知覚する時の「質感クオリア」という形で、簡潔に記号化されている。これが我々の「経験」の正体なのです。この問題はさておき、実証されない推測ばかりで何百年も困難につきあたっていたこの分野で重要なことは、我々の枠組みが操作上の意識のテストを提供しているということだ。ゾンビ・エージェントは現時点の情報だけを扱うので、短期記憶を必要としない。例えば、差し伸べられた手をみて、自分の手を伸ばし握手をする。このとき、差し伸べられた手を見てから自分の手を伸ばすまでに、ちょっとした遅れを課されると、ゾンビ・エージェントはすでに役に立たなくなる。このような状況はゾンビ・エージェントの守備範囲外であって、こういう状況を扱うために進化してきたのは、より強力な(ただし作用するのに時間がかかる)意識システムなのだ。こういったゾンビ・システムにはできないが、意識システムにはできる行動を基にして、「意識テスト」とでも呼べるような、簡単な操作的なテストを考えられる。このテストは主観的経験を容易に伝えられない動物、赤ん坊、患者などに、意識があるかを試すことができる。つまり、直感的な行動を抑制した後に、数秒遅れて反応を起こすというような選択を動物にさせる。もし、その生物がそれほど学習を必要とせずにそうした非直感的な遅れた行動をとれることができれば、その動物は計画を立てるのに関連した機能が備わっていると考えられる。少なくとも人間においては、計画に関わる仕組みと意識とは密接に繋がっている。よって、その動物は何らかの意識を持っている可能性が高いと考えられる。逆に、NCCが破壊あるいは不活化されれば、数秒の遅れを跨ぐような行動をとることはできなくなるだろう。
*「正体」と言っているが、正体は何かわかっていない。
*「意識テスト」はおもしろそうだ。
ジャーナリスト:しかしこれでは、意識の厳格な定義とは言えないのではないでしょうか 。
*
コッホ:まだゲームは始まったばかりだから、現時点で正式な定義を立てるには早すぎる。一九五〇年代のことを思い起こしてほしい。もし分子生物学者たちが「遺伝子」の正確な定義は何かとあれこれ悩んでいたら、ここまで分子生物学は進んだだろうか?現在でさえ、「遺伝子」を正確に定義するのはそれほど簡単ではない。我々の意識の遅れテストを、チューリングテストのようなものだと考えて欲しい。ただし、チューリングテストは「知性」があるかないかをテストするが、遅れテストは「意識」の有無を明らかにするという違いがある。科学において重要なのは、遅れテストが、夢遊病者、サル、マウス、ハエに応用できることだ。
*
ジャーナリスト:ちょっと待って下さい。虫にも意識があるかもしれないってことですか?
*
コッホ:意識が可能となるためには、自分自身を振り返るために、言語と自己の表象が必要だと考えている学者は多い。確かに、人間が自分自身について再帰的に考えることができるということに疑いの余地はないが、この機能は大昔に進化したより基礎的な生物システムに最後に付け加えられた機能に過ぎない。意識は非常に原始的な感覚と結びついている可能性がある。赤い色をみたり、痛みを感じたりする時に、言語だとか高度に発達した自己だとかいう観念が必要だろうか? 重度の自閉症の子供達やひどい自己妄想や離人症症候群を持った患者ですら、世界を見て、聞いて、嗅いでいる。これらの言語や自己の表象が著しく侵された人々も基礎的な知覚的意識は正常なのだ。
*そうですね。離人症の人も、忙しいときはそれなりにやっています。自省する瞬間があると、自分の感覚がおかしいと意識し始めて苦しいといいます。
言語を持った動物が進化の過程で現れてくる以前に、ある種の動物は意識を持っていた。私の研究対象の意識とは、そういう類の意識だが、となると、意識が進化のどの過程で生まれてきたのかが気になるところだ。さらに言えば、Ur‐NCC(NCCの原型)は、いつごろ地球上に現われたのだろう? 哺乳動物は、我々人類と進化上枝分かれしてからそう時間も経っていないし、脳の構造も我々のものと良く似ている。だから、サル、イヌ、ネコ、は少なくとも見たり、聞いたり、臭いを嗅ぐという我々と同じような経験・質感を持っていてもおかしくはないだろう。
*そうですね。
ジャーナリスト:マウスはどうでしょうか? 生物学や医学の研究で最も頻繁に使われている哺乳動物ですよね。
*
コッホ:マウスを使うと、新しい遺伝子を挿入したり、既存の遺伝子をノックアウトするとなどという、ゲノムの操作が他の哺乳動物と比べると簡単なんです。だからマウスはモデル動物として非常に有用だ。マウスに遅れテストを実験的に適用することは実際可能なので、分子生物学の手法と組み合わせて、NCCの基礎を遺伝子操作を使って神経科学が研究するという強力なモデルになるだろう。私の研究室は他の研究室と共同で、古典的なパブロフの条件付けパラダイムを用いて、注意と「気づきアウェアネス」のマウス・モデルを開発しようとしている。
*
ジャーナリスト:今、意識コンシャスネスの代わりに気づきアウェアネスとおっしゃいましたね。それらは別の概念なのですか?
*
コッホ:いや、同じことです。慣習的にそういう実験では「気づきアウェアネス」と言うことになってるんです。意識(Consciousness)が、我々研究者の間では、「Cワード」と呼ばれることもあるように、研究者の中には強い嫌悪を示す人たちがいる。したがって、研究費を申請する時やや論文を投稿するときには別の言葉を使ったほうがいい。気づき(Awareness)という単語はそういうレーダーをたいていくぐり抜けるようだ。
動物の意識について続けましょう。意識がマウスで見つかるならば、そこで立ち止まる必要はない。哺乳動物で止まる必要すらない。大脳皮質が無ければ意識は生まれるはずは無いと、勝手に、大脳に対して狂信的である必要もない。大脳やその附随構造が知覚意識に必要だとは実証されていないんです。イカも意識を持っているんじゃないか?ハチはどうか? ハチは百万個ものニューロンをもっており、彼らは非常に複雑な行動を取ることが知られている。視覚的な刺激を覚えておいて、答えるというパターンマッチングをはじめ、色々なことができる。私が知る限り、数十万個のニューロンがあれば、見たり、嗅いだり、痛みを感じたりするのに十分かもしれない!ショウジョウバエすら意識を持っている可能性はある。恐らく、彼らの意識は非常に限られたものだろう。現時点では分かっていないだけの話だ。
*
ジャーナリスト:これも検証できない推測のように私には思えますが。
*
コッホ:現時点では、確かにそうです。しかし、操作的なテストによってこれらの推測を実験で確かめることができる。これは非常に新しいことなのです。我々はつい最近まで、そういう意識のリトマス紙、なんて考えもつかなかったのだ。
*
ジャーナリスト:遅れテストは、機械が意識を持つかを確かめるのに応用できるのでしょうか?
*
コッホ:私はカリフォルニア工科大学の生物学部の教授でもあり、応用科学工学部の教授でもあるから、もちろん人工意識についても考えている。神経生物学への類似から考えるに、遅れテストで試されるような能力を持った生命体(機械も含む)は、感覚を持っている可能性があると思う。そういう生命体は、本能的な行動を抑えて、なんらかの方法で記号の意味を表現できなければいけない。そういう意味で、一見、世界中のコンピューターを繋いでいるインターネットは非常に面白い例だ。ノードの役割をする無数のコンピュータが作り出す、分散型で、かつ、高度に相互連結したネットワークは、新らしいシステムといえる。インターネットには、多くのコンピュータ同士でファイルを交換プログラムや、千台以上のパソコンに分散させても解けないような数学的に厄介な問題を解決するアルゴリズムがあり、非常に複雑な行動を取っているかのように思える。ところが、このインターネットで繋がったパソコンの集合体と、大脳皮質中で互いに興奮・抑制をしあっているニューロンの連合との間には、ほとんど関係性が見られない。特に神経系と異なるのは、ワールド・ワイド・ウェブ(WWW)には、ある一つの、統一された目的を達成するための行動みたいなものが見られないことだ。今のところ、ソフトウェアに元々設計されていなかった、目的のある大規模な振る舞いが自発的に出現したということは起こっていない。そういう振る舞いが、自発的に現れてこない限り、インターネットの意識について話しても意味がない。今のところ、ネットワークコンピューターが、勝手に、電力量の割り当て制御や、飛行機の交通網の整理とか、金融市場の操作などを、作り手の意図とは独立に為された試しがない。ただし、自分の行動を完全に自分でコントロールするようなコンピューター・ウィルスやワームの類が出現すると、こういう現在の状況が未来永劫変わらないとは言えなくなってくる。
*「本能的な行動を抑えて、」別の行動をとることは、別段自意識がなくても、可能なことである。
*「なんらかの方法で記号の意味を表現できなければいけない」というが、このことも、本質的な要請ではない。
ジャーナリスト:反射のような行動をもったロボットに意識は宿ると思いますか?障害物を避けることができて、電池切れにならないように自分の電力をチェックし、必要になればどこかへ充電しにいく。そういう能力に加えて、汎用性を持った計画を立てるためのモジュールが備わったロボットには、意識があると言えると思いますか?
*結局「意識がある」という言葉の意味に還元される。
コッホ:そうですねえ。例えば、そのプラニング・モジュールが非常に強力だとしましょう。自分の身体のイメージ、そしてデータから検索された現在の状況に関する情報を含めて、ロボット自身の周囲の現在環境をセンサーを通して感覚的に表象が可能だとする。その結果、そのロボットが、単独で目的のある振る舞いを生成することができる。さらに、そのロボット、センサーからの情報を将来に生じる損益と結び付けて、自分の行動を律することができる、とここまで仮定しよう。そういうロボットは、例えば、部屋の温度が高くなってくれば、その状況が機械の供給電圧の低下を引き起こすかもしれないので、ロボットはなんとしてもその状況を避けなければならない、ということもわかっている。ここまでくると、「高温」というのはもう、単なる抽象的な数字ではなく、ロボットにとっては、安寧に密接に関わる重要な動機付けの要因と考えられる。そのようなロボットには、ひょっとしたら、あるレベルの原意識とでもいうものを持っているかもしれない。
*
ジャーナリスト:なんだか、非常に原始的な「意味」とでも言うべきものに聞こえてきますね。
*
コッホ: 確かにそうです。しかし、我々人間も、生まれて間もない時点では、恐らく、痛みとか喜びくらいしか意識できていないでしょう。しかし、「意味」には、こういった原始的なもの以外の起源がある。ロボットで言えば、プログラマーが「これは正しい、それは間違い」と教えることなしに、教師なしで学習するアルゴリズムで、知覚と運動をつなぐ表象を学んでいくところを想像してみてください。道を歩こうとして、つまずいたり、よろめいたりしながら、試行錯誤を通して、自分の行動が予測可能な結果に結びつくことを学んでいく。この時、同時進行で、より抽象的な表象も構築されていくだろう。例えば、視覚と聴覚からの入力を比べて、ある種の唇の動きが、特定の発音パターンと頻繁に入力されることが多いことなどを学んでいく。ここでは、「表象が明示的で、はっきりしたものになるのにつれて、その表象によって表される概念がより高度に意図的になっていく」ということが重要だ。ロボットをデザインしている研究者が、もし人間の幼年期の発育過程と同じような過程をたどるロボットを造ることができれば、こういう「意味」というものをより深く研究していくのも可能になるかもしれない。
*人間の発達を考えれば一番分かり易い。精子と卵子から始まって、成人になるまで、どこかで段差があるわけではないのだ。連続しているはずだ。したがって、ニューロンネットワークで説明できるはずだ。
ジャーナリスト:まるで、映画「2001年宇宙の旅」にでてくる偏執病のコンピュータHALの世界ですね!でも、ロボットが「意味」を持つかどうかについてはわかりましたが、まだ私の最初の質問、ロボットの意識に対して答えてもらっていません。コッホ教授が提唱する遅れテストは、意識を持った「ふり」をしているだけのロボットと、本当に意識を持った機械を区別できるのでしょうか?
*できないと思う。「意識を持ったふりができる」ということは、意識を持っているということだと私はおもう。日本語がわかるふりができる犬は、結局、日本語がわかっているのだと私は思う。その場合も、「日本語がわかるとはどういうことか」というところに問題は還元されるようだ。
*今日、出そうなパチンコ台を、どう考えても非合理的としか思えない方法で判断しているおばあちゃんの場合、結果として、あてているという「相関」があれば、それは尊重するしかない。因果関係として認定するのは早いとしても。(これは適切でないたとえかもしれない。)
コッホ:遅れテストが生物の意識システムと反射システムを区別するからといって、同じことがロボットにもあてはまるとは限らない。「我々人間には意識がある。よって、人間に似ている動物ほど、感覚を持っている可能性は高い」という議論に基づいて、進化過程、行動パターン、脳構造などがどれだけ人類と類似しているかを考慮して、ある程度の動物種は感覚を持っていると仮定するのは納得がいくでしょう。けれども、デザインや歴史的な起源、形に至るまでが根本的に異なるロボットについては、そういう議論を前提に意識を考えることはできない。
*
ジャーナリスト:それでは、この話題はひとまずおいておいて、もう一度、これまでに発展させてきたクリック&コッホの視覚意識に相関する神経活動(NCC)仮説についての考えをお聞せ下さい。それはどのような仮説だったのでしょうか?
*
コッホ:一九九〇年に、我々は意識についての初めて最初の論文を発表しました。その論文では、複数の脳部位における神経活動の動的な「結び付け」が、ある種の視覚意識には必要だ、と強く主張した。
*
ジャーナリスト:ちょっとまって下さい。「結び付け」とは何のことですか?
*
コッホ: 赤いフェラーリがそばを過ぎ去っていく場面を想像して下さい。フェラーリは脳の全体にわたる無数の場所で神経活動を引き起こす。活動は色々な場所で起きるにもかかわらず、あなたが意識するのは、単一の知覚だ。自動車の形をした赤い物体が、ある方角に向かって、激しい音を立てて走り抜けていく。この統合された知覚は、運動をコードしているニューロンの活動、赤を表わすニューロンの活動、あるいは形や音や他のものを表わすニューロンの活動、これらをなんらかの方法で「結び付け」た結果、生じるものだ。もう一つの結び付け問題は、フェラーリの傍に犬を散歩させている人がいる場合に生じる。その犬を散歩させている人は、フェラーリと混同されないように、脳内に表現されて、別々に結び付けられなければならない。
*
我々の一九九〇年の論文発表時には、ヴォルフ・ジンガーとラインハート・エックホルン、それぞれが率いる二つのドイツのグループが、猫の視覚皮質のニューロンがある条件下で、それらの発火パターンを同期させるということを発見した。この同期発火は周期的に起こるため、有名な四十ヘルツの振動につながる。私たちは、この四十ヘルツの振動こそが、意識が起きたことを示すニューロンの「目印」みたいなものだと主張したんです。
*
ジャーナリスト: ニューロンの同期と四十ヘルツの振動については、現時点ではコッホ教授はどのように考えているんでしょうか?その後、どんな証拠が得られましたか?
*
コッホ:神経科学界の間では、振動と同期についての見解は、当時も今も、激しく対立し、深い分裂がみられています。ある科学論文雑誌で振動や同期には機能があって、それが意識に関連しているという仮説を支持する証拠が公表されたかと思うと、同じ雑誌のすぐ次の号では、その内容を元も子もないほどに笑い者にするような論文が発表される。しかし、信頼できる証拠が全く無い低温核融合とは違って、ニューロンが二十ヘルツから七十ヘルツの周期で振動する活動すること、そしてニューロンは同期して発火すること、これらの神経活動現象が「存在する」ことに関しては疑いの余地が無い。それでも、異論反論の尽きない問題は数多く残っている。今のところ、我々の解釈では、同期発火や振動には、ニューロン連合を形作るのを助けるという機能があるようだ。ある知覚を表現するニューロン連合が、他のニューロン連合との競合が起こったときに、優位になるように同期・振動が助けているようだ。こういう仕組みは、注意のバイアスをかけているような時に、特に重要かもしれない。しかし、四十ヘルツの振動が意識が生じるのに「必要」だ、とは現在ではもう信じていはいない。
*このあたりのことを我慢強く提案し続けることが大切だとおもう。
*重要なのは、この関係での、測定方法だとおもう。昔の人が電流計を知らなかったように、私たちもまだ、大切な何かの測定法を知らないのだろうと、漠然と思う。しかしそれは電流や磁気と同じように、現世の物理学に属するものであり、超越的な何かでは全くないだろう。
このように、理論に流行り廃りがあって、我々の知識が不安定なのは、精神の基礎となっているニューロンのネットワークを研究するための既存の道具が力不足だからだ。大脳には何百億もの細胞があるのに、現在の最先端技術の電気生理学の技術をもってしても、せいぜい数百個のニューロンから発火を記録するのがせいいっぱいなのだ。つまり、一億個に一個の割合だ。一万から十万個のニューロンの活動を同時に記録できるようにならなければ、本当に大きな成果を得るのは難しい。
*
ジャーナリスト:何百億個もニューロンが大脳にあるのであるば、たとえNCCがあるニューロン連合の活動に基づくとしても、かなりたくさんのニューロンの活動を記録しなれば、NCCを見過ごしてしまいますね。
*
コッホ: まさにそのとおり。現在のニューロン記録技術で科学者がやろうとしているのは、適当に選んだ二、三人の人たちの日常会話を基にして、次回の大統領選挙の結果を占おう、というのに近いでしょう。
*
ジャーナリスト: なるほど、もっともです。では、最初に十九九〇年の論文を発表した後は、クリック&コッホはどのような仮説を提唱してきたのでしょうか。
*
コッホ: 次に我々は、意識の機能に注目した論文を一九九五年に発表しました。様々な状況に応じた対処を素早く行なえるように、将来の計画を立てるようにするというのが、意識の主な機能であろう、と我々は仮定した。この仮定自体は、他の思想家たちがすでに提案してきた仮説に比べて目新しいものではなかった。我々はこの議論をもう一歩押し進めて、この仮定と神経解剖構造からどんな結論が導かれるか、について考えた。脳の中の行動計画に関わる部位は前頭葉に位置するので、NCCは前頭葉に直接にアクセスできなければならない。一方で、サルの脳では、頭の後ろに位置する第一次視覚野(V1)内のニューロンは、脳の前部へ出力を全く送っていないということがわかっていたのです。したがって、我々は、V1ニューロンは直接に視覚的な意識を生み出すのには不十分であり、視覚意識はより高次の視覚野で引き起こされていると結論付けた。
*意識の機能として、「自分の内部状態をモニターして、その延長として、他人の内部状態を推定し、他人とかかわるときに、有利な結果を引き出せるようにする」という考えがある。悲しくて誰かに慰めてほしい場面だと思ったら、慰めてあげる、そうすれば友達になれる、まあ、そんな話。自己の内部モニターが壊れている人がいて、そうすると、他人のこともうまく解釈できなくて、人間関係を滑らかにできなくなってしまう。先天的に視力の弱い人がいるように、先天的に自己モニターが不正確な人はいるもので、それがある種の性格の基盤になるだろうと思う。
コッホ:ここで注意して欲しいのは、我々は無傷のV1は視覚意識に不必要だ、と言っているわけではないということだ。ちょうど眼の網膜にあるニューロンの発火活動が視覚的な知覚に相当しないように、V1の活動も意識の内容に直接相当するわけではない。もしも、網膜の活動と視覚が一致するんだったら、盲点に相当する場所(視神経が集まって眼球から外へ出る所にある、光受容体が全く存在しないところ)には、灰色の穴がぽっかりと開いたようにいつも見えるはずでしょう。つまり、網膜も大脳皮質の一部であるV1も、見るのに必要だが不十分だということです。V1は、目を閉じた時に想像する具体的な視覚イメージとか、鮮明に感じる視覚的な夢を見るのにも不必要かもしれない。
*
ジャーナリスト: どうしてそんなにV1こだわるんですか。NCCがV1に無かったということがわかったとしても、そんなに重要な発見でしょうか?
*まあね。
コッホ: 仮に我々の仮説が正しくて本当にV1にNCCは無いならば、わずかではあるけれども、着実に意識の探求へと向けてにステップを進めていることになるでしょう。特に、最近出てきている証拠は我々の仮説を支持するものが多いようです。そういう結果は、特に科学者にとっては、とても励みになるものだと思う。正しい方法で科学的にアプローチすれば、意識の物質的基礎を発見する、というゴールに向かって進展が得られることを実証するからだ。我々の仮説はさらに、皮質での活動がすべて意識に昇るとは限らないということも含んでいる。
*
ジャーナリスト:それでは、広大な大脳皮質のどの部位に、NCCがあると思いますか?
*
コッホ:腹側経路、すなわち、「知覚のための視覚」を司っているこの経路のどこかに視覚意識のNCCはあるだろうと考えています。さらに言うと、下側頭葉の中やその周りのニューロンがつくるニューロン連合が非常に大事だろう。この連合は、帯状回や前頭葉のニューロンからのフィードバック活動によって活動が維持されている。このフィードバックによる反響的リヴァーブレイトリーな活動によって、競合相手の活動を抑えて優勢になることができる。こういう連合同士の競合の様子は、EEGや機能イメージングを使って観測可能だ。今までは謎の多かったこれらの脳の領域の研究は、電気生理学によってどんどん、日進月歩で進んでいる。中でも特にパワフルな戦略は、「錯視」を使った研究だ。ある錯視では、見せる映像に対して生じる知覚が、一対一の関係にならないことがある。入力映像はずっとコンピューター画面の上に出ているのに、ある時はその刺激がある風に見えて、また別の時にはそうは見えない、そういう錯視がある。ネッカーの立方体はこのパラダイムの良い例だ。そういう双安定バイステイブルの知覚は、前脳部に見つかっている色々なタイプのニューロンの中から、「意識の足跡」を追跡するために使われている。
*実際自分で経験してみると、不思議である。前に紹介した、右回りと左回りのダンサー。
ジャーナリスト:どうして、大脳皮質の後ろの方の知覚エリアと、計画・思考・推論を司る大脳の前部との間での反響的なループが重要なのでしょうか?
*
コッホ:私がまさに先ほど述べたように、生物にとって、意識が重要なのは、それが計画・思考・推論と深く関わっているからでしょう。生命を危機に晒すような事が起きると、それに伴って様々な今まで経験したことの無いような状況に立ち向かわなければならない。そういう状況で、 無意識の知覚運動ゾンビ・システムだけでは対処しきれないだろう。今まで経験したことの無いような状況に対処することが、意識の重要な役割なのです。頭の中に小人(ホムンクルス)がいて、その本当の「私」が世界を見ているという感覚をつくり出しているのは、おそらく、前頭前野と知覚皮質との間の投射が原因でしょう。脳の前部に座っている小人が後部の脳を見ていると考えることができる。解剖学的な用語で言えば、前部帯状回、前頭前野、前運動皮質が、後脳部からの強い駆動型のシナプス入力を受けているということだ。
*これは印象を良く説明していると思う。
ジャーナリスト: でも、脳の前部にホムンクルスがいるとすると、今度は誰がホムンクルスの頭の内部にいるのでしょうか?無限ループに陥ってしまって、説明にならないのではないでしょうか?
*これが古典的な指摘。
コッホ:ホムンクルス自体が無意識ならば、もしくは、我々の意識が持っている機能よりも限られた機能しかもたないと考えれば、無限ループには陥らずにすむ 。
*そうかな?
ジャーナリスト:ホムンクルスが自由意志を持って、我々の意志とは独立に行動を起こすことはできるのでしょうか?
*
コッホ: 自由意志について語るときには、自分には自由意志がある、と知覚することと、意志の力とをはっきり区別することが重要だ。例えば、ほら、私はこうやって手を上げることができでしょう。それに、私は「私」がこの行動を自発的に起こしたと確信できる。誰かが私にそうしろといったのでもないし、また、数秒前にまで、私はこんなことを考えてもいなかった。自分の体などを自分で制御しているという感覚、自分が自分を一身に引き受けているという行動の主体とも言うべき感覚は、生存にとって極めて重要だ。脳がそれぞれの行動を自分が起こした、とラベルを貼って区別するのを可能にする。(もちろん、この主体知覚にはそれ自身のNCCがあるだろう。) 神経心理学者ダニエル・ウェグナーが指摘するように、「私は行動を引き起こすことができる」というのはある種の楽観論だ。そう考えることによって、悲観論者が試みもしないようなことを、我々は確信と熱意をもって成し遂げることができる。
*自由意志もまた大問題。
ジャーナリスト: でも、あなたが手を挙げたとき、それは事前に起きた事から必然として起きたことなのでしょうか? それとも、あるいは自由意志によって起こされたのでしょうか?
*
コッホ: あなたの質問を言い換えると、「物理法則は、形而上の意味において『自由な』意志が働く余地を残しているか」ということですね。誰しもがこの昔から議論されてきた問題に関する意見を持っている。しかし、一般に認められている答えはない。ただ、私は、個人の行動とその意図が解離しているという実例が多くあることも知っている。自分の人生でそういう矛盾した行動と意志の例を探し出すことができるでしょう。例えば、岩棚の上に「登ろう」と思っていても、身体が脅えてついてこないとか。あるいは山の中を走っていて、精神的にはくたびれているが、脚が勝手に走り続けてしまったりとか。催眠術、心霊術、自動筆記、パソコンを使ったコミュニケーション法(ファシリテイティッド・コミュニケーション、FC法)、憑依現象、群衆の中にいる時に感じる没個性化、臨床における解離性同一性障害などは、行動と意志経験の間の解離の極端な例だ。結局、私が手を上げるのが本当に自由なのかどうか、それがリヒャルト・ワーグナーの「ニーベルングの指輪」に出てくるジークフリート神が世界秩序を破壊するときぐらい自由なのかどうかは、私にはわからない。
*わたしは自由意志は錯覚だと主張せざるを得ない。しかし、ここで言葉の意味を哲学的に掘り下げている暇があったら、人間のニューロン・ネットワークをどのようにして「測定」するのか、かなり奇妙なアイディアまで含めて、トライした方がいい。
ジャーナリスト: コッホ教授にとっては、自由意志の問題は、NCCの探究とは別問題だととらえてもよろしいでしょうか。
*
コッホ: まさにそのとおり。自由意志が存在しても存在しなくても、感覚経験という難問については説明がなされなければならない。
*そうです。
ジャーナリスト: NCCの発見は、我々に何をもたらすと思いますか?
*
コッホ: NCCの状態をオンラインで測定する技術のような、実際に役に立つものが我々に身近になるのは確かでしょう。医療従事者は、そういう意識計のようなものを使って、未熟児および幼児、重度の自閉症患者あるいは老人性痴呆症、負傷のため話すことも合図を送ることもできない患者などの意識状態をモニターすることができるようになる。また、それによって、麻酔技術もさらに進むだろう。意識がどのように脳から生じるのかが理解されれば、科学者はどの動物種には感覚能力があるかがわかるようになるだろう。霊長類は、世界を我々と同じように視覚と聴覚を通して経験しているだろうか? 哺乳動物はどうか? 多細胞生物は? これらの問題の解決は、動物権アニマル・ライトの議論に深く影響するはずだ。
*そうかな?
ジャーナリスト: 具体的にはどのように?
*
コッホ: NCCを持たない種は、ある知覚入力に対して一定の運動を起こす、というシステムの集合体、すなわち、主観的な経験のないゾンビと見なせる。そのようなゾンビ的な生物に、様々な状況でNCCを示す動物と同じレベルの保護を与える必要はないだろう。
*そうか?
ジャーナリスト: ということは、苦痛を感じる動物をつかって動物実験などはできないことになりますか?
*
コッホ: 理想的にいえば、確かに動物実験などしないほうがいい。しかし、実際にはそうもいかない。私は一人の娘を乳幼児突然死症候群で誕生の八週間後に失ったことがある。私の父親はパーキンソン病で十二年間も苦しみ、最期にはアルツハイマー病との合併症を起こして死んでしまった。私の親友は精神分裂病の最も強烈な発作中に自殺してしまった。こういう悲劇や数多くの神経系の病理を根絶するためには、動物実験はどうしても必要となる。細心の注意と、同情、場合によっては、(この本に記述されたサル研究の大部分のように)動物達が自発的に我々に協力してくれるような環境を整えて実験することが大事だ。
*
ジャーナリスト: 倫理問題や宗教に対してNCCの発見はどのような意味をもつでしょうか?
*
コッホ: 形而上学の視点から言えば、神経科学が相関関係コリレーションを越えて因果関係コーゼーションに辿り着けるかどうかというのが重要なポイントになる。科学者が求めているのは、神経の活動から主観的な知覚表象へと続く、一続きの因果関係を説明する理論なのだ。「どの生物」に「どんな条件の下で」主観的な感情は生成されるのか?「何のために」、そして「どのように」意識が生じてくるのかを説明する理論が。もしも、万に一つの可能性として、そういう理論を公式化することができたとしよう。その公式が、客観的に測定することができない、今のところ知られていない存在論上の実体を含まずに構築されるとしよう。このような理論体系は、ルネッサンスにはじまった科学的な努力の結晶が、最後の大きな山を登りつめたことの証となるだろう。数学的に言えば、「閉じた系」において、精神が物質からどのように発生するかを定量的に説明することが可能になる。この理論は、倫理問題への重大な影響を与えることになるし、新しい人間の概念を生み出すことにもつながるだろう。人間はいつの時代も、どの文化においても、あるべき人の姿というものを概念として伝統的につくりあげてきたが、そういう従来のイメージとは根本的に異なる人間像が生まれてくるかもしれない。
*それはそうだ。でも、そんな風呂敷を広げる前に、「何か」を「測定」しよう。
ジャーナリスト:必ずしも、誰でもがそういったシナリオに興奮するわけではないと思います。理論化が成功すれば、宇宙からすべての意味を奪い去ってしまうことになるかもしれない。科学は無慈悲で、人間性を失わせる側面があるが、意識の解明に至っては、その最たるものだと主張する人たちも出てくるでしょう。
*理論化が成功していなければ、安心していられるのですか?その人たちは。おかしなことだ。
*たとえていえば、円周率は、3.1と3.2の間にあるだろうと言われていて、しかし、はっきりとは証明されなくて、具体的に、3.15よりも大きいのか小さいのかも分かっていないという段階であるとして、しかしそれでも、半径と円周との間には、比例的な関係があるだろうとは推定できるのであって、はっきりしていないから、比例もしないだろうと言っているのはやはり納得できない。
コッホ: そんなことはない。新たな知識を得ることで、世界の素晴らしさを感じられなくなってしまうなんてことはない。物を見たり、嗅いだり、味わったり、触れたりすることのできる、全ての物質はたった九十二個の原子から出来上がっているということに対して、私は畏怖の念すら感じる。あなたも私も、この本も空気も地面も、空の星だって、全部が全部ですよ。これらの原子は、周期表の上に並べることすらできる。原子はさらに、陽子・中性子・電子のより3つの基本的な要素からできている。神秘主義の知識がこういった科学知識以上に、満足感と畏怖をもたらすことがあるだろうか?また、科学知識の理解によって、人類・犬・自然・読書・音楽への私の愛が一ビットたりとも減少するなんてことは全くない。
*ここはわたしは違う。世界観や人間観に大きな影響があると思う。そして、すでにあるべきだと思うのである。それがないというのは、何か誤解をしているのだろうと思う。
ジャーナリスト:宗教はどうでしょうか?多くの人が身体が死んだ後も生き続けるある種の永久の魂を信じています。彼等に対しては何ていいますか。
*
コッホ:彼らが抱いている信仰の多くは、現代科学の世界観とはどうしても矛盾を起こしてしまう。私がはっきりと言えるのは、すべての意識的な行為や意図には、物理的な何かに相関しているということだ。生命が終わると、意識も終わる。脳なしに精神は存在しないからだ。この否定しようのない事実も、魂の存在、蘇生の可能性、および神に関しての信仰と矛盾しないかもしれない。
*彼らが抱いている信仰の多くは確かに矛盾をひきおこす。しかし、非常に限られた、すばらしく洗練された信仰の体系は、現代科学の世界観と矛盾を起こさない。神に関しての信仰と矛盾しない。
ジャーナリスト: コッホ教授は今、この本を書くという五年間の苦難を終えました。お子さんも大学に入学しましたし、これからの人生の目標についてお聞かせください。
*
コッホ:モーリス・ヘルツォクがヒマラヤ山脈の初登頂を成し遂げたときの記録「アンナプルナ」の結びの言葉の通りです:人生には他にもアンナプルナ山麓はあるさ。
『意識の探求』の参考文献80-92
参考文献80
• Tamura, H. and Tanaka, K. “Visual response properties of cells in
the ventral and dorsal parts of the macque inferotemporal cortex,”
Cerebral Cortex 11:384–399 (2001).
• Tanaka, K. “Inferotemporal cortex and object vision,” Ann. Rev.
Neurosci. 19:109–139 (1996).
• Tanaka, K. “Columnar organization in the inferotemporal cortex.” In:
Cerebral Cortex. Vol. 12. Rockland, K.S., Kaas, J.H., and Peters, A.,
eds., pp. 469–498. New York: Plenum Press (1997).
• Tanaka, K. “Columns for complex visual object features in the inferotemporal
cortex: Clustering of cells with similar but slightly different
stimulus selectivities,” Cerebral Cortex 13:90–99 (2003).
• Tang, S. and Guo, A. “Choice behavior of Drosophila facing contradictory
visual cues,” Science 294:1543–1547 (2001).
• Tang, Y.-P., Shimizu, E., Dube, G.R., Rampon, C., Kerchner, G.A.,
Zhuo, M., Liu, G., and Tsien, J.Z. “Genetic enhancement of learning
and memory in mice,” Nature 401:63–69 (1999).
• Taylor, J.G. The Race for Consciousness. Cambridge, UK: MIT Press
(1998).
• Taylor, J.L. and McCloskey, D.I. “Triggering of preprogrammedmovements
as reactions to masked stimuli,” J. Neurophysiol. 63:439–444
(1990).
• Teller, D.Y. “Linking propositions,” Vision Res. 24:1233–1246 (1984).
• Teller, D.Y. and Pugh, E.N. Jr. “Linking propositions in color vision.”
In: Color Vision: Physiology and Psychophysics. Mollon, J.D. and
Sharpe, L.T., eds., London: Academic Press (1983).
• Thiele, A., Henning, P., Kubschik, M., and Hoffmann, K.-P. “Neural
mechanisms of saccadic suppression,” Science 295:2460–2462 (2002).
• Thiele, A. and Stoner, G. “Neuronal synchrony does not correlate with
motion coherence in cortical area MT,” Nature 23:366–370 (2003).
• Thier P., Haarmeier, T., Treue, S., and Barash, S. “Absence of a
common functional denominator of visual disturbance in cerebellar
disease,” Brain 122:2133–2146 (1999).
参考文献81
• Thomas, O.M., Cumming, B.G., and Parker, A.J. “A specialization
for relative disparity in V2,” Nature Neurosci. 5:472–478 (2002).
• Thompson, K.G. and Schall, J.D. “The detection of visual signals by
macaque frontal eye field during masking,” Nature Neurosci. 2:283–
288 (1999).
• Thompson, K.G., and Schall, J.D. “Antecedents and correlates of visual
detection and awareness in macaque prefrontal cortex,” Vision
Res. 40:1523–1538 (2000).
• Thorpe, S., Fize, D., and Marlot, C. “Speed of processing in the human
visual system,” Nature 381:520–522 (1996).
• Tolias, A.S., Smirnakis, S.M., Augath, M.A., Trinath, T., and Logothetis,
N.K. “Motion processing in the macaque: Revisited with
functional magnetic resonance imaging,” J. Neurosci. 21:8594–8601
(2001).
• Tomita, H., Ohbayashi,M., Nakahara, K., Hasegawa, I., andMiyashita,
Y. “Top-down signal from prefrontal cortex in executive control of
memory retrieval,” Nature 401:699–703 (1999).
• Tong, F. and Engel, S.A. “Interocular rivalry revealed in the human
cortical blind-spot representation,” Nature 411:195–199 (2001).
• Tong, F., Nakayama, K., Vaughan, J.T., and Kanwisher, N. “Binocular
rivalry and visual awareness in human extrastriate cortex,” Neuron
21:753–759 (1998).
• Tong, F., Nakayama, K., Moscovitch,M.,Weinrib, O., and Kanwisher,
N. “Response properties of the human fusiform face area,” Cogn. Neuropsychol.
17:257–279 (2000).
• Tononi, G. and Edelman, G.M. “Consciousness and complexity,” Science
282:1846–1851 (1998).
• Tootell, R.B. and Hadjikhani, N. “Where is ‘dorsal V4’ in human
visual cortex? Retinotopic, topographic, and functional evidence,”
Cerebral Cortex 11:298–311 (2001).
• Tootell, R.B., Hadjikhani, N., Mendola, J.D., Marrett, S., and Dale,
A.M. “From retinotopy to recognition: Functional MRI in human
visual cortex,” Trends Cogn. Sci. 2:174–183 (1998).
参考文献82
• Tootell, R.B., Mendola, J.D., Hadjikhani, N., Ledden, P.J., Liu, A.K.,
Reppas, J.B., Sereno, M.I., and Dale, A.M. “Functional analysis of
V3A and related areas in human visual cortex,” J. Neurosci. 17:7060–
7078 (1997).
• Tootell, R.B., Reppas, J.B., Dale, A.M., Look, R.B., Sereno, M.I.,
Malach, R., Brady, T.J., and Rosen, B.R. “Visual motion aftereffect
in human cortical area MT revealed by functional magnetic resonance
imaging,” Nature 375:139–141 (1995).
• Tootell, R.B. and Taylor, J.B. “Anatomical evidence for MT and additional
cortical visual areas in humans,” Cerebral Cortex 5:39–55
(1995).
• Tranel, D. and Damasio, A.R. “Knowledge without awareness: An
autonomic index of facial recognition by prosopagnosics,” Science
228:1453–1454 (1985).
• Treisman, A. “Features and Objects: The Fourteenth Bartlett Memorial
Lecture,” Quart. J. Exp. Psychology 40A:201–237 (1988).
• Treisman, A. “The binding problem,” Curr. Opinion Neurobiol. 6:171–
178 (1996).
• Treisman, A. “Feature binding, attention and object perception,”
Proc. R. Soc. Lond. B 353:1295–1306 (1998).
• Treisman, A. and Gelade, G. “A feature-integration theory of attention,”
Cogn. Psychol. 12:97–136 (1980).
• Treisman, A. and Schmidt, H. “Illusory conjunctions in the perception
of objects,” Cogn. Psychol. 14:107–141 (1982).
• Treue, S. and Martinez-Trujillo, J.C. “Feature-based attention influences
motion processing gain in macaque visual cortex,” Nature
399:575–578 (1999).
• Treue, S. and Maunsell, J.H.R. “Attentional modulation of visual motion
processing in cortical areas MT and MST,” Nature 382:539–541
(1996).
• Tsal, Y. “Do illusory conjunctions support feature integration theory?
A critical review of theory and findings,” J. Exp. Psychol. Hum.
Percept. Perform. 15:394–400 (1989).
参考文献83
• Tsotsos, J.K. “Analyzing vision at the complexity level,” Behav.Brain
Sci. 13:423–469 (1990).
• Tsunoda, K., Yamane, Y., Nishizaki, M., and Tanifuji, M. “Complex
objects represented in macaque inferotemporal cortex by the combination
of feature columns,” Nature Neurosci. 4:832–838 (2001).
• Tully, T. “Toward a molecular biology of memory: The light’s coming
on!,” Nature Neurosci. 1:543–545 (1998).
• Tully, T. and Quinn, W.G. “Classical conditioning and retention in
normal and mutant Drosophila melanogaster,” J. Comp. Physiol. A
157:263–277 (1985).
• Tulunay-Keesey, ¨U. “Fading of stabilized retina images,” J. Opt. Soc.
Am. 72:440–447 (1982).
• Tulving, E. “Memory and consciousness,” Canadian Psychology 26:1–
26 (1985).
• Tulving, E. “Varieties of consciousness and levels of awareness in memory.”
In: Attention: Selection, Awareness and Control. A Tribute to
Donald Broadbent. Baddeley, A. and Weiskrantz, L., eds., pp. 283–
299. Oxford, UK: Oxford University Press (1993).
• Turing, A. “Computing machinery and intelligence,” Mind 59:433–
460 (1950).
• Ullman, S. “Visual routines,” Cognition 18:97–159 (1984).
• Ungerleider, L.G. and Mishkin, M. “Two cortical visual systems.”
In: Analysis of Visual Behavior. Ingle, D.J., Goodale, M.A., and
Mansfield, R.J.W., eds., pp. 549–586. Cambridge, MA: MIT Press
(1982).
• Vallar, G. and Shallice, T., eds. Neuropsychological Impairments of
Short-Term Memory. Cambridge, UK: Cambridge University Press
(1990).
• Vanduffel, W., Fize, D., Peuskens, H., Denys, K., Sunaert, S., Todd,
J.T., and Orban, G.A. “Extracting 3D from motion: Differences in human
and monkey intraparietal cortex,” Science 298:413–415 (2002).
• Van Essen, D.C. and Gallant, J.L. “Neural mechanisms of form and
motion processing in the primate visual system,” Neuron 13:1–10
(1994).
参考文献84
• Van Essen, D.C., Lewis, J.W., Drury, H.A., Hadjikhani, N., Tootell,
R.B., Bakircioglu, M., and Miller, M.I. “Mapping visual cortex in
monkeys and humans using surface-based atlases,” Vision Res. 41:1359–
1378 (2001).
• VanRullen, R. and Koch, C. “Competition and selection during visual
processing of natural scenes and objects,” J. Vision 3:75–85 (2003a).
• VanRullen, R. and Koch, C. “Visual selective behavior can be triggered
by a feed-forward process,” J. Cogn. Neurosci. 15:209–217
(2003b).
• VanRullen, R. and Koch, C. “Is perception discrete or continuous?”
Trends Cogn. Sci. 7:207–213 (2003c).
• VanRullen, R., Reddy L., and Koch, C. “Parallel and preattentive
processing are not equivalent,” J. Cogn. Neurosci., in press (2004).
• VanRullen, R. and Thorpe, S. “The time course of visual processing:
From early perception to decision making,” J. Cogn. Neurosci.
13:454–461 (2001).
• van Swinderen, B. and Greenspan, R.J. “Salience modulates 20–30 Hz
brain activity in Drosophila,” Nature Neurosci. 6:579–586 (2003).
• Varela, F. “Neurophenomenology: A methodological remedy to the
hard problem,” J. Consc. Studies 3:330–350 (1996).
• Varela, F., Lachaux, J.-P., Rodriguez, E., and Martinerie, J. “The
brainweb: Phase synchronization and large-scale integration,” Nature
Rev. Neurosci. 2:229–239 (2001).
• Velmans, M. “Is human information processing conscious?” Behav.
Brain Sci. 14:651–726 (1991).
• Venables, P.H. “Periodicity in reaction time,” Br. J. Psychol. 51:37–
43 (1960).
• Vgontzas, A.N. and Kales, A. “Sleep and its disorders,” Ann. Rev.
Med. 50:387–400 (1999).
• Vogeley, K. “Hallucinations emerge from an imbalance of self-monitoring
and reality modeling,” Monist 82:626–644 (1999).
• Volkmann, F.C., Riggs, L.A., and Moore, R.K. “Eyeblinks and visual
suppression,” Science 207:900–902 (1980).
参考文献85
• von der Heydt, R., Peterhans, E., and Baumgartner, G. “Illusory contours
and cortical neuron responses,” Science 224:1260–1262 (1984).
• von der Heydt, R., Zhou, H., and Friedman, H.S. “Representation of
stereoscopic edges in monkey visual cortex,” Vision Res. 40:1955–
1967 (2000).
• von der Malsburg, C. “The correlation theory of brain function.” MPI
Biophysical Chemistry, Internal Report 81–2 (1981). Reprinted in
Models of Neural Networks II, Domany, E., van Hemmen, J.L., and
Schulten, K., eds. Berlin: Springer (1994).
• von der Malsburg, C. “Binding in models of perception and brain
function,” Curr. Opin. Neurobiol. 5:520–526 (1995).
• von der Malsburg, C. “The what and why of binding: The modeler’s
perspective,” Neuron 24:95–104 (1999).
• von Economo, C. and Koskinas, G.N. Die Cytoarchitektonik der Hirnrinde
des erwachsenen Menschen. Wien, Austria: Julius Springer
(1925).
• von Helmholtz, H. Handbook of Physiological Optics. New York: Dover.
(1962). Translation of Handbuch der physiologischen Optik. 3 volumes,
ed. and trans. by Southall, J.P.C., Hamburg, Voss, 1856, 1860,
and 1988.
• Von Senden, M. Space and Sight: The Perception of Space and Shape
in the Congenitally Blind Before and After Operation. Glencoe, IL:
Free Press (1960).
• Vuilleumier, P., Armony, J.L., Clarke, K., Husain, M., Driver, J.,
and Dolan, R.J. “Neural response to emotional faces with and without
awareness: Event-related fMRI in a parietal patient with visual
extinction and spatial neglect,” Neuropsychologia 40:156–166 (2002).
• Vuilleumier, P., Armony, J.L., Driver, J., and Dolan, R.J. “Effects
of attention and emotion on face processing in the human brain: An
event-related fMRI study,” Neuron 30:829–841 (2001).
• Vuilleumier, P., Hester, D., Assal, G., and Regli, F. “Unilateral spatial
neglect recovery after sequential strokes,” Neurol. 46:184–189 (1996).
• Wachtler, T., Sejnowski, T.J., and Albright, T.D. “Representation
of color stimuli in awake macaque primary visual cortex,” Neuron
37:681–691 (2003).
参考文献86
• Wada, Y. and Yamamoto, T. “Selective impairment of facial recognition
due to a haematoma restricted to the right fusiform and lateral
occipital region,” J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 71:254–257
(2001).
• Wade, A.R., Brewer, A.A., Rieger, J.W., and Wandell, B.A. “Functional
measurements of human ventral occipital cortex: Retinotopy
and colour,” Phil. Trans. R. Soc. Lond. B 357:963–973 (2002).
• Walther, D., Itti, L., Riesenhuber, M., Poggio, T., and Koch, C. “Attentional
selection for object recognition—A gentle way.” In: Biologically
Motivated Computer Vision. B¨ulthoff, H.H., Lee, S.-W., Poggio,
T., and Wallraven, C., eds., pp. 472–479. Berlin: Springer (2002).
• Wandell, B.A. Foundations of Vision. Sunderland, MA: Sinauer (1995).
• Wang, G., Tanaka, K., and Tanifuji, M. “Optical imaging of functional
organization in the monkey inferotemporal cortex,” Science
272:1665–1668 (1996).
• Warland, D.K., Reinagel, P., and Meister, M. “Decoding visual information
from a population of retinal ganglion cells,” J. Neurophysiol.
78:2336–2350 (1997).
• Watanabe, T., Harner, A.M., Miyauchi, S., Sasaki, Y., Nielsen, M.,
Palomo, D., and Mukai, I. “Task-dependent influences of attention on
the activation of human primary visual cortex,” Proc. Natl. Acad.
Sci. USA 95:11489–11492 (1998).
• Watanabe, M. and Rodieck, R.W. “Parasol and midget ganglion cells
of the primate retina,” J. Comp. Neurol. 289:434–454 (1989).
• Watkins, J.C. and Collingridge, G.L., eds. The NMDA Receptor. Oxford,
UK: IRL Press (1989).
• Watson, L. Jacobson’s Organ and the Remarkable Nature of Smell.
New York: Plume Books (2001).
• Webster, M.J., Bachevalier, J., and Ungerleider, L.G. “Connections of
inferior temporal areas TEO and TE with parietal and frontal cortex
in macaque monkeys,” Cerebral Cortex 4:470–483 (1994).
• Wegner, D.M. The Illusion of Conscious Will. Cambridge, MA: MIT
Press (2002).
参考文献87
• Weiskrantz, L. “Blindsight revisited,” Curr. Opinion Neurobiol. 6:215–
220 (1996).
• Weiskrantz, L. Consciousness Lost and Found. Oxford, UK: Oxford
University Press (1997).
• Weller, L.,Weller, A., Koresh-Kamin, H., and Ben-Shoshan, R.“Menstrual
synchrony in a sample of working women,” Psychoneuroendocrinology
24:449–459 (1999).
• Wen, J., Koch, C., and Braun, J. “Spatial vision thresholds in the
near absence of attention,” Vision Res. 37:2409–2418 (1997).
• Wertheimer, M. “Experimentelle Studien ¨uber das Sehen von Bewegung,”
Z. Psychologie 61:161–265 (1912).
• Wessinger, C.M., Fendrich, R., and Gazzaniga, M.S. “Islands of residual
vision in hemianopic patients,” J. Cogn. Neurosci. 9:203–211
(1997).
• Westheimer, G. and McKee, S.P. “Perception of temporal order in
adjacent visual stimuli,” Vision Res. 17:887–892 (1977).
• Whinnery, J.E. and Whinnery, A.M. “Acceleration-induced loss of
consciousness,” Archive Neurol. 47:764–776 (1990).
• White, C. “Temporal numerosity and the psychological unit of duration,”
Psychol. Monographs: General & Appl. 77:1–37 (1963).
• White, C. and Harter, M.R. “Intermittency in reaction time and perception,
and evoked response correlates of image quality,” Acta Psychol.
30:368–377 (1969).
• White, E.L. Cortical Circuits. Boston: Birkh¨auser (1989).
• Wigan, A.L. “Duality of the mind, proved by the structure, functions,
and diseases of the brain,” Lancet 1 :39–41 (1844).
• Wilken, P.C. “Capacity limits for the detection and identification of
change: Implications for models of visual short-term memory.” Ph.D.
Thesis. University of Melbourne, Australia (2001).
• Wilkins, A.J., Shallice, T., and McCarthy, R. “Frontal lesions and
sustained attention,” Neuropsychologia 25:359–65 (1987).
• Williams, D.R., MacLeod, D.E.A., and Hayhoe, M.M. “Foveal tritanopia,”
Vision Res. 21:1341–1356 (1981).
参考文献88
• Williams, D.R., Sekiguchi, N., Haake, W., Brainard, D., and Packer,
O. “The cost of trichromacy for spatial vision.” In: Pigments to
Perception. Lee, B. and Valberg, A., eds., pp. 11–22. New York:
Plenum Press (1991).
• Williams, S.R. and Stuart, G.J. “Dependence of EPSP efficacy on
synapse location in neocortical pyramidal neurons,” Science 295:1907–
1910 (2002).
• Williams, S.R. and Stuart, G.J. “Role of dendritic synapse location in
the control of action potential output,” Trends Neurosci. 26:147–154
(2003).
• Williams, T. The Milk Train Doesn’t Stop Here Anymore. Norfolk,
CT: A New Directions Book (1964).
• Williams, Z.M., Elfar, J.C., Eskandar, E.N., Toth, L.J., and Assad,
J.A. “Parietal activity and the perceived direction of ambiguous apparent
motion,” Nature Neurosci. 6:616–623 (2003).
• Wilson, B.A. and Wearing, D. “Prisoner of consciousness: A state
of just awakening following Herpes Simplex Encephalitis.” In: Broken
Memories: Neuropsychological Case Studies. Campbell, R. and
Conway, M., eds., pp. 15–30. Oxford, UK: Blackwell (1995).
• Wilson, H.R., Levi, D., Maffei, L., Rovamo, J., and DeValois, R. “The
Perception of Form: Retina to Striate Cortex.” In: Visual Perception:
The Neurophysiological Foundations. Spillman, L. and Werner, J.S.,
eds., pp. 231–272. San Diego, CA: Academic Press (1990).
• Wilson, M.A. and McNaughton, B.L. “Dynamics of the hippocampal
ensemble code for space,” Science 261:1055–1058 (1993).
• Wittenberg, G.M. and Tsien, J.Z. “An emerging molecular and cellular
framework for memory processing by the hippocampus,” Trends
Neurosci. 25:501–505 (2002).
• Wojciulik, E. and Kanwisher, N. “Implicit but not explicit feature
binding in a Balint’s patient,” Visual Cognition 5:157–181 (1998).
• Wolfe, J.M. “Reversing ocular dominance and suppression in a single
flash,” Vision Res. 24:471–478 (1984).
• Wolfe, J.M. “‘Effortless’ texture segmentation and ‘parallel’ visual
search are not the same thing,” Vision Res. 32:757–763 (1992).
参考文献89
• Wolfe, J.M. “Guided search 2.0: A revised model of visual search,”
Psychon. Bull. Rev. 1:202–238 (1994).
• Wolfe, J.M. “Visual Search.” In: The Psychology of Attention. Pashler,
H., ed., pp. 13–73. Cambridge, MA: MIT Press (1998a).
• Wolfe, J.M. “Visual Memory: What do you know about what you
saw?” Curr. Biol. 8:R303–R304 (1998b).
• Wolfe, J.M. “Inattentional amnesia.” In: Fleeting Memories. Coltheart,
V., ed., pp. 71–94. Cambridge, MA: MIT Press (1999).
• Wolfe, J.M. and Bennett, S.C. “Preattentive object files: Shapeless
bundles of basic features,” Vision Res. 37:25–44 (1997).
• Wolfe, J.M. and Cave, K.R. “The psychophysical evidence for a binding
problem in human vision,” Neuron 24:11–17 (1999).
• Wong, E. and Mack, A. “Saccadic programming and perceived location,”
Acta Psychologica 48:123–131 (1981).
• Wong-Riley, M.T.T. “Primate visual cortex: Dynamic metabolic organization
and plasticity revealed by cytochrome oxidase.” In: Cerebral
Cortex. Vol. 10. Peters, A. and Rockland, K.S., eds., pp. 141–200.
New York: Plenum Press (1994).
• Woolf, N.J. “Cholinergic transmission: Novel signal transduction.”
In: Neurochemistry of Consciousness. Perry, E., Ashton, H., and
Young, A., eds., pp. 25–41. Amsterdam: John Benjamins (2002).
• Wu, M.-F., Gulyani, S.A., Yau, E., Mignot, E., Phan, B., and Siegel,
J.M. “Locus coeruleus neurons: Cessation of activity during cataplexy,”
Neurosci. 91:1389–1399 (1999).
• Wurtz, R.H., Goldberg, M.E., and Robinson, D.L. “Brain mechanisms
of visual attention,” Sci. Am. 246:124–135 (1982).
• Yabuta, N.H., Sawatari, A., and Callaway, E.M. “Two functional
channels from primary visual cortex to dorsal visual cortical areas,”
Science 292:297–300 (2001).
• Yamagishi, N., Anderson, S.J., and Ashida H. “Evidence for dissociation
between the perceptual and visuomotor systems in humans,”
Proc. R. Soc. Lond. B 268:973–977 (2001).
参考文献90
• Yamamoto, M., Wada, N., Kitabatake, Y., Watanabe, D., Anzai, M.,
Yokoyama, M., Teranishi, Y., and Nakanishi, S. “Reversible suppression
of glutamatergic neurotransmission of cerebellar granule cells in
vivo by genetically manipulated expression of tetanus neurotoxin light
chain,” J. Neurosci. 23:6759–6767 (2003).
• Yang, Y., Rose, D., and Blake, R. “On the variety of percepts associated
with dichoptic viewing of dissimilar monocular stimuli,” Perception
21:47–62 (1992).
• Young, M.P. “Connectional organisation and function in the macaque
cerebral cortex. In: Cortical Areas: Unity and Diversity, Sch¨uz, A.
and Miller, R., eds., pp. 351–375. London: Taylor and Francis (2002).
• Young, M.P. and Yamane, S. “Sparse population coding of faces in
the inferotemporal cortex,” Science 256:1327–1331 (1992).
• Yund, E.W., Morgan, H., and Efron, R. “The micropattern effect and
visible persistence,” Perception & Psychophysics 34:209–213 (1983).
• Zafonte, R.D. and Zasler, N.D. “The minimally conscious state: Definition
and diagnostic criteria,” Neurology 58:349–353 (2002).
• Zeki, S. “Color coding in rhesus monkey prestriate cortex,” Brain Res.
27:422–427 (1973).
• Zeki, S. “Functional organization of a visual area in the posterior bank
of the superior temporal sulcus of the rhesus monkey,” J. Physiol.
236:549–573 (1974).
• Zeki, S.“Colour coding in the cerebral cortex: The responses of wavelengthselective
and color-coded cells in monkey visual cortex to changes in
wavelength composition,” Neurosci. 9:767–781 (1983).
• Zeki, S. “A century of cerebral achromatopsia,” Brain 113:1721–1777
(1990).
• Zeki, S. “Cerebral akinetopsia (Visual motion blindness),” Brain 114:811–
824 (1991).
• Zeki, S. A Vision of the Brain. Oxford, UK: Oxford University Press
(1993).
• Zeki, S. “The motion vision of the blind,” Neuroimage 2:231–235
(1995).
参考文献91
• Zeki, S. “Parallel processing, asynchronous perception, and a distributed
system of consciousness in vision,” Neuroscientist 4:365–372
(1998).
• Zeki, S. “Localization and globalization in conscious vision,” Ann.
Rev. Neurosci. 24:57–86 (2001).
• Zeki, S. “Improbable areas in the visual brain,” Trends Neurosci.
26:23–26 (2003).
• Zeki, S. and Bartels, A. “Toward a theory of visual consciousness,”
Consc. & Cognition 8:225–259 (1999).
• Zeki, S., McKeefry, D.J., Bartels, A., and Frackowiak, R.S.J. “Has a
new color area been discovered?” Nature Neurosci. 1:335–336 (1998).
• Zeki, S. and Moutoussis, K. “Temporal hierarchy of the visual perceptive
systems in the Mondrian world,” Proc. R. Soc. Lond. B
264:1415–1419 (1997).
• Zeki, S. and Shipp, S. “The functional logic of cortical connections,”
Nature 335:311–317 (1988).
• Zeki, S., Watson, J.D., Lueck, C.J., Friston, K.J., Kennard, C., and
Frackowiak, R.S.J. “A direct demonstration of functional specialization
in human visual cortex,” J. Neurosci. 11:641–649 (1991).
• Zeki, S., Watson, J.D., and Frackowiak, R.S.J. “Going beyond the
information given: The relation of illusory motion to brain activity,”
Proc. Roy. Soc. Lond. B 252:215–222 (1993).
• Zeman, A. “Consciousness,” Brain 124:1263–1289 (2001).
• Zhang, K., Ginzburg, I., McNaughton, B.L., and Sejnowski, T.J. “Interpreting
neuronal population activity by reconstruction: Unified
framework with application to hippocampal place cells,” J. Neurophysiol.
79:1017–1044 (1998).
• Zihl J., von Cramon, D., and Mai, N. “Selective disturbance of movement
vision after bilateral brain-damage,” Brain 106:313–340 (1983).
• Zipser, D. and Andersen, R.A. “A back-propagation programmed network
that simulates response properties of a subset of posterior parietal
neurons,” Nature 331:679–684 (1988).
参考文献92
• Zrenner, E. Neurophysiological Aspects of Color Vision in Primates:
Comparative Studies on Simian Retinal Ganglion Cells and the Human
Visual System. Berlin: Springer (1983).
『意識の探求』の参考文献60-79
参考文献60
• Rockland, K.S., Kaas, J.H., and Peters, A., eds., pp. 205–241. New
York: Plenum (1997).
• Nunn, J.A., Gregory, L.J., Brammer, M., Williams, S.C.R., Parslow,
D.M., Morgan, M.J., Morris, R.G., Bullmore, E.T., Baron-Cohen, S.,
and Gray, J.A. “Functional magnetic resonance imaging of synesthesia:
Activation of V4/V8 by spoken words,” Nature Neurosci. 5:371–
375 (2002).
• O’Connor, D.H., Fukui, M.M., Pinsk, M.A., and Kastner, S. “Attention
modulates responses in the human lateral geniculate nucleus,”
Nature Neurosci. 5:1203–1209 (2002).
• O’Craven, K. and Kanwisher, N. “Mental imagery of faces and places
activates corresponding stimulus-specific brain regions,” J. Cogn. Neursci.
12:1013–1023 (2000).
• ¨Ohman, A. and Soares, J.J. “Emotional conditioning to masked stimuli:
Expectancies for aversive outcomes following nonrecognized fearrelevant
stimuli,” J. Exp. Psychol. Gen. 127:69–82 (1998).
• Ojemann, G.A., Ojemann, S.G., and Fried, I. “Lessons from the human
brain: Neuronal activity related to cognition,” Neuroscientist
4:285–300 (1998).
• Ojima, H. “Terminal morphology and distribution of corticothalamic
fibers originating from layers 5 and 6 of cat primary auditory cortex,”
Cerebral Cortex 4:646–663 (1994).
• O’Keefe, J. and Nadel, L. The Hippocampus as a Cognitive Map. Oxford,
UK: Clarendon (1978).
• O’Keefe, J. and Recce, M.L. “Phase relationship bteween hippocampal
place units and the EEG theta rhythm,” Hippocampus 3:317–330
(1993).
• Ono, H. and Barbeito, R. “Ultocular discrimination is not sufficient
for utrocular identification,” Vision Res. 25:289–299 (1985).
• O’Regan, J.K. “Solving the ‘real’ mysteries of visual perception: The
world as an outside memory,” Canadian J. Psychol. 46:461–488
(1992).
• O’Regan, J.K. and No¨e, A. “A sensorimotor account of vision and
visual consciousness,” Behav. Brain Sci. 24:939–1001 (2001).
参考文献61
• O’Regan, J.K., Rensink, R.A., and Clark, J.J. “Change-blindness as
a result of mudsplashes,” Nature 398:34 (1999).
• O’Shea, R.P. and Corballis, P.M. “Binocular rivalry between complex
stimuli in split-brain observers,” Brain & Mind 2:151–160 (2001).
• Oxbury, J., Polkey, C.E., and Duchowny, M., eds. Intractable Focal
Epilepsy. Philadelphia: Saunders (2000).
• Pagels, H. The Dreams of Reason. New York: Simon and Schuster
(1988).
• Palm, G. Neural Assemblies: An Alternative Approach to Artificial
Intelligence. Berlin: Springer (1982).
• Palm, G. “Cell assemblies as a guideline for brain research,” Concepts
Neurosci. 1:133–147 (1990).
• Palmer, L.A., Jones, J.P., and Stepnoski, R.A. “Striate receptive fields
as linear filters: Characterization in two dimensions of space.” In: The
Neural Basis of Visual Function. Leventhal, A.G., ed., pp. 246–265.
Boca Raton, FL: CRC Press (1991).
• Palmer, S. Vision Science: Photons to Phenomenology. Cambridge,
MA: MIT Press (1999).
• Pantages, E. and Dulac, C. “A novel family of candidate pheromone
receptors in mammals,” Neuron 28:835–845 (2000).
• Parasuraman, R., ed. The Attentive Brain. Cambridge, MA: MIT
Press (1998).
• Parker, A.J. and Krug, K. “Neuronal mechanisms for the perception
of ambiguous stimuli,” Curr. Opinion Neurobiol. 13:433–439 (2003).
• Parker, A.J. and Newsome, W.T. “Sense and the single neuron: Probing
the physiology of perception,” Ann. Rev. Neurosci. 21:227–277
(1998).
• Parra, G., Gulyas, A.I., and Miles, R. “How many subtypes of inhibitory
cells in the hippocampus?” Neuron 20:983–993 (1998).
• Parvizi, J. and Damasio, A.R. “Consciousness and the brainstem,”
Cognition 79:135–159 (2001).
• Pashler, H.E. The Psychology of Attention. Cambridge, MA: MIT
Press (1998).
参考文献62
• Passingham, R. The Frontal Lobes and Voluntary Action. Oxford,
UK: Oxford University Press (1993).
• Pastor, M.A. and Artieda, J., eds. Time, Internal Clocks, and Movement.
Amsterdam, Netherlands: Elsevier (1996).
• Paulesu, E., Harrison, J., Baron-Cohen, S., Watson, J.D., Goldstein,
L., Heather, J., Frackowiak, R.S.J., and Frith, C.D. “The physiology
of coloured hearing. A PET activation study of colour-word synaesthesia,”
Brain 118:661–676 (1995).
• Payne, B.R., Lomber, S.G., Villa, A.E., and Bullier, J. “Reversible deactivation
of cerebral network components,” Trends Neurosci. 19:535–
542 (1996).
• Pedley, T.A. and Guilleminault, C. “Episodic nocturnal wanderings
responsive to anticonvulsant drug therapy,” Ann. Neurol. 2:30–35
(1977).
• Penfield, W. The Mystery of the Mind. Princeton, NJ: Princeton
University Press (1975).(邦訳)塚田裕三, 山河宏訳,脳と心の正体,
法政大学出版局(1987).
• Penfield, W. and Jasper, H. Epilepsy and the Functional Anatomy of
the Human Brain. Boston: Little & Brown (1954).
• Penfield, W. and Perot, P. “The brain’s record of auditory and visual
experience: A final summary and discussion,” Brain 86:595–696
(1963).
• Penrose, R. The Emperor’s New Mind. Oxford, UK: Oxford University
Press (1989).(邦訳)林一訳,皇帝の新しい心: コンピュータ・心・
物理法則,みすず書房(1994).
• Penrose, R. Shadows of the Mind. Oxford, UK: Oxford University
Press (1994).(邦訳)林一訳,心の影: 意識をめぐる未知の科学を探
る1, 2,みすず書房(2001, 2002).
• Perenin, M.T. and Rossetti, Y. “Grasping without form discrimination
in a hemianopic field,” Neuroreport 7:793–797 (1996).
• Perez-Orive, J., Mazor, O., Turner, G.C., Cassenaer, S., Wilson, R.I.,
and Laurent, G. “Oscillations and sparsening of odor representation
in the mushroom body,” Science 297:359–365 (2002).
参考文献63
• Perrett, D.I., Hietanen, J.K., Oram, M.W., and Benson, P.J. “Organization
and functions of cells responsive to faces in the temporal
cortex,” Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. B 335:23–30 (1992).
• Perry, E., Ashton, H., and Young, A., eds. Neurochemistry of Consciousness.
Amsterdam, Netherlands: John Benjamins (2002).
• Perry, E., Walker, M., Grace, J., and Perry, R. “Acetylcholine in
mind: A neurotransmitter correlate of consciousness,” Trends Neurosci.
22:273–280 (1999).
• Perry, E. and Young, A. “Neurotransmitter networks.” In: Neurochemistry
of Consciousness. Perry, E., Ashton, H., and Young, A.,
eds., pp. 3–23. Amsterdam, Netherlands: John Benjamins (2002).
• Pessoa, L. and DeWeerd, P., eds. Filling-In: From Perceptual Completion
to Cortical Reorganization. New York: Oxford University Press
(2003).
• Pessoa, L., Thompson, E., and No¨e, A. “Finding out about filling in:
A guide to perceptual completion for visual science and the philosophy
of perception,” Behavioral and Brain Sci. 21:723–802 (1998).
• Peterhans, E. “Functional organization of area V2 in the awake monkey.”
In: Cerebral Cortex, Vol 12. Rockland, K.S., Kaas, J.H., and
Peters, A., eds., pp. 335–358. New York: Plenum Press (1997).
• Peterhans, E. and von der Heydt, R. “Subjective contours: Bridging
the gap between psychophysics and physiology,” Trends Neurosci.
14:112–119 (1991).
• Peters, A. and Rockland, K.S., eds. Cerebral Cortex. Vol. 10. New
York: Plenum Press (1994).
• Pettigrew, J.D. and Miller, S.M. “A ‘sticky’ interhemishperic switch in
bipolar disorder?” Proc. R. Soc. Lond. B Biol. Sci. 265:2141–2148
(1998).
• Philbeck, J.W. and Loomis, J.M. “Comparisons of two indicators of
perceived egocentric distance under full-cue and reduced-cue conditions,”
J. Exp. Psychology: Human Perception & Performance 23:72–
85 (1997).
• Pickersgill, M.J. “On knowing with which eye one is seeing,” Quart.
J. Exp. Psychol. 13:168–172 (1961).
参考文献64
• Pitts, W. and McCulloch, W.S. “How we know universals: The perception
of auditory and visual forms,” Bull. Math. Biophysics 9:127–
147 (1947).
• Plum, F. and Posner, J.B. The Diagnosis of Stupor and Coma. 3rd
ed. Philadelphia: FA Davis (1983).
• Pochon, J.-B., Levy, R., Poline, J.-B., Crozier, S., Leh´ericy, S., Pillon,
B., Deweer, B., Le Bihan, D., and Dubois, B. “The role of dorsolateral
prefrontal cortex in the preparation of forthcoming actions: An fMRI
study,” Cerebral Cortex 11:260–266 (2001).
• Poggio, G.F. and Poggio, T. “The analysis of stereopsis,” Ann. Rev.
Neurosci. 7:379–412 (1984).
• Poggio, T. “A theory of how the brain might work,” Cold Spring
Harbor Symp. Quant. Biol. 55:899–910 (1990).
• Poggio, T., Torre, V., and Koch, C. “Computational vision and regularization
theory,” Nature 317:314–319 (1985).
• Poincar´e, H. “Mathematical discovery.” In: Science and Method. pp.
46–63. New York: Dover Books (1952).(邦訳)吉田洋一訳,科学と
方法,岩波文庫(1953).
• Pollen, D.A. “Cortical areas in visual awareness,” Nature 377:293–294
(1995).
• Pollen, D.A. “On the neural correlates of visual perception,” Cerebral
Cortex 9:4–19 (1999).
• Pollen, D.A. “Explicit neural representations, recursive neural networks
and conscious visual perception,” Cerebral Cortex 13:807–814
(2003).
• Polonsky, A., Blake, R., Braun, J., and Heeger, D. “Neuronal activity
in human primary visual cortex correlates with perception during
binocular rivalry,” Nature Neurosci. 3:1153–1159 (2000).
• Polyak, S.L. The Retina. Chicago, IL: University of Chicago Press
(1941).
• P¨oppel, E. “Time perception.” In: Handbook of Sensory Physiology.
Vol. 8: Perception. Held, R., Leibowitz, H.W., and Teuber, H.-L.
eds., pp. 713–729. Berlin: Springer (1978).
参考文献65
• P¨oppel, E. “A hierarchical model of temporal perception,” Trends
Cogn. Sci. 1:56–61 (1997).
• P¨oppel, E., Held, R., and Frost, D. “Residual visual function after
brain wounds involving the central visual pathways in man,” Nature
243:295–296 (1973).
• P¨oppel, E. and Logothetis, N.K. “Neural oscillations in the brain.
Discontinuous initiations of pursuit eye movements indicate a 30-
Hz temporal framework for visual information processing,” Naturwissenschaften
73:267–268 (1986).
• Popper, K.R. and Eccles, J.C. The Self and its Brain. Berlin: Springer
(1977).(邦訳)大村裕, 西脇与作, 沢田允茂訳,自我と脳,新思索社
(2005).
• Porac, C. and Coren, S. “Sighting dominance and utrocular discrimination,”
Percept. Psychophys. 39:449–41 (1986).
• Posner, M.I. and Gilbert, C.D. “Attention and primary visual cortex,”
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 16:2585–2587 (1999).
• Posner, M.I., Snyder, C.R.R. and Davidson, B.J. “Attention and the
detection of signals,” J. exp. Psychol.: General 109:160–174 (1980).
• Potter, M.C. “Very short-term conceptual memory,” Memory & Cognition
21:156–161 (1993).
• Potter, M.C. and Levy, E.I. “Recognition memory for a rapid sequence
of pictures,” J. Exp. Psychol. 81:10–15 (1969).
• Pouget, A. and Sejnowski, T.J. “Spatial transformations in the parietal
cortex using basis functions,” J. Cogn. Neurosci. 9:222–237
(1997).
• Preuss, T.M. “What’s human about the human brain?” In: The New
Cognitive Neurosciences. 2nd ed., Gazzaniga, M.S., ed., pp. 1219–
1234. Cambridge, MA: MIT Press (2000).
• Preuss, T.M., Qi, H., and Kaas, J.H. “Distinctive compartmental organization
of human primary visual cortex,” Proc. Natl. Acad. Sci.
USA 96:11601–11606 (1999).
• Pritchard, R.M., Heron, W., and Hebb, D.O. “Visual perception approached
by the method of stabilized images,” Canad. J. Psychol.
14:67–77 (1960).
参考文献66
• Proffitt, D.R., Bhalla, M., Gossweiler, R., and Midgett, J. “Perceiving
geographical slant,” Psychonomic Bulletin & Rev. 2:409–428 (1995).
• Przybyszewski, A.W., Gaska, J.P., Foote, W., and Pollen, D.A. “Striate
cortex increases contrast gain of macaque LGN neurons,” Visual
Neurosci. 17:485–494 (2000).
• Puccetti, R. The Trial of John and Henry Norton. London: Hutchinson
(1973).
• Purpura, K.P. and Schiff, N.D. “The thalamic intralaminar nuclei:
Role in visual awareness,” Neuroscientist 3:8–14 (1997).
• Purves, D., Paydarfar, J.A., and Andrews, T.J. “The wagon wheel
illusion in movies and reality,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93:3693–
3697 (1996).
• Quinn, J.J., Oommen, S.S., Morrison, G.E., and Fanselow,M.S. “Posttraining
excitotoxic lesions of the dorsal hippocampus attenuate forward
trace, backward trace, and delay fear conditioning in a temporallyspecific
manner,” Hippocampus 12:495–504 (2002).
• Rafal, R.D. “Hemispatial neglect: Cognitive neuropsychological aspects.”
In: Behavioral Neurology and Neuropsychology. Feinberg,
T.E. and Farah, M.J., eds., pp. 319–336. New York: McGraw-Hill
(1997a).
• Rafal, R.D. “Balint syndrome.” In: Behavioral Neurology and Neuropsychology.
Feinberg, T.E. and Farah, M.J., eds., pp. 337–356. New
York: McGraw-Hill (1997b).
• Rafal, R.D. and Posner, M. “Deficits in human visual spatial attention
following thalamic lesions,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA 84:7349–
7353 (1987).
• Rakic, P. “A small step for the cell, a giant leap for mankind: A hypothesis
of neocortical expansion during evolution,” Trends Neurosci.
18:383–388 (1995).
• Ramachandran, V.S. “Blind spots,” Sci. Am. 266:86–91 (1992).
• Ramachandran, V.S. and Gregory, R.L. “Perceptual filling in of artificially
induced scotomas in human vision,” Nature 350:699–702 (1991).
参考文献67
• Ramachandram, V.S. and Hubbard, E.M. “Psychophysical investigations
into the neural basis of synaesthesia,” Proc. R. Soc. Lond. B
268:979–983 (2001).
• Ram`on y Cajal, S. “New ideas on the structure of the nervous system
of man and vertebrates.” Translated by Swanson, N. and Swanson,
L.M. fromLes nouvelles id´ees sur la structure du syst`eme nerveux chez
l’homme et chez les vert´ebr´es. Cambridge, MA: MIT Press (1991).
• Rao, R.P.N. and Ballard, D.H. “Predictive coding in the visual cortex:
A functional interpretation of some extra-classical receptive-field
effects,” Nature Neurosci. 2:79–87 (1999).
• Rao, R.P.N, Olshausen, B.A., and Lewicki, M.S., eds. Probabilistic
Models of the Brain. Cambridge, MA: MIT Press (2002).
• Rao, S.C., Rainer, G., and Miller, E.K. “Integration of what and
where in the primate prefrontal cortex,” Science 276:821–824 (1997).
• Ratliff, F. and Hartline, H.K. “The responses of Limulus optic nerve
fibers to patterns of illumination on the receptor mosaic,” J. Gen.
Physiol. 42:1241–1255 (1959).
• Ray, P.G., Meador, K.J., Smith, J.R., Wheless, J.W., Sittenfeld, M.,
and Clifton, G.L. “Cortical stimulation and recording in humans,”
Neurology 52:1044–1049 (1999).
• Reddy, L., Wilken, P., and Koch, C. “Face-gender discrimination in
the near-absence of attention,” J. Vision, in press (2004).
• Rees, G., Friston, K., and Koch, C. “A direct quantitative relationship
between the functional properties of human and macaque V5,” Nature
Neurosci. 3:716–723 (2000).
• Rees, G., Wojciulik, E., Clarke, K., Husain, M., Frith, C., and Driver,
J. “Unconscious activation of visual cortex in the damaged right hemisphere
of a parietal patient with extinction,” Brain 123:1624–1633
(2000).
• Reeves, A.G., ed. Epilepsy and the Corpus Callosum. New York:
Plenum Press (1985).
• Reingold, E.M. and Merikle, P.M. “On the inter-relatedness of theory
and measurement in the study of unconscious processes,” Mind Lang.
5:9–28 (1990).
参考文献68
• Rempel-Clower, N.L. and Barbas, H. “The laminar pattern of connections
between prefrontal and anterior temporal cortices in the rhesus
monkey is related to cortical structure and function,” Cerebral Cortex
10:851–865 (2000).
• Rensink, R.A. “Seeing, sensing, and scrutinizing,” Vision Res. 40:1469–
1487 (2000a).
• Rensink, R.A. “The dynamic representation of scenes,” Visual Cognition
7:17–42 (2000b).
• Rensink, R.A., O’Regan, J.K., and Clark, J.J. “To see or not to see:
The need for attention to perceive changes in scenes,” Psychological
Sci. 8:368–373 (1997).
• Revonsuo, A. “The reinterpretation of dreams: An evolutionary hypothesis
of the function of dreaming,” Behav. Brain Sci. 23:877–901
(2000).
• Revonsuo, A., Johanson, M., Wedlund, J.-E., and Chaplin, J. “The
zombie among us.” In: Beyond Dissociation. Rossetti, Y. and Revonsuo,
A., eds., pp. 331–351. Amsterdam, Netherlands: John Benjamins
(2000).
• Revonsuo, A., Wilenius-Emet, M., Kuusela, J., and Lehto, M. “The
neural generation of a unified illusion in human vision,” Neuroreport
8:3867–3870 (1997).
• Reynolds, J.H., Chelazzi, L., and Desimone, R. “Competitive mechanisms
subserve attention in macaque areas V2 and V4,” J. Neurosci.
19:1736–1753 (1999).
• Reynolds, J.H. and Desimone, R. “The role of neural mechanisms of
attention in solving the binding problem,” Neuron 24:19–29 (1999).
• Rhodes P.A. and Llin´as, R.R. “Apical tuft input efficacy in layer
5 pyramidal cells from rat visual cortex,” J. Physiol. 536:167–187
(2001).
• Ricci, C. and Blundo, C. “Perception of ambiguous figures after focal
brain lesions,” Neuropsychologia 28:1163–73 (1990).
• Riddoch, M.J. and Humphreys, G.W. “17 + 14 = 41? Three cases of
working memory impairment.” In: Broken Memories: Case Studies
in Memory Impairment. Campbell, R. and Conway, M.A., eds., pp.
253–266. Oxford, UK: Blackwell (1995).
参考文献69
• Ridley, M. Nature Via Nurture. New York: Harper Collins (2003).
• Rieke, F., Warland, D., van Steveninck, R.R.D., and Bialek, W.
Spikes: Exploring the Neural Code. Cambridge, MA: MIT Press
(1996).
• Ritz, R. and Sejnowski, T.J. “Synchronous oscillatory activity in sensory
systems: New vistas on mechanisms,” Curr. Opinion Neurobiol.
7:536–546 (1997).
• Rizzuto, D.S., Madsen, J.R., Bromfield, E.B., Schulze-Bonhage, A.,
Seelig, D., Aschen-brenner-Scheibe, R., and Kahana, M.J. “Reset of
human neocortical oscillations during a working memory task,” Proc.
Natl. Acad. Sci. USA 100:7931–7936 (2003).
• Robertson, L. “Binding, spatial attention, and perceptual awareness,”
Nature Rev. Neurosci. 4:93–102 (2003).
• Robertson, I.H. and Marshall, J.C., eds. Unilateral Neglect: Clinical
and Experimental Studies. Hove, UK: Lawrence Erlbaum (1993).
• Robertson, L., Treisman, A., Friedman-Hill, S., and Grabowecky,
M. “The interaction of spatial and object pathways: Evidence from
Balint’s syndrome,” J. Cogn. Neurosci. 9:295–317 (1997).
• Robinson, D.L. and Cowie, R.J. “The primate pulvinar: Stuctural,
functional, and behavioral components of visual salience.” In: The
Thalamus. Jones, E.G., Steriade, M., and McCormick, D.A., eds., pp.
53–92. Amsterdam: Elsevier (1997).
• Robinson, D.L. and Petersen, S.E. “The pulvinar and visual salience,”
Trends Neurosci. 15:127–132 (1992).
• Rock, I. and Gutman, D. “The effect of inattention on form perception,”
J. Exp. Psychol. Hum. Perception & Performance 7:275–285
(1981).
• Rockel, A.J., Hiorns, R.W., and Powell, T.P.S. “The basic uniformity
in structure of the neocortex,” Brain 103:221–244 (1980).
• Rockland, K.S. “Further evidence for two types of corticopulvinar
neurons,” Neuroreport 5:1865–1868 (1994).
• Rockland, K.S. “Two types of corticopulvinar terminations: Round
(type 2) and elongate (type 1),” J. Comp. Neurol. 368:57–87 (1996).
参考文献70
• Rockland, K.S. “Elements of cortical architecture: Hierarchy revisited.”
In: Cerebral Cortex, Vol. 12. Rockland, K.S., Kaas, J.H., and
Peters, A., eds., pp. 243–293. New York: Plenum Press (1997).
• Rockland, K.S. and Pandya, D.N. “Laminar origins and terminations
of cortical connections of the occipital lobe in the rhesus monkey,”
Brain Res. 179:3–20 (1979).
• Rockland, K.S. and Van Hoesen, G.W. “Direct temporal-occipital
feedback connections to striate cortex (V1) in the macaque monkey,”
Cerebral Cortex 4:300–313 (1994).
• Rodieck, R.W. The First Steps in Seeing. Sunderland, MA: Sinauer
Associates (1998).
• Rodieck, R.W., Binmoeller, K.F., and Dineen, J.T. “Parasol and
midget ganglion cells of the human retina,” J. Comp. Neurol. 233:115–
132 (1985).
• Rodriguez, E., George, N., Lachaux, J.-P., Martinerie, J., Renault, B.,
and Varela, F.J. “Perception’s shadow: Long-distance synchronziation
of human brain activity,” Nature 397:430–433 (1999).
• Roe, A.W. and Ts’o, D.Y. “The functional architecture of area V2
in the macaque monkey: Physiology, topography, and connectivity.”
In Cerebral Cortex, Vol 12: Extrastriate Cortex in Primates, Rockland,
K.S., Kaas, J.H., and Peters, A., eds., pp. 295–334. New York:
Plenum Press (1997).
• Roelfsema, P.R., Lamme, V.A.F., and Spekreijse, H. “Oject-based
attention in the primary visual cortex of the macaque monkey,” Nature
395:376–381 (1998).
• Rolls, E.T. “Spatial view cells and the representation of place in the
primate hippocampus,” Hippocampus 9:467–480 (1999).
• Rolls, E.T., Aggelopoulos, N.C., and Zheng, F. “The receptive fields
of inferior temporal cortex neurons in natural scenes,” J. Neurosci.
23:339–348 (2003).
• Rolls, E.T. and Deco, G. Computational Neuroscience of Vision. Oxford,
UK: Oxford University Press (2002).
• Rolls, E.T. and Tovee, M.J. “Processing speed in the cerebral cortex
and the neurophysiology of visual masking,” Proc. R. Soc. Lond. B
257:9–15 (1994).
参考文献71
• Rolls, E.T. and Tovee, M.J. “The responses of single neurons in the
temporal visual cortical areas of the macaque when more than one
stimulus is present in the receptive field,” Exp. Brain Res. 103:409–
420 (1995).
• Romo, R., Brody, C.D., Hern´andez, A., and Lemus, L. “Neuronal
correlates of parametric working memory in the prefrontal cortex,”
Nature 399:470–473 (1999).
• Roorda, A. and Williams, D.R. “The arrangement of the three cone
classes in the living human eye,” Nature 397:520–522 (1999).
• Rosen, M. and Lunn, J.N., eds. Consciousness, Awareness, and Pain
in General Anaesthesia. London: Butterworths (1987).
• Rossen, R., Kabat, H., and Anderson, J.P. “Acute arrest of cerebral
circulation in man,” Arch. Neurol. Psychiatry 50:510–528 (1943).
• Rossetti, Y. “Implicit short-lived motor representations of space in
brain damaged and healthy subjects,” Consc. & Cognition 7:520–558
(1998).
• Rousselet, G., Fabre-Thorpe, M., and Thorpe, S. “Parallel processing
in high-level visual scene categorization,” Nature Neurosci. 5:629–630
(2002).
• Ryle, G. The Concept of the Mind London: Hutchinson (1949).(邦
訳)坂本百大〔ほか〕共訳,心の概念,みすず書房(1987).
• Sacks, O. Migraine. Rev. ed. Berkeley, CA: University of California
Press (1970).(邦訳)後藤真, 石館宇夫訳,偏頭痛百科,晶文社(1990).
• Sacks, O. Awakenings. New York: E.P. Dutton (1973).(邦訳)石館
康平, 石館宇夫訳,レナードの朝,晶文社(1993).
• Sacks, O. A Leg to Stand On. New York: Summit Books (1984).(邦
訳)金沢泰子訳,左足をとりもどすまで,晶文社(1994).
• Sacks, O. The Man Who Mistook His Wife for a Hat. New York:
Harper & Row (1985).(邦訳)高見幸郎, 金沢泰子訳,妻を帽子とまち
がえた男,晶文社(1992).
• Sacks, O. “The mind’s eye: What the blind see.” The New Yorker,
July 28, pp. 48–59 (2003).
参考文献72
• Saenz, M., Buracas, G.T., and Boynton, G.M. “Global effects of
feature-based attention in human visual cortex,” Nature Neurosci.
5:631–632 (2002).
• Saint-Cyr, J.A., Ungerleider, L.G., and Desimone, R. “Organization
of visual cortical inputs to the striatum and subsequent outputs to the
pallido-nigral complex in the monkey,” J. Compa. Neurol. 298:129–
156 (1990).
• Sakai, K., Watanabe, E., Onodera, Y., Uchida, I., Kato, H., Yamamoto,
E., Koizumi, H., and Miyashita, Y. “Functional mapping of
the human colour centre with echo-planar magnetic resonance imaging,”
Proc. R. Soc. Lond. B 261:89–98 (1995).
• Saleem, K.S., Suzuki, W., Tanaka, K., and Hashikawa, T. “Connections
between anterior inferotemporal cortex and superior temporal
sulcus regions in the macaque monkey,” J. Neurosci. 20:5083–5101
(2000).
• Salin, P.-A. and Bullier, J. “Corticocortical connections in the visual
system: Structure and Function,” Physiol. Rev. 75:107–154 (1995).
• Salinas, E. and Abbott, L.F. “Transfer of coded information from
sensory to motor networks,” J. Neurosci. 15:6461–6474 (1995).
• Salinas, E. and Sejnowski, T.J. “Correlated neuronal activity and the
flow of neural information,” Nature Rev. Neurosci. 2:539–550 (2001).
• Salzman, C.D., Murasugi, C.M., Britten, K.H., and Newsome, W.T.
“Microstimulation in visual area MT: Effects on direction discrimination
performance,” J. Neurosci. 12:2331–2355 (1992).
• Salzman, C.D. and Newsome, W.T. “Neural mechanisms for forming
a perceptual decision,” Science 264:231–237 (1994).
• Sammon, P.M. Future Noir: The Making of Blade Runner. NewYork,
HarperPrims (1996).
• Sanderson,M.J. “Intercellular waves of communication,” New Physiol.
Sci. 11:262–269 (1996).
• Sanford, A.J. “A periodic basis for perception and action.” In: Biological
Rhythms and Human Performance. Colquhuon, W., ed., pp.
179–209. New York: Academic Press (1971).
参考文献73
• Savic, I. “Imaging of brain activation by odorants in humans,” Curr.
Opinion Neurobiol. 12:455–461 (2002).
• Savic, I., Berglund, H., Gulyas, B., and Roland, P. “Smelling of odorous
sex hormone-like compounds causes sex-differentiated hypothalamic
activations in humans,” Neuron 31:661–668 (2001).
• Sawatari, A. and Callaway, E.M. “Diversity and cell type specificity of
local excitatory connections to neurons in layer 3B of monkey primary
visual cortex,” Neuron 25:459–471 (2000).
• Scalaidhe, S.P., Wilson, F.A., and Goldman-Rakic, P.S. “Areal segregation
of face-processing neurons in prefrontal cortex,” Science 278:1135–
1138 (1997).
• Schall, J.D. “Neural basis of saccadic eye movements in primates.”
In: The Neural Basis of Visual Function. Leventhal, A.G., ed., pp.
388–441. Boca Raton, FL: CRC Press (1991).
• Schall, J.D. “Visuomotor areas of the frontal lobe. In: Cerebral Cortex.
Vol. 12. Rockland, K.S., Kaas, J.H., and Peters, A., eds., pp.
527–638. New York: Plenum Press (1997).
• Schall, J.D. “Neural basis of deciding, choosing and acting,” Nature
Rev. Neurosci. 2:33–42 (2001).
• Schank, J.C. “Menstrual-cycle synchrony: Problems and new directions
for research,” J. Comp. Psychology 115:3–15 (2001).
• Schenck, C.H. and Mahowald, M.W. “An analysis of a recent criminal
trial involving sexual misconduct with a child, alcohol abuse and a
successful sleepwalking defence: Arguments supporting two proposed
new forensic categories,” Med. Sci. Law 38:147–152 (1998).
• Schiff, N.D. “The neurology of impaired consciousness: Challenges
for cognitive neuroscience.” In: The New Cognitive Neurosciences.
Gazzaniga, M., ed. Cambridge, MA: MIT Press (2004).
• Schiff, N.D. and Plum, F. “The role of arousal and ‘gating’ systems
in the neurology of impaired consciousness,” J. Clinical Neurophysiol.
17:438–452 (2000).
• Schiffer, F. “Can the different cerebral hemispheres have distinct personalities?
Evidence and its implications for theory and treatment of
PTSD and other disorders?” J. Traum. Dissoc. 1:83–104 (2000).
参考文献74
• Schiller, P.H. and Chou, I.H. “The effects of frontal eye field and
dorsomedial frontal-cortex lesions on visually guided eye-movements,”
Nature Neurosci. 1:248–253 (1998).
• Schiller, P.H. and Logothetis, N.K. “The color-opponent and broadbased
channels of the primate visual system,” Trends Neurosci. 13:392–
398 (1990).
• Schiller, P.H., True, S.D., and Conway, J.L. “Effects of frontal eye
field and superior colliculus ablations on eye movements,” Science
206:590–592 (1979).
• Schlag, J. and Schlag-Rey, M. “Visuomotor functions of central thalamus
in monkey. II. Unit activity related to visual events, targeting,
and fixation,” J. Neurophysiol. 51:1175–1195 (1984).
• Schlag, J. and Schlag-Rey, M. “Through the eye, slowly: Delays
and localization errors in the visual system,” Nature Rev. Neurosci.
3:191–215 (2002).
• Schmidt, E.M., Bak, M.J., Hambrecht, F.T., Kufta, C.V., O’Rourke,
D.K., and Vallabhanath, P. “Feasibility of a visual prosthesis for the
blind based on intracortical microstimulation of the visual cortex,”
Brain 119:507–522 (1996).
• Schmolesky, M.T., Wang, Y., Hanes, D.P., Leutgeb, S., Schall, J.B.,
and Leventhal, A.G. “Signal timing across the macaque visual system,”
J. Neurophysiol. 79:3272–3280 (1998).
• Schooler, J.W. and Melcher, J. “The ineffability of insight.” In: The
Creative Cognition Approach. Smith, S.M., Ward, T.B., and Finke,
R.A., eds., pp. 97–133. Cambridge, MA: MIT Press (1995).
• Schooler, J.W., Ohlsson, S., and Brooks, K. “Thoughts beyond words:
When language overshadows insight,” J. Exp. Psychol. Gen. 122:166–
183 (1993).
• Schr¨odinger, E.What Is Life? Cambridge, UK: Cambridge University
Press (1944).(邦訳)岡小天, 鎮目恭夫共訳,生命とは何か: 物理学者
のみた生細胞,岩波新書(1951).
• Scoville, W.B. and Milner, B. “Loss of recent memory after bilateral
hippocampal lesions,” J. Neurochem. 20:11–21 (1957).
参考文献75
• Searle, J.R. The Mystery of Consciousness. NewYork: TheNewYork
Review of Books (1997).
• Searle, J.R. “Consciousness,” Ann. Rev. Neurosci. 23:557–578 (2000).
• Seckel, A. The Art of Optical Illusions. Carlton Books (2000).
• Seckel, A. More Optical Illusions. Carlton Books (2002).
• Sennholz, G. “Bispectral analysis technology and equipment,” Minerva
Anestesiol. 66:386–388 (2000).
• Shadlen, M.N., Britten, K.H., Newsome, W.T., and Movshon, J.A.
“A computational analysis of the relationship between neuronal and
behavioral responses to visual motion,” J. Neurosci. 16:1486–1510
(1996).
• Shadlen, M.N. and Movshon, J.A. “Synchrony unbound: A critical
evaluation of the temporal binding hypothesis,” Neuron 24:67–77
(1999).
• Shallice, T. From Neuropsychology to Mental Structure. Cambridge,
UK: Cambridge University Press (1988).
• Shapley, R. and Ringach, D. “Dynamics of responses in visual cortex.”
In: The New Cognitive Neurosciences. 2nd ed., Gazzaniga, M.S., ed.,
pp. 253–261. Cambridge, MA: MIT Press (2000).
• Shear, J., ed. Explaining Consciousness: The Hard Problem. Cambridge,
MA: MIT Press (1997).
• Sheinberg, D.L. and Logothetis, N.K. “The role of temporal cortical
areas in perceptual organization,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA
94:3408–3413 (1997).
• Sheinberg, D.L. and Logothetis, N.K. “Noticing familiar objects in
real world scenes: The role of temporal cortical neurons in natural
vision,” J. Neurosci. 15:1340–1350 (2001).
• Sheliga, B.M., Riggio, L., and Rizzolatti, G. “Orienting of attention
and eye movements,” Exp. Brain Res. 98:507–522 (1994).
• Shepherd, G.M. Foundations of the Neuron Doctrine. NewYork: Oxford
University Press (1991).
参考文献76
• Shepherd, M., Findlay, J.M., and Hockey, R.J. “The relationship between
eye movements and spatial attention,” Quart. J. Exp. Psychol.
38:475–491 (1986).
• Sherk, H. “The claustrum.” In: Cerebral Cortex Vol. 5. Jones, E.G.
and Peters, A., eds., pp. 467–499. New York: Plenum (1986).
• Sherman, S.M. and Guillery, R. Exploring the Thalamus. San Diego,
CA: Academic Press (2001).
• Sherman, S.M. and Koch, C. “Thalamus.” In: The Synaptic Organization
of the Brain. 4th ed., Shepherd, G. ed., pp. 289–328. New
York: Oxford University Press (1998).
• Sheth, B.R., Nijhawan, R., and Shimojo, S. “Changing objects lead
briefly flashed ones,” Nature Neurosci. 3:489–495 (2000).
• Shimojo, S., Tanaka, Y., and Watanabe, K. “Stimulus-driven facilitation
and inhibition of visual information processing in environmental
and retinotopic representations of space,” Brain Res. Cogn. Brain
Res. 5:11–21 (1996).
• Siegel, J.M. “Nacrolepsy,” Scientific American 282:76–81 (2000).
• Siewert, C.P. The Significance of Consciousness. Princeton, NJ: Princeton
University Press (1998).
• Simons, D.J. and Chabris, C.F. “Gorillas in our midst: Sustained
inattentional blindness for dynamic events,” Perception 28:1059–1074
(1999).
• Simons, D.J. and Levin, D.T. “Change blindness,” Trends Cogn. Sci.
1:261–267 (1997).
• Simons, D.J. and Levin, D.T. “Failure to detect changes to people
during a real-world interaction,” Psychonomic Bull. & Rev. 5:644–
649 (1998).
• Simpson, J. Touching the Void. New York: HarperPerennial (1988).
• Singer, W. “Neuronal synchrony: A versatile code for the definition
of relations?” Neuron 24:49–65 (1999).
• Skoyles, J.R. “Another variety of vision,” Trends Neurosci. 20:22–23
(1997).
参考文献77
• Slimko, E.M., McKinney, S., Anderson, D.J., Davidson, N., and Lester,
H.A. “Selective electrical silencing of mammalian neurons in vitro by
the use of invertebrate ligand-gated chloride channels,” J. Neurosci.
22:7373–7379 (2002).
• Smith, S. “Utrocular, or ‘which eye’ discrimination,” J. Exp. Psychology
35:1–14 (1945).
• Snyder, L.H., Batista, A.P., and Andersen, R.A. “Intention-related activity
in the posterior parietal cortex: A review,” Vis. Res. 40:1433–
1441 (2000).
• Sobel, E.S. and Tank, D.W. “In vivo Ca2+ dynamics in a cricket auditory
neuron: An example of chemical computation,” Science 263:823–
826 (1994).
• Sobel, N., Prabhakaran, V., Hartely, C.A., Desmond, J.E., Glover,
G.H., Sullivan, E.V., and Gabrieli, D.E. “Blindsmell: Brain activation
induced by an undetected air-borne chemical,” Brain 122:209–217
(1999).
• Softky, W.R. “Simple codes versus efficient codes,” Curr. Opinion
Neurobiol. 5:239–247 (1995).
• Solms, M. The Neuropsychology of Dreams. Mahwah, NJ: Lawrence
Erlbaum (1997).
• Somers, D.C., Dale, A.M., Seiffert, A.E., and Tootell, R.B. “Functional
MRI reveals spatially specific attentional modulation in human
primary visual cortex,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA 96:1663–1668
(1999).
• Sperling, G. “The information available in brief presentation,” Psychological
Monographs 74. Whole No. 498 (1960).
• Sperling, G. and Dosher, B. “Strategy and optimization in human information
processing.” In: Handbook of Perception and Performance
Vol. 1. Boff, K., Kaufman, L., and Thomas, J., eds., pp. 1–65. New
York: Wiley (1986).
• Sperling, G. andWeichselgartner, E. “Episodic theory of the dynamics
of spatial attention,” Psych. Rev. 102:503–532 (1995).
• Sperry, R.W. “Cerebral organization and behavior,” Science 133:1749–
1757 (1961).
参考文献78
• Sperry, R.W. “Lateral specialization in the surgically separated hemispheres.”
In: Neuroscience 3rd Study Program. Schmitt, F.O. and
Worden, F.G., eds. Cambridge, MA: MIT Press (1974).
• Spinelli, D.W., Pribram, K.H., andWeingarten, M. “Centrifugal optic
nerve responses evoked by auditory and somatic stimulation,” Exp.
Neurol. 12:303–318 (1965).
• Sprague, J.M. “Interaction of cortex and superior colliculus in mediation
of visually guided behavior in the cat,” Science 153:1544–1547
(1966).
• Squire, L.R. and Kandel, E.R. Memory: From Mind to Molecules.
New York: Scientific American Library, Freeman (1999).
• Standing, L. “Learning 10,000 pictures,” Quart. J. Exp. Psychol.
25:207–222 (1973).
• Stapledon, O. Star Maker. New York: Dover Publications (1937).
• Steinmetz, P.N., Roy, A., Fitzgerald, P.J., Hsiao, S.S., Johnson, K.O.,
and Niebur, E. “Attention modulates synchronized neuronal firing in
primary somatosensory cortex,” Nature 404:187–190 (2000).
• Steriade, M. and McCarley, R.W. Brainstem Control of Wakefullness
and Sleep. New York: Plenum Press (1990).
• Stern, K. and McClintock, M.K. “Regulation of ovulation by human
pheromones,” Nature 392:177–179 (1998).
• Sternberg, E.M. “Piercing together a puzzling world: Memento,” Science
292:1661–1662 (2001).
• Sternberg, S. “High-speed scanning in human memory,” Science 153:652–
654 (1966).
• Stevens, C.F. “Neuronal diversity: Too many cell types for comfort?”
Curr. Biol. 8:R708–R710 (1998).
• Stevens, R. “Western phenomenological approaches to the study of
conscious experience and their implications.” In: Methodologies for
the Study of Consciousness: A New Synthesis. Richardson, J. and
Velmans, M., eds., pp. 100–123. Kalamazoo, MI: Fetzer Institute
(1997).
参考文献79
• Stoerig, P. and Barth, E. “Low-level phenomenal vision despite unilateral
destruction of primary visual cortex,” Consc. & Cognition
10:574–587 (2001).
• Stoerig, P., Zontanou, A., and Cowey, A. “Aware or unaware: Assessment
of cortical blindness in four men and a monkey,” Cerebral
Cortex 12:565–574 (2002).
• Stopfer, M., Bhagavan, S., Smith, B.H., and Laurent, G. “Impaired
odour discrimination on desynchronization of odour-encoding neural
assemblies,” Nature 390:70–74 (1997).
• Stowers, L., Holy, T.E., Meister, M., Dulac, C., and Koentges, G.
“Loss of sex discrimination and male-male aggression in mice deficient
for TRP2,” Science 295:1493–1500 (2002).
• Strayer, D.L. and Johnston, W.A. “Driven to distraction: Dual-task
studies of simulated driving and conversing on a cellular phone,” Psychol.
Sci. 12:462–466 (2001).
• Stroud, J.M. “The fine structure of psychological time.” In: Information
Theory in Psychology. Quastler, H., ed., pp. 174–205. Glencoe,
IL: Free Press (1956).
• Strawson, G. Mental Reality. Cambridge, MA: MIT Press (1996).
• Sup`er, H., Spekreijse, H., and Lamme, V.A.F. “Two distinct modes of
sensory processing observed in monkey primary visual cortex,” Nature
Neurosci. 4:304–310 (2001).
• Swick, D. and Knight, R.T. “Cortical lesions and attention.” In: The
Attentive Brain. Parasurama R., ed., pp. 143–161. Cambridge, MA:
MIT Press (1998).
• Swindale, N.V. “How many maps are there in visual cortex,” Cerebral
Cortex 10:633–643 (2000).
• Tallal, P., Merzenich, M., Miller, S., and Jenkins, W. “Language learning
impairment: Integrating basic science, technology and remediation,”
Exp. Brain Res. 123:210–219 (1998).
• Tallon-Baudry, C. and Bertrand, O. “Oscillatory gamma activity in
humans and its role in object representation,” Trends Cogn. Sci.
3:151–161 (1999).
『意識の探求』の参考文献40-59
参考文献40
• Jolicoeur, P., Ullman, S., and MacKay, M. “Curve tracing: A possible
basic operation in the perception of spatial relations,” Mem. Cognition
14:129–140 (1986).
• Jones, E.G. The Thalamus. New York: Plenum Press (1985).
• Jones, E.G. “Thalamic organization and function after Cajal,” Progress
Brain Res. 136:333–357 (2002).
• Jordan, G. and Mollon, J.D. “A study of women heterozygous for
color deficiences,” Vision Res. 33:1495–1508 (1993).
• Jovicich, J., Peters, R.J., Koch, C., Braun, J., Chang, L., and Ernst,
T. “Brain areas specific for attentional load in a motion tracking task,”
J. Cogn. Neurosci. 13:1048–1058 (2001).
• Judson, H.J. The Eighth Day of Creation. London: Penguin Books
(1979).
• Julesz, B. Foundations of Cyclopean Perception. Chicago, IL: University
of Chicago Press (1971).
• Julesz, B. “Textons, the elements of texture perception, and their
interactions,” Nature 290:91–97 (1981).
• Kahana, M.K., Sekuler, R., Caplan, J.B., Kirschen, M., and Madsen,
J.R. “Human theta oscillations exhibit task dependence during virtual
maze navigation,” Nature 399:781–784 (1999).
• Kamitani, Y. and Shimojo, S. “Manifestation of scotomas created by
transcranial magnetic stimulation of human visual cortex,” Nature
Neurosci. 2:767–771 (1999).
• Kandel, E.R. “A new intellectual framework for psychiatry,” Am. J.
Psychiatry 155:457–469 (1998).
• Kandel, E.R. “The molecular biology of memory storage: A dialogue
between genes and synapses,” Science 294:1030–1038 (2001).
• Kanizsa, G. Organization in Vision: Essays in Gestalt Perception.
New York: Praeger (1979).
• Kanwisher, N. and Driver, J. “Objects, attributes, and visual attention:
Which, what and where,” Curr. Direct. Psychol. Sci. 1:26–31
(1997).
参考文献41
• Kanwisher, N., McDermott, J., and Chun, M.M. “The fusiform face
area: A module in human extrastriate cortex specialized for face perception,”
J. Neurosci. 17:4302–4311 (1997).
• Kaplan, E. “The receptive field structure of retinal ganglion cells in cat
and monkey.” In: The Neural Basis of Visual Function. Leventhal,
A.G., ed., pp. 10–40. Boca Raton, FL: CRC Press (1991).
• Kaplan-Solms, K. and SolmsM. Clinical Studies in Neuro-Psychoanalysis.
London: Karnac Books (2000).
• Karnath, H.-O. “New insights into the functions of the superior temporal
cortex,” Nature Rev. Neurosci. 2:568–576 (2001).
• Karnath, H.-O., Ferber, S., and Himmelbach, M. “Spatial awareness
is a function of the temporal, not the posterior parietal lobe,” Nature
411:950–954 (2001).
• Kastner, S., DeWeerd, P., Desimone, R., and Ungerleider, L.G. “Mechanisms
of directed attention in the human extrastriate cortex as revealed
by functional MRI,” Science 282:108–111 (1998).
• Kastner, S. and Ungerleider, L.G. “Mechanisms of visual attention in
the human cortex,” Ann. Rev. Neurosci. 23:315–341 (2000).
• Kavey, N.B., Whyte, J., Resor, S.R. Jr., and Gidro-Frank, S. “Somnambulism
in adults,” Neurol. 40:749–752 (1990).
• Keil, A., M¨uller, M.M., Ray, W.J., Gruber, T., and Elbert, T. “Human
gamma band activity and perception of a gestalt,” J. Neurosci.
19:7152–7161 (1999).
• Keller, E.F. The Century of the Gene. Cambridge, MA: Harvard
University Press (2000).
• Kennedy, H. and Bullier, J. “A double-labelling investigation of the afferent
connectivity to cortical areas V1 and V2,” J. Neurosci. 5:2815–
2830 (1985).
• Kentridge, R.W., Heywood, C.A., and Weiskrantz, L. “Residual vision
in multiple retinal locations within a scotoma: Implications for
blindsight,” J. Cogn. Neurosci. 9:191–202 (1997).
• Kentridge, R.W., Heywood, C.A., andWeiskrantz, L. “Attention without
awareness in blindsight,” Proc. Roy. Soc. Lond. B 266:1805–
1811 (1999).
参考文献42
• Kessel, R.G. and Kardon, R.H. Tissues and Organs: A Text-Atlas of
Scanning Electron Microscopy. San Francisco, CA: Freeman (1979).
• Keverne, E.B. “The vomeronasal organ,” Science 286:716–720 (1999).
• Keysers, C. and Perrett, D.I. “Visual masking and RSVP reveal neural
competition,” Trends Cogn. Sci. 6:120–125 (2002).
• Keysers, C., Xiao, D.-K., F¨oldi´ak, P., and Perrett, D.I. “The speed of
sight,” J. Cogn. Neurosci. 13:1–12 (2001).
• Kinney, H.C., Korein, J., Panigrahy, A., Dikkes, P., and Goode, R.
“Neuropathological findings in the brain of Karen Ann Quinlan,” New
England J. Med. 330:1469–1475 (1994).
• Kinomura, S., Larsson, J., Guly´as, B., and Roland, P.E. “Activation
by attention of the human reticular formation and thalamic intralaminar
nuclei,” Science 271:512–515 (1996).
• Kirk, R. “Zombies versusmaterialists,” Aristotelian Society 48 (suppl.):
135–152 (1974).
• Kitcher, P. Freud’s Dream: A Complete Interdisciplinary Science of
Mind. Cambridge, MA: MIT Press (1992).
• Kleinschmidt, A., Buchel, C., Zeki, S., and Frackowiak, R.S.J. “Human
brain activity during spontaneously reversing perception of ambiguous
figures,” Proc. R. Soc. Lond. B 265:2427–2433 (1998).
• Klemm, W.R., Li, T.H., and Hernandez, J.L. “Coherent EEG indicators
of cognitive binding during ambigious figure tasks,” Consc. &
Cognition 9:66–85 (2000).
• Klimesch, W. “EEG alpha and theta oscillations reflect cognitive
and memory performance: A review and analysis,” Brain Res. Rev.
29:169–195 (1999).
• Knuttinen, M.-G., Power, J.M., Preston, A.R., and Disterhoft, J.F.
“Awareness in classical differential eyeblink conditioning in young and
aging humans,” Behav. Neurosci. 115:747–757 (2001).
• Kobatake, E.,Wang, G., and Tanaka, K. “Effects of shape-discrimination
training on the selectivity of inferotemporal cells in adult monkeys,”
J. Neurophysiol. 80:324–330 (1998).
参考文献43
• Koch, C. “The action of the corticofugal pathway on sensory thalamic
nuclei: A hypothesis,” Neurosci. 23:399–406 (1987).
• Koch, C. “Visual awareness and the thalamic intralaminar nuclei,”
Consc. & Cognition 4:163–165 (1995).
• Koch, C. Biophysics of Computation. New York: Oxford University
Press (1999).
• Koch, C. and Crick, F.C. “Some further ideas regarding the neuronal
basis of awareness.” In: Large-Scale Neuronal Theories of the Brain.
Koch, C. and Davis, J., eds., pp. 93–110, Cambridge, MA: MIT Press
(1994).
• Koch, C. and Laurent, G. “Complexity and the nervous system,” Science
284:96–98 (1999).
• Koch, C. and Tootell, R.B. “Stimulating brain but not mind,” Nature
383:301–303 (1996).
• Koch, C. and Ullman, S. “Shifts in selective visual attention: Towards
the underlying neural circuitry,” Human NeuroBiol. 4:219–227
(1985).
• Koffka, K. Principles of Gestalt Psychology. New York: Hartcourt
(1935).
• Kohler, C.G., Ances, B.M., Coleman, A.R., Ragland, J.D., Lazarev,
M., and Gur, R.C. “Marchiafava-Bignami disease: Literature review
and case report,” Neuropsychiatry, Neuropsychol. Behav. Neurol.
13:67–76 (2000).
• K¨ohler, W. The Task of Gestalt Psychology. Princeton, NJ: Princeton
University Press (1969).
• Kolb, F.C. and Braun, J. “Blindsight in normal observers,” Nature
377:336–338 (1995).
• Komatsu, H., Kinoshita, M., and Murakami, I. “Neural responses in
the retinotopic representation of the blind spot in the macaque V1 to
stimuli for perceptual filling-in,” J. Neurosci. 20:9310–9319 (2000).
• Komatsu, H. and Murakami, I. “Behavioral evidence of filling-in at
the blind spot of the monkey,” Vis. Neurosci. 11:1103–1113 (1994).
参考文献44
• Konorski, J. Integrative Activity of the Brain. Chicago, IL: University
of Chicago Press (1967).
• Kosslyn, S.M. “Visual Consciousness.” In: Finding Consciousness
in the Brain. Grossenbacher P.G., ed., pp. 79–103. Amsterdam,
Netherlands: John Benjamins (2001).
• Kosslyn, S.M., Ganis, G., and Thompson, W.L. “Neural foundations
of imagery,” Nature Rev. Neurosci. 2:635–642 (2001).
• Kosslyn, S.M., Thompson, W.L., and Alpert, N.M. “Neural systems
shared by visual imagery and visual perception: A PET study,” Neuroimage
6:320–334 (1997).
• Koulakov, A.A. and Chklovskii, D.B. “Orientation preference patterns
in mammalian visual cortex: A wire length minimization approach,”
Neuron 29:519–527 (2001).
• Krakauer, J. Eiger Dreams. New York: Lyons & Burford (1990).
• Kreiman, G. On the neuronal activity in the human brain during visual
recognition, imagery and binocular rivalry. Ph.D. Thesis. Pasadena:
California Institute of Technology (2001).
• Kreiman G., Fried, I., and Koch, C. “Single-neuron correlates of subjective
vision in the human medial temporal lobe,” Proc. Natl. Acad.
Sci. USA 99:8378–8383 (2002).
• Kreiman, G., Koch, C., and Fried, I. “Category-specific visual responses
of single neurons in the human medial temporal lobe,” Nature
Neurosci. 3:946–953 (2000a).
• Kreiman, G., Koch, C., and Fried, I. “Imagery neurons in the human
brain,” Nature 408:357–361 (2000b).
• Kreiter, A.K. and Singer, W. “Oscillatory neuronal responses in the visual
cortex of the awake macaque monkey,” Eur. J. Neurosci. 4:369–
375 (1992).
• Kreiter, A.K. and Singer, W. “Stimulus-dependent synchronization of
neuronal responses in the visual cortex of the awake macaque monkey,”
J. Neurosci. 16:2381–2396 (1996).
• Krekelberg, B. and Lappe, M. “Neuronal latencies and the position of
moving objects,” Trends Neurosci. 24:335–339 (2001).
参考文献45
• Kretschmann, H.-J. andWeinrich,W. Cranial Neuroimaging and Clinical
Neuroanatomy. Stuttgart, Germany: Georg Thieme (1992).
• Kristofferson, A.B. “Successiveness discrimination as a two-state, quantal
process,” Science 158:1337–1339 (1967).
• Kuffler, S.W. “Neurons in the retina: Organization, inhibition and excitatory
problems,” Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol. 17:281–
292 (1952).
• Kulli, J. and Koch, C. “Does anesthesia cause loss of consciousness?”
Trends Neurosci. 14:6–10 (1991).
• Kunimoto, C., Miller, J., and Pashler, H. “Confidence and accuracy of
near-threshold discrimination responses,” Cons. & Cogn. 10:294–340
(2001).
• Kustov, A.A. and Robinson, D.L. “Shared neural control of attentional
shifts and eye movements,” Nature 384:74–77 (1996).
• LaBerge, D. and Buchsbaum, M.S. “Positron emission tomographic
measurements of pulvinar activity during an attention task. J. Neurosci.
10:613–619 (1990).
• Laming, P.R., Sykov´a, E., Reichenbach, A., Hatton, G.I., and Bauer,
H., Glia Cells: Their Role in Behavior. Cambridge, UK: Cambridge
University Press (1998).
• Lamme, V.A.F. “Why visual attention and awareness are different,”
Trends Cogn. Sci. 7:12–18 (2003).
• Lamme, V.A.F. and Roelfsema, P.R. “The distinct modes of vision
offered by feed-forward and recurrent processing,” Trends Neurosci.
23:571–579 (2000).
• Lamme, V.A.F. and Spekreijse, H. “Contextual modulation in primary
visual cortex and scene perception.” In: The New Cognitive
Neurosciences. 2nd ed., Gazzaniga, M.S., ed., pp. 279–290. Cambridge,
MA: MIT Press (2000).
• Lamme, V.A.F., Zipser, K., and Spekreijse, H. “Figure-ground activity
in primary visual cortex is suppressed by anesthesia,” Proc. Natl.
Acad. Sci. USA 95:3263–3268 (1998).
• Langston, J.W. and Palfreman, J. The Case of the Frozen Addicts.
New York: Vintage Books (1995).
参考文献46
• Lashley, K.S. “Cerebral organization and behavior.” In: The Brain
and Human Behavior. Proc. Ass. Nervous & Mental Disease, pp.
1–18. New York: Hafner (1956).
• Laurent, G. “A systems perspective on early olfactory coding,” Science
286:723–728 (1999).
• Laurent, G., Stopfer, M., Friedrich, R.W., Rabinovich, M.I., Volkovskii,
A., and Abarbanel, H.D. “Odor encoding as an active, dynamical process:
Experiments, computation, and theory,” Ann. Rev. Neurosci.
24:263–297 (2001).
• Laureys, S., Faymonville, M.E., Degueldre, C., Fiore, G.D., Damas,
P, Lambermont, B., Janssens, N., Aerts, J., Franck, G., Luxen, A.,
Moonen, G., Lamy, M., and Maquet, P. “Auditory processing in the
vegetative state,” Brain 123:1589–1601 (2000).
• Laureys, S., Faymonville, M.E., Peigneux, P., Damas, P., Lambermont,
B., Del Fiore, G., Degueldre, C., Aerts, J., Luxen, A., Franck,
G., Lamy, M., Moonen, G., and Maquet, P. “Cortical processing
of noxious somatosensory stimuli in the persistent vegetative state,”
Neuroimage 17:732–741 (2002).
• Le Bihan, D., Mangin, J.F., Poupon, C., Clark, C.A., Pappata, S.,
Molko, N., and Chabriat, H. “Diffusion tensor imaging: Concepts and
applications,” J. Magnetic Resonance Imaging 13:534–546 (2001).
• Lechner, H.A.E., Lein, E.S., and Callaway, E.M. “A genetic method
for selective and quickly reversible silencing of mammalian neurons,”
J. Neurosci. 22:5287–5290 (2002).
• LeDoux, J. The Emotional Brain. New York: Simon and Schuster
(1996).
• Lee, D.K., Itti, L., Koch, C., and Braun, J. “Attention activates
winner-take-all competition amongst visual filters,” Nature Neurosci.
2:375–381 (1999).
• Lee, D.N. and Lishman, J.R. “Visual proprioceptive control of stance,”
J. Human Movement Studies 1:87–95 (1975).
• Lee, S.-H. and Blake, R. “Rival ideas about binocular rivalry,” Vision
Res. 39:1447–1454 (1999).
参考文献47
• Lehky, S.R. and Maunsell, J.H.R. “No binocular rivalry in the LGN
of alert macaque monkeys,” Vision Res. 36:1225–1234 (1996).
• Lehky, S.R. and Sejnowski, T. J. “Network model of shape-fromshading:
Neural function arises from both receptive and projective
fields”, Nature 333:452–454 (1988).
• Lennie, P. “Color vision.” In: Principles of Neural Science. 4th ed.,
Kandel, E.R., Schwartz, J.H., and Jessel, T.M. eds., pp. 583–599.
New York: McGraw Hill (2000).
• Lennie, P. “The cost of cortical computation,” Current Biol. 13:493–
497 (2003).
• Leopold, D.A. and Logothetis, N.K. “Activity changes in early visual
cortex reflects monkeys’ percepts during binocular rivalry,” Nature
379:549–553 (1996).
• Leopold, D.A. and Logothetis, N.K. “Multistable phenomena: Changing
views in perception,” Trends Cogn. Sci. 3:254–264 (1999).
• Leopold, D.A., Wilke, M., Maier, A., and Logothetis, N.K. “Stable
perception of visually ambiguous patterns,” Nature Neurosci. 5:605–
609 (2002).
• LeVay, S., Connolly, M., Houde, J., and Van Essen, D.C. “The complete
pattern of ocular dominance stripes in the striate cortex and
visual field of the macaque monkey,” J. Neurosci. 5:486–501 (1985).
• LeVay, S. and Gilbert, C.D. “Laminar patterns of geniculocortical
projection in the cat,” Brain Res. 113:1–19 (1976).
• LeVay, S. and Nelson, S.B. “Columnar organization of the visual cortex.”
In: The Neural Basis of Visual Function. Leventhal, A.G., ed.,
pp. 266–314. Boca Raton, FL: CRC Press (1991).
• Levelt, W. On Binocular Rivalry. Soesterberg, Netherlands: Institute
for Perception RVO-TNO (1965).
• Levick, W.R. and Zacks, J.L. “Responses of cat retinal ganglion cells
to brief flashes of light,” J. Physiol. 206:677–700 (1970).
• Levine, J. “Materialism and qualia: The explanatory gap.” Pacific
Philos. Quart. 64:354–361 (1983).
参考文献48
• Levitt, J.B., Kiper, D.C., and Movshon, J.A. “Receptive fields and
functional architecture of macaque V2,” J. Neurophysiol. 71:2517–
2542 (1994).
• Lewis, J.W. and Van Essen, D.C. “Mapping of architectonic subdivisions
in the macaque monkey, with emphasis on parieto-occipital
cortex,” J. Comp. Neurol. 428:79–111 (2000).
• Li, F.F., VanRullen, R., Koch, C., and Perona, P. “Rapid natural
scene categorization in the near absence of attention,” Proc. Natl.
Acad. Sci. USA 99:9596–9601 (2002).
• Li, W.H., Parigi, G., Fragai, M., Luchinat, C., and Meade, T.J.
“Mechanistic studies of a calcium-dependent MRI contrast agent,”
Inorg. Chem. 41:4018–4024 (2002).
• Liang, J., Williams, D.R., and Miller, D.T. “Supernormal vision and
high-resolution retinal imaging through adaptive optics,” J. Opt. Soc.
Am. A 14:2884–2892 (1997).
• Libet, B. “Brain stimulation and the threshold of conscious experience.”
In: Brain and Conscious Experience. Eccles, J.C., ed., pp.
165–181. Berlin: Springer (1966).
• Libet, B. “Electrical stimulation of cortex in human subjects and conscious
sensory aspects.” In: Handbook of Sensory Physiology, Vol II:
Somatosensory Systems. Iggo, A. ed., pp. 743–790. Berlin: Springer
(1973).
• Libet, B. Neurophysiology of Consciousness: Selected Papers and New
Essays by Benjamin Libet. Boston: Birkh¨auser (1993).
• Lichtenstein, M. “Phenomenal simultaneity with irregular timing of
components of the visual stimulus,” Percept. Mot. Skills 12:47–60
(1961).
• Lisman, J.E. “Bursts as a unit of neural information: Making unreliable
synapses reliable,” Trends Neurosci. 20:38–43 (1997).
• Lisman, J.E. and Idiart, M. A. “Storage of 7±2 short-term memories
in oscillatory subcycles,” Science 267:1512–1515 (1995).
• Livingstone, M.S. “Mechanisms of direction selectivity in macaque
V1,” Neuron 20:509–526 (1998).
参考文献49
• Livingstone, M.S. and Hubel, D.H. “Effects of sleep and rousal on
the processing of visual information in the cat,” Science 291:554–561
(1981).
• Livingstone, M.S. and Hubel, D.H. “Anatomy and physiology of a
color system in the primate visual system,” J. Neurosci. 4:309–356
(1984).
• Livingstone, M.S. and Hubel, D.H. “Connections between layer 4B of
area 17 and thick cytochrome oxidase stripes of area 18 in the squirrel
monkey,” J. Neurosci. 7:3371–3377 (1987).
• Llin´as, R.R. and Par´e, D. “Of dreaming and wakefulness,” Neurosci.
44:521–535 (1991).
• Llin´as, R.R., Ribary, U., Contreras, D., and Pedroarena, C. “The
neuronal basis for consciousness,” Phil. Trans. R. Soc. Lond. B.
Biol. Sci. 353:1841–1849 (1998).
• Loftus, G.R., Duncan, J., and Gehrig, P. “On the time course of
perceptual information that results from a brief visual presentation,”
J. Exp. Psychol. Human Percept. & Perform. 18:530–549 (1992).
• Logothetis, N.K. “Single units and conscious vision,” Phil. Trans. R.
Soc. Lond. B 353:1801–1818 (1998).
• Logothetis, N.K. “The neural basis of the blood-oxygen-level-dependent
functional magnetic resonance imaging signal,” Phil. Trans. R. Soc.
Lond. B 357:1003–1037 (2002).
• Logothetis, N.K. “MR imaging in the non-human primate: Studies
of function and dynamic connectivity,” Curr. Opinion Neurobiol. in
press (2004).
• Logothetis, N.K., Guggenberger, H., Peled, S., and Pauls, J. “Functional
imaging of the monkey brain,” Nature Neurosci. 2:555–562
(1999).
• Logothetis, N.K., Leopold, D.A., and Sheinberg, D.L. “What is rivalling
during binocular rivalry,” Nature 380:621–624 (1996).
• Logothetis, N.K. and Pauls, J. “Psychophysical and physiological evidence
for viewer-centered object representations in the primate,” Cerebral
Cortex 5:270–288 (1995).
参考文献50
• Logothetis, N.K., Pauls, J., Augath, M., Trinath, T., and Oeltermann,
A. “Neurophysiological investigation of the basis of the fMRI signal,”
Nature 412:150–157 (2001).
• Logothetis, N.K., Pauls, J., B¨ulthoff, H.H., and Poggio, T. “Viewdependent
object recognition by monkeys,” Curr. Biol. 4:401–414
(1994).
• Logothetis, N.K. and Schall, J.D. “Neuronal correlates of subjective
visual perception,” Science 245:761–763 (1989).
• Logothetis, N.K. and Sheinberg, D.L. “Visual object recognition,”
Ann. Rev. Neurosci. 19:577–621 (1996).
• Louie, K. and Wilson, M.A. “Temporally structured replay of awake
hippocampal ensemble activity during rapid eye movement sleep,”
Neuron 29:145–156 (2001).
• Lovibond, P.F. and Shanks, D.R. “The role of awareness in Pavlovian
conditioning: Empirical evidence and theoretical implications,”
J. Exp. Psychology: Animal Behavior Processes 28:3–26 (2002).
• Lucas, J.R. “Minds, machines and G¨odel,” Philosophy 36:112–127
(1961).
• Luce, R.D. Response Times. Oxford, UK: Oxford University Press
(1986).
• Luck, S.J., Chelazzi, L., Hillyard, S.A., and Desimone, R. “Neural
mechanisms of spatial attention in areas V1, V2, and V4 of macaque
visual cortex,” J. Neurophysiol. 77:24–42 (1997).
• Luck, S.J., Hillyard, S.A., Mangun, G.R., and Gazzaniga, M.S. “Independent
hemispheric attentional systems mediate visual search in
split-brain patients,” Nature 342:543–545 (1989).
• Luck, S.J., Hillyard, S.A., Mangun, G.R., and Gazzaniga, M.S. “Independent
attentional scanning in the separated hemispheres of splitbrain
patients,” J. Cogn. Neurosci. 6:84–91 (1994).
• Lumer, E.D., Friston, K.J., and Rees, G. “Neural correlates of perceptual
rivalry in the human brain,” Science 280:1930–1934 (1998).
• Lumer, E.D. and Rees, G. “Covariation of activity in visual and prefrontal
cortex associated with subjective visual perception,” Proc.
Natl. Acad. Sci. USA 96:1669–1673 (1999).
参考文献51
• Lux, S., Kurthen, M., Helmstaedter C., Hartje, W., Reuber, M., and
Elger, C.E. “The localizing value of ictal consciousness and its constituent
functions,” Brain 125:2691–2698 (2002).
• Lyon, D.C. and Kaas, J.H. “Evidence for a modified V3 with dorsal
and ventral halves in macaque monkeys,” Neuron 33:453–461 (2002).
• Lytton, W.W. and Sejnowski, T.J. “Simulations of cortical pyramidal
neurons synchronized by inhibitory interneurons,” J. Neurophysiol.
66:1059–1079 (1991).
• Mack, A. and Rock, I. Inattentional Blindness. Cambridge, MA: MIT
Press (1998).
• Mackintosh, N.J. Conditioning and Associative Learning. Oxford,
UK: Clarendon Press (1983).
• Macknik, S.L. and Livingstone, M.S. “Neuronal correlates of visibility
and invisibility in the primate visual system,” Nat Neurosci. 1:144–
149 (1998).
• Macknik, S.L. and Martinez-Conde, S. “Dichoptic visual masking in
the geniculocortical system of awake primates,” J. Cogn. Neurosci.
in press (2004).
• Macknik, S.L., Martinez-Conde, S., and Haglund, M.M. “The role of
spatiotemporal edges in visibility and visual masking,” Proc. Natl.
Acad. Sci. USA. 97:7556–7560 (2000).
• MacLeod, K., Backer, A., and Laurent, G. “Who reads temporal information
contained across synchronized and oscillatory spike trains?”
Nature 395:693–698 (1998).
• MacNeil, M.A. andMasland, R.H. “Extreme diversity among amacrine
cells: Implication for function,” Neuron 20:971–982 (1998).
• Macphail, E.M. The Evolution of Consciousness. Oxford, UK: Oxford
University Press (1998).
• Madler, C. and P¨oppel, E. “Auditory evoked potentials indicate the
loss of neuronal oscillations during general anaesthesia,” Naturwissenschaften
74:42–43 (1987).
• Magoun, H.W. “An ascending reticular activating system in the brain
stem,” Arch. Neurol. Psychiatry 67:145–154 (1952).
参考文献52
• Makeig, S., Westerfield, M., Jung, T.P., Enghoff, S., Townsend, J.,
Courchesne, E., and Sejnowski, T.J. “Dynamic brain sources of visual
evoked responses,” Science 295:690–694 (2002).
• Mandler, G. Consciousness Recovered: Psychological Functions and
Origins of Conscious Thought. Amsterdam, Netherlands: John Benjamins
(2002).
• Manford, M. and Andermann, F. “Complex visual hallucinations:
Clinical and neurobiological insights,” Brain 121:1819–1840 (1998).
• Mark, V. “Conflicting communicative behavior in a split-brain patient:
Support for dual consciousness.” In: Toward a Science of Consciousness:
The First Tucson Discussions and Debates. Hameroff,
S.R., Kaszniak, A.W., and Scott, A.C., eds., pp. 189–196. Cambridge,
MA: MIT Press (1996).
• Marr, D. Vision. San Francisco, CA: Freeman (1982).(邦訳)乾敏郎,
安藤広志訳,ビジョン: 視覚の計算理論と脳内表現,産業図書(1987).
• Mars´alek, P., Koch, C., and Maunsell, J.H.R. “On the Relationship
between Synaptic Input and Spike Output Jitter in Individual Neurons,”
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94:735–740 (1997).
• Martinez, J.L. and Kesner, R.P., eds. Neurobiology of Learning and
Memory. New York: Academic Press (1998).
• Masand P., Popli, A.P., andWeilburg, J.B. “Sleepwalking,” Am. Fam.
Physician 51:649–654 (1995).
• Masland, R.H. “Neuronal diversity in the retina,” Curr. Opinion
Neurobiol. 11:431–436 (2001).
• Mather, G., Verstraten, F., and Anstis, S. The Motion Aftereffect: A
Modern Perspective. Cambridge, MA: MIT Press (1998).
• Mathiesen, C., Caesar, K., ¨Oren, N.A., and Lauritzen, M. “Modification
of activity-dependent increases of cerebral blood flow by excitatory
synaptic activity and spikes in rat cerebellar cortex,” J. Physiology
512:555–566 (1998).
• Mattingley, J.B., Husain, M., Rorden, C., Kennard, C., and Driver,
J. “Motor role of human inferior parietal lobe revealed in unilateral
neglect patients,” Nature 392:179–182 (1998).
参考文献53
• Maunsell, J.H.R. and Van Essen, D.C. “Functional properties of neurons
in middle temporal visual area of the macaque monkey. II. Binocular
interactions and sensitivity to binocular disparity,” J. Neurophysiol.
49:1148–1167 (1983).
• McAdams, C.J. andMaunsell, J.H.R. “Effects of attention on orientationtuning
functions of single neurons in macaque cortical area V4,” J.
Neurosci. 19:431–441 (1999).
• McAdams, C.J. and Maunsell, J.H.R. “Attention to both space and
feature modulates neuronal responses in macaque area V4,” J. Neurophysiol.
83:1751–1755 (2000).
• McBain, C.J. and Fisahn, A. “Interneurons unbound,” Nature Rev.
Neurosci. 2:11–23 (2001).
• McClintock, M.K. “Whither menstrual synchrony?” Ann. Rev. Sex
Res. 9:77–95 (1998).
• McComas, A.J. and Cupido, C.M. “The RULER model. Is this how
somatosensory cortex works?” Clinical Neurophysiol. 110:1987–1994
(1999).
• McConkie, G.W. and Currie, C.B. “Visual stability across saccades
while viewing complex pictures,” J. Exp. Psych.: Human Perception
& Performance 22:563–581 (1996).
• McCullough, J.N., Zhang, N., Reich, D.L., Juvonen, T.S., Klein, J.J.,
Spielvogel, D., Ergin, M.A., and Griepp, R.B. “Cerebral metabolic
suppression during hypothermic circulatory arrest in humans,” Ann.
Thorac. Surg. 67:1895–1899 (1999).
• McGinn, C. The Problem of Consciousness. Oxford, UK: Blackwell
(1991).
• McMullin, E. “Biology and the theology of the human.” In: Controlling
Our Destinies. Sloan, P.R., ed., pp. 367–400. Notre Dame, IN:
University of Notre Dame Press (2000).
• Meador, K.J., Ray, P.G., Day, L.J., and Loring, D.W. “Train duration
effects on perception: Sensory deficit, neglect and cerebral lateralization,”
J. Clinical Neurophysiol. 17:406–413 (2000).
• Meadows, J.C. “Disturbed perception of colours associated with localized
cerebral lesions,” Brain 97:615–632 (1974).
参考文献54
• Medina, J.F., Repa, J.C., Mauk, M.D., and LeDoux, J.E. “Parallels
between cerebellum- and amygdala-dependent conditioning,” Nature
Rev. Neurosci. 3:122–131 (2002).
• Meenan, J.P. and Miller, L.A. “Perceptual flexibility after frontal or
temporal lobectomy,” Neuropsychologia 32:1145–1149 (1994).
• Meister, M. “Multineuronal codes in retinal signaling,” Proc. Natl.
Acad. Sci. USA 93:609–614 (1996).
• Merigan, W.H. and Maunsell, J.H.R. “How parallel are the primate
visual pathways?” Ann. Rev. Neurosci. 16:369–402 (1993).
• Merigan, W.H., Nealey, T.A., and Maunsell, J.H.R. “Visual effects of
lesions of cortical area V2 in macaques,” J. Neurosci. 13:3180–3191
(1993).
• Merikle, P.M. “Perception without awareness. Critical issues,” Am.
Psychol. 47:792–795 (1992).
• Merikle, P.M. and Daneman, M. “Psychological investigations of unconscious
perception,” J. Consc. Studies 5:5–18 (1998).
• Merikle, P.M., Smilek, D., and Eastwood, J.D. “Perception without
awareness: Perspectives from cognitive psychology,” Cognition
79:115–134 (2001).
• Merleau-Ponty, M. The Phenomenology of Perception. C. Smith,
transl., London: Routledge & Kegan Paul (1962).
• Metzinger, T., ed. Conscious Experience. Exeter, UK: Imprint Academic
(1995).
• Metzinger, T., ed. Neural Correlates of Consciousness: Empirical and
Conceptual Questions. Cambridge, MA: MIT Press (2000).
• Michael, C.R. “Color vision mechanisms in monkey striate cortex:
Dual-opponent cells with concentric receptive fields,” J. Neurophysiol.
41:572–588 (1978).
• Michael, C.R. “Columnar organization of color cells in monkey’s striate
cortex,” J. Neurophysiol. 46:587–604 (1981).
• Miller, E.K. “The prefrontal cortex: Complex neural properties for
complex behavior,” Neuron 22:15–17 (1999).
参考文献55
• Miller, E.K. and Cohen, J.D. “An integrative theory of prefrontal
cortex function,” Ann. Rev. Neurosci. 24:167–202 (2001).
• Miller, E.K., Gochin, P.M., and Gross, C.G. “Suppression of visual
responses of neurons in inferior temporal cortex of the awake macaque
by addition of a second stimulus,” Brain Res. 616:25–29 (1993).
• Miller, E.K., Erickson, C.A., and Desimone, R. “Neural mechanisms
of visual working memory in prefrontal cortex of the macaque,” J.
Neurosci. 16:5154–5167 (1996).
• Miller, G.A. “The magical number seven, plus or minus two: Some
limits on our capacity for processing information,” Psychol. Rev.
63:81–97 (1956).
• Miller, K.D., Chapman, B., and Stryker, M.P. “Visual responses in
adult cat visual cortex depend on N-methyl-D-aspartate receptors,”
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 86:5183–5187 (1989).
• Miller, S.M., Liu, G.B., Ngo, T.T., Hooper, G., Riek, S., Carson, R.G.,
and Pettigrew, J.D. “Interhemispheric switching mediates perceptual
rivalry,” Curr. Biol. 10:383–392 (2000).
• Millican, P. and Clark, A., eds. Machines and Thought: The Legacy
of Alan Turing. Oxford, UK: Oxford University Press (1999).
• Milner, A.D. and Dyde, R. “Why do some perceptual illusions affect
visually guided action, when others don’t?” Trends Cogn. Sci. 7:10–
11 (2003).
• Milner, A.D. and Goodale, M.A. The Visual Brain in Action. Oxford,
UK: Oxford University Press (1995).
• Milner, A.D., Perrett, D.I., Johnston, R.S., Benson, P.J., Jordan,
T.R., Heeley, D.W., Bettucci, D., Mortara, F., Mutani, R., Terazzi,
E., and Davidson, D.L.W. “Perception and action in form agnosia,”
Brain 114:405–428 (1991).
• Milner, B. “Disorders of learning and memory after temporal lobe
lesions in man,” Clin. Neurosurg. 19:421–446 (1972).
• Milner, B., Squire, L.R., and Kandel, E.R. “Cognitive neuroscience
and the study of memory,” Neuron 20:445–468 (1998).
• Milner, P. “A model for visual shape recognition,” Psychol. Rev.
81:521–535 (1974).
参考文献56
• Minamimoto, T. and Kimura, M. “Participation of the thalamic CMPf
complex in attentional orienting,” J. Neurophysiol. 87:3090–3101
(2002).
• Minsky, M. The Society of Mind. New York: Simon and Schuster
(1985).(邦訳)安西祐一郎訳,心の社会、産業図書(1990).
• Mitchell, J.P., Macrae, C.N., and Gilchrist, I.D. “Working memory
and the suppression of reflexive saccades,” J. Cogn. Neurosci. 14:95–
103 (2002).
• Miyashita, Y., Okuno, H., Tokuyama, W., Ihara, T., and Nakajima,
K. “Feedback signal from medial temporal lobe mediates visual associative
mnemonic codes of inferotemporal neurons,” Brain Res. Cogn.
Brain Res. 5:81–86 (1996).
• Moldofsky, H., Gilbert, R., Lue, F.A., and MacLean, A.W. “Sleeprelated
violence,” Sleep 18:731–739 (1995).
• Montaser-Kouhsari, L., Moradi, F., Zand-Vakili, A., and Esteky, H.
“Orientation selective adaptation during motion-induced blindness,”
Perception, in press (2004).
• Moore, G.E. Philosophical Studies. London: Routledge & Kegan Paul
(1922).
• Moran, J. and Desimone, R. “Selective attention gates visual processing
in extrastriate cortex,” Science 229:782–784 (1985).
• Morris, J.S., Ohman, A., and Dolan, R.J. “A subcortical pathway to
the right amygdala mediating ‘unseen’ fear,” Proc. Natl. Acad. Sci.
USA 96:1680–1685 (1999).
• Moruzzi, G. and Magoun, H.W. “Brain stem reticular formation and
activation of the EEG,” EEG Clin. Neurophysiol. 1:455–473 (1949).
• Motter, B.C. “Focal attention produces spatially selective processing
in visual cortical areas V1, V2, and V4 in the presence of competing
stimuli,” J. Neurophysiol. 70:909–919 (1993).
• Mountcastle, V.B. “Modality and topographic properties of single
neurons of cat’s somatic sensory cortex,” J. Neurophysiol. 20:408–
434 (1957).
• Mountcastle, V.B. Perceptual Neuroscience. Cambridge, MA: Harvard
University Press (1998).
参考文献57
• Mountcastle, V.B., Andersen, R.A., and Motter, B.C. “The influence
of attentive fixation upon the excitability of light-sensitive neurons of
the posterior parietal cortex,” J. Neurosci. 1:1218–1235 (1981).
• Moutoussis, K. and Zeki, S. “Functional segregation and temporal
hierarchy of the visual perceptive systems,” Proc. R. Soc. Lond. B
264:1407–1415 (1997a).
• Moutoussis, K. and Zeki, S. “A direct demonstration of perceptual
asynchrony in vision,” Proc. R. Soc. Lond. B 264:393–399 (1997b).
• Mumford, D. “On the computational architecture of the neocortex. I.
The role of the thalamo-cortical loop,” Biol. Cybernetics 65:135–145
(1991).
• Mumford, D. “Neuronal architectures for pattern-theoretic problems.”
In: Large Scale Neuronal Theories of the Brain. Koch, C., and Davis,
J.L., eds, pp. 125–152. Cambridge, MA: MIT Press (1994).
• Murakami, I., Komatsu, H., and Kinoshita, M. “Perceptual filling-in
at the scotoma following a monocular retinal lesion in the monkey,”
Visual Neurosci. 14:89–101 (1997).
• Murayama, Y., Leopold, D.A., and Logothetis, N.K. “Neural activity
during binocular rivalry in the anesthetized monkey,” Soc. Neurosci.
Abstr. 448.11 (2000).
• Murphy, N. “Human nature: Historical, scientific, and religious issues.”
In: Whatever Happened to the Soul? Scientific and Theological
Portraits of Human Nature. Brown, W.S., Murphy, N., and Malony
H.N., eds., pp. 1–30. Minneapolis, MN: Fortress Press (1998).
• Myerson, J., Miezin, F., and Allman, J.M. “Binocular rivalry in macaque
monkeys and humans: A comparative study in perception,” Behav.
Anal. Lett. 1:149–159 (1981).
• Naccache, L., Blandin, E., and Dehaene, S. “Unconscious masked
priming depends on temporal attention,” Psychol. Sci. 13:416–424
(2002).
• Nadel, L. and Eichenbaum, H. “Introduction to the special issue on
place cells,” Hippocampus 9:341–345 (1999).
• Nagarajan, S., Mahncke, H., Salz, T., Tallal, P., Roberts, T., and
Merzenich, M.M. “Cortical auditory signal processing in poor readers,”
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 96:6483–6488 (1999).
参考文献58
• Nagel, T. “What is it like to be a bat?” Philosophical Rev. 83:435–450
(1974).
• Nagel, T. “Panpsychism.” In: Mortal Questions. Nagel, T., ed., pp.
181–195. Cambridge, UK: Cambridge University Press (1988).
• Nakamura, R.K. and Mishkin, M. “Blindness in monkeys following
non-visual cortical lesions,” Brain Res. 188:572–577 (1980).
• Nakamura, R.K. and Mishkin, M. “Chronic ‘blindness’ following lesions
of nonvisual cortex in the monkey,” Exp. Brain Res. 63:173–184
(1986).
• Nakayama, K. and Mackeben, M. “Sustained and transient components
of focal visual attention,” Vision Res. 29:1631–1647 (1989).
• Nathans, J. “The evolution and physiology of human color vision:
Insights from molecular genetic studies of visual pigments,” Neuron
24:299–312 (1999).
• Naya, Y., Yoshida, M., and Miyashita, Y. “Backward spreading of
memory-retrieval signal in the primate temporal cortex,” Science 291:
661–664 (2001).
• Newman, J.B. “Putting the puzzle together: Toward a general theory
of the neural correlates of consciousness,” J. Consc. Studies 4:47–66
(1997).
• Newsome, W.T., Britten, K.H. and Movshon, J.A. “Neuronal correlates
of a perceptual decision,” Nature 341:52–54 (1989).
• Newsome, W.T., Maunsell, J.H.R., and Van Essen, D.C. “Ventral
posterior visual area of the macaque: Visual topography and areal
boundaries,” J. Comp. Neurol. 252:139–153 (1986).
• Newsome, W.T. and Pare, E.B. “A selective impairment of motion
perception following lesions of the Middle Temporal visual area (MT),”
J. Neurosci. 8:2201–2211 (1988).
• Niebur, E. and Erd˝os, P. “Theory of the locomotion of nematodes:
Control of the somatic motor neurons by interneurons,” Math. Biosci.
118:51–82 (1993).
• Niebur, E., Hsiao, S.S., and Johnson, K.O. “Synchrony: A neuronal
mechanism for attentional selection?” Curr. Opinion Neurobiol. 12:
190–194 (2002).
参考文献59
• Niebur, E. and Koch, C. “A model for the neuronal implementation
of selective visual attention based on temporal correlation among neurons,”
J. Computational Neurosci. 1: 141–158 (1994).
• Niebur, E., Koch, C., and Rosin, C. “An oscillation-based model
for the neuronal basis of attention,” Vision Research 33:2789–2802
(1993).
• Nijhawan, R. “Motion extrapolation in catching,” Nature 370:256–
257 (1994).
• Nijhawan, R. “Visual decomposition of colour through motion extrapolation,”
Nature 386:66–69 (1997).
• Nimchinsky, E.A., Gilissen, E., Allman, J.M., Perl, D.P., Erwin J.M.,
and Hof, P.R. “A neuronal morphologic type unique to humans and
great apes,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA 96:5268–5273 (1999).
• Nirenberg, S., Carcieri, S.M., Jacobs, A.L., and Latham, P.E. “Retinal
ganglion cells act largely as independent encoders,” Nature 411:698–
701 (2001).
• Nishida, S. and Johnston, A. “Marker correspondence, not processing
latency, determines temporal binding of visual attributes,” Curr. Biol.
12:359–368 (2002).
• No¨e, A. Action in Perception. Cambridge, MA: MIT Press (2004).
• Noesselt, T., Hillyard, S.A., Woldorff, M.G., Schoenfeld, A., Hagner,
T., Jancke, L., Tempelmann, C., Hinrichs, H., and Heinze, H.J.
“Delayed striate cortical activation during spatial attention,” Neuron
35:575–587 (2002).
• Nordby, K. “Vision in a complete achromat: A personal account.”
In: Night Vision: Basic, Clinical and Applied Aspects. Hess, R.F.,
Sharpe, L.T., and Nordby, K., eds., pp. 290–315. Cambridge, UK:
Cambridge University Press (1990).
• Norman, R.A., Maynard, E.M., Guillory, K.S., and Warren, D.J.
“Cortical implants for the blind,” IEEE Spectrum 33:54–59 (1996).
• Norretranders, T. The User Illusion. New York: Penguin (1998).
• Nowak, L.G. and Bullier, J. “The timing of information transfer in
the visual system.” In: Extrastriate Cortex in Primates, Vol. 12.
『意識の探求』の参考文献20-39
参考文献20
• Dennett, D. “Are we explaining consciousness yet?” Cognition 79:221–
237 (2001).
• Dennett, D. “The gift horse of philosophical instruction,” Trends
Cogn. Sci., in press (2004).
• Dennett, D. and Kinsbourne, M. “Time and the observer,” Behavioral
& Brain Sci. 15:183–247 (1992).
• Desimone, R. and Duncan, J. “Neural mechanisms of selective visual
attention,” Ann. Rev. Neurosci. 18:193–222 (1995).
• Desimone, R., Wessinger M., Thomas, L., and Schneider, W. “Attentional
control of visual perception: Cortical and subcortical mechanisms,”
Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol. 55:963–971 (1990).
• Destrebecqz, A. and Cleeremans, A. “Can sequence learning be implicit?
New evidence with the process dissociation procedure,” Psychonomic
Bull. Rev. 8:343–350 (2001).
• DeVries, S.H. and Baylor, D.A. “Mosaic arrangement of ganglion
cell receptive fields in rabbit retina,” J. Neurophysiol. 78:2048–2060
(1997).
• DeWeerd, P., Gattass, R., Desimone, R., and Ungerleider, L.G. “Responses
of cells in monkey visual cortex during perceptual filling-in of
an artificial scotoma,” Nature 377:731–734 (1995).
• DeWeerd, P., Peralta, III M.R., Desimone, R., and Ungerleider, L.G.
“Loss of attentional stimulus selection after extrastriate cortical lesions
in macaques,” Nature Neurosci. 2:753–758 (1999).
• DeYoe, E.A., Carman, G.J., Bandettini, P., Glickman, S., Wieser, J.,
Cox, R., Miller, D., and Neitz, J. “Mapping striate and extrastriate
visual areas in human cerebral cortex,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA
93:2382–2386 (1996).
• DiCarlo, J.J. and Maunsell, J.H.R. “Form representation in monkey
inferotemporal cortex is virtually unaltered by free viewing,” Nature
Neurosci. 3:814–821 (2000).
• DiLollo, V., Enns, J.T., and Rensink, R.A. “Competition for consciousness
among visual events: The psychophysics of reentrant visual
processes,” J. Exp. Psychol. Gen. 129:481–507 (2000).
参考文献21
• Ditterich, J., Mazurek, M.E., and Shadlen, M.N. “Microstimulation of
visual cortex affects the speed of perceptual decisions,” Nature Neurosci.
6:891–898 (2003).
• Di Virgilio, G. and Clarke, S. “Direct interhemisphere visual input to
human speech areas,” Human Brain Map. 5:347–354 (1997).
• Dmytryk, E. On Film Editing: An Introduction to the Art of Film
Construction. Boston: Focal Press (1984).
• Dobelle,W.H. “Artificial vision for the blind by connecting a television
camera to the visual cortex,” Am. Soc. Artificial Internal Organs J.
46:3–9 (2000).
• Dolan, R.J. “Emotion, cognition, and behavior,” Science 298:1191–
1194 (2002).
• Dosher, B. A. and Sperling, G. “A century of human information
processing theory: Vision, attention, memory.” In: Perception and
Cognition at Century’s End. Hochberg J., ed., pp. 201–254. New
York: Academic Press (1998).
• Douglas, R., Koch, C., Mahowald, M., Martin, K., and Suarez, H.
“Recurrent excitation in neocortical circuits,” Science 269:981–985
(1995).
• Dow, B.M. “Orientation and color columns in monkey visual cortex,”
Cerebral Cortex 12:1005–1015 (2002).
• Dowling, J.E. The Retina: An Approachable Part of the Brain. Cambridge,
MA: Harvard University Press (1987).
• Doyle, D.A., Cabral, J.M., Pfuetzner, R.A., Kuo, A., Gulbis, J.M.,
Cohen, S.L., Chait, B.T., and MacKinnon, R. “The structure of the
potassium channel: Molecular basis of K+ conduction and selectivity,”
Science 280:69–77 (1998).
• Dragoi, V., Sharma, J., and Sur, M. “Adaptation-induced plasticity of
orientation tuning in adult visual cortex,” Neuron 28:287–298 (2000).
• Dragunow, M. and Faull, R. “The use of c-fos as a metabolic marker in
neuronal pathway tracing,” J. Neurosci. Methods, 29:261–265 (1989).
• Driver, J. and Baylis, G.C. “Attention and visual object segmentation.”
In: The Attentive Brain. Parasurama R., ed., pp. 299–325.
Cambridge, MA: MIT Press (1998).
参考文献22
• Driver, J. and Mattingley, J.B. “Parietal neglect and visual awareness,”
Nature Neurosci. 1:17–22 (1998).
• Drummond, J.C. “Monitoring depth of anesthesia: With emphasis on
the application of the bispectral index and the middle latency auditory
evoked response to the prevention of recall,” Anesthesiology 93:876–
882 (2000).
• Dudai, Y. The Neurobiology of Memory: Concepts, Findings, Trends.
New York: Oxford University Press (1989).
• Duncan, J. “Selective attention and the organization of visual information,”
J. Exp. Psychology: General 113:501–517 (1984).
• Duncan, J. “Converging levels of analysis in the cognitive neuroscience
of visual attention,” Phil. Trans. R. Soc. Lond. B 353:1307–1317
(1998).
• Duncan, J. “An adaptive coding model of neural function in prefrontal
cortex,” Nature Rev. Neurosci. 2:820–829 (2001).
• Eagleman, D.M. and Sejnowski, T.J. “Motion integration and postdiction
in visual awareness,” Science 287:2036–2038 (2000).
• Ebner, A., Dinner, D.S., Noachtar, S., and L¨uders, H. “Automatisms
with preserved responsiveness: A lateralizing sign in psychomotor
seizures,” Neurology 45:61–64 (1995).
• Eccles, J.C. “Do mental events cause neural events analogously to the
probability fields of quantum mechanics?” Proc. Roy. Soc. Lond. B
227:411–428 (1986).
• Eccles, J.C. Evolution of the Brain: Creation of the Self. London:
Routledge (1988).(邦訳)伊藤正男訳,脳の進化,東京大学出版会(1990).
• Eckhorn, R., Bauer, R., Jordan, W., Brosch, M., Kruse, W., Munk,
M., and Reitb¨ock, H.J. “Coherent oscillations: a mechanism of feature
linking in the visual cortex?” Biol. Cybern. 60:121–130 (1988).
• Eckhorn, R., Frien, A., Bauer, R., Woelbern, T., and Kehr, H. “High
frequency (60–90 Hz) oscillations in primary visual cortex of awake
monkey,” Neuroreport 4:243–246 (1993).
• Edelman, G.M. The Remembered Present: A Biological Theory of
Consciousness. New York: Basic Books (1989).
参考文献23
• Edelman, G.M. “Naturalizing consciousness: A theoretical framework,”
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100:5520–5524 (2003).
• Edelman, G.M. and Tononi, G. A Universe of Consciousness. New
York: Basic Books (2000).
• Efron, R. “The duration of the present,” Annals New York Acad. Sci.
138:713–729 (1967).
• Efron, R. “The minimum duration of a perception,” Neuropsychologia
8:57–63 (1970a).
• Efron, R. “The relationship between the duration of a stimulus and
the duration of a perception,” Neuropsychologia 8:37–55 (1970b).
• Efron, R. “An invariant characteristic of perceptual systems in the
time domain,” Attention and Performance 4:713–736 (1973a).
• Efron, R. “Conservation of temporal information by perceptual systems,”
Perception & Psychophysics 14:518–530 (1973b).
• Egeth, H.E. and Yantis, S. “Visual attention: Control, representation,
and time course,” Ann. Rev. Psychol. 48:269–297 (1997).
• Eichenbaum, H. The Cognitive Neuroscience of Memory. New York:
Oxford University Press (2002).
• Ekstrom, A.D., Kahana, M.J., Caplan, J.B., Fields, T.A., Isham,
E.A., Newman, E.L., and Fried, I. “Cellular networks underlying human
spatial navigation,” Nature 425:184–188 (2003).
• Elger, C.E. “Semeiology of temporal lobe seizures.” In: Intractable
Focal Epilepsy. Oxbury, J., Polkey, C.E., and Duchowny, M., eds., pp.
63–68. Philadelphia: Saunders (2000).
• Eliasmith, C. How Neurons Mean: A Neurocomputational Theory of
Representational Content. Ph.D. Dissertation, Dept. of Philosophy,
Washington University, St. Louis, MO (2000).
• Ellenberger, H.F. The Discovery of the Unconscious. NewYork: Basic
Books (1970).
• Elston, G.N. “Pyramidal cells of the frontal lobe: All the more spinous
to think with,” J. Neurosci. 20:RC95 (1–4) (2000).
参考文献24
• Elston, G.N. and Rosa, M.G.P. “The occipitoparietal pathway of
the macaque monkey: Comparison of pyramidal cell morphology in
layer III of functionally related cortical visual areas,” Cerebral Cortex
7:432–452 (1997).
• Elston, G.N. and Rosa, M.G.P. “Morphological variation of layer III
pyramidal neurones in the occipitotemporal pathway of the macaque
monkey visual cortex,” Cerebral Cortex 8:278–294 (1998).
• Elston, G.N., Tweedale, R., and Rosa, M.G.P. “Cortical integration in
the visual system of the macaque monkey: Large-scale morphological
differences in the pyramidal neurons in the occipital, parietal and
temporal lobes,” Proc. R. Soc. Lond. B 266:1367–1374 (1999).
• Engel, A.K., Fries, P., K¨onig, P., Brecht, M., and Singer, W. “Temporal
binding, binocular rivalry, and consciousness,” Consc. & Cognition
8:128–151 (1999).
• Engel, S.A., Glover, G.H., and Wandell, B.A. “Retinotopic organization
in human visual cortex and the spatial precision of functional
MRI,” Cerebral Cortex 7:181–192 (1997).
• Engel, A.K., K¨onig, P., Gray, C.M., and Singer, W. “Stimulus-dependent
neuronal oscillations in cat visual cortex: Inter-columnar interaction
as determined by cross-correlation analysis,” Eur. J. Neurosci. 2:588–
606 (1990).
• Engel, A.K., K¨onig, P., Kreiter, A.K., and Singer, W. “Interhemispheric
synchronization of oscillatory neuronal responses in cat visual
cortex,” Science 252:1177–1179 (1991).
• Engel, A.K. and Singer, W. “Temporal binding and the neural correlates
of sensory awareness,” Trends Cogn. Sci. 5:16–25 (2001).
• Engel, S.A., Zhang, X., and Wandell, B.A. “Colour tuning in human
visual cortex measured with functional magnetic resonance imaging,”
Nature 388:68–71 (1997).
• Enns, J.T. and DiLollo, V. “What’s new in visual masking,” Trends
Cogn. Sci. 4:345–352 (2000).
• Enroth-Cugell, C. and Robson, J.G. “Functional characteristics and
diversity of cat retinal ganglion cells,” Inv. Ophthalmol. Vis. Sci.
25:250–267 (1984).
参考文献25
• Epstein, R. and Kanwisher, N. “A cortical representation of the local
visual environment,” Nature 392:598–601 (1998).
• Ermentrout, B.G. and Kleinfeld, D. “Traveling electrical waves in cortex:
Insights form phase dynamics and speculation on a computational
role,” Neuron 29:33–44 (2001).
• Fahle, M. “Figure-ground discrimination from temporal information,”
Proc. R. Soc. Lond. B 254:199–203 (1993).
• Farah, M.J. Visual Agnosia. Cambridge, MA: MIT Press (1990).
• Farber, I. and Churchland, P.S. “Consciousness and the neurosciences:
Philosophical and theoretical issues.” In: The Cognitive Neurosciences.
1st ed., Gazzaniga, M.S., ed., pp. 1295–1306. Cambridge, MA: MIT
Press (1995).
• Fearing, F. Reflex Action. Cambridge, MA: MIT Press (1970).
• Feldman, M.H. “Physiological observations in a chronic case of lockedin
syndrome,” Neurol. 21:459–478 (1971).
• Felleman, D.J. and Van Essen, D.C. “Distributed hierarchical processing
in the primate cerebral cortex,” Cerebral Cortex 1:1–47 (1991).
• Fendt, M. and Fanselow, M.S. “The neuroanatomical and neurochemical
basis of conditioned fear,” Neurosci. & Biobehavioral Rev. 23:743–
760 (1999).
• Ffytche, D.H., Guy, C.N., and Zeki, S. “Motion specific responses
from a blind hemifield,” Brain 119:1971–1982 (1996).
• Ffytche, D.H., Howard, R.J., Brammer, M.J., David, A., Woodruff,
P., and Williams, S. “The anatomy of conscious vision: An fMRI
study of visual hallucinations,” Nature Neurosci. 1:738–742 (1998).
• Finger, S. Origins of Neuroscience. New York: Oxford University
Press (1994).
• Fiorani, M. Jr., Rosa, M.G.P., Gattass, R., and Rocha-Miranda, C.E.
“Dynamic surrounds of receptive fields in primate striate cortex: A
physiological basis for perceptual completion?” Proc. Natl. Acad.
Sci. USA 89:8547–8551 (1992).
• Flaherty, M.G. A Watched Pot: How We Experience Time. New
York: University Press (1999).
参考文献26
• Flanagan, O. Consciousness Reconsidered. Cambridge, MA: MIT
Press (1992).
• Flanagan, O. Dreaming Souls. New York: Oxford University Press
(2000).
• Flanagan, O. The Problem of the Soul. New York: Basic Books (2002).
• Flohr, H. “NMDA receptor-mediated computational processes and
phenomenal consciousness.” In: Neural Correlates of Consciousness:
Empirical and Conceptual Questions. Metzinger, T., ed., pp. 245–258.
Cambridge, MA: MIT Press (2000).
• Flohr, H., Glade, U., and Motzko, D. “The role of the NMDA synapse
in general anesthesia,” Toxicology Lett. 100:23–29 (1998).
• Foote, S.L., Aston-Jones, G., and Bloom, F.E. “Impulse activity of locus
coeruleus neurons in awake rats and monkeys is a function of sensory
stimulation and arousal,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA 77:3033–
3037 (1980).
• Foote, S.L. and Morrison, J.H. “Extrathalamic modulation of cortical
function,” Ann. Rev. Neurosci. 10:67–95 (1987).
• Forster, E.M. and Whinnery, J.E. “Recovery from Gz-induced loss
of consciousness: Psychophysiologic considerations,” Aviation, Space,
Env. Med. 59:517–522 (1988).
• Frank, L.M., Brown, E.N., and Wilson, M. “Trajectory encoding in
the hippocampus and entorhinal cortex,” Neuron 27:169–178 (2000).
• Franks, N.P. and Lieb, W.R. “Molecular and cellular mkechanisms of
general anesthesia,” Nature 367:607–614 (1994).
• Franks, N.P. and Lieb, W.R. “The molecular basis of general anesthesia:
Current ideas.” In: Toward a Science of Consciousness II.
Hameroff, S.R., Kaszniak, A.W., and Scott, A.C., eds., pp.443–457.
Cambridge, MA: MIT Press (1998).
• Franks, N.P. and Lieb, W.R. “The role of NMDA receptors in consciounsess:
What can we learn from anesthetic mechanisms?” In:
Neural Correlates of Consciousness: Empirical and Conceptual Questions.
Metzinger, T., ed., pp. 265–269. Cambridge, MA: MIT Press
(2000).
参考文献27
• Franz, V.H., Gegenfurtner, K.R., B¨ulthoff, H.H., and Fahle, M. “Grasping
visual illusions: No evidence for a dissociation between perception
and action,” Psychol. Sci. 11:20–25 (2000).
• Freedman, D.J., Riesenhuber, M., Poggio, T., and Miller, E.K. “Categorical
representation of visual stimuli in the primate prefrontal cortex,”
Science 291:312–316 (2001).
• Freedman, D.J., Riesenhuber, M., Poggio, T., and Miller, E.K. “Visual
categorization and the primate prefrontal cortex: Neurophysiology
and behavior,” J. Neurophysiol. 88:929–941 (2002).
• Freeman, W.J. Mass Action in the Nervous System. New York: Academic
Press (1975).
• Freud, S. “Das Unbewusste,” Int. Zeitschrift Psychoanal. 3(4):189–
203 and 3(5):257–269 (1915).
• Freud, S. The Standard Edition of the Complete Psychological Works
of Sigmund Freund, Vol. 1: 1886–1899. Strachey, J., ed., London:
The Hogart Press (1966).
• Freund, T.F. and Buzs´aki, G. “Interneurons in the hippocampus,”
Hippocampus 6:347–470 (1996).
• Fried, I. “Auras and experiental responses arising in the temporal
lobe.” In: The Neuropsychiatry of Limbic and Subcortical Disorders.
Salloway S., Malloy P., and Cummings J.L., eds., pp. 113–122. Washington,
DC: American Psychiatric Press (1997).
• Fried, I., Wilson, C.L., MacDonald, K.A., and Behnke, E.J. “Electric
current stimulates laughter,” Nature 391:650 (1998).
• Friedman-Hill, S., Maldonado, P.E., and Gray, C.M. “Dynamics of
striate cortical activity in the alertmacaque: I. Incidence and stimulusdependence
of gamma-band neuronal oscillations,” Cerebral Cortex
10:1105–1116 (2000).
• Fries, P., Neuenschwander, S., Engel, A.K., Goebel, R., and Singer,W.
“Rapid feature selective neuronal synchronization through correlated
latency shifting,” Nature Neurosci. 4:194–200 (2001a).
• Fries, P., Reynolds, J.H., Rorie, A.E., and Desimone, R. “Modulation
of oscillatory neuronal synchronization by selective visual attention,”
Science 291:1560–1563 (2001b).
参考文献28
• Fries, P., Schr¨oder, J.-H., Singer, W., and Engel, A.K. “Conditions
of perceptual selection and suppression during interocular rivalry in
strabismic and normal cats,” Vision Res. 41:771–783 (2001c).
• Fries, W. “Pontine projection from striate and prestriate visual cortex
in the macaque monkey: An anterograde study,” Vis. Neurosci.
4:205–216 (1990).
• Fries, P., Roelfsema, P.R., Engel, A.K., K¨onig, P., and Singer, W.
“Synchronization of oscillatory responses in visual cortex correlates
with perception in interocular rivalry,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA
94:12699–12704 (1997).
• Frith, C.D. “The role of prefrontal cortex in self-consciousness: The
case of auditory hallucinations,” Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. B
351:1505–1512 (1996).
• Fuster, J.M. “Unit activity in prefrontal cortex during delayed-response
performance: Neuronal correlates of transient memory,” J. Neurophysiol.
36:61–78 (1973).
• Fuster, J.M. Memory in the Cerebral Cortex. Cambridge, MA: MIT
Press (1995).
• Fuster, J.M. The Prefrontal Cortex: Anatomy, Physiology, and Neuropsychology
of the Frontal Lobe. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott-
Raven (1997).
• Fuster, J.M. “Executive frontal functions,” Exp. Brain Res. 133:66–
70 (2000).
• Gail, A., Brinksmeyer, H.J., and Eckhorn, R. “Perception-related
modulations of local field potential power and coherence in primary
visual cortex of awakemonkey during binocular rivalry,” Cerebral Cortex,
in press (2004).
• Galambos, R., Makeig, S., and Talmachoff, P.J. “A 40-Hz auditory
potential recorded from the human scalp,” Proc. Natl. Acad. Sci.
78:2643–2647 (1981).
• Galin, D. “The structure of awareness: Contemporary applications of
William James’ forgotten concept of ‘the fringe’,” J. Mind & Behavior
15:375–402 (1997).
参考文献29
• Gallant, J.L., Connor, C.E., and Van Essen, D.C. “Neural activity in
areas V1, V2 and V4 during free viewing of natural scenes compared
to controlled viewing,” Neuroreport 9:2153–2158 (1997).
• Gallant, J.L., Shoup, R.E., and Mazer, J.A. “A human extrastriate
area functionally homologous to macaque V4,” Neuron 27:227–235
(2000).
• Gallistel, C.R. The Organization of Learning. Cambridge, MA: MIT
Press (1990).
• Gandhi, S.P., Heeger, D.J., and Boynton, G.M. “Spatial attention
affects brain activity in human primary visual cortex,” Proc. Natl.
Acad. Sci. USA 96:3314–3319 (1999).
• Gangestad, S.W., Thornhill, R., and Garver, C.E. “Changes in women’s
sexual interests and their partners’ mate-retention tactics across the
menstrual cycle: Evidence for shifting conflicts of interest,” Proc. Roy.
Soc. Lond. B 269:975–982 (2002).
• Gawne, T.J. and Martin, J.M. “Activity of primate V1 cortical neurons
during blinks,” J. Neurophysiol. 84:2691–2694 (2000).
• Gazzaniga, M.S. “Principles of human brain organization derived from
split-brain studies,” Neuron 14:217–228 (1995).
• Gegenfurtner, K. R. and Sperling, G. “Information transfer in iconic
memory experiments,” J. Exp. Psychol. 19:845–866 (1993).
• Geissler, H.G., Schebera, F.U., and Kompass, R. “Ultra-precise quantal
timing: evidence from simultaneity thresholds in long-range apparent
movement,” Percept. Psychophys. 61:707–726 (1999).
• Gershon, M.D. The Second Brain: The Scientific Basis of Gut Instinct.
New York: Harper Collins (1998).
• Geschwind, N. and Galaburda, A.M. Cerebral Laterization. Cambridge,
MA: MIT Press (1987).
• Gho, M. and Varela, F.J. “A quantitative assessment of the dependency
of the visual temporal frame upon the cortical rhythm,” J.
Physiol. Paris 83:95–101 (1988).
• Ghose, G.M. and Maunsell, J.H.R. “Attentional modulation in visual
cortex depends on task timing,” Nature 419:616–620 (2002).
参考文献30
• Giacino, J.T. “Disorders of consciousness: Differential diagnosis and
neuropathologic features,” Seminars Neurol. 17:105–111 (1997).
• Gibson, J.J. The Senses Considered as a Perceptual System. Boston:
Houghton Mifflin (1966).
• Gibson, J.R., Beierlein, M., and Connors, B.W. “Two networks of
electrically coupled inhibitory neurons in neocortex,” Nature 402:75–
79 (1999).
• Gladwell, M. “Wrong turn,” The New Yorker, June 11, 50–61 (2001).
• Glickstein, M. “How are visual areas of the brain connected to motor
areas for the sensory guidance of movement?” Trends Neurosci.
23:613–617 (2000).
• Gloor, P. “Consciousness as a neurological concept in epileptology: A
critical review,” Epilepsia 27 (Suppl 2):S14–S26 (1986).
• Gloor, P., Olivier A., and Ives J. “Loss of consciousness in temporal
lobe seizures: Observations obained with stereotaxic depth electrode
recordings and stimulations.” In: Adv. in Epileptology: 11th Epilepsy
Intl. Symposium. Canger, R., Angeleri, F., and Penry, J.K., eds., pp.
349–353. New York: Raven Press (1980).
• Goebel, R., Khorram-Sefat, D., Muckli, L., Hacker, H., and Singer,W.
“The constructive nature of vision: Direct evidence from functional
magnetic resonance imaging studies of apparent motion and motion
imagery,” Eur. J. Neurosci. 10:1563–1573 (1998).
• Gold, J.L. and Shadlen, M.N. “Banburismus and the brain: Decoding
the relationship between sensory stimuli, decisions, and reward,”
Neuron 36:299–308 (2002).
• Goldberg, E. The Executive Brain: Frontal Lobes and the Civilized
Mind. New York: Oxford University Press (2001).
• Goldman-Rakic, P.S. “Architecture of the prefrontal cortex and the
central executive,” Annals New York Acad. Sci. 769:71–83 (1995).
• Goldman-Rakic, P.S., Scalaidhe, S.P.O., and Chafee, M.W. “Domain
specificity in cognitive systems.” In: The New Cognitive Neurosciences.
2nd ed., Gazzaniga, M.S., ed., pp. 733–742. Cambridge,
MA: MIT Press (2000).
参考文献31
• Goldstein, K. and Gelb, A. “Psychologische Analysen hirnpathologischer
F¨alle auf Grund von Untersuchungen Hirnverletzter. I Zur Psychologie
des optische Wahr-nehmungs-und Erkennungsvorganges,” Z.
Neurologie & Psychiatrie 41:1–142 (1918).
• Goodale, M.A. “Perception and action in the human visual system.”
In: The New Cognitive Neurosciences. 2nd ed., Gazzaniga, M.S., ed.,
pp. 365–377. Cambridge, MA: MIT Press (2000).
• Goodale, M.A., Jakobson, L.S., and Keillor, J.M. “Differences in the
visual control of pantomimed and natural grasping movements,” Neuropsychologia
32:1159–1178 (1994).
• Goodale, M.A. and Milner, A.D. Sight Unseen. Oxford, UK: Oxford
University Press (2004).
• Goodale, M.A., P´elisson, D., and Prablanc, C. “Large adjustments
in visually guided reaching do not depend on vision of the hand or
perception of target displacement,” Nature 320:748–750 (1986).
• Gordon, H. W. and Bogen, J.E. “Hemispheric lateralization of singing
after intracarotid sodium amylobarbitone,” J. Neurol. Neurosurg.
Psychiat. 37:727–738 (1974).
• Gottlieb, J.P., Kusunoki, M., and Goldberg, M.E. “The representation
of visual salience in monkey parietal cortex,” Nature 391:481–484
(1998).
• Gowdy, P.D., Stromeyer, C.F. III, and Kronauer, R.E. “Detection of
flickering edges: Absence of a red-green edge detector,” Vision Res.
39:4186–4191 (1999).
• Grafman, J., Holyoak, K.J., and Boller, F., eds. Structure and Function
of the Human Prefrontal Cortex. Annals New York Acad. Sci.
769 (1995).
• Granon, S., Faure, P., and Changeux, J.P. “Executive and social behaviors
under nicotinic receptor regulation,” Proc. Natl. Acad. Sci.
USA 100:9596–9601 (2003).
• Gray, C.M. “The temporal correlation hypothesis of visual feature
integration: Still alive and well,” Neuron 24:31–47 (1999).
• Gray, C.M., K¨onig, P., Engel, A.K., and Singer, W. “Oscillatory responses
in cat visual cortex exhibit inter-columnar synchronization
which reflects global stimulus properties,” Nature 338:334–337 (1989).
参考文献32
• Gray, C.M. and Singer, W. “Stimulus-specific neuronal oscillations in
orientation columns of cat visual cortex,” Proc. Natl. Acad. Sci.
USA 86:1698–1702 (1989).
• Graziano, M.S.A., Taylor, C.R.S., and Moore, T. “Complex movements
evoked by microstimulation of precentral cortex,” Neuron 34:841–
851 (2002).
• Greenfield, S.A. Journeys to the Centers of the Mind. Toward a Science
of Consciousness. New York: W.H. Freeman (1995).
• Gregory, R.L. “Cognitive contours,” Nature 238:51–52 (1972).
• Gregory, R.L. Eye and Brain: The Psychology of Seeing. 5th ed.
Princeton, NJ: Princeton University Press (1997).
• Grieve, K.L., Acuna, C., and Cudeiro, J. “The primate pulvinar nuclei:
Vision and action,” Trends Neurosci. 23:35–38 (2000).
• Griffin, D.R. Animal Minds: Beyond Cognition to Consciousness.
Chicago, IL: University of Chicago Press (2001).(邦訳)長野敬, 宮
木陽子訳,動物の心,青土社(1995).
• Griffin, D.R. and Speck, G.B. “New evidence of animal consciousness,”
Animal Cognition, in press (2004).
• Grimes, J. “On the failure to detect changes in scenes across saccades.”
In: Perception (Vancouver Studies in Cognitive Science, Vol.
2). Akins, K., ed., pp. 89–110. Oxford, UK: Oxford University Press
(1996).
• Gross, C.G. Brain, Vision, Memory: Tales in the History of Neuroscience.
Cambridge, MA: MIT Press (1998).
• Gross, C.G. “Genealogy of the ‘Grandmother cell’, ” Neuroscientist
8:512–518 (2002).
• Gross, C.G., Bender, D.B., and Rocha-Miranda, C.E. “Visual receptive
fields of neurons in inferotemporal cortex of the monkey,” Science
166:1303–1306 (1969).
• Gross, C.G. and Graziano, M.S.A. “Multiple representations of space
in the brain,” Neuroscientist 1:43–50 (1995).
• Gross, C.G., Rocha-Miranda C.E., and Bender D.B. “Visual properties
of neurons in inferotemporal cortex of the macaque,” J. Neurophysiol.
35:96–111 (1972).
参考文献33
• Grossberg, S. “The link between brain learning, attention, and consciousness,”
Conscious. Cogn. 8:1–44 (1999).
• Grossenbacher, P.G. and Lovelace, C.T. “Mechanisms of synaesthesia:
Cognitive and physiological constraints,” Trends Cogn. Sci. 5:36–41
(2001).
• Grossmann, R.G. “Are current concepts and methods in neuroscience
inadequate for studying the neural basis of consciosuness and mental
activity?” In: Information Processing in the Nervous System, Pinsker,
H.M. and Willis, W.D. Jr., eds. New York: Raven Press (1980).
• Grunewald, A., Bradley, D.C., and Andersen, R.A. “Neural correlates
of structure-from-motion perception in macaque V1 and MT,”
J. Neurosci. 22:6195–6207 (2002).
• Grush, R. and Churchland, P.S. “Gaps in Penrose’s toiling,” J. Consc.
Studies 2:10–29 (1995).
• Gr¨usser, O.J. and Landis, T. Visual Agnosias and Other Disturbances
of Visual Perception and Cognition. Houndmills, UK: MacMillan
Press (1991).
• Guilleminault, C. “Cataplexy.” In: Narcolepsy. Guilleminault, C.,
Dennet, W.C., and Passouant, P. eds., pp. 125–143. New York: Spectrum
(1976).
• Gur, M. and Snodderly, D.M. “A dissociation between brain activity
and perception: Chromatically opponent cortical neurons signal chromatic
flicker that is not perceived,” Vision Res. 37:377–382 (1997).
• Haarmeier, T., Thier, P., Repnow, M., and Petersen, D. “False perception
of motion in a patient who cannot compensate for eye movements,”
Nature 389:849–852 (1997).
• Hadamard, J. The Mathematician’s Mind. Princeton, NJ: Princeton
University Press (1945).
• Hadjikhani, N., Liu, A.K., Dale, A.M., Cavanagh, P., and Tootell,
R.B. “Retinotopy and color sensitivity in human visual cortical area
V8,” Nature Neurosci. 1:235–241 (1998).
• Hahnloser, R.H.R., Kozhevnikov, A.A., and Fee, M.S. “An ultrasparse
code underlies the generation of neural sequences in a songbird,”
Nature 419:65–70 (2002).
参考文献34
• Haines, R.F. “A breakdown in simultaneous information processing.”
In: Presbyopia Research: From Molecular Biology to Visual Adaptation.
Obrecht, G. and Stark, L., eds., pp. 171–175. New York:
Plenum Press (1991).
• Hameroff, S.R. and Penrose, R. “Orchestrated reduction of quantum
coherence in brain microtubules: A model for consciousness.” In:
Toward a Science of Consciousness. Hameroff, S.R., Kaszniak, A.W.,
and Scott, A.C., eds., pp. 507–540. Cambridge, MA: MIT Press
(1996).
• Hamker, F.H. “A dynamic model of how feature cues guide spatial
attention,” Vision Res., in press (2004).
• Hamker F.H. and Worcester, J. “Object detection in natural scenes
by feedback.” In: Biologically Motivated Computer Vision. Lecture
Notes in Computer Science. B¨uelthoff, H.H., ed., pp. 398–407. Berlin:
Springer (2002).
• Han, C.J., O’Tuathaigh, C.M., van Trigt, L., Quinn, J.J., Fanselow,
M.S., Mongeau, R., Koch, C., and Anderson, D.J. “Trace but not
delay fear conditioning requires attention and the anterior cingulate
cortex,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 100:13087–13092 (2003).
• Hardcastle, V.G. “Attention versus consciousness.” In: Neural Basis
of Consciousness. Osaka N., ed., pp. 105–121. Amsterdam, Netherlands:
John Benjamins (2003).
• Hardin, C.L. Color for Philosophers: Unweaving the Rainbow. Indianapolis,
IN: Hackett Publishing Company (1988).
• Harris, K.D., Csicsvar, J., Hirase, H., Dragoi, G., and Buzs´aki, G.
“Organization of cell assembles in the hippocampus,” Nature 424:552–
556 (2003).
• Harrison, R.V., Harel, N., Panesar, J., and Mount, R.J. “Blood capillary
distribution correlates with hemodynamic-based functional imaging
in cerebral cortex,” Cerebral Cortex 12:225–233 (2002).
• Harter, M.R., “Excitability cycles and cortical scanning: A review of
two hypotheses of central intermittency in perception,” Psychol. Bull.
68:47–58 (1967).
参考文献35
• Haxby, J.V., Gobbini, M.I., Furey, M.L., Ishai, A., Schouten, J.L., and
Pietrini, P. “Distributed and overlapping representations of faces and
objects in ventral temporal cortex,” Science 293:2425–2430 (2001).
• Haxby, J.V., Hoffman, E.A., and Gobbini, M.I. “The distributed human
neural system for face perception,” Trends Cogn. Sci. 4:223–233
(2000).
• He, S., Cavanagh, P., and Intrilligator, J. “Attentional resolution and
the locus of visual awareness,” Nature 383:334–337 (1996).
• He, S., Cohen, E.R., and Hu, X. “Close correlation between activity in
brain area MT/V5 and the perception of a visual motion aftereffect,”
Curr. Biol. 8:1215–1218 (1998).
• He, S. and MacLeod, D.I.A. “Orientation-selective adaptation and tilt
aftereffect from invisible patterns,” Nature 411:473–476 (2001).
• Hebb, D.O. The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory.
New York: Wiley (1949).
• Heeger, D.J., Boynton, G.M., Demb, J.B., Seideman, E., and Newsome,
W.T. “Motion opponency in visual cortex,” J. Neurosci. 19:7162–
7174 (1999).
• Heeger, D.J., Huk, A.C., Geisler, W.S., and Albrecht, D.G. “Spikes
versus BOLD: What does neuroimaging tell us about neuronal activity,”
Nature Neurosci. 3:631–633 (2000).
• Heilman, K.M.,Watson, R.T., and Valenstein, E. “Neglect and related
disorders.” In: Clinical Neuropsychology. 4th ed., Heilman, K.M. and
Valenstein, E., eds., pp. 296–346. New York: Oxford University Press
(2003).
• Heinemann, S.H., Terlau, H., St¨uhmer, W., Imoto, K., and Numa, S.
“Calcium-channel characteristics conferred on the sodium-channel by
single mutations,” Nature 356:441–443 (1992).
• Heisenberg, M. and Wolf, R. Vision in Drosophila: Genetics of Microbehavior.
Studies in Brain Function, Vol. 12. Heidelberg, Germany:
Springer (1984).
• Herrigel, E. Zen in the Art of Archery. New York: Pantheon Books
(1953).
参考文献36
• Herzog, M. and Koch, C. “Seeing properties of an invisible object:
Feature inheritance and shine-through,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA
98:4271–4275 (2001).
• Herzog, M., Parish, L., Koch, C., and Fahle, M. “Fusion of competing
features is not serial,” Vision Res. 43:1951–1960 (2003).
• Hess, R.H., Baker, C.L., and Zihl, J. “The motion-blind patient: Lowlevel
spatial and temporal filters,” J. Neurosci. 9:1628–1640 (1989).
• Heywood, C.A. and Zihl, J. “Motion blindness.” In: Case Studies
in the Neuropsychology of Vision. Humphreys, G.W., ed., pp. 1–16.
Psychology Press (1999).
• Hilgetag, C.-C., O’Neill, M.A., and Young, M.P. “Indeterminate organization
of the visual system,” Science 271: 776–777 (1996).
• Hille, B. Ionic Channels of Excitable Membranes. 3rd ed. Sunderland,
MA: Sinauer Associates: (2001).
• Hirsh, I.J. and Sherrick, C.E. “Perceived order in different sense modalities,”
J. Exp. Psychol. 62:423–432 (1961).
• Hobson, J.A. Sleep. New York: Scientific American Library, Freeman
(1989).
• Hobson, J.A. Consciousness. New York: Scientific American Library,
Freeman (1999).
• Hobson, J.A., Stickgold, R., and Pace-Schott, E.F. “The neurophysiology
of REM sleep dreaming,” Neuroreport 9:R1–R14 (1998).
• Hochstein, S. and Ahissar, M. “View from the top: Hierarchies and
reverse hierarchies in the visual system,” Neuron 36:791–804 (2002).
• Hofst¨otter, C., Koch, C., and Kiper, D.C. “Absence of high-level contributions
to the formation of afterimages,” Soc. Neurosci. Abstr.,
819:24 (2003).
• Holender, D. “Semantic activation without conscious identification in
dichotic listening, parafoveal vision, and visual masking: A survey
and appraisal,” Behav. Brain Sci. 9:1–23 (1986).
• Holt, G.R. and Koch, C. “Electrical interactions via the extracellular
potential near cell bodies,” J. Computat. Neurosci. 6:169–184 (1999).
参考文献37
• Holy, T.E., Dulac, C., and Meister, M. “Responses of vomeronasal
neurons to natural stimuli,” Science 289:1569–1572 (2000).
• Horgan, J. The End of Science. Reading, MA: Addison-Wesley (1996).
• Horton, J.C. and Hedley-Whyte, E.T. “Mapping of cytochrome oxidase
patches and ocular dominance columns in human visual cortex,”
Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. B 304:255–272 (1984).
• Horton, J.C. and Hoyt, W.F. “The representation of the visual field
in human striate cortex,” Arch. Opthalmology 109:816–824 (1991a).
• Horton, J.C. and Hoyt, W.F. “Quadratic visual field defects: A hallmark
of lesions in extrastriate (V2/V3) cortex,” Brain 114:1703–1718
(1991b).
• Hu, Y. and Goodale, M.A. “Grasping after a delay shifts size-scaling
from absolute to relative metrics,” J. Cogn. Neurosci. 12:856–868
(2000).
• Hubel, D.H. Eye, Brain, and Vision. New York: Scientific American
Library (1988).
• Hubel, D.H. and Wiesel, T.N. “Receptive fields of single neurons in
the cat’s striate cortex,” J. Physiol. 148:574–591 (1959).
• Hubel, D.H. and Wiesel, T.N. “Receptive fields, binocular interaction
and functional architecture in the cat’s visual cortex,” J. Physiol.
160:106–154 (1962).
• Hubel, D.H. and Wiesel, T.N. “Receptive fields and functional architecture
of monkey striate cortex,” J. Physiol. 195:215–243 (1968).
• H¨ubener M., Shoham, D., Grinvald, A., and Bonhoeffer, T. “Spatial
relationships among three columnar systems in cat area 17,” J. Neurosci.
17:9270–9284 (1997).
• Huerta, M.F., Krubitzer, L.A., and Kaas, J.H. “Frontal eye field as defined
by intracortical microstimulation in squirrel monkeys, owl monkeys
and macaque monkeys: I. Subcortical connections,” J. Comp.
Neurol. 253:415–439 (1986).
• Huk, A.C., Ress, D., and Heeger, D.J. “Neuronal basis of the motion
aftereffect reconsidered,” Neuron 32:161–172 (2001).
参考文献38
• Hunter, J. and Jasper, H.H. “Effects of thalamic stimulation in unanesthetized
cats,” EEG Clin. Neurophysiol. 1:305–315 (1949).
• Hupe, J.M., James, A.C., Payne, B.R., Lomber, S.G., Girard, P., and
Bullier, J. “Cortical feedback improves discrimination between figure
and background by V1, V2, and V3 neurons,” Nature 394:784–787
(1998).
• Husain, M. and Rorden, C. “Non-spatially lateralized mechanisms in
hemispatial neglect,” Nature Rev. Neurosci. 4:26–36 (2003).
• Huxley, T.H. Animal Automatism, and Other Essays. Humboldt Library
of Popular Science Literature. New York: J. Fitzgerald (1884).
• Ilg, U.J. and Thier, P. “Inability of rhesus monkey area V1 to discriminate
between self-induced and externally induced retinal image
slip,” Eur. J. Neurosci. 8:1156–1166 (1996).
• Inoue, Y. and Mihara, T. “Awareness and responsiveness during partial
seizures,” Epilepsia 39:7–10 (1998).
• Ishai, A., Ungerleider, L.G., Martin, A., and Haxby, J.V. “The representation
of objects in the human occipital and temporal cortex,” J.
Cogn. Neurosci. 12 (Suppl. 2):35–51 (2000).
• Ito, M. and Gilbert, C.D. “Attention modulates contextual influences
in the primary visual cortex of alert monkeys,” Neuron 22:593–604
(1999).
• Ito, M., Tamura, H., Fujita, I., and Tanaka, K. “Size and position
invariance of neuronal responses in monkey inferotemporal cortex,” J.
Neurophysiol. 73:218–226
(1995).
• Itti, L. and Koch, C. “A saliency-based search mechanism for overt
and covert shifts of visual attention,” Vision Res. 40:1489–1506
(2000).
• Itti, L. and Koch, C. “Computational modeling of visual attention,”
Nature Rev. Neurosci. 2:194–204 (2001).
• Itti, L., Koch, C., and Niebur, E. “A model of saliency-based visual
attention for rapid scene analysis,” IEEE Trans. Pattern Analysis &
Machine Intell. (PAMI) 20:1254–1259 (1998).
参考文献39
• Jackendoff, R. Consciousness and the Computational Mind. Cambridge,
MA: MIT Press (1987).
• Jackendoff, R. “How language helps us think,” Pragmatics & Cognition
4:1–34 (1996).
• Jacobson, A., Kales, A., Lehmann, D., and Zweizig, J.R. “Somnambulism:
All-night electroencephalographic studies,” Science 148:975–
977 (1965).
• Jacoby, L.L. “A process dissociation framework: Separating automatic
from intentional uses of memory,” J. Memory Lang. 30:513–541
(1991).
• James, W. The Principles of Psychology. New York: Dover Publications
(1890).
• James, W. Psychology: Briefer Course. New York: Collier Books
(1962).
• Jameson, K.A., Highnote, S.M., and Wasserman, L.M. “Richer color
experience in observers with multiple photopigment opsin genes,” Psychonomic
Bulletin & Rev. 8:244–261 (2001).
• J¨arvilehto, T. “The theory of the organism-environment system: IV.
The problem of mental activity and consciousness,” Int. Physiol. Behav.
Sci. 35:35–57 (2000).
• Jasper, H.H. “Sensory information and conscious experience,” Adv.
Neurol. 77:33–48 (1998).
• Jaynes, J. The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral
Mind. Boston: Houghton Mifflin (1976).
• Jeannerod, M. The Cognitive Neuroscience of Action. Oxford, UK:
Blackwell (1997).
• Johnson, R.R. and Burkhalter, A. “A polysynaptic feedback circuit
in rat visual cortex,” J. Neurosci. 17:129–140 (1997).
• Johnson-Laird, P.N. “A computational analysis of consciousness,” Cognition
& Brain Theory 6:499–508 (1983).
• Johnston, R.W. “Pheromones, the vomeronasal system, and communication.”
In: Olfaction and Taste XII: An International Symposium.
Murphy, C., ed., pp. 333–348. Annals New York Acad. Sci. 855
(1998).
『意識の探求』の参考文献1-19
参考文献1
『意識の探求』の参考文献
• Abbott, L.F., Rolls, E.T., and Tovee, M.J. “Representational capacity
of face coding in monkeys,” Cerebral Cortex 6:498–505 (1996).
• Abeles, M. Corticonics: Neural Circuits of the Cerebral Cortex. Cambridge,
UK: Cambridge University Press (1991).
• Abeles, M., Bergman, H., Margalit, E., and Vaadia, E. “Spatiotemporal
firing patterns in the frontal cortex of behaving monkeys,” J.
Neurophysiol. 70:1629–1638 (1993).
• Aboitiz, F., Scheibel, A.B., Fisher, R.S., and Zaidel, E. “Fiber composition
of the human corpus callosum,” Brain Res. 598:143–153
(1992).
• Abrams, R.A. and Landgraf, J.Z. “Differential use of distance and location
information for spatial localization,” Perception & Psychophysics
47:349–359 (1990).
• Achenbach, J. Captured by Aliens: The Search for Life and Truth in
a Very Large Universe. New York: Simon & Schuster (1999).
• Adolphs, R., Tranel, D., Hamann, S., Young, A.W., Calder, A.J.,
Phelps, E.A., Anderson, A., Lee G.P., and Damasio, A.R. “Recognition
of facial emotion in nine individuals with bilateral amygdala
damage,” Neuropsychologia 37:1111–1117 (1999).
• Aglioto, S., DeSouza, J.F.X., and Goodale, M.A. “Size-contrast illusions
deceive the eye but not the hand,” Curr. Biol. 5:679–685
(1995).
• Ahmed, B., Anderson, J., Douglas, R., Martin, K., and Nelson, C.
“Polyneuronal innervation of spiny stellate neurons in cat visual cortex,”
J. Comp. Neurol. 341:39–49 (1994).
• Akelaitis, A.J. “Studies on corpus callosum: Higher visual functions
in each homonymous field following complete section of corpus callosum,”
Arch. Neurol. Psych. (Chicago) 45:788–798 (1941).
• Akelaitis, A.J. “A study of gnosis, praxis and language following section
of the corpus callosum and anterior commisure,” J. Neurosurg.
1:94–102 (1944).
参考文献2
• Aksay, E., Gamkrelidze, G., Seung, H.S., Baker, R., and Tank, D.W.
“In vivo intracellular recording and perturbation of persistent activity
in a neural integrator,” Nature Neurosci. 4:184–193 (2001).
• Alauddin, M.M., Louie, A.Y., Shahinian, A., Meade, T.J., and Conti,
P.S. “Receptor mediated uptake of a radiolabeled contrast agent sensitive
to beta-galactosidase activity,” Nucl. Med. Biol. 30:261–265
(2003).
• Albright, T.D. “Cortical processing of visual motion,” Rev. Oculomot.
Res. 51:77–201 (1993).
• Aldrich, M.S., Alessi, A.G., Beck, R.W., and Gilman, S. “Cortical
blindness: Etiology, diagnosis and prognosis,” Ann. Neurol. 21:149–
158 (1987).
• Alkire, M.T., Haier, R.J., Shah, N.K., and Anderson, C.T. “Positron
emission tomograpy study of regional cerebral metabolism in humans
during isoflurane anesthesia,” Anesthesiology 86:549–557 (1997).
• Alkire, M.T., Pomfrett, C.J.D., Haier, R.J., Gianzero, M.V., Chan,
C.M., Jacobsen, B.P., and Fallon, J.H. “Functional brain imaging
during anesthesia in humans,” Anesthesiology 90:701–709 (1999).
• Allen, W. Getting Even. New York: Random House (1978).
• Allman, J.M. “Stimulus specific responses from beyond the classical
receptive field: Neurophysiological mechanisms for local-global comparisons
in visual neurons,” Ann. Rev. Neurosci. 8:407–430 (1985).
• Allman, J.M. Evolving Brains. New York: Scientific American Library
(1999).
• Allman, J.M. and Kaas, J.H. “A representation of the visual field
in the caudal third of the middle temporal gyrus of the owl monkey
(Aotus trivirgatus),” Brain Res. 31:85–105 (1971).
• Anderson, M.C. and Green, C. “Suppressing unwanted memories by
executive control,” Nature 410:366–369 (2001).
• Andersen, R.A. “Neural mechanisms of visual motion perception in
primates,” Neuron 18:865–872 (1997).
• Andersen, R.A. “Encoding of intention and spatial location in the
posterior parietal cortex,” Cerebral Cortex 5:457–469 (1995).
参考文献3
• Andersen, R.A., Asanuma, C., Essick, G., and Siegel, R.M. “Corticocortical
connections of anatomically and physiologically defined subdivisions
within the inferior parietal lobule,” J. Comp. Neurol. 296:65–
113 (1990).
• Andersen, R.A, Essick, G., and Siegel, R. “Encoding of spatial location
by posterior parietal neurons,” Science 230:456–458 (1985).
• Andersen, R.A., Snyder L.H., Bradley, D.C., and Xing, J. “Multimodal
representation of space in the posterior parietal cortex and its
use in planning movements,” Ann. Rev. Neurosci. 20:303–330 (1997).
• Andrews, T.J., Halpern, S.D., and Purves, D. “Correlated size variations
in human visual cortex, lateral geniculate nucleus and optic
tract,” J. Neurosci. 17:2859–2868 (1997).
• Andrews, T.J., and Purves, D. “Similarities in normal and binocularly
rivalrous viewing,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94:9905–9908 (1997).
• Antkowiak, B. “How do general anesthetics work,” Naturwissenschaften
88:201–213 (2001).
• Arnold, D.H., Clifford, C.W.G., and Wenderoth, P. “Asynchronous
processing in vision: Color leads motion,” Curr. Biol. 11:596–600
(2001).
• Asenjo, A.B., Rim, J., and Oprian, D.D. “Molecular determinants of
human red/green color discrimination,” Neuron 12:1131–1138 (1994).
• Astafiev, S.V., Shulman, G.L., Stanley, C.M., Snyder, A.Z., Van Essen,
D.C., and Corbetta, M. “Functional Organization of Human Intraparietal
and Frontal Cortex for Attending, Looking, and Pointing,”
J. Neurosci. 23:4689–4699 (2003).
• Attneave, F. “In defense of homunculi.” In: Sensory Communication.
Rosenblith W.A., ed., pp. 777–782. New York: MIT Press (1961).
• Baars, B.J. A Cognitive Theory of Consciousness. Cambridge, UK:
Cambridge University Press (1988).
• Baars, B.J. “Surprisingly small subcortical structures are needed for
the state of waking consciousness, while cortical projection areas seem
to provide perceptual contents of consciousness,” Consc. & Cognition
4:159–162 (1995).
参考文献4
• Baars, B.J. In the Theater of Consciousness. New York: OxfordUniversity
Press (1997).
• Baars, B.J. “The conscious access hypothesis: Origins and recent evidence,”
Trends Cogn. Sci. 6:47–52 (2002).
• Bachmann, T. Psychophysiology of Visual Masking. Commack, NY:
Nova Science Publishers (1994).
• Bachmann T. Microgenetic Approach to the Conscious Mind. Amsterdam,
Netherlands: Johns Benjamins (2000).
• Baddeley, A. Working Memory. London, UK: Oxford University Press
(1986).
• Baddeley, A. Human Memory: Theory and Practice. Boston: Allyn
& Bacon (1990).
• Baddeley, A. “The episodic buffer: A new component of working memory?”
Trends Cogn. Sci. 4:417–423 (2000).
• Baer, P.E., and Fuhrer, M.J. “Cognitive processes in the differential
trace conditioning of electrodermal and vasomotor activity,” J. Exp.
Psychology 84:176–178 (1970).
• Bair,W. “Spike timing in the mammalian visual system,” Curr. Opinion
Neurobiol. 9:447–453 (1999).
• Bair, W. and Koch, C. “Temporal precision of spike trains in extrastriate
cortex of the behaving monkey,” Neural Comp. 8:1185–1202
(1996).
• Baizer, J.A., Ungerleider, L.G., and Desimone, R. “Organization of
visual inputs to the inferior temporal and posterior parietal cortex in
macaques,” J. Neurosci. 11:168–190 (1991).
• Bar, M. and Biederman, I. “Subliminal visual priming,” Psychological
Science 9:464–469 (1998).
• Bar, M. and Biederman, I. “Localizing the cortical region mediating
visual awareness of object identity,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA
96:1790–1793 (1999).
• Barbas, H. “Pattern in the laminar origin of corticocortical connections,”
J. Comp. Neurol. 252:415–422 (1986).
参考文献5
• Barcelo, F., Suwazono, S., and Knight, R.T. “Prefrontal modulation
of visual processing in humans,” Nature Neurosci. 3:399–403 (2000).
• Bargmann, C.I. “Neurobiology of the Caenorhabditis elegans genome,”
Science 282:2028–2033 (1998).
• Barlow, H.B. “Single units and sensation: A neuron doctrine for perceptual
psychology,” Perception 1:371–394 (1972).
• Barlow, H.B. “The neuron doctrine in perception.” In: The Cognitive
Neurosciences. 1st ed., Gazzaniga, M., ed., pp. 415–435. Cambridge,
MA: MIT Press (1995).
• Barone, P., Batardiere, A., Knoblauch, K., and Kennedy, H. “Laminar
distribution of neurons in extrastriate areas projecting to visual areas
V1 and V4 correlates with the hierarchical rank and indicates the
operation of a distance rule,” J. Neurosci. 20:3263–3281 (2000).
• Barrow, J.D., and Tipler, F.J. The Anthropic Cosmological Principle.
Oxford, UK: Oxford University Press (1986).
• Bateson, W. “Review of The Mechanism of Mendelian Heredity by
T.H. Morgan, A.H. Sturtevant, H.J. Muller, and C.B. Bridges,” Science
44:536–543 (1916).
• Batista, A.P. and Andersen, R.A. “The parietal reach region codes the
next planned movement in a sequential reach task,” J. Neurophysiol.
85:539–544 (2001).
• Bauby, J.-D. The Diving Bell and the Butterfly: A Memoir of Life in
Death. New York: Alfred A. Knopf (1997).
• Bauer, R.M. and Demery, J.A. “Agnosia.” In: Clinical Neuropsychology.
4th ed., Heilman, K.M., and Valenstein, E., eds., pp. 236–295.
New York: Oxford University Press (2003).
• Bayne, T. and Chalmers, D.J. “What is the unity of consciousness?”
In: The Unity of Consciousness. Cleeremans, A., ed., pp. 23–58.
Oxford, UK: Oxford University Press (2003).
• Beckermann, A., Flohr, H., and Kim, J., eds. Emergence or Reduction?
Essays on the Prospects of Nonreductive Physicalism. Berlin:
Walter de Gruyter (1992).
参考文献6
• Beierlein, M., Gibson, J.R., and Connors, B.W. “A network of electrically
coupled interneurons drives synchronized inhibition in neocortex,”
Nature Neurosci. 3:904–910 (2000).
• Bennett, C.H. “Logical depth and physical complexity.” In: The Universal
Turing Machine. A Half-Century Survey. Herken, R., ed., pp.
227–258. Oxford, UK: Oxford University Press (1988).
• Benton, A. and Tranel, D. “Visuoperceptual, visuospatial, and visuoconstructive
disorders.” In: Clinical Neurosychology. 3rd ed., Heilman,
K.M. and Valenstein, E., eds., pp. 165–278. New York: Oxford
University Press (1993).
• Bergen, J.R. and Julesz, B. “Parallel versus serial processing in rapid
pattern discrimination,” Nature 303:696–698 (1983).
• Berns, G.S., Cohen, J.D., and Mintun, M.A. “Brain regions responsive
to novelty in the absence of awareness,” Science 276:1272–1275
(1997).
• Berti, A. and Rizzolatti, G. “Visual processing without awareness: Evidence
from unilateral neglect,” J. Cogn. Neurosci. 4:345–351 (1992).
• Bhalla, M. and Proffitt, D.R. “Visual-motor recalibration in geographical
slant perception,” J. Exp. Psychol.: Human Perception & Performance
25:1076–1096 (1999).
• Bialek W., Rieke, F., van Steveninck, R.R.D., andWarland, D. “Reading
a neural code,” Science 252:1854–1857 (1991).
• Biederman, I. “Perceiving real-world scenes,” Science 177:77–80 (1972).
• Billock, V.A. “Very short term visual memory via reverberation: A
role for the cortico-thalamic excitatory circuit in temporal filling-in
during blinks and saccades?” Vision Res. 37:949–953 (1997).
• Bisiach, E. and Luzzatti, C. “Unilateral neglect of representational
space,” Cortex 14:129–133 (1978).
• Bisley, J.W. and Goldberg, M.E. “Neuronal activity in the lateral
intraparietal area and spatial attention,” Science 299:81–86 (2003).
• Blackmore, S.J. Beyond the Body: An Investigation of Out-Of-The-
Body Experiences. London: Heinemann (1982).
参考文献7
• Blackmore, S., Brelstaff, G., Nelson, K., and Tsoscianko, T. “Is the
richness of our visual world an illusion? Transsaccadic memory for
complex scenes,” Perception 24:1075–1081 (1995).
• Blake, R. “A neural theory of binocular rivalry,” Psychol. Rev. 96:145–
167 (1989).
• Blake, R. “What can be “perceived” in the absence of visual awareness?”
Curr. Direction Psychol. Sci. 6:157–162 (1998).
• Blake, R. and Cormack, R.H. “On utrocular discrimination,” Perception
& Psychophysics 26:53–68 (1979).
• Blake, R. and Fox, R. “Adaptation to invisible gratings and the site
of binocular rivalry suppression,” Nature 249:488–490 (1974).
• Blake, R. and Logothetis, N.K. “Visual Competition,” Nature Rev.
Neurosci. 3:13–21 (2002).
• Blanke, O., Ortigue, S., Landis, T., and Seeck, M. “Stimulating illusory
own-body perceptions,” Nature 419:269–270 (2002).
• Blasdel, G.G. “Orientation selectivity, preference, and continuity in
monkey striate cortex,” J. Neurosci. 12:3139–3161 (1992).
• Blasdel, G.G. and Lund, J.S. “Termination of afferent axons in macaque
striate cortex,” J. Neurosci. 3:1389–1413 (1983).
• Blaser, E., Sperling, G., and Lu, Z.-L. “Measuring the amplification
of attention,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA 96:11681–11686 (1999).
• Blatow, M., Rozov, A., Katona, I., Hormuzdi, S.G., Meyer, A.H.,
Whittington, M.A., Caputi, A., and Monyer, H. “A novel network
of multipolar bursting interneurons generates theta frequency oscillations
in neocortex,” Neuron 38:805–817 (2003).
• Block, N. “On a confusion about a function of consciousness,” Behav.
Brain Sci. 18:227–247 (1995).
• Block, N. “How can we find the neural correlate of consciousness?”
Trends Neurosci. 19:456–459 (1996).
• Block, N., Flanagan, O., and G¨uzeldere, G., eds. Consciousness:
Philosophical Debates. Cambridge, MA: MIT Press (1997).
• Bogen, J.E. “Mental duality in the intact brain,” Bull. Clinical Neurosci.
51:3–29 (1986).
参考文献8
• Bogen, J.E. “The callosal syndromes.” In: Clinical Neurosychology.
3rd ed., Heilman, K.M. and Valenstein, E., eds., pp. 337–407. New
York: Oxford University Press (1993).
• Bogen, J.E. “On the neurophysiology of consciousness: I. An overview,”
Consc. & Cognition 4:52–62 (1995a).
• Bogen, J.E. “On the neurophysiology of consciousness: II. Constraining
the semantic problem,” Consc. & Cognition 4:137–158 (1995b).
• Bogen, J.E. “Some neurophysiologic aspects of consciousness,” Sem.
Neurobiol. 17:95–103 (1997a).
• Bogen, J.E. “The neurosurgeon’s interest in the corpus callosum.” In:
A History of Neurosurgery in its Scientific and Professional Contexts.
Greenblatt S.H., ed., chapter 24. Park Ridge, IL: American Association
of Neurological Surgeons (1997b).
• Bogen, J.E. “Does cognition in the disconnected right hemisphere require
right hemisphere possession of language?” Brain & Language
57:12–21 (1997c).
• Bogen, J.E., Fisher, E.D., and Vogel, P.J. “Cerebral commissurotomy:
A second case report,” J. Am. Med. Assoc. 194:1328–1329 (1965).
• Bogen, J.E. and Gazzaniga, M.S. “Cerebral commissurotomy in man:
Minor hemisphere dominance for certain visuospatial functions,” J.
Neurosurg. 23:394–399 (1965).
• Bogen, J.E. and Gordon, H. W. “Musical tests for functional lateralization
with intracarotid amobarbital,” Nature 230:524–525 (1970).
• Bonneh, Y.S., Cooperman, A., and Sagi, D. “Motion-induced blindness
in normal observers,” Nature 411:798–801 (2001).
• Booth, M.C.A. and Rolls, E.T. “View-invariant representations of familiar
objects by neurons in the inferior temporal visual cortex,” Cerebral
Cortex 8:510–523 (1998).
• Borrell, V. and Callaway, E.M. “Reorganization of exuberant axonal
arbors contributes to the development of laminar specificity in ferret
visual cortex,” J. Neurosci. 22:6682–6695 (2002).
• Bourassa, J. and Deschenes, M. “Corticothalamic projections from
the primary visual cortex in rats: A single fiber study using biocytin
as an anterograde tracer,” Neurosci. 66:253–263 (1995).
参考文献9
• Braak, H. “On the striate area of the human isocortex. A Golgi and
pigmentarchitectonic study,” J. Comp. Neurol. 166:341–364 (1976).
• Braak, H. Architectonics of the Human Telencephalic Cortex. Berlin:
Springer (1980).
• Bradley, D.C., Chang, G.C., and Andersen, R.A. “Encoding of threedimensional
structure-from-motion by primate areaMT neurons,” Nature
392:714–717 (1998).
• Braitenberg, V. and Sch¨uz, A. Anatomy of the Cortex. Heidelberg:
Springer (1991).
• Braun, J. “Visual search among items of different salience: Removal of
visual attention mimics a lesion in extrastriate area V4,” J. Neurosci.
14:554–567 (1994).
• Braun, J. “Natural scenes upset the visual applecart,” Trends Cogn.
Neurosci. 7:7–9 (2003).
• Braun, A.R., Balkin, T.J.,Wesensten, N.J., Gwadry, F., Carson, R.E.,
Varga, M., Baldwin, P., Belenky, G., and Herscovitch, P. “Dissociated
pattern of activity in visual cortices and their projections during human
rapid eye movement sleep,” Science 279:91–95 (1998).
• Braun, J. and Julesz, B. “Withdrawing attention at little or no cost:
Detection and discrimination tasks,” Perception & Psychophysics 60:1–
23 (1998).
• Braun, J., Koch, C., and Davis, J.L., eds. Visual Attention and Cortical
Circuits. Cambridge, MA: MIT Press (2001).
• Braun, J. and Sagi, D. “Vision outside the focus of attention,” Perception
& Psychophysics 48:277–294 (1990).
• Brefczynski, J.A. and DeYoe, E.A. “A physiological correlate of the
‘spotlight’ of visual attention,” Nature Neurosci. 2:370–374 (1999).
• Breitmeyer, B.G. Visual Masking: An Integrative Approach. Oxford,
UK: Oxford University Press (1984).
• Breitmeyer, B.G. and ¨Ogmen, H. “Recent models and findings in backward
visual masking: A comparison, review and update,” Percept. &
Psychophysics 62:1572–1595 (2000).
参考文献10
• Brewer, A.A., Press, W.A., Logothetis, N.K., and Wandell, B.A. “Visual
areas in macaque cortex measured using functional magnetic resonance
imaging,” J. Neurosci. 22:10416–10426 (2002).
• Brickner, R.M. The Intellectual Functions of the Frontal Lobes. New
York: Macmillan (1936).
• Bridgeman, B., Hendry, D., and Stark, L. “Failure to detect displacement
of the visual world during saccadic eye movements,” Vision Res.
15:719–722 (1975).
• Bridgeman, B., Kirch, M., and Sperling, A. “Segregation of cognitive
and motor aspects of visual function using induced motion,” Percept.
Psychophys. 29:336–342 (1981).
• Bridgeman, B., Lewis, S., Heit, G., and Nagle, M. “Relation between
cognitive and motor-oriented systems of visual position perception,”
J. Exp. Psychol. Hum. Percept. 5:692–700 (1979).
• Bridgeman, B., Peery S., and Anand, S. “Interaction of cognitive
and sensorimotor maps of visual space,” Perception & Psychophysics
59:456–469 (1997).
• Brindley, G.S., Gautier-Smith, P.C., and Lewin, W. “Cortical blindness
and the functions of the non-geniculate fibres of the optic tracts,”
J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 32:259–264 (1969).
• Britten, K.H., Newsome, W.T., Shadlen, M.N., Celebrini, S., and
Movshon, J.A. “A relationship between behavioral choice and the visual
responses of neurons in macaque MT,” Visual Neurosci. 13:87–
100 (1996).
• Britten, K.H., Shadlen, M.N., Newsome, W.T., and Movshon, A. “The
analysis of visual motion: A comparison of neuronal and psychophysical
performance,” J. Neurosci. 12:4745–4765 (1992).
• Broca, A. and Sulzer, D. “La sensation lumineuse fonction du temps,”
J. de Physiol. Taphol. Generale 4:632–640 (1902).
• Brodmann, K. “Physiologie des Gehirns,” Neue Deutsche Chirurgie
11:85–426 (1914).
• Brooke, R.N., Downes, J., and Powell, T.P. “Centrifugal fibres to the
retina in the monkey and cat,” Nature 207:1365–1367 (1965).
参考文献11
• Broughton, R., Billings, R., Cartwright, R., Doucette, D., Edmeads,
J., Edwardh, M., Ervin, F., Orchard, B., Hill, R., and Turrell, G.
“Homicidal somnambulism: A case report,” Sleep 17:253–264 (1994).
• Brown, E.N., Frank, L.M., Tang, D., Quirk, M.C., and Wilson, M.A.
“A statistical paradigm for neural spike train decoding applied to
position prediction from ensemble firing patterns of rat hippocampal
place cells,” J. Neurosci. 18:7411–7425 (1998).
• Brown, W.S., Murphy, N., and Malony, H.N., eds. Whatever Happened
to the Soul? Scientific and Theological Portraits of Human Nature.
Minneapolis, MN: Fortress Press (1998).
• Bruce, C.J., Desimone, R., and Gross, C.G. “Both striate cortex and
superior colliculus contribute to visual properties of neurons in superior
temporal polysensory area of the macaque monkey,” J. Neurophysiol.
55:1057–1075 (1986).
• Budd, J.M. “Extrastriate feedback to primary visual cortex in primates:
A quantitative analysis of connectivity,” Proc. R. Soc. Lond.
B 265:1037–1044 (1998).
• Bullier, J. “Feedback connections and conscious vision,” Trends Cogn.
Sci. 5:369–370 (2001).
• Bullier, J., Girard, P., and Salin, P.-A. “The role of area 17 in the
transfer of information to extrastriate visual cortex.” In: Cerebral
Cortex Vol. 10. Peters, A. and Rockland, K.S., eds., pp. 301–330.
New York: Plenum Press (1994).
• Burkhalter, A. and Van Essen, D.C. “Processing of color, form and
disparity information in visual areas VP and V2 of ventral extrastiriate
cortex in the macaque monkey,” J. Neurosci. 6:2327–2351 (1986).
• Burle, B. and Bonnet, M. “Further argument for the existence of a
pacemaker in the human information processing system,” Acta Psychol.
97:129–143 (1997).
• Burle, B. and Bonnet, M. “What’s an internal clock for? From temporal
information processing to temporal processing of information,”
Behavioural Processes 45:59–72 (1999).
• Burr, D.C., Morrone, M.C., and Ross, R. “Selective suppression of
the magnocellular visual pathway during saccadic eye movements,”
Nature 371:511–513 (1994).
参考文献12
• Buxhoeveden, D.P. and Casanova, M.F. “The minicolumn hypothesis
in neuroscience,” Brain 125:935–951 (2002).
• Buzs´aki, G. “Theta oscillations in the hippocampus,” Neuron 33:325–
340 (2002).
• Byrne, A. and Hilbert, D.R., eds. Readings on Color: The Science of
Color. Vol. 2. Cambridge, MA: MIT Press (1997).
• Calkins, D.J. “Representation of cone signals in the primate retina,”
J. Optical Soc. Am. A 17:597–606 (2000).
• Callaway, E.M. and Wiser, A.K. “Contributions of individual layer
2–5 spiny neurons to local circuits in macaque primary visual cortex,”
Vis. Neurosci. 13:907–922 (1996).
• Calvin, W.H. “Competing for consciousness: A Darwinian mechanism
of an appropriate level of explanation.” J. Consc. Studies 5:389–404
(1998).
• Calvin, W.H. and Ojemann, G.A. Conversations with Neil’s Brain.
Reading, MA: Addison-Wesley (1994).
• Campbell, K.K. Body and Mind. New York: Doubleday (1970).
• Carey, D.P. “Do action systems resist visual illusions?” Trends Cogn.
Sci. 5:109–113 (2001).
• Carmichael, S.T. and Price, J.L. “Architectonic subdivision of the orbital
and medial prefrontal cortex in the macaque monkey,” J. Comp.
Neurol. 346:366–402 (1994).
• Carrillo, M.C., Gabrieli, J.D.E., and Disterhoft, J.F. “Selective effects
of division of attention on discrimination conditioning,” PsychoBiol.
28:293–302 (2000).
• Carter, R.M., Hofst¨otter, C., Tsuchiya, N., and Koch, C. “Working
memory and fear conditoning,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA
100:1399–1404 (2003).
• Castet, E. and Masson, G.S. “Motion perception during saccadic eye
movements,” Nature Neurosci. 3:177–183 (2000).
• Castiello, U., Paulignan, Y., and Jeannerod, M. “Temporal dissociation
of motor responses and subjective awareness,” Brain 114:2639–
2655 (1991).
参考文献13
• Cauller, L.J. and Kulics, A.T. “The neural basis of the behaviorally
relevant N1 component of the somatosensory-evoked potential in SI
cortex of awake monkeys: Evidence that backward cortical projections
signal conscious touch sensation,” Exp. Brain Res. 84:607–619
(1991).
• Cave, K.R. and Bichot, N.P. “Visuospatial attention: Beyond a spotlight
model,” Psychonomic Bull. Rev. 6:204–223 (1999).
• Celesia, G.G. “Persistent vegetative state: Clinical and ethical issues,”
Theor. Medicine 18:221–236 (1997).
• Celesia, G.G., Bushnell, D., Cone-Toleikis, S., and Brigell, M.G. “Cortical
blindness and residual vision: Is the second visual system in humans
capable of more than rudimentary visual perception?” Neurol.
41:862–869 (1991).
• Chalmers, D.J. The Conscious Mind: In Search of a Fundamental
Theory. New York: Oxford University Press (1996).(邦訳)林一訳,
意識する心:脳と精神の根本理論を求めて,白揚社(2001).
• Chalmers, D.J. “What is a neural correlate of consciousness?” In:
Neural Correlates of Consciousness: Empirical and Conceptual Questions.
Metzinger, T., ed., pp. 17–40. Cambridge, MA: MIT Press
(2000).
• Chalmers, D.J., ed. Philosophy of Mind: Classical and Contemporary
Readings. Oxford, UK: Oxford University Press (2002).
• Changeux, J.P. L’homme neuronal. Paris: Fayard (1983).
• Chatterjee, S. and Callaway, E.M. “S cone contributions to the magnocellular
visual pathway in macaque monkey,” Neuron 35:1135–1146
(2002).
• Cheesman J. and Merikle, P.M. “Distinguishing conscious from unconscious
perceptual processes,” Can. J. Psychol. 40:3433–367 (1986).
• Chelazzi, L., Miller, E.K., Duncan, J., and Desimone, R. “A neural
basis for visual search in inferior temporal cortex,” Nature 363:345–
347 (1993).
• Cherniak, C. “Neural component placement,” Trends Neurosci. 18:522–
527 (1995).
参考文献14
• Chun, M. M. and Wolfe, J. M. “Just say no: How are visual searches
terminated when there is no target present?” Cogn. Psychology
30:39–78 (1996).
• Churchland, P.S. Neurophilosophy. Cambridge,MA:MIT Press (1986).
(邦訳)信原幸弘,宮島昭二訳,認知哲学:脳科学から心の哲学へ,産
業図書(1997).
• Churchland, P.S. Brain-Wise: Studies in Neurophilosophy. Cambridge,
MA: MIT Press (2002).
• Churchland, P.S. and Ramachandran, V.S. “Filling in: Why Dennett
is wrong.” In: Dennett and His Critics: Demystifying Mind.
Dahlbom, B., ed., pp. 28–52. Oxford, UK: Blackwell Scientific (1993).
• Clark, R.E. and Squire, L.R. “Classical conditioning and brain systems:
The role of awareness,” Science 280:77–81 (1998).
• Clark, R.E. and Squire, L.R. “Human eyeblink classical conditioning:
Effects of manipulating awareness of the stimulus contingencies,”
Psychological Sci. 10:14–18 (1999).
• Cleeremans, A., et al. “Implicit learning: News from the front,”
Trends Cogn. Sci. 2:406–416 (1998).
• Cleeremans, A., ed. The Unity of Consciousness. Oxford, UK: Oxford
University Press (2003).
• Clifford, C.W.G., Arnold, D.H., and Pearson, J. “A paradox of temporal
perception revealed by a stimulus oscillating in colour and orientation,”
Vision Res. 43:2245–2253 (2003).
• Colby, C.L. and Goldberg, M.E. “Space and attention in parietal cortex,”
Ann. Rev. Neurosci. 22:319–349 (1999).
• Cole, J. Pride and a Daily Marathon. Cambridge, MA: MIT Press
(1995).
• Coltheart, M. “Iconic memory,” Phil. Trans. R. Soc. Lond. B
302:283–294 (1983).
• Coltheart, V., ed. Fleeting Memories: Cognition of Brief Visual Stimuli.
Cambridge, MA: MIT Press (1999).
• Colvin, M.K., Dunbar, K., and Grafman, J. “The effects of frontal lobe
lesions on goal achievement in the water jug task,” J. Cogn. Neurosci.
13:1139–1147 (2001).
参考文献15
• Compte, A., Brunel, N., Goldman-Rakic, P.S., andWang, X.J. “Synaptic
mechanisms and network dynamics underlying spatial working
memory in a cortical network model,” Cerebral Cortex 10:10–123
(2000).
• Conway, B.R., Hubel, D.H., and Livingstone, M.S. “Color contrast in
macaque V1,” Cerebral Cortex 12:915–925 (2002).
• Cook, E.P. and Maunsell, J.H.R. “Dynamics of neuronal responses in
macaque MT and VIP during motion detection,” Nature Neurosci.
5:985–994 (2002).
• Coppola, D. and Purves, D. “The extraordinary rapid disappearance
of entoptic images,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93:8001–8004
(1996).
• Corbetta, M. “Frontoparietal cortical networks for directing attention
and the eye to visual locations: Identical, independent, or overlapping
neural systems?” Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95:831–838 (1998).
• Corkin, S., Amaral, D.G., Gonzalez, R.G., Johnson, K.A., and Hyman,
B.T. “H. M.’s medial temporal lobe lesion: Findings from magnetic
resonance imaging,” J. Neurosci. 17:3964–3979 (1997).
• Cornell-Bell, A.H., Finkbeiner, S.M., Cooper, M.S., and Smith, S.J.
“Glutamate induces calcium waves in cultured astrocytes: Long-range
glial signaling,” Science 247:470–473 (1990).
• Cotterill, R. Enchanted Looms: Conscious Networks in Brains and
Computers. Cambridge, UK: Cambridge University Press (1998).
• Courtney, S.M., Petit, L., Maisog, J.M., Ungerleider, L.G., and Haxby,
J.V. “An area specialized for spatial working memory in human frontal
cortex,” Science 279:1347–1351 (1998).
• Cowan, N. “The magical number 4 in short-term memory: A reconsideration
of mental storage capacity,” Behav. Brain Sci. 24:87–185
(2001).
• Cowey, A. and Heywood, C.A. “Cerebral achromatopsia: Color blindness
despite wavelength processing,” Trends Cogn. Sci. 1:133–139
(1997).
• Cowey, A. and Stoerig, P. “The neurobiology of blindsight,” Trends
Neurosci. 14:140–145 (1991).
参考文献16
• Cowey, A. and Stoerig, P. “Blindsight in monkeys,” Nature 373:247–
249 (1995).
• Cowey, A. and Walsh, V. “Tickling the brain: Studying visual sensation,
perception and cognition by transcranial magnetic stimulation,”
Prog Brain Reserch 134:411–425 (2001).
• Creutzfeldt, O.D. Cortex Cerebri: Performance, Structural and Functional
Organization of the Cortex. Oxford, UK: Oxford University
Press (1995).
• Creutzfeldt, O.D. and Houchin, J. “Neuronal basis of EEG waves.”
In: Handbook of Electroencephalography and Clinical Neurophysiology.
Vol. 2., Remond, A., ed., pp. 3–55. Amsterdam, Netherlands:
Elsevier (1984).
• Crick, F.C. “Thinking about the brain,” Scientific American 241:219–
232 (1979).
• Crick, F.C. “Function of the thalamic reticular complex: The searchlight
hypothesis,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA 81:4586–4590 (1984).
• Crick, F.C. The Astonishing Hypothesis. New York: Charles Scribner’s
Sons (1994).(邦訳)中原英臣訳,DNA に魂はあるか:驚異の仮
説,講談社(1995).
• Crick, F.C. and Jones, E.G. “Backwardness of human neuroanatomy,”
Nature 361:109–110 (1993).
• Crick, F.C. and Koch, C. “Towards a neurobiological theory of consciousness,”
Sem. Neurosci. 2:263–275 (1990a).
• Crick, F.C. and Koch, C. “Some reflections on visual awareness,” Cold
Spring Harbor Symp. Quant. Biol. 55:953–962 (1990b).
• Crick, F.C. and Koch, C. “The problem of consciousness,” Sci. Am.
267:153–159 (1992).
• Crick, F.C. and Koch, C. “Are we aware of neural activity in primary
visual cortex?” Nature 375:121–123 (1995a).
• Crick, F.C. and Koch, C. “Why neuroscience may be able to explain
consciousness,” Sci. Am. 273:84–85 (1995b).
• Crick, F.C. and Koch, C. “Constraints on cortical and thalamic projections:
The no-strong-loops hypothesis,” Nature 391:245–250 (1998a).
参考文献17
• Crick, F.C. and Koch, C. “Consciousness and neuroscience,” Cerebral
Cortex 8:97–107 (1998b).
• Crick, F.C. and Koch, C. “The Unconscious Homunculus. With commentaries
by multiple authors,” Neuro-Psychoanalysis 2:3–59 (2000).
• Crick, F.C. and Koch, C. “A framework for consciousness,” Nature
Neurosci. 6:119–126 (2003).
• Crunelli, V. and Leresche, N. “Childhood absence epilepsy: Genes,
channels, neurons and networks,” Nature Rev. Neurosci. 3:371–382
(2002).
• Culham, J.C., Brandt, S.A., Cavanagh, P., Kanwisher, N.G., Dale,
A.M., and Tootell, R.B. “Cortical fMRI activation produced by attentive
tracking of moving targets,” J. Neurophysiol. 80:2657–2670
(1998).
• Cumming, B.G. and DeAngelis, G.C. “The physiology of stereopsis,”
Ann. Rev. Neurosci. 24:203–238 (2001).
• Cumming, B.G. and Parker, A.J. “Responses of primary visual cortical
neurons to binocular disparity without depth perception,” Nature
389:280–283 (1997).
• Cumming, B.G. and Parker, A.J. “Binocular neurons in V1 of awake
monkeys are selective for absolute, not relative, disparity,” J. Neurosci.
19:5602–5618 (1999).
• Cumming, B.G. and Parker, A.J. “Local disparity not perceived depth
is signalled by binocular neurons in cortical area V1 of the macaque,”
J. Neurosci. 20:4758–4767 (2000).
• Curcio, C.A., Allen, K.A., Sloan, K.R., Lerea, C.L. Hurley, J.B.,
Klock, I.B., and Milam, A.H. “Distribution and morphology of human
cone photoreceptors stained with anti-blue opsin,” J. Comp. Neurol.
312:610–624 (1991).
• Curran, T. “Implicit learning revealed by the method of opposition,”
Trends Cogn. Sci. 5:503–504 (2001).
• Cytowic, R.E. The Man Who Tasted Shapes. Cambridge, MA: MIT
Press (1993).
• Dacey, D.M. “Circuitry for color coding in the primate retina,” Proc.
Natl. Acad. Sci. USA 93:582–588 (1996).
参考文献18
• Dacey, D.M., Peterson, B.B., Robinson, F.R., and Gamlin, P.D. “Fireworks
in the primate retina: In vitro photodynamics reveals diverse
LGN-projecting ganglion cell types,” Neuron 37:15–27 (2003).
• Damasio, A.R. The Feeling of What Happens: Body and Emotion in
the Making of Consciousness. New York: Harcourt Brace (1999).(邦
訳)田中三彦訳,無意識の脳 自己意識の脳:身体と情動と感情の神
秘,講談社(2003).
• Damasio, A.R. “A neurobiology for consciousness.” In: Neural Correlates
of Consciousness: Empirical and Conceptual Questions. Metzinger,
T., ed., pp. 111–120. Cambridge, MA: MIT Press (2000).
• Damasio, A.R. and Anderson, S.W. “The frontal lobes.” In: Clinical
Neuropsychology. 4th ed., Heilman, K.M. and Valenstein, E. eds., pp.
404–446. New York: Oxford University Press (2003).
• Damasio, A.R., Eslinger, P., Damasio, H., Van Hoesen, G.W., and
Cornell, S. “Multimodal amnesic syndrome following bilateral temporal
and basal forebrain damage,” Arch. Neurol. 42:252–259 (1985).
• Damasio, A.R., Tranel, D., and Rizzo, M. “Disorders of complex visual
processing.” In: Principles of Behavioral and Cognitive Neurology.
Mesulam, M.M., ed., pp. 332–372. Oxford, UK: Oxford University
Press (2000).
• Damasio, A.R., Yamada, T., Damasio, H., Corbet, J., and McKee,
J. “Central achromatopsia: Behavioral, anatomic and physiologic aspects,”
Neurol. 30:1064–1071 (1980).
• Dantzker, J.L. and Callaway, E.M. “Laminar sources of synaptic input
to cortical inhibitory interneurons and pyramidal neurons,” Nature
Neurosci. 7:701–707 (2000).
• Das, A. and Gilbert, C.D. “Distortions of visuotopic map match orientation
singularities in primary visual cortex,” Nature 387:594–598
(1997).
• Davis, W. Passage of Darkness: The Ethnobiology of the Haitian Zombie.
Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press (1988).
• Dawson M.E. and Furedy, J.J. “The role of awareness in human differential
autonomic classical conditioning: The necessary gate hypothesis,”
Psychophysiology 13:50–53 (1976).
参考文献19
• Dayan P. and Abbott, L. Theoretical Neuroscience. Cambridge, MA:
MIT Press (2001).
• DeAngelis, G.C., Cumming, B.G., and Newsome, W.T. “Cortical area
MT and the perception of stereoscopic depth,” Nature 394:677–680
(1998).
• DeAngelis, G.C. and Newsome, W.T. “Organization of disparity-selective
neurons in macaque area MT,” J. Neurosci. 19:1398–1415 (1999).
• de Fockert, J.W., Rees, G., Frith, C.D., and Lavie, N. “The role of
working memory in visual selective attention,” Science 291:1803–1806
(2001).
• Dehaene, S. “Temporal oscillations in human perception,” Psychol.
Sci. 4:264–270 (1993).
• Dehaene, S. and Changeux, J.-P. “Neural mechanisms for access to
consciousness.” In: The Cognitive Neurosciences. 3rd ed., Gazzaniga,
M., ed., in press. Cambridge, MA: MIT Press (2004).
• Dehaene, S. and Naccache, L. “Towards a cognitive neuroscience of
consciousness: Basic evidence and a workspace framework,” Cognition
79:1–37 (2001).
• Dehaene, S., Naccache, L., Cohen, L., Le Bihan, D., Mangin J.-F., Poline
J.-B., and Riv`ere, D. “Cerebral mechanisms of word masking and
unconscious repetition priming,” Nature Neurosci. 4:752–758 (2001).
• Dehaene, S., Sergent, C., and Changeux, J.P. “A neuronal model
linking subjective report and objective neurophysiological data during
conscious perception,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100:8520–8525
(2003).
• de Lima, A.D., Voigt, T., and Morrison, J.H. “Morphology of the cells
within the inferior temporal gyrus that project to the prefrontal cortex
in the macaque monkey,” J. Comp. Neurol. 296:159–172 (1990).
• Dennett, D. Content and Consciousness. Cambridge, MA: MIT Press
(1969).
• Dennett, D. Brainstorms. Cambridge, MA: MIT Press (1978).
• Dennett, D. Consciousness Explained. Boston: Little & Brown (1991).
(邦訳)山口泰司訳,解明される意識,青土社(1998).
ナルシス・ナル君
まず芸能関係から引用
*****
矢田亜希子が赤ちゃんを産んだっていうニュースが報じられたけど、そのほとんどが、ダンナの押尾学が、自分たちのことを「美男美女の夫婦」って言ってのけたって部分をピックアップして伝えてた。たとえば、「日刊スポーツ」には、こんなふうに書いてあった。
(前略)押尾は「男でも女でもどっちでもいい。健康であればね。でもさ、美男美女の夫婦の子供で、かわいい子が生まれたの見たことがない」と、語っていた。(後略)
それで、スポーツ紙の記事を見ながら放送してたワイドショーでも、この部分を取り上げて、「自分で自分たちのことを美男美女だなんて、押尾さんらしいですね」ってコメントして、笑いのネタにしてた。だから、きっと、スポーツ紙を読んだ人たちも、ワイドショーを見た人たちも、みんな、おんなじように思っただろう。なんせ、押尾学は、「押尾語録」ってのが作られてるほど、自画自賛の嵐の天然男だから、こうした記事を読めば、誰もが「いかにも押尾学が言いそうなセリフだ」って思うからだ。
この流れを知れば、押尾学がお得意の自画自賛を炸裂させたんじゃなくて、何でもない普通のやり取りだったってことが分かったと思う。そして、このセリフは、「またまた押尾学が自画自賛のアホ発言をした」って思わせるために、悪意を持って編集されたものだってことも分かったと思う。
押尾学は、「赤ちゃんが男の子だった」ってことに対して、「男でも女でもどっちでもいい。健康であればね」って答えたワケで、そのあとの「美男美女のカップルですから、きっとかわいいお子さんなんでしょうね?」って質問に対して、「でもさ、美男美女の夫婦の子供で、かわいい子が生まれたの見たことがない」って答えたワケだ。だから、このやり取りには、どこにも、押尾チックな部分、テングになってる部分はない。それなのに、この2つのセリフを1つのカギカッコでくくって、いかにも続けてしゃべったように編集されたことによって、ミゴトなまでの押尾ワールドが全開になったってワケだ。
-----
というわけで、押尾学という人は、銀色夏生だと「ナルシス・ナル君」で、ある先生の好きな言い方だと「ナルちゃん」で、正式の言い方では、ナルシスティック・パーソナリティである、ということらしい。
これが病気にまで高まると、Narcissistic Personality Disorder と呼ばれ、発音はナルシシスティックであるが、省略して、ナルシスティックでもよいと、小此木先生がおっしゃった。日本語で、自己愛性人格障害である。ナーシスティック。
上記の中に、自画自賛とかテングとかの言葉が見えている。
-----
「あらゆる星が北極星を中心として動いているように、世界は私を中心として動いている。私は秩序そのものであり、法律そのものである」
シェークスピア「ジュリアス・シーザー」
シーザーだから、これでいい。ただの人がこんな風に思っているとして、ひそかに思って、日記に綴っているだけなら、害はない。他人の前で露出してしまうから、問題で、嫌われる。しかし、きらいな人は離れてゆくだけで、おおむねは問題ないのだが、上司と部下だったり、会社の同僚だったりすると、苦手な人だから離れているというわけにもいかない。上司がシーザーだったら、どうします?
ひょっとして、「そんな人こそ私にふさわしい、喜んでついていく」という人もいるだろうが、あなたもちょっとナルちゃんだ。
-----
「こんなあさましい身と成り果てた今でも、己は、己の詩集が長安風流人士の机の上に置かれている様を、夢に見ることがあるのだ。岩窟の中に横たわって見る夢にだよ。嗤ってくれ。詩人になりそこなって虎になった哀れな男を」 ―― 中島敦 「山月記」より
これもまあ、妻子には迷惑をかけたが、こんな人もいなければ、世の中は進歩しないので、これでいい。わたしはこの人をナルシスティックとはあまり思わないけれど。
自己愛性人格障害は、もっと平凡な人生を歩いていて、平凡な人間なのに、なぜか自分だけ特別だと思っているのである。理由がないのに。
自己愛性人格障害(Narcissistic Personality Disorder)とは、ありのままの自分を愛せず、自分は優越的で素晴らしく特別で偉大な存在でなければならないと思い込む人格障害である。
押尾学と矢田亜希子ならば、かなり特別なのであって、ナルちゃんとは私は思わない。
問題なのは、たとえば、こんな人たち。
御都合主義的な白昼夢に耽る。
自分のことにしか関心がない。
高慢で横柄な態度。
特別な人間であると思っている。
自分は特別な人間にしか理解されないと思っている。
冷淡で、他人を利用しようとする。
批判に対して過剰に反応する。
虚栄心から、嘘をつきやすい。
有名人の追っかけ。
宗教の熱烈な信者。
こんな感じのことを文章で描写すると、次のようになる。
なんでも自分の思い通りになるという空想に耽る。万能感の空想。すべて自分にとって都合のいいように事が運んで、最後には自分が絶大な称賛を浴びるという空想。自分だけが特別に評価されて大抜擢され、とんとん拍子に出世するという空想。
聞かれもしないのに、やたらと自分のことをしゃべりたがる人。話が他へ移ろうとすると、強引に自分の話に戻そうとする。話の内容は自慢話ばかりで、聞いている方はうんざりする。他人にはあまり関心がないので、相手がうんざりしていようとお構いなし。
自分は特別な人間だと確信している。小市民的な生き方を軽蔑し、そういう人達と一緒にされることを嫌う。裏付けとなるものがなにもないのに、一目置かれる存在であることに非常にこだわる。
あるいは、自分という人間は特別な人しか理解することができないのだと思ったりする。たとえば、以前マスターソンがラジオで自己愛人格障害の話をしたところ、自分は自己愛人格障害なのでぜひ治療してもらいたいという人が何人も電話してきた。そこでそのうちの十人を治療することになったが、実際に治療するのは高名なマスターソン本人ではないと知ったとき、十人が十人とも治療を断った。無名の医師ではダメ。
他人に対する共感に乏しく、他人を自分のために利用する。他人の業績を横取りして自分のものにする。優越感に浸るために他人を利用する。
もともと、裏付けのない優越感だから、話のつじつまを合わせるために嘘をつくこともある。本人には嘘をついているという意識はあまりない。ときにはホラ話のように、話がどんどん大きくなっていって、どこまで本当なのか分からなくなる。
有名人に近付くことで自分を特別な存在だと思い込んだりする。政治的な大物に近付いて自分の誇大感を膨らませることもある。自分も同じ世界の人間になったように錯覚して、裏付けのない空想的な野心にのめり込んだりすることもある。
誇大感を持つ人には二つのタイプがある。自分は素晴らしいと言うタイプと、あなたは素晴らしいというタイプである。あなたは素晴らしいというタイプの人は、その素晴らしい人に奉仕している私も素晴らしい特別な存在だと信じる。偉大な独裁者を崇拝する献身的な国民、偉大な神に身を捧げる熱狂的な信者、ワンマン経営者に心酔して滅私奉公する素晴らしい幹部社員、有名な歌手の応援をする熱狂的なファンなど。
すべてに言えることは、ありのままの自分が愛せないこと。自分は優越的な存在でなければならない。素晴らしい特別な存在であり、偉大な輝きに満ちた存在でなければならない。愛すべき自分は、とにかく輝いていなければならない。
しかし、これはありのままの自分ではないので、現実的な裏付けを欠くことになる。無理を通すので、時々は、現実にそぐわないことになる。
しかし、本人にしてみれば、高慢だと言われてもぴんと来ない。それよりは、その人に対して、「あなたは、他人や周囲の出来事を過小評価している」と言った方が理解されやすいかもしれない。自分より優れたものを認めたがらず馬鹿にしているので、他人の能力や才能が見えず、他人の優秀さを無視する。そして、他人を見下したり軽蔑したりすることに快感を覚える。
こんなタイプが上司だったら、どうします?
-----
ナルシシズムに特徴的な信念体系と性格行動パターンを抽出してみる。通していえることは、「自分は特別だ」という信念を抱き続けるために、無理をする、現実を無視するということだ。
1.私は、普通の大衆とは異なる特別に非凡で優れた人間である。……おおむね、一般大衆が気に入らない。自分は特別なのだから、一般大衆は、愚かでなければならない。
2.私は、目立ちたがり屋でいつも皆に注目されていたい。……自分より目立つ人がいてはならない。
3.私は、自分の容姿や知性、能力、所作、実績に自信を持っている。……自分は特別なのだから自信を持たなければならない。
4.私は、他人の意見に押し流されないだけの強い自分の意見を持ち、それを理路整然と主張することができる。……自分は特別なのだから、意見も主張も、特別な価値がなければならない。
5.私は、今以上の尊敬や賞賛、崇拝を受けて当然の存在である。……自分は特別なのだから、現在は不遇でも、将来、賞賛を集めなければならない。
6.私は、同一人物に対する評価が極端に変化して気分の波が激しい。(自分を低く評価したり、自分の意見に反対する相手を、公正に評価することはできないし許すことができない)……自分は特別なのだから、そのことを認めない他人に対しては、攻撃しなければならない。逆に、自分を賞讃するなら、その人も特別な人間に属する。
7.私は、鏡に向かって自分の姿を眺めるのが好きで落ち着く。……自分は特別なのだから、まず自分が、自分のすばらしさを確認しなければならない。
8.私の周りには、私を慕って尊敬する多くの人間(取り巻き)がいるべきだと思う。……自分は特別なのだから、周囲の人間は自分を尊敬しなければならない。
以上のように、おおむね、「自分は特別である」という信念を保持し強化するための行動であると解釈できる。
-----
いつも出てくる、DSM-IVをみてみると、こんな風。
自己愛性人格障害
誇大性(空想または行動における)、賞賛されたいという欲求、共感の欠如の広範な様式で、成人期早期に始まり、種々の状況で明らかになる。
以下のうち5つ(またはそれ以上)で示される。
自己の重要性に関する誇大な感覚(例:業績や才能を誇張する、十分な業績がないにもかかわらず優れていると認められることを期待する)。
限りない成功、権力、才気、美しき、あるいは理想的な愛の空想にとらわれている。
自分が特別であり、独特であり、他の特別なまたは地位の高い人達に(または施設で)しか理解されない、または関係があるべきだ、と信じている。
過剰な賞賛を求める。
特権意識つまり、特別有利な取り計らい、または自分の期待に自動的に従うことを理由なく期待する。
対人関係で相手を不当に利用する、つまり、自分自身の目的を達成するために他人を利用する。
共感の欠如:他人の気持ちおよび欲求を認識しようとしない、またはそれに気づこうとしない。
しばしば他人に嫉妬する、または他人が自分に嫉妬していると思い込む。
尊大で傲慢な行動 または態度。
-----
つねにこんな感じという人も多くはないけれど、一時的に、こんな感じが強くなるといった程度の人なら、少なくない。
程度の問題だし、場面の問題でもある。ナル君になっていい場面でも、あくまでも謙虚と言うのも、困りものだ。時と場合に応じて、適応的な行動が取れるのが大人である。たとえば、恋愛の一場面では、ナル君になってくれないと、話が続かない。
「自分は特別である」という確信は、残念ながら、現実に反する確信なので、(つまり、妄想的なので)、現実と矛盾し、折り合いがつかず、他人を困惑させ、不愉快にさせてしまう場面も出てくる。
普通は、そのような場面での気まずさから、これではいけないと気付き、現実的な路線をとるものだ。
しかしナルシス・ナル君たちは、あくまで、「自分は特別だ」と信じ続けたいのだ。そのことが現実的な利益をもたらすわけではないし、友人もいなくなり、自分は抑うつ的になり、いいことばかりではないのだが、それでも、「自分は特別だ」と信じたいのだ。
-----
自己愛性人格障害(ナルシスト)とは、「自分自身を愛する」という行為が病的なほど大きくなり、「自分は重要な人間だ」「周りには自分を理解できない」といった誇大感を持つようになり、ありのままの自分を愛することができず、空想的誇大的自己を保持するために不自然な事態となっている人である。
自分を愛するという行為は、健全な心の発達のためには必要なものであるが、程度がすぎると問題である。
ありのままの自分を愛することができるなら、健全な人である。
しかし、ありのままの自分に満足できないというのも、向上心と考えれば、一面では、悪くない面がある。一時的で限定的なら、いいことなのである。
惨めな現実を受け入れられず、空想的な誇大的な自己を作り出している。これも、自分を守るための、一時的なことならば、いいことでもある。
惨めな自分をすっきりと受け入れて、気持ちも惨めにならないということは難しい。適当なところで、多少の脚色をしながら、自分を慰めながら、だんだんと現実の惨めさを受け入れてゆくものだ。ナル君たちは、その、脚色から、いつまでたっても、抜けられない人と言ってもいいだろう。
でも、そういう人たちには、一種特別なエネルギーがあることがある。「自分は特別」なのだから、人一倍努力する部分があったり、リスクを恐れずゲームに参加したり、そんな面もある。そして、成功してしまえば、その人は一気に、現実に、賞賛にふさわしい人になる。だから、若いうちの自己愛性傾向は、悪いことでもない。いつまでもそのままというのは人生を難しくしてしまうけれど。
「俺は特別だ、甲子園に行くぞ。親父はそのために金を稼いでくれ。お袋は栄養管理をしてくれ。」というくらいでないと、なかなか甲子園にはいけない。「わたしは特別だ、もっときれいになって、せりふも覚えて、デビューするぞ」というくらいでないと、芸能界デビューも難しい。
自分の息子をプロ野球選手にしようとして特別に育てたという人の一部には、ナル君が混じっているのかもしれない。誰でも、自分の子供の将来については、過大な期待を抱き、夢を見る。それは社会的に容認された、ひそかなナルシスティック傾向なのかもしれない。
ーーーーー
誇大感に満ちた空想は現実感を奪う。たとえば、本当は自分が他人に嫉妬しているのに、他人が自分に嫉妬していると思ったりする。他人から批判されると、あれは私に嫉妬しているからだと解釈する。こういう防衛機制によって現実を再解釈して、納得しようとする。
ナルシス・ナル君はなにがなんでも自分が優位に立つ必要がある。どんな卑怯な手段を使ってでも、どんなにつじつまの合わない妄想であろうと、自分を守るためにしがみつかざるを得ない。嘘をついたり、他人を利用したりすることも、「自分は特別だ」という信念を補強するためと考えれば、合目的的なのである。
他人から侮辱されたと思い込んだりした場合、自分を守るために、非常に激しく怒ったりする。あまりにも自己中心的な怒り方であり、周囲の反感を買うが、本人は必死である。自己愛的憤怒と呼んでいる。
妄想の種になるようなものがないときは、他人の欠点を捜し出して見下したりする。ありとあらゆる理由をつけて他人を見下す。貧乏人の癖に、不細工な顔をしているくせに、頭が悪いくせに。実際にどうであるかということよりも、とにかく見下すことができればそれでいい。それは、ただ、「自分は特別だ」という信念を補強したいからだ。
他人を見下すということは、ときには他人からの報復攻撃として、自分が陥れられるかもしれないという疑いを生み、非常に疑い深くなったりする。他人に心を開くことなく、自分の妄想の殻の中に閉じこもる。これは二次的な必然である。大抵は、こんなことになったらつらいので、「自分は特別だ」信念を捨てるのだが、この人たちは、捨てない。
こういったことは様々な不都合を生む。しかし自我の崩壊を防ぐことができる。もし、妄想が崩れたら一気にうつ状態になったり、あるいはパニックになったりする。少なくとも妄想にしがみついていられる間はこのような悲惨な状態にはならない。
WHOのICD-10では正式な精神障害としては採用されていない。
境界性人格障害でも原因として日本では過保護、アメリカでは虐待が多いという指摘があるが、自己愛性人格障害に関しても似たような言説がある。私としては、そのまま信じることはできない。
まずフロイト、マスターソン、コフートを勉強する。日本語なら、小此木またはその一派の文献が基本。
自己愛(narcissism, self-love)ヘイベロック・エリス(Havelock Ellis)
フロイト(S.Freud, 1856-1939)性的精神発達理論(リビドー発達論)『乳幼児期の正常な自己愛』と『思春期以降の異常な自己愛』
S.フロイトの一次性ナルシシズムと二次性ナルシシズム
一次性ナルシシズムは、『母子分離不安』を弱めようとする防衛機制
マーガレット・S・マーラー(1897-1985)『分離・個体化期(separation-individuation)』
S.フロイトは、正常なリビドー(性的欲動)の充足対象の変遷として『自体愛→自己愛→対象愛の発達ライン』を考えていたので、異性に性的な関心が芽生えてくる思春期以降の二次性ナルシシズムは『病的な性倒錯』であると主張した。思春期や成人期にある男女が、自分の持つ魅力(属性)に自己愛的に陶酔したり、自己の性的身体を自体愛的に欲望するのは、リビドー発達が障害された結果としての性倒錯であり、成人の持つべき生殖能力を失わせる『幼児的な部分性欲への退行』であると言う。
フロイト『自己愛から対象愛への移行』『本能変遷』
二次性ナルシシズム……退行(regression)と固着(fixation)
コフートの自己心理学と自己愛理論。
フロイトは、自己愛(ナルシシズム)を病理的な性倒錯の一種であると考えた。
しかし、自己心理学のハインツ・コフート(Heinz Kohut, 1913)は、自己肯定的な自尊心と活動性の原動力となる『自己愛の発達』を正常な精神発達ラインの一つとした。
『健全な自己愛(self-love)』の成長を促進することで、他者を共感的に思いやる対象愛(object love)も発達し、社会活動に積極的に参加しようとする適応性も高まる。
コフートの自己愛とは、『自己存在の積極的な肯定』であり『理想化と関係する自尊心(自信)の基盤』である。
コフートの自己心理学には『自己愛と対象愛は表裏一体である(自己愛がなければ他者を愛せない)』という信念がある。フロイトにとって、自己愛は『自己愛から対象愛への正常な移行(本能変遷)』を成し遂げられなかった病理的状態であるが、コフートにとっての自己愛は『誰もが持つべき自己肯定感(自尊心)の基盤』であり、苛酷な人生を乗り切る為に必要な“生のエネルギー”の源泉である。
コフートは自己愛の定義として、『自分自身を愛する自己愛』と『自己対象を愛する自己愛』を挙げている。つまり、コフートの言う自己愛とは、自分にとって大切な他者である“自己対象(self-object)”を含むものであり、単純に、内向的かつ排他的な自己愛ではない。(自己心理学では、対象 object という言葉は独自の意味を持っている。)
意欲的な創造性や適度な自尊心を生み出す『健全な自己愛』に対して、自己愛性人格障害の原因となる『病的な自己愛』というのは、自分自身の権力や幸福、名声、成功のみに固執し、自己顕示欲求と誇大妄想的な自己陶酔を満たす為に、他人を不当に攻撃したり身勝手に利用したりする“過剰な自己愛”である。過剰な自己愛は、『尊大さ・傲慢さ・横柄さ』といった言葉で表現される、他者を侮蔑して否定する行動(発言・態度)となって現れる。
実際の自分以上に自分に価値があると妄想的に思い込み、『自分は凡人とは違う特別な人間だから、もっと丁重に敬意を持って扱われるべきだ』といった要求を明示的・暗示的に主張し、『私の実力や魅力、価値を評価できない人間は、物事の価値が分からない無能な人間であり付き合う価値がない(私の実力を高く評価できる人間は、私には及ばないもののなかなか優秀な人間である)』といった排他的かつ独善的な態度を示すこともある。他者に自分への賞賛と従属、関心を強制して、自分の力を認めない人や自分に従わない人たちを遠ざけることで(お世辞やご追従を言うご機嫌取りを周囲に集めることで)、外部の現実原則から自分を守ろうとする。
こんな人がいてもかまわないけれど、そして、その人がそれで得をするもと思わないけれど、そんな人と否応なく付き合わなければならない人は大変だ。やっと異動になって自分は逃れられたと思ったら、友人が今度はその人の部下になってしまい、慰め役になってあげたり。
自己愛が過剰に強くなることで、自己愛性人格障害や演技性人格障害といった病理的な人格構造が形成されてくると、現実的な自己評価を逸脱する誇大自己の拡大が起こり、その結果として特異的な行動パターンを示す。即ち、尊大(横柄)な態度や傲慢な発言が多くなり、自己顕示欲(エゴイズム)を満たす為に他人を利用しようとする。本人は『自分には他人を利用して満足を得る当然の権利と能力がある』と思い込んでいるので反省しない。自分を批判する者や自分の価値を引き下げる対応をする者は許すことが出来ないので、衝動的に激しく攻撃したり(自己愛性憤怒)、防衛的に無視して距離を取ろうとする。病的な自己愛の持ち主と一緒に居る相手は、独特な不快感や違和感を味わわされることになり、自己愛性人格障害の人は、一般的にわがままで自己顕示欲が強い人、傲慢不遜で非常識な性格の持ち主といった形で認知される。
『病的な自己愛=自己愛性人格障害の原因となる自己愛』もあるものの、自己心理学の自己愛理論では、適切に自己愛の強度と内容を調整できるのであれば、自己愛性人格障害のような人格構造の歪曲の問題は起きないと考える。
『良い自己評価を伴う正常な心理構造』の一部である自己愛や承認欲求(社会的欲求)は誰もが持っているものであり、自己愛そのものが病理的な悪影響をもたらすのではなく、自己愛のバランスの崩れや調節障害が自己愛性人格障害の苦悩や被害を生み出す。このあたりの論述がフロイトとの相違点である。
コフートは、人間は誰もが発達早期に受けた心理的な傷つき(欲求充足の欠如)を抱えているという『欠損モデル』を前提にしている。
生まれて間もない自他未分離の状態にある乳幼児は、母親・父親からの保護と世話を必要としており、その生存を全面的に養育者に依拠している。発達早期(0~2歳くらい)の乳幼児と母親は、二人の間にある境界線を意識しておらず、『幻想的な母子一体感』に浸った状態にある。
マーラー、ウィニコット、ボールビーなど。母子関係を扱ったりしているものは、なかなか難解。
しかし、実際には母親も不完全な人間で、子どもにミルクを与える時間が遅れたり、離れた場所にいて子どもの泣き声が聴こえなかったり、子どもが我がままを言って母親が怒ったりすることがある。そういった瞬間に幻想的な母子一体感が破られて、乳児は『幼児的な全能感』が通用しない欲求不満を感じ、『欠損モデル(defect model)』でいう心(自己愛)の傷つきや欠損を体験する。こういった欠損の存在は全ての人間にあるものであり、発達早期に欠損を感じた経験が自己の不完全さや欲求不満につながり、理想化や誇大性を求める『自己愛の起源』になる。
H.コフートは、自己愛の発達を対象愛の発達と同様に『正常な精神発達過程の一つ』と考えた。
中核自己(nuclear self, 私が私であるという自意識)の自己愛の発達過程には、『誇大自己(grandiose self)』と『理想化された親イマーゴ(idealized parent imago)』という二つのラインがある。欠損モデルに基づく中核自己(自我意識)は、向上心と理想という二つの極(方向性)を持つので双極自己(bipolar self)とも呼ばれる。
誇大自己(grandiose self)は「向上心」の極で発達していき、理想化された親イマーゴ(idealized parent imago)は「理想」の極で発達していく。
共感的な親(反応性の良い温かい母親)の元で、「誇大自己(grandiose self)」の自己愛の発達に成功すると、現実原則に適応できる成熟した誇大自己(自尊心や向上心の基盤)が成長し、非共感的な親(反応性の乏しい冷たい母親)の元で誇大自己ラインの自己愛の発達に失敗すると、幼稚な快楽原則に支配された未成熟な誇大自己(自己顕示欲の強い傲慢さや横柄さ)が強くなる。発達早期の母子関係を重視したコフートは、非共感的な親が乳児の心的構造の欠損(心的な外傷)を大きくして、乳児の精神内界に自己表象の「断片化(fragmentation)」を引き起こし、自己愛の病理の発症リスクを高めると考えた。
自己表象の「断片化(fragmentation)」なんていうことが乳児の精神内界で起こるのかな。でもまあ、このあたり、コーハット的。kohutをコフートとは発音しないだろうな。
「理想化された親イマーゴ(idealized parent imago)」では、親という表象(イマーゴ)や自己対象を理想化して同一化しようとする。その為、発達早期の親が非共感的な反応を示して乳児を無視したり拒絶したりすると、乳児は「最適な欲求不満(optimal frustration)」を経験することが出来なくなり、自己対象である親を理想化する契機(チャンス)を失う。「理想化された親イマーゴ」の形成に失敗するということは、心理内面に安定的に存在して自己愛の支えとなる「対象恒常性」の確立に失敗するということと同義であり、外界に対応する為の心理構造が非常に不安定になる。
共感的な親の元で、「理想化された親イマーゴ」の自己愛の発達に成功すると、自己愛性人格障害の原因となる『不適応な誇大自己』の発達を抑制することが出来るが、それは、精神内界に安定した「自己対象の恒常性」が確立することで「過剰防衛を行う誇大な自己」を強調する必要性がなくなるからである。子どもは自分に価値があるという実感や自分が評価されているという満足の原初的体験を親子関係の中でしていくが、そういった共感的な被承認体験が出来ないと、自己愛的な賞賛と評価を必死に求める誇大自己の拡大が見られるようになる。子どもに対して完全に無関心だったり拒絶的だったりする“冷たい母親”の元では、「理想化された親イマーゴ」の形成に必然的に失敗するので、理想化の自己対象を見失って衝動的な行動や抑うつ的な反応が目立ってくることになる。親の子どもに対する徹底的な無視や冷たい対応というのは、精神分析的な心因論では、うつ病や統合失調症、ボーダーライン(境界例)、境界性人格障害、自己愛性人格障害、反社会性人格障害などの原因になると考えられている。実証的な統計学的研究(疫学的研究)のエビデンスが十分に積み重ねられていないので、「愛情不足の親子関係」だけがそれらの精神疾患(人格障害)の危険因子になるわけではない。
少し前までは、発達早期の心的外傷のようなことがよく言われたが、最近は、やや下火であるように思う。
向上心を伴う『誇大自己(grandiose self)』と理想を構築する『理想化された親イマーゴ(idealized parent imago)』が相互作用することで進む心的構造の形成過程を『変容性内在化(transmuting internalization)』という。コフートの自己心理学に基づくと、自己愛性人格障害の人格形成過程とは、変容性内在化(transmuting internalization)の不適切な進行であり、もっと正確に言うならば、自己成熟へと向かう『誇大自己』と『理想化された親イマーゴ』のバランスの取れた統合的発展の失敗であると言うことが出来る。
誇大自己は、自分自身の鏡像を自己対象とする『鏡面化』の発達過程をたどる最も純粋な自己愛のルーツ(起源)であるが、乳幼児は鏡に写った自分の鏡像を見てナルシシスティックに自己の強力な力や有能性を確信する。露出的で誇大妄想的な誇大自己が強くなりすぎると、自己顕示や支配的野心の抑制を欠いて自己愛性人格障害の原因となる。理想化された親イマーゴは、自分の両親(養育者)を自己対象とする『理想化』の発達過程を形成し、発達早期の母子関係に問題があると、「過剰な誇大自己の発達水準」に固着が起こる。「過剰な誇大自己の発達水準」へと防衛的に退行することで、誇大な自己顕示性と利己主義を特徴とする自己愛性人格障害の行動パターンが生まれる。
「鏡」の比喩はいろいろと活躍する。私も大好きな比喩だ。鏡の不思議さと、自己が自己を認知する不思議さは、やはり、重なり合うはずだと思う。
自己愛性人格障害に見られる傲慢不遜な態度や過度の自己顕示欲を精神分析的に分析すると、『正常な自己イメージと対象恒常性』の形成に失敗した子どもが、不適応な誇大自己の発達地点で発達停止を起こしている状態と言える。つまり、傲慢な態度や自信過剰な発言は『危険な世界』や『信頼できない他者』に対する防衛機制(過剰防衛)の現れであり、幼児的な全能感を抑制して現実的な野心(理想)を持たせるためには、統合された自己イメージと安定した心理構造の再構築を行う必要がある。自己愛性人格障害を予防する『自己の健全な発達』を実現する為には、『誇大自己の鏡面的自己対象』のプロセスと『理想化された親イマーゴの自己対象の理想化』のプロセスが、共感的に相互作用して、『誇大自己の向上心(野心的願望・自尊心)』を現実的なレベルに調整しなければならない。
一応こんな風になるけれど、だからといって、こんな話を信じるわけでもない。空論だとまではいわない。確かに説得力はあるし、背景には、必然性もある。乳幼児の実際の観察を基盤にしつつもある。精神分析が一般に、その説明の背景として、生物学的な理論と結合しつつあるのはとても意味のあることで、それはまさに、初期フロイト的な方向だと思うし、私はその方向が好きだ。
理解不足を棚に上げて、空理空論と言うつもりもない。こんなことを考える人はいるだろう。しかし、それを支持しそれに賛同する人がこんなに多くなっていることに驚く。
ナルシスティック・パーソナリティは大きな問題だ。そしてもうひとつ、ナルシスティック・パーソナリティをこのような仕方で議論して理論化している人たちがこんなにも多いのだという現状を不思議な思いで眺めている。
同じことはフロイトの前期と後期についてもいえることで、私にとってフロイト前期は実に理由があって、天才的だと思う。ニュートンとライプニッツの登場のように、必然的だったと思う。後期は、あまり感心しない。多分、よく理解していないからだろう。
うつ病と人格障害 阿部徳一郎 尾崎紀夫
「うつ病」の一部は確かに人格障害の要素があることを考えながら治療にあたる。
*****
臨床精神薬理61453-1459,2003
うつ病と人格障害
阿部徳一郎 尾崎紀夫
抄録:症状を重視する操作的診断法の普及によって,うつ病という単一疾患名の下にあまりに も多彩な症例を包含することになった。一方,多軸診断法はcomorbidityという概念によって, 多様なうつ病者の特徴を捉えるのに寄与している。また従来,発症や予後に関わる因子とされ てきた人格障害ないし人格傾向について,統計学的な検証が可能になった。本稿ではこれらの 検証結果を紹介すると共に,症状に依拠して人格障害を診断する際の問題点や,慢性に経過す る軽症うつ病(気分変調症)を人格障害と捉える考え方があることを指摘した。また,人格障害 を伴わないうつ病においても症例の不均質性が報告されていることを述べた。最後に,従来の 範疇的かつ成因論的なうつ病概念と,DSMに代表される,操作的かつ多軸診断を前提としたうつ 病概念との間には葛藤が存在し,これを理解することは臨床実施上有用であると共に,また教 育的でもあることを強調した。
*
I.はじめに-診断分類体系とcomorbidityの関係-
*
うつ病と人格障害のcomorbidityについて述べる前に,「comorbidity」という概念そのものに ついての理解に混乱が生じていると感じられるので,最初にこの概念の定義について触れてお きたい。精神医学における「comorbidity」という概念は,Burkeらによれば「ある限定された 期間において一人の個人に2つ以上のspedficな障害が存在すること」と規定されている。残 念ながらこの概念を言い表す適切な邦訳は未だなく,医学一般で使い慣れた「合併症 complication)」という概念とは一部意味が重なるが,区別して考えられている。この2つの概 念の差異は以下のような症例を思い浮かべると納得できるだろう。
-糖尿病に糖尿病性腎症がある。
-Systemic lupus elrythematosus の経過中にうつ病性障害が認められる。
-心筋梗塞の寛解過程でうつ病性障害が出現した。
-うつ病性障害にアルコール依存症がある。
-パニック障害とうつ病性障害が経過中に認められる。
-うつ病性障害と共に境界性人格障害の診断基準を満たす。
最初の一例について,併存する障害を「合併症」とすることに誰しも異論はないと思う。しかしそれ以外については簡単にコンセンサスが得られるだろうか。そこで,一人の患者に認めら れる複数の障害の関係に拘泥せず,もれなく情限を記載することを優先して診断するという立 場を取った場合,障害相互の関係は一括してcomorbidityという概念で捉えられている。すな わち共存する複数の障害の関係は多様で,背後に生物学的な共通基盤を想定させるものもあれ ば,一つが心理社会的な要因をなして別の障害を引き起こしたと捉えられるもの,そもそも診 断基準のいくつかが重なっているものなどもある。
*
精神医学の歴史においては,一人の患者に一つの診断を下そうとする努力が長らく続けられて きたが,眼前の精神疾患の表現型が多様であるが故に,かえって臨床家の間で疾患概念の混乱 を招くことになった。そこでこの混乱を解消すべく考案されたのがDSM診断体系に代表される 多軸診断法や操作的診断法である。DSM診断体系は,精神疾患を多面的に把握し,しかも評価者 間での一致率を上げる(共通言語の使用)という意図のもとに導入された。しかし,一方で,同 一患者に対して,多軸にわたる複数の障害名を記入する,すなわちcomorbidしている疾患を全 て記載するという診断習慣は,精神医学における従来の範躊的な疾患概念との問に大きな齟齬 を生んでいる。Comorbidityという概念を理解し活用するためには,このような経緯を無視す ることはできない。
*
本稿では,うつ病と人格障害のcomorbidityの観点から,現在の精神臨床におけるこの概念の有用性と問題点を議論する。
*
Ⅱ.「うつ病性障害」と「人格障害」のcomorbidity -DSM診断体系に依拠した研究-
*
DSMではうつ病の診断は,一定期間持続する症状のセットを参照して行われる。「大うつ病性障害」と「気分変調性障害」,それ以外の「特定不能のうつ病性障害」の3つの診断基準があり,縦断的経過とそれぞれの病相の特徴を記述する用語が別に用意されている。このような状態記述のみによる診断方法は,範疇的かつ成因論的観点を考慮した従来のうつ病の診断方法と比べて,評価者間の信頼性を高めた反面,単一疾患名とするにはあまりにも異質な症例を包含してしまう結果になった。一方,このような診断手順の単調さを補うため,DSMでは多軸診断法が採用されており,多様なうつ病者の病状を捉えるのに与っている。すなわち,うつ病性障害と診断された場合(第1軸),個々の症例に関して人格障害の診断(第2軸),うつ病性障害の発症前状況や,経過に影響を与えうる心理社会的問題の存在(第4軸)を記載することになっている。そして「うつ病性障害の発症あるいは予後因子としてどのようなcomorbidな診断(または他の軸における記載事項)があるか」という問いを立て,統計的な裏付けをもってこれらの因子を同定するのを目標としている。
*
従来,臨床上利用されていた範躊的なうつ病診断法は,発症に関与する因子と共に,薬物を含めた治療への反応性,寛解後の社会的機能水準など予後に影響を与える因子が反映されたものであると信じられていた。これに対してDSMでは,発症あるいは予後に影響するとされていた「症状以外の因子」について,妥当性を検証し直すため診断基準の外側に追い出したと考えることができる。このような経緯から,DSMは従来の診断体系に比して臨床的な有用性に乏しいという意見もある。しかしDSMは,間断なく検証と改訂が繰り返されており,やがて発症や予後に関わる因子が同定され,診断基準の中にしかるべき場所が与えられるときまで,現行の版は暫定的なものとして考えるのが公平な見方であろう。
*
「うつ病にcomorbidする因子としての人格障害(あるいは人格傾向)」とは,DSMにおいて上に述べた文脈で捉えられていることを確認した上で,過去の報告に関する検討を始めることにする。
*
DSM-Ⅲの発表以降,うつ病性障害に随伴する人格障害については夥しい数の文献が発表されている(表1)。大うつ病性障害と同時に人恪障害と診断される割合は入院患者では30~60%,外来患者では20~80%と報告によって大きな差がある。慢性うつ病者(2年以上続く大うつ病,気分変調障害あるいはそのどちらもが重なった重複うつ病)を対象にした研究では,51%に何らかの人格障害が認められている。また,人格障害の内訳の一例を表2に示したが,これら人格障害の比率は経過中の躁病や軽躁病のエピソードの有無に左右されないとの報告がある。人格障害の有病率が報告ごとに人きな幅を持つ理由は,訓査対象の規模,うつ病の罹病期間などが多様で,もっぱら臨床症状をもとに人格障害の診断を行うDSMにも一因があるとされている。うつ病者の中で複数の人格障害が診断される割合は5~5̃5%と広い範囲にあり,さらに,一般に人格障害の重複診断が25%程度と報告されているのを斟酌すると,DSMによる人格障害診断法の妥当性について考えて直してみる必要がある。Hirschfeldは慢性うつ病(2年以上の大うつ病性障害,気分変調症および重複うつ病),患者のうち薬物療法に反応したものについて,治療前後の人格障害の有病率の変化を報告している(表3)。薬物治療28週後の評価では,人格障害の有病率は62%と低下し,薬物療法が,うつ病と共に人格障害にも有効であったとしている。さらにclusterA(妄想性,分裂病型,分裂病質)に比較し,dusterB(反社会性,境界性,演技性,自己愛性)やclusterC(回避性,依存性,強迫性,依存性)に分類される人格障害は,うつ病の改善に伴う有病率の低下が著しいと述べている。しかしこの結果から,ただちに薬物療法がそれぞれの人格障害に有効であったと判断できるだろうか。例えば,うつ病の診断基準項目のいくつかが人格障害の診断に影響を与える交絡因子(confounding factors)である場合には同じ結果が予想される。従って人格障害の診断の際には,「疾患エピソード(この例ではうつ病)に由来すると思われる行動や人格傾向は考慮に入れない」という大原則が重要な意味を持ってくる。実際,DSMを用いて行われたうつ病の予後研究を通覧すると,予後因子としての人格障害の意義についてコンセンサスが得られているとは言えず,結果の解釈に慎重でなければならない。
*
表1 大うつ病性障害(DSM-Ⅲ,DSM-Ⅲ-R)における人格障害の有病率
表2 大うつ病性障害(DSM-Ⅲ,DSM-Ⅲ-R)における各人格障害の有病率
表3 薬物療法が有効な慢性うつ病における人格障害の有病率の変化
*
Ⅲ.慢性の軽症うつ病、「気分変調性障害」は人格障害か -「抑うつ性人格障害」との関係-
*
近年,慢性に経過する軽症うつ病が増加し,またこれらの患者の一部は抗うつ薬による治療によく反応することが知られている。そこで従来の範躊的かつ成因論的なうつ病分類,すなわち内因性と心因性(神経症性)うつ病の区別は再考を迫られることになった。このような臨床的状況のさなか,Akiskalは一連の実証的研究の成果に基づ いて,軽症うつ病を性格スベクトラム障害(character-spectrum disorders)と亜感情病性気分変調症(subaffective dysthymic disorders)とに分け,前者は様々な人格障害が同時に診断されることが多く,後者は薬物への良好な反応が期待されるとした(表4)。現在用いられている「気分変調症(dysthymia)」の診断概念は,歴史的にAkiskalが提案したこれらの2種類の軽症うつ病を包含している。しかし,DSMの診断基準を一瞥しただけでは,症状の程度と持続期間の点で大うつ病性障害と区別されているに過ぎないため,気分変調性障害は単なる「慢性かつ軽症のうつ病」と捉えられがちである。
*
表4 性格スペクトラム障害と亜感情病性気分変調症
* 性格スペクトラム障害 感情病性気分変調症 薬物への反応 三環系,MAOI,Liが奏効しない 三環系,MAOI,Liが有効 REM潜時 短縮なし 短縮あり 症状の特徴 メランコリー病像なし 一次性うつ病の病像に近縁 家族歴 アルコール症が多い 単極性あるいは双極性感情障害者がいる 人格障害,性格傾向の特徴 依存性,演技性,反社会性,分裂病性などの性格障害の病理があり Schneiderの「抑うつ者」
*
Akiskalの提案を受けて,大うつ病や人格障害と気分変調性障害との関係を調べた実証的な研究が数多く報告されてきている。気分変調症者の家系における,うつ病性障害や人格障害の有病率の研究もその一つである。Kleinによると,21歳以下の気分変調性障害者の第一度親族における同症の有病率は対照に比較し有意に高く,うつ病性障害の中でも気分変調性障害が独自の疾患単位であることを示唆している。
*
気分変調症をうつ病の亜型とするこれらの考え方に対し,年余に亘って認められる抑うつ気分やアンヘドニアを,人格障害とする流れが一方に存在している。当初,Kraepelinによって大うつ病の病前性格として概念化された「うつ病性格」は,Schneiderによって独立した人格障害のカテゴリーとされ,その後精神分析的な観点からも繰り返し検討を重ねられてきた。にも拘わらず,DSMにおいて「抑うつ性人格障害(depressive personality)」が「今後検討を要する課題」として付録(appendix)での記状に格下げされた事情は,症候論的に気分変調症との区別が曖昧なためと,人格障害とした場合に抗うつ薬による薬物療法の対象から排除されるという予断を避けるためである。
*
IV.人格障害をcomorbidしない「うつ病者」の多様性
*
ここまでは,うつ病者のうち20~80%にもなるとされる,人格障害をcomorbidする症例群について考察してきた。それではそれ以外のうつ病者は,人格傾向という観点でどのような特徴が認められるのであろうか。従来の内因性うつ病では,抑うつ気分やアンヘドニア,行動抑制など,うつ病共通の精神症状の他に,early-morning worseningと表現される気分の日内変化や,早朝覚醒を特徴とする不眠、体重減少などの身体的症状が知られていた。DSMにおいてもこれらの患者群は「メランコリー型」として受け継がれていて,REM潜時の短縮やnon-REM睡眠時間の減少,ECTや薬物療法が有効であるなどの点で,他の患者群と区別されている。一方,人格障害のcomorbidという観点で見ると,このメランコリー型のうつ病は,いずれの人格障害にもあてはまらないという特徴が指摘されている(すなわち文化的背景を考慮に入れても患者の思考や行動の様式は社会適応的という意味である)。そしてさらに他者配慮を旨とした秩序への従順さを特徴とする「メランコリー親和型性格」や「執着気質」といった人格は,このうつ病亜型に共通して認められると信じられてきた。
*
一方,この説に対する反論は,患者の人格を判定する際の情報が,そのときの患者の抑うつに影響を受け(state effect),また自己評価と近親者の評価は必ずしも一致するとは限らないという点にあった。我々もまた,人格検査の一つであるTemperament and Charaderl nventory(TCI)の結果が大うつ病患者の抑うつ状態によって変化するか否か,抗うつ薬治療の前後で検討して,大うつ病の状態像がTCIの結果に影響をおよぼすことを明らかにしている。さらにFurukawaらは,メランコリー性格尺度を用いて近親者からの評価と患者の自己評価を比較している。その結果,症候論的にメランコリー型うつ病(DSM-IV-TR)に相当する内因性うつ病(ICD-10)では,自己評価と客観的な評価との一致率が高いとし,その他のうつ病において自称メランコリー性格者が多いのと対照的であると報告している。
*
人格障害に該当しないうつ病者の人格特徴については,人格の次元モデルを用いた研究も報告されている。これらの研究の前提は,人格が独立した計量可能な「因子」に規定されていて,そのうちの一部は遺伝的,生物学的な背景を持つというものである。前方視的手法を用いたHirschfeldらの報告では,うつ病者は病前から有意にneuroticismが高いが,これは他の精神障害についても認められるので非特異的な所見であるというものであり,その他の報告も臨床的に有用な知見を提示するまでには至っていない。
*
V.DSM以後のうつ病概念に求められるもの
*
症状のセットを診断基準に据えて多軸診断を行うDSMの考え方が,eomorbidityという概念を産んだ背景を説明してきた。これによってうつ病にcomorbidしている人格障害や人格傾向の持つ意味が,統計的に検証可能になったことは問違いない。しかし果たしてこのような統計的な手法によって,個別の患者の抑うつへの理解が深まり,治療上の対応を決めるに必要な知見が手に入ると言えるのだろうか。例えば,メランコリー性格者が状況の変化によってそれまで馴れ親しんできた生活様式から即別し,新しい状況への適応の途上でうつ病を発症した場合と,境界性人格障害者が主たる養育者との死別や主治医の転勤をきっかけに気分変調症と診断された場合を想像してみよう。この2つのケースで見られる抑うつ感の質的な差異について統計的な検証はあまり役に立たず,むしろ抑うつ感を巡る患者の個別的かつ主観的な体験についての理解が治療的対応に欠かせない情報である。
*
Gundersonらは,DSMの第2軸に境界性人格障害が当てはまるときの第1軸診断との関係を次の4つに整理している。すなわち,第1軸の障害が一次的で人格障害や人格傾向が二次的に派生した場合,第2軸の人格障害が一次的でうつ病などの疾患の脆弱性を決めている場合,あるいは第1軸の障害と第2軸の人格障害が共通の別の原因に基づいていると考えられる場合,さらに両者が偶然に随伴したと考えられる場合である。列挙した第1軸の障害と第2軸の関係はそれぞれ互いに排除するものではないと考えられるので,事情は一層複雑である。これは,従来の成因論的な診断分類において,(病前の)人格傾向と発病状況,そして病像を一つのセットと見なし,特に前二者の間に発症に至る内的な連関を求めているのと対照的である。そして,このような発症についての解釈は,往々にして患者自身の主観的体験と一致していて,認知行動療法をはじめとした治療の過程で積極的に利用できることが多い。この意味では,DSMに代表される統計的な検証方法の分は悪く,連綿と集積されてきた臨床家の問にある経験をすくいとっているとは言えない状況である。本稿で辿ってきたように,成因論的かつ範疇的なうつ病の診断方法とDSMとの間にある葛藤を理解することは,精神科の臨床経験を豊かにする,極めて教育的な作業であると考えるものである。
*
文献
1)Akiskal,H.S.,Bitar,A.H.,Puzantian,V.R.et al.:The nosological status of neurotic depression:a prospective 3-4 year follow-up examination in light of the primaly secondary and the unipolar-bipolar dichotomies.Arch.Gen.Psychiatry,35:756-766,1978.
2)Akiskal,H.S.:Dysthymic disorder:psychopathology of proposed chronic depressive subtypes.Am.J.Psychiatry,140:11-20,1983.
3)Alnaes,R.,Torgersell,S.:Personality and personality disorders predict development and relapses of major depression.Acta Psychiatr. Scand.,95:336-342,1997.
4)American Psychiatric Association:DSM,IV sourse book. APA,Washington,D.C.,1996.
5)American Psychiatric Association:Diagnostic and Staitical Manual of Mental Disorders,4th ed. text revision(DSM-TR,TR).APA,Washington, D.C.2000.(高橋三郎,大野裕,染矢俊幸訳: DSM-IV-TR精神疾患の診断・統計マニュアル。医学書院,東京,2002.)
6)Bagby,R.M.Ryder,A.G.,Cristi,C,:Psychosocial and clinical predictors of response to pharmacotherapy for depression.J.Psychiatry Neurosci.,27:250-257,2002.
7)Biellvenu,O.J.,Brown,C.,Samuels,J.F.et al.: Normal personamy traits and comorbjdity among phobic,panic and major depressive disorders.Psychiatry Res.,102:73-85,2001.
8)Burke,J.D.,Wittchen,H.U.,Regier,D.A.et al.:Extractinlg infomation from diagnostic interviews on cooccurrence of symptoms of anxiely and depression.ln:Comorbidity of Mood and Anxiety Disorders(ed.by Master,J.D.alld Cloninger,C.R.),pp.649-667,American Psychjatric Press,lnc.,Washington,D.C。1990.
9)Cloninger,C.R.,Svrakic,D.M.and Przybeck,T. R.:A psychological mode of temperament and character.Arch.Ge11.Psyc11jatry,50:975-990, 1993.
10)Corruble,E.,Ginestet,D.,Guelfi,J.D.:Comorbidity of personality disorders and unipolar major depression:A review.J.Afrect.Djsor.,37: 157-170,1996,
11)Fabrega,Jr.H.,Pilkonis,P.,Mezzich,J.et al.: EXplaining diagnostic complexity in an intake setting.Compr.Psychiatry,31:5-14,1990.
12)Furukawa,T.,N0akanishi,M.,Hamanaka,T.:Typus melancholicus is not the premorbid personality trait of unipolar(endogenous) depression. Psychiatry Clin,Neurosci.,51:197-202,1997.
13)Gunderson,J.G.,Phillips,K.A.:A cullent view of the interface between borderline persollality disorder and depression.Am.J.Psychiatry,148:967-975,1991.
14)Hirano,S.,Sato,T.,Narita,T.et al.:Evaluating the state dependency of the Temperament and Character lnventory dimensions in patients with major depression:a methodological contribution.J.Affect,Disord.,69:31-38,2002.
15)Hirschfeld,R.M.A.,Klerman,G.L.,Ulvori,P.et al.:Premorbid personality assessments of first onset of major depression.Arch.Gen.Psychiatry,46:345-350,1989.
16)Hirschfeld,R.M.A.:Personality disorders and depression: Comorbidity.Depress.Anxiely,10: 142-146,1999.
17)Joffe,R.T.,Bagby,R.M.,Levitt,A.J.et al.:The Tridimensional Personality Questionnaille in major depression,Amj.Psychiatry,150:959-960, 1993.
18)笠原嘉,木村敏:うつ状態の臨床的分類に関する研究。精神経誌,77:715-735,1975.
19)Keller,M.B.,Gelenberg,A.Jo Hirschfeld,R.M. A.et al.:The treatment of chronic depression, part 2:a doubleblind,randomized trial of sertraline and imipramine.J.Clin.Psychiatry,59:598- 607,1998.
20)Kernberg,O.;Clinical dimensions of masochism.ln:Masochism;Current Psychoanalytic Perspectives ed.by Glick,R.A.,Meyers,D.I., Hillsdale,N.J.),pp.61-80,Analylicpress, Hillsdale,1988.
21)Klein,D.N.,Riso,L.P.,Donaldson,S.K.et al.: Family study of earlyonset dysthymia:mood and personality disorders in relatives of outpatients with dysthymia and episodic major depression and normal controls.Arch.Gen.Psychiatry, 52:487-496,1995.
22)中安信夫:精神科臨床診断の思想一臨床診断基準に求められるものは何か.臨床精神医学講座 24,精神医学研究方法(松下正明総編集),pp.69- 81,中山書店,東京,1999.
23)Rossi,A.,Marinangeli,M.G.,Butti,G.etal.: Personality disorders in bipolar and depressive disorders.J.Aflect.Disord。65:3-8,2001.
24)坂元薫:臨床精神病理学的観点からみた Comorbidity概念の意義と問題点.精神科治療学,12:751-759,1997.
25)下田光造:操うつ病の病前性格について.精神経誌,45:101-103,1941.
26)Tellenbach,H.:Melancholie,Vierte,erweiterte Auflage.Springer-verlag,Berlin,1983.(木村敏訳:メランコリー.みすず書房,東京,1985.)
27)Ueki,H.,Holzapfel,C.,Washino,K.et al.:Concordance between self and observer-ratings on Kasahara’s lnventory for the melancholic type personality.Psychiatr.Clin.Neurosci.,56:569- 574,2002.
28)吉松和哉:Comorbidityとは何か.精神科治療学,12:739-749,1997.
うつ状態の臨床分類と生物学的基盤 大森哲郎
1.シュナイダー先生のお話は、改めて鋭いと思う。
2.遺伝背景、病前性格、状況、ストレス、こういった事項を生物学的言葉に翻訳して、どの程度精密さを維持できるかが問題である。笠原先生は、心理学の大陸があり、一方で生物学の大陸があり、いまは遠く離れているが、両方から接近しつつあるのだといった意味のことを書いている。
*****
臨床精神医学34(5):581-585,2005
「うつ状態」とその分類
うつ状態の臨床分類と生物学的基盤
大森哲郎
Keywords:depression,classification,heterogeneity
1.はじめに
*
この四半世紀にわが国の精神科診断分類は大きく変わった。その中でも,うつ状態の分類は最 も大きく変わった領域の1つである。ドイツ精神医学の流れをくむ従来診断が背景に退き,メ ランコリー親和型性格に注目する発病状況論の台頭を経て,症候論に基づく国際診断分類が日常臨床の中に定着している。臨床分類は病態や病因と対応しているのが望ましいが,精神疾患 ではそれを実現してはいない。それでも疾患の基盤に生物学的異常があるとすれば,診断分類 との関係を考えておくことは大切である。本稿では,診断分類の変遷にそって,それぞれの生物学的基盤に関して大づかみに検討する。細部の異同を捨ててDSM-Ⅲ,DSM-IVおよびICD-10を併せて国際分類と総称し,大うつ病エピソードやうつ病エピソードの表記はうつ病に統一した 。
*
2.従来診断における生物学的異常の措定
*
従来診断では,うつ状態を内因性と心因性(神経症性)に分ける成因論的観点からの分類が普通であった。内因性うつ病は脳の機能障害を伴う精神疾患であり,心因性(神経症性)うつ病は体 験に伴う心理性格反応とされていた。このような分類規定はドイツ精神医学に基づいている 。最近は伝統的なドイツ精神医学は省みられることが少なくなっているが,筆者が精神科の研修を始めた頃(1981年)は,クルト・シュナイダーの「臨床精神病理学(平井静也,鹿子木敏範訳 )」やヤスパースの精神病理学原論(西丸四方訳)は,入門者の必読書とされていた。
*
クルト・シュナイダーによれば,循環病(躁うつ病)は,未知の脳の疾病の心理的表現である。 この疾患は,脳器質疾患に準ずるような身体的な疾患であり,循環病という心理学的事実に対 応する未知の脳内異常事象の存在が措定された。この措定を支持するのは,遺伝傾向の存在, 全身性の身体変化の随伴,身体療法(薬物療法導入前の電気けいれん療法などと思われる)の有効性などである。しかし,それ以上に重視されたのは,循環病の患者では正常な精神生活およびそのバリエーションとは全く類似性を持たない症状までも現れるということ,およびその症状は心理的体験のために生じるのではないという精神病理学的事実である。
*
つまり,典型的躁うつ病相は,納得できる心理的きっかけがなくても生じ,症状は程度が強いというだけでなく内容が極端で,日常生活で経験する憂うつや高揚とは明らかに隔絶し,身体面の症状も多く含む。治療には(現在ならば)薬物療法や電気けいれん療法などの生物学的方法 が有効である。こういうことから,典型的躁うつ病相に,脳の疾病を措定している。
*
シュナイダーの時代には,脳の異常の正体は全く不明であった。当時から現在までに,神経科学は驚くべき進歩を遂げ,生物学的研究はうつ病の病態に関し膨大な知見を提供している。しかし,その全貌はいまだに明らかではない。現在においても,うつ病に生物学的異常を仮定するうえで,またそれを探求する研究を正当化するうえで,厳密な臨床観察に基づくシュナイダ ーの精神病理学的考察は,その価値を失っていないと思われる。生物学的研究所見の集積から 脳の異常が示唆されたのではなく,緻密な臨床観察から脳の異常が措定されたという歴史的経緯を,臨床医は忘れるべきではない。
*
なお,従来診断においても,躁うつ病が何らかの心理的出来事に続発することは知られていた 。しかし,それは誘因ではあっても病因として作用するのではないとされ,心理的次元と生物学的次元は切り離して理解されていた。
*
3.生物学的観点からみた性格反応型うつ病
*
うつ病の発症に心理的体験が関与しているようにみえる場合は実際には少なくない。日本の下田光造とドイツのテレンバッハは,その意義を積極的に評価し考察した。彼らの考え方が日本の臨床家に広まったのは,1975年に発表された笠原・木村のうつ状態の分類に負うところが 大きい。この分類は,「病前性格一発病状況一病像一治療への反応一経過」をセットとして気分障害を6つに分けたものであるが,特に注目されたのはそのI型である。性格(状況)反応型と名づけられたⅠ型は,病前性格にメランコリー親和型性格ないし執着性格を持つものが,転勤 や昇任,家族成員の移動などの生活状況変化に際して発症し,病像は典型的な内因性うつ病であって,抗うつ薬によく反応し,経過もよくてしばしば単相のうつ病である。この分類は,軽症うつ病を診療する機会の増加した臨床医の支持を集めた。精神病理学的には,性格と状況が典型的な内因性病像を作り出す過程を,心身二元論を超越したところで考察した点に大きな意義があると思われる。
*
しかし,この性格は英語圏では注目されなかった。また,日本でも1990年代以降になって行われた実証的研究は,うつ病の病前性格として必ずしもメランコリー親和型が多いわけではないことを示している。ある時期までの日本社会には相当数見られたこの性格が,ここ10数年の間 に急速に少数派に転じたということかもしれない。実際,メランコリー親和型性格の減少は最近も指摘されている。他方,さまざまな生活上の出来事が発病に先駆することがあることはク レペリンやシュナイダーの時代からどの言語圏でも認められている。したがって,性格に重点を置くよりは,生活上の出来事に重点を置く方が,時代と社会を越えて普遍的である。ここで生活上の出来事をストレス体験という角度から見れば,生物学的立場との架け橋ができる。
*
早くも山下は1978年に,遺伝素因や身体条件とともに心理社会的要因がうつ病発症に関与する仕組みについて,先見的な仮説を提唱している。当時,うつ病の背景に脳内モノアミン代謝の変化があるらしいことが,いくつかの臨床生化学的研究および抗うつ薬の作用機序研究から推定されていた。一方で,脳内モノアミン代謝には,遺伝的に規定される個体差だけでなく,加 齢などの身体条件や,さまざまな情動刺激が大きな影響を及ぼすことも明らかになりつつあっ た。山下は,抑うつ状態を心理的なうつ症状と表裏一体をなすであろうモノアミン代謝という 平面の上におろすと,内因も身体要因も心理社会的要因もモノアミン代謝の変化を通して抑う つ状態を引き起こす点において,みな共通の性質を持つと考えることができると提唱した。す なわち,心理社会的要因もストレスとして働いてモノアミン代謝の変化を起こし,素因と相乗 的に慟いて抑うつ症状を作り出すのである。このように考えると,心理社会的な要因が一見反 応性にうつ病を引き起こすことがあり,しかもそのときの病像が誘因なしに生じる場合と全く 同じ病像となり,かつ薬物療法によく反応することを無理なく説明することができる。当時, 脳内モノアミン代謝変化に絞り込まれたかに見えたうつ病の病態は,その後の研究からそれよりはるかに複雑で広範に及ぶことが示され,平行してストレスの影響も広範囲の脳機能系に及 ぶことが明らかとなったが,両者の範囲はおおむね重なっている。「脳内モノアミン代謝の変 化」を「脳内モノアミン系を含む機能障害」と読み換えれば,この仮説の骨子は四半世紀後の 現在もそのまま成り立っている。
*
うつ病に脳機能障害を仮定する立場からメランコリー親和型性格の意昧づけを逆照射すると, この性格は特定の環境変化が過度のストレスを伴いやすいという点で病態促進的に働くが,同 時に症状の表現様式にも大きな影響を持つ可能性がある。同一の脳内機能変化が生じた場合, 心理行動面に表れる症状は基本的には類似したものとなるが,文化や社会や環境にも規定され るし,微妙な身体条件によっても左右され,とりわけ性格には大きな影響を受けると思われる 。例えば,一定濃度のアルコールが脳内に作用した場合,それは共通の心理行動効果をもたら すとともに,それぞれの体質と性格と環境によって微妙に千差万別の効果をも作り出す。うつ 病の病態は,アルコールのように外因的でも均一でもなく,それよりはるかに複雑である。し かし,脳機能障害が心理社会的要因に修飾されて心理行動症状に表現されるという単純化した 思考モデルを当てはめると,勤勉で几帳面で責任感が強く対人関係を気遣うメランコリー親和 型性格の人に「脳内モノアミン系を含む機能障害」が生じると,抑うつ気分と意欲低下を強く 自覚するだけでなく,仕事量の低下に苛立ち,自責的となって自己処罰的な自殺念慮をつのら せるという推定が成り立つ。うつ病の精神症状が顕著に表に出るのである。逆に,不真面目, ルーズ,無責任で自己本位な人に,同様の「脳内モノアミン系を含む機能障害」が生じた場合 には,症状の中に他罰的言辞,なげやりな態度,短絡的な行動化などが混入して,うつ病症状が 迷彩化される可能性がある。この意味でメランコリー親和型性格は,元来の性格という「地」 から,うつ病症状という「図」をくっきりと浮かび上がらせる構造を持っているように思われ る。
*
4.国際分類における生物学的基盤
*
周知のように,国際分類は症候論に立った操作的な分類である。気分障害の分類の特徴は,第 一にはいわゆる内因と心因の区別を廃し神経症性うつ病を気分障害へと同化したことであり, 第二には単極と双極という極性へ着目したことにある。しかしながら,ICD-10に述べられてい るように,「気分障害の病因,症状,基盤にある生化学的過程,治療への反応,および転帰との間 の関連はまだ十分わかっていないので,この疾患を誰もが十分納得できるような形で分類する ことはできない」のであり,この分類の妥当性を生物学的観点から論ずることは時期尚早と言 わざるを得ない。ここでは,薬物治療への反応という観点に限定して,若干の整理を試みる。
*
4-1.神経症性うつ病の気分障害への同化
*
従来診断においては,躁うつ病が脳の機能的疾患であるのに対し,神経症性うつ病は心理性格 環境要因から生じる反応性のものであり,正常心理の延長ともいえるものであった。躁うつ病 には薬物治療を含め身体レベルに作用する治療法が有効であるが,神経症性うつ病には薬物療 法には積極的な意義はなく,環境調節や精神療法が重要であるとされていた。このように古典 的には,対比的に理解されていた神経症性うつ病を気分障害の中に同化したことは,国際診断 の大きな特徴となっている。もちろん,この大胆な転換の背景には多くの研究があるのであり ,神経症性うつ病として発症しても,数年間経過観察すると,内因性うつ病,精神病性うつ病,躁病,軽躁病などのエピソードが高率に出現することを示した経過研究などは,その重要な1つで あろう。
*
では,薬物治療への反応からはこの転換は支持されるだろうか。従来診断の神経症性うつ病は ,国際分類では,うつ病エピソードの一部および気分変調症の相当部分に該当する。もし,抗う つ薬に対する反応性が気分変調症においてもうつ病と同等に高ければ,うつ病と共通する脳機 能障害がこの疾患においても示唆され,極端に低ければ気分変調症にはむしろ従来の神経症性 うつ病の名がふさわしく,それを気分障害の中へ分類する妥当性には疑義が生じることになる 。
*
うつ病と気分変調症の両者を含む抗うつ薬効果のメタ解析によれば,12週間以内の治療期間において,抑うつ症状の半減した気分変調症は,プラセボ群の37%に対し,選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)服用者が大部分を構成する新規抗うつ薬群で59%,三環系抗うつ薬を用いた群でも同じく59%である。うつ病では,数週の試験期間中に抑うつ症状が半減する割合は ,新規抗うつ薬群で51%であり,プラセボ群では32%であった。新規抗うつ薬と三環系抗うつ薬との間の差はない。この手の研究の常として,臨床家の実感と比べると抗うつ薬の効果が小さ くプラセボの効果が大きい印象はある。しかし,新規抗うつ薬にしても三環系抗うつ薬にして も,気分変調症においてもうつ病と同等の効果があるのであり,薬物反応性という観点からみ ると,両疾患は類似性が高い。気分変調症に該当する症例を神経症性とみて成因論的に別種の ものとした従来診断よりも,気分障害の中で並列的に分類した国際分類の方を支持する結果と いえるだろう。
*
4-2.極性への着目
*
単極型と双極型の区別は国際分類のもう1つの大きな特徴である。そもそも従来診断では単極 性のうつ病はまだその存在が明示されていなかった。前述したシュナイダーの本では循環病 としてしか論じられていない。我国でも,1978年版の諏訪望や1976年版の村上仁らなどの当時 の代表的な教科書においても,躁うつ両病相をとる経過を中心に記載され,単極性うつ病は躁 うつ病のむしろ特殊型という位置づけに読める。単極性と双極性に分けたのは,1950年代後半 以降の,ドイツのLeonhalt,スイスのAngust,スウェーデンのPerris,米国のWinokurらの経過研 究を嚆矢とし,臨床遺伝学的にも支持され,国際分類へ採用されるに至ったのである。気分障 害に関しては,国際分類は症候よりは,むしろ経過に基づく分類であるとさえ言える。
*
薬物治療への反応性からは,この極性に基づく分類は支持されるだろうか。リチウムをはじめ とする気分安定薬は,双極性障害の躁うつ両病相の治療と予防に有効であり,単極うつ病の治 療や予防には通常は有効ではない。単極うつ病に有効な抗うつ薬は,双極うつ病(双極性障害 のうつ病相)の治療での有効性には否定的な見解もあり,少なくとも単剤使用は推奨されてい ない。周知のように抗うつ薬の直接作用はモノアミン取り込み阻害であることが確立してお り,気分安定薬はいくつかの細胞内シグナル伝達系が有力候補である。たとえばリチウムでは ,イノシトールモノフォスファターゼ,イノシトール多リン酸モノフォスファターゼ,グリコー ゲンシンターゼキナーゼ3βなどに対する阻害作用が注目されている。単極型と双極型が,こ のように作用点の異なる薬物に反応するということは,両者の生物学的基盤が異なることを推 測させるものであり,極性に基づく分類を支持していると言える。
*
おわりに
*
従来分類,性格反応型および国際分類という3つのうつ状態の臨床分類と生物学的基盤との関 連について,筆者の理解の及ぶ範囲で私見を交えて通覧した。精神病理学的考察からの生物学 的異常の措定には現在もなお意義があること,および性格反応型においても生物学的立場から の考察が可能であることを述べた。ついで,従来分類と比較した場合の国際分類の特徴を,神 経症性うつ病の同化と極性重視の分類とみて,この2つの特徴を治療薬物への反応性という観 点から評価すれば,国際分類の方が生物学的基盤との整合性があることを述べた。
*
しかし,このことは気分障害の国際分類が生物学的基盤に立脚していることを意味しない。薬 物反応性の観点からも,抗うつ薬に反応しないうつ病の存在はうつ病内部における異種性を示 唆しているともいえるし,不安障害や強迫性障害に広がる抗うつ薬の有効性はそれらの疾患と うつ病との境界を曖昧にしているともいえるのである。病態や病因と対応した診断分類の実 現へ向けて,さまざまな立場からの臨床研究の集積がぜひとも必要である。
*
文献
*
1)阿部隆明:時代による精神疾患の病像変化気分障害.精神医学47:125-131,2005
2)AkiskalHS,BitarAH,PuzantianvRetal:The nosological status of neurotic depression:a prospective three-to four-year follow-up examination in light of the primary-secondary and unipolar-bipolar dichotomies.Arch Gen Psychiatr 735:756-766,1978
3)Akiskal H:Mood Disorders:introduction and overview.Kaplan&Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry,7th edition.Lippincott Williams&Wilkins,Philadelphia,pp1284 --1298,2000
4)秋山剛,津田均,松本聡子ほか:循環気質とメランコリー気質:気分障害の性格特徴に関する 実証研究.精神神経学雑誌105:533-543,
5)Funrukawa T,Nakanishi M,Hamanaka T:Typus melancholicus is not the premorbid personality trait of unipolar(endogenous)depression.Psychiatry Clin Neurosci 51:197-202,1997
6)GhaemiSN,RosenquistKJ,KOJYetal:Antidepressanttreatmentjnbipo】arversusunipolar depression.AmJPsychiatry161:163-165,2004
7)木村敏,笠原嘉:うつ状態の臨床的分類に関する研究.精神神経学雑誌77:715-735,1975
8)SchneiderK:KlinjschePsychopathologie.平井静也,鹿子木敏範訳:臨床精神病理学改訂増補第6版,文光堂,東京,1962
9)Lenox RH,Frazer A:Mechanism of action of antidepressants and mood stabilizers.ln Davis K et al (Eds):Neuropsychopharmacology:TheFifth Generation of Progress,American COllege of Neuropsychopharmacology.Williams&Wilkins, Lippincott,2002
10)村上仁,満田久敏,大橋博司監修:精神医学第三版,医学書院,東京,1976
11)諏訪望:最新精神医学-精神科臨床の基本-新訂版.南江堂,東京,1978
12)Williams JW,Mulrow CD,Chiquette Eetal:A systematic review of newer phamlacotherapies for depression in adults:evidence report summaly.Ann lntern Med 132:743-756,2000
13)山下格:心因と内因.精神医学20:2-3,1978
シュガー社員
「バブル景気を享受してきた親」「ゆとり教育世代」「IT主体で直接コミュニケーションが苦手」「能力主義による転職志向」などを背景として、「自己中心的で会社に甘える若手社員」のこと。
・何かあると親が出てくる〈ヘリ親依存型〉
・自己中心型の〈俺リスペクト型〉
・楽な方へ逃げる〈プリズンブレーク型〉
・仕事が増えるとパニックになる〈ワンルームキャパシティー型〉
・勤め人意識がもっとも希薄な〈私生活延長型〉
の5タイプに分類している。
≪「苦い上司」の5カ条≫
(1)叱る時は感情をむき出しにしない
「特に俺リスペクト型の場合、『惜しいなぁ』『君らしくないなぁ』と期待感を匂わせて叱る。罵倒などもってのほか。行動が変わるまで粘り強く」
(2)やる気を促そうと褒めるのはムダ。特に最初の3年は厳禁
「褒めれば褒めるだけ、『俺はもう一人前』と勘違いをする。偉いな! すごいな! 素晴らしいぞ! の3語は使わず、評価するなら具体的に『今回○○の部分を頑張ったね』とドライに」
(3)メールで連絡をしてきたからといってメールで返信する必要なし
「あの子への連絡は、メールのほうがいいのかな」という気遣いは百害あって一利なし。「君はメールで言ってきたけど、これは直接話し合うべき問題だ」と言うべきことは直接言う。
(4)部下が挨拶をしなくても自分から挨拶を
「うちの若いのは挨拶もできない」と嘆いても何も変わらない。上司から「やる気茶屋」の店員くらい大きな声で挨拶を。シュガー社員も自分から「おはようございます」と言うようになります。
(5)トラブルで親が来たら毅然とした態度で
「下手に出過ぎたり、逆に怒ったり、嫌だったら辞めろと言うのはNG。会社は親への応対が不慣れなのでトラブルのもと」
「シュガー社員」が「企業を溶かす」んだそうだ。
新型商売
世の中に新型商売がいくつもある。
今日の話では、「日本語講師になるための講座」。
何十万円かのお金で、講習を受ける。
世界各国にある日本語学校に派遣してもらえる話だという。
出版の話も、似たようなことで、
ある出版社は、本を売って稼ぐのではなく、
本を作ってあげて、著者からお金を取る。
売れなくても、自己責任。
そのような商売。
心療内科関係では、
心理士になれるとかなんとかの講座があるとかの話。
心理士といっても、臨床心理士も国家資格ではないし、
病院心理士とか、ただカウンセラーといったりとか、
いろいろで、講座を修了すれば、何かの仕事があるように匂わせるらしい。
しかし実際は、一流大学の大学院を出て、臨床心理士になった人が、
つらい思いをしている業界なのだ。
医療事務なんかも似たところがある。
お金を払って、やっと指定された講習を終わって、
その挙句、通勤に二時間もかかる場所を紹介されたりする。
仕事に就けますと匂わせて、お金を巻き上げる。
最後は、あなたの努力が足りないと突っぱねる。
経口避妊薬の長期使用により子宮頸癌のリスクが倍増、中止後は漸減
11月10日付Lancet誌に報告が載っている。
従来は、経口避妊薬と子宮頚癌の関係について、薬物そのものの影響という考えと、薬剤使用の結果として性交パートナー数が増え、ヒトパピローマウイルスに感染する機会が増大するからという考えとがあった。
今回の調査は、「使用期間5年以上で相対リスクが倍増、中止後は漸減」「10年以上が経過すると非使用者と同等のリスクに戻る」という報告で、薬剤そのものが問題だったという側面が強調されている。
*****
子宮頸癌の相対リスクはconditional logistic regressionを用いて解析し、試験、年齢、性交パートナー数、初回性交年齢、喫煙、スクリーニング法などで層別化した。経口避妊薬の現使用者においては、使用期間が長くなるに従って浸潤性子宮頸癌のリスクが増大し、使用期間5年以上の女性の相対リスクは非使用女性の約2倍に達した(相対リスク:1.90、95%信頼区間:1.69~2.13)。浸潤癌およびCIN3とも同じリスクパターンがみられ、ヒトパピローマウイルス(HPV)感染リスクの高い女性でも同様であった。また、患者背景の異なる女性間で、相対リスクの実質的な違いはみられなかった。
*****
どう解釈するのか。
混合型経口避妊薬そのものは、普通の性ホルモンだろう。飲んだからといって、性ホルモン濃度が普通よりも特に高くなるわけでもないだろう。
子宮頚部の細胞は脱落と再生が激しい場所なので、細胞ががん化する機会は多いだろう。がん細胞の増殖を免疫機構が抑制している一方で、性ホルモンが増殖を促進するだろう。しかし薬剤は自然の性ホルモンと濃度レベルは変わらないし、物質としても同じなら、とくに自然状態と比較して変化はないのだろうと考えられる。むしろ、規則正しく濃度変化が起こるので、細胞の再生と脱落のリズムが規則的にできて、がん細胞の「処理」には都合がいいようにも思える。
免疫機構の点では、胎児という一種の異物を収納する関係で、免疫機構は少しだけ監視をゆるめるだろう。ということは、がん細胞は生き延びるチャンスが増える。女性ホルモンが低レベルの方が、がん細胞監視には有利だろう。
経口避妊薬の内容を検討して、もっと低容量ではどうだろうかとか、各個人の性ホルモンの濃度をまず測定して、それに合わせて薬の量を調整するとかすれば、がんの対策になるのかもしれない。
いずれにしても、経口避妊薬を中止して10年以上経過すれば、非使用者と同等のリスクに戻るというのだから、やはり薬剤そのものが怪しいといわざるを得ないが、それでもまだまだ違う解釈の余地はある。実験室みたいに条件をコントロールできるわけではないからだ。
臨床心理士採用模擬試験-2
臨床心理士採用模擬試験
以下の優秀論文を読み、問に答えなさい。
問1.変化した内因性うつ病に残存する「不変項」は何であるか、かみ砕いて、述べよ。
問2.治療論について、自分のカウンセリングスタイルの中に取り入れることができる要素があれば、それを具体的に述べよ。
*****
精神療法第32巻第3号
うつ病態の精神療法
現代型うつ病
松浪克文*上瀬大樹*
はじめに
われわれが,1991年に発表した「現代型うつ病」(松浪ら,1991a)は,比較的若いサラリーマンなどに典型的に見られる軽症の内因性うつ病の変異型で,抑うつ気分よりも制止症状が前景に立ち,恐怖症的心性に関係すると思われるいくつかの特徴を有する。われわれは当初,この病像を,大都市における職場倫理・生活意識の現代的変質や現代人の性格傾向の変化が内因性うつ病の病像を修飾しうることを例証するものとして提示した。病像が変化したのだとすると,うつ病像のうちの何か変化したのかがまず問題となるが,われわれはむしろ何か変化していないのかを明確にとらえることもまた重要ではないかと考えた。なぜなら,あるものが「変化した」といいうるためには,変化の前後を通じて不変のままとどまっている成分が存在することが論理的に要請されるが,その不変のままの成分や性質こそ,そのものの同一性を保証するものだからである。つまり,現代的な病像変化を被ってもなお変わらないでいる特徴,つまり変化した内因性うつ病に残存する「不変項」の抽出がうつ病の本態を知る上で貴重な手がかりとなると考えたのである。
I 症例呈示
1991年の発表において提示した症例を再度提示する
34歳の地方出身の技術者。2人兄弟の長男。国立高専卒業後,入社。共働きで子どもはいない。長身で痩せ型,色白,神経質で几帳面な性格。妻によると,家では何でも一人でやってしまって手がかからないとのこと。謙虚な態度で物腰柔らか,気弱な感じである。和太鼓を趣味にして9年になる。また中学時代にやっていたバレーボールを今でも続けている。入社時,希望とは異なるコンピューター部門に配属されてがっかりした。コンピューターは時代の花形分野だが,「緻密で先端的なものは嫌いなんです,もっとひっそりと自分のペースでやれるようなものがいい」と述べた。学生時代に初めてコンピューターに接して,これはいやだなと直感したそうで,「機械が好きで論理的に動くものは嫌いじゃないけど,どういうわけかそう思った」と言う。朝,家を出るときに会社に行きたくないと思う,ということを主訴に精神科初診。2年前から出社するのが嫌だという気持ちがあったが,初診前年の2月ごろがいちばんひどく,1週間続けて休んでしまった。今の仕事は続けたくないと思う。休んでいる日は,家でテレビをつけて,ぽけーっと観ている。初診時の5月から9月まで4ヵ月の病休をとった。嫌なヤツがパートナーになった頃から休みたい気持ちが強くなった。
それまでの本社勤めでは,仕事は嫌だったが気持ちはフレッシュで頑張っていた。「今考えると,なぜあんなに馬鹿みたいに頑張っていたのか不思議でしょうがない」と当時を述懐し,今は仕事中もぼーっとしていて,集中力かなく,能率は半分以下に落ちている,と訴える。入眠困難,熟眠感のなさ,早朝覚醒が続いている。「何かいい仕事はないかな,と思うけど自分に合う仕事がわからない。……会社は辞めたくないけど,出たり休んだりではねえ……。内心,困ったなあという感じです」と斜に構えたような当惑顔。4月の病休明けから制限勤務(50%~80%)を続け,6月にはパートナーを変えてもらったが,症状がなくなり抗うつ剤を中止する段階になっても,「自分のペースを守るために」制限勤務を希望した。さらに8ヵ月間の制限解除状態を続けた後に配置替えとなった。なんとか出勤していたが,2ヵ月後に再び集中力低下,易疲労感を訴えて1ヵ月間の病休をとった。この病休から復職するとき,動悸,発汗,めまいを伴った強烈な不安に襲われ,会社の社屋の前で身体がふるえて中に入れず,帰ってきてしまうというエピソードがあった。職場が恐いと言い,あのあわただしい仕事の流れの中に戻ることがつらい,と語った。
以下に,この症例記述に即して,いくつかの特徴的な点を項目に分けて整理してみる。
1)主訴(主症状):「会社に行きたくない」というのが初診時の主訴であった。患者は,一旦は会社に適応したようで「フレッシュな気持ち」で「馬鹿みたいに頑張っていた」のであるから,会社に行きたくないと思うことは患者にとって,異常かつ異質な事態であり,これが主訴となったのであろう。しかし,初診時には他にも「集中力がなく,能率が半分以下」と訴えており,また職場復帰途上で挫折し再び病休をとる時にも「集中力低下,易疲労感」を訴えている。これらは制止症状ととってよいと思われるが,こちらの方が患者の社会的機能を深刻に損なう障害を直接的に表していることは明らかである。ただし,初診時に苦境を訴える話しぶりは比較的要領を得て,とつとつと話すがさして滞ることがなく,質問にもほぼ的確に応答するので,制止症状の程度は比較的軽いと言えるだろう
2)恐怖症:復職時に吹き出した「動悸,発汗,めまいを伴った強烈な不安」もまたこの症例の症状論的特徴である。「あのあわただしい仕事の流れの中に戻ることがつらい」という述懐からは,この恐怖症の対象が「あわただしさ」の中に身を置くことなのだと推測される。初診時には取り立ててはっきりとした恐怖症的心理は訴えられなかったからか,復職時にパニック発作様の恐怖が出現したことは治療者にとっては,予測不能と言うわけではなかったものの,やや唐突に思えた。遷延化したうつ病例に時に見られる復帰時の恐怖症の状態と酷似しているが,後述するように,遷延化例でこのような恐怖症状が出現するときには,すでに何回かの復職に失敗し,復帰に難航している場合が多い。換言すれば,初発の病相からの復帰時において早くも,遷延化例におけるような恐怖症状が出現することが特徴的だと言えるだろう。この恐怖心の背景には次項に述べる忌避感が存在する。
3)忌避感:患者は現代社会に含まれる何らかの属性を忌み嫌うという心理を学生時代(おそらくそれ以前)から自覚している。この症例では忌避の対象が「コンピューター」「先端的なもの」と表現されている。この心理は当然,主訴の「会社に行きたくない」「仕事を続けたくない」という心理の背景に潜在していたものと思われる。初診後,会社を休むようになったのは「嫌なヤツ」がパートナーになったことがきっかけだったが,しかし,この特定の人物への嫌悪はそれ以前から訴えられた忌避感とは異なるようである。というのは,後に「嫌なヤツ」がパートナーではなくなってからはこの嫌悪感は消失したのに,何かに対する忌避感は存続しつづけたからである。実状は,心底にある忌避感に耐えて勤続してきたところに「嫌なヤツ」が現れ,それがきっかけとなって忌避感がつのってはっきりとした拒否感となった,ということであろう。この心理の移り変わりについては,まず漠然とした忌避感があり,それが発病時に明確な拒否感と形を変えて自覚され,復帰時には恐怖症的心理になったという道筋が考えられる。
4)当惑感:患者の「斜に構えたような当惑」もこの症例の特徴である。「ぼーっとする」ことや能率の低下に困り果てているという風情のこの陳述は抑うつ気分の表現だと解せなくもないが,休日に家でテレビをつけてぼーっと見ていると述べており,抑うつ感ははっきりとは言語化されうる程には深まっていない。(私見だが,テレビを観られるかどうか,どの程度楽しめるかは,うつ病の症状の重症度をかなり正確に反映している)。この当惑感は苦境の中にある人間の呻吟というよりも,むしろ自分の能率低下や意欲低下の状態から少し距離をとった視点を保持し,第三者的に自分の状態を見ていることを示している。また,「何かいい仕事はないかなと思う……」という後の述懐には半ばあきらめたような醒めたトーンがあり,“もともと嫌だったが,やはりはっきりと嫌いになってしまった,やはりだめだったか”とでもいうような心理がうかがえ,患者にはこの苦しい事態の到来が以前から察知されていたように見える。
5)所属意識の希薄さ:患者は「何かいい仕事はないかな,と思うけど自分に合う仕事がわからない。……会社は辞めたくないけど,出たり休んだりではねぇ……」と述べており,自分の勤める会社にさして執着はないように見える。辞めたくはないけど,辞めることもしかたないかなとでもいうようなこの述懐に,会社への帰属意識の希薄さが伺える。もちろん,この所属意識の希薄さの背景にも上述の忌避感が存在するのであろう。患者は入社後,仕事をこなすという意味での適応努力をしたが,上述した忌避感のために,職場に緊密に同化する気持ちには至らなかったものと思われる。また,34歳になっても「自分に合う仕事がわからない」と述べていることから,特定の社会的組織への帰属意識が希薄なために,アイデンティティが分化しておらず,一種のアイデンティティの混乱が重畳しているように見える。
6)性格:患者は「長身で痩せ型,色白,神経質で几帳面」であり,「謙虚な態度で物腰柔らか,気弱な感じ」の人物である。身の回りのことでも「何でも一人でやってしま」い,妻に負担をかけない,というところからは,助け合うことに含まれる負債や返済という連携を避けているような心理が伺える。おそらく返済が重荷となることを予想して緊密な一体感を抱くことに危険を感じるようなタイプで,配偶者に対してでさえ相互依存的関係性に至らず,どこかあっさりした関係性を保っている。
7)趣味:和太鼓やバレーボールなどの趣味的活動を長年続け,職業を続けていくことが困難になった時期にも維持された。患者にとっては,これは1週間のうちの決められた定期的活動であって,なぜずっと続けているのかと聞いても,上手になるのが楽しいとか,趣味を通じた人とのつきあいが楽しいなどの理由は述べられなかった。職場では比較的明瞭な制止症状が出ているのに,趣味は続けられるという点で,広瀬の「逃避型抑うつ」において「選択的制止」として記述された症状と,少なくとも現象面において同一であるが,趣味的活動が必ずしも楽しみのために行われているのではないように見える点で,多少性質を異にする(後述)。
Ⅱ 「現代型うつ病」の病像
おおむね提示症例と類似したうつ病像を「現代型うつ病」としたのだが,冒頭に述べたように,われわれはこれを中核的な,従来のうつ病象の変化像として捉え,主に「従来型うつ病」との比較を考察の中心にしていた。以下に,より一般的に,この病像について,「従来型うつ病」と比較しながら,解説する(表1)
表1現代型うつ病の特徴
①比較的若年者
②組織への一体化を拒絶しているために,罪責感の表明が少ない。むしろ当惑ないし困惑
③早期に受診→不全型発病
④症状が出そろわない;cf)SSD身体症状と制止が主景,選択的制止
⑤自己中心的(に見える);対他配慮性が少ない
⑥趣味を持つ;cf)逃避型
⑦職場恐怖症的心理+当惑感
⑧インクルデンツを回避;几帳面,律儀ではない
⑨レマネンツ恐怖;締め切りに弱い
「従来型うつ病」と異なる「現代型うつ病」の特徴は,①やや若い年齢層(30歳すぎから)に見られること,②患者は自分の言動や状態を異常だと感じており,ほとんどすべての症例で患者が自ら進んで受診すること,③症状が「不全型」であること(うつ病の症状が出そろっていないこと),④自責的ではなくむしろ当惑感を抱いていること,⑤職場への忠誠心や同僚への連帯感を表明せず,職場への帰属意識が希薄なこと,などである。
会社組織に帰属したくないという心理は,「別に会社の一員であることを誇りに思ってはいません」「社内のつきあいはできるだけ少ない方がいい」などと,気負うことなく淡々と表明されることが多い。また,提示症例のように「会社に行きたくない」という理由で仕事を休むという行動が怠業のようであるし,休むことが他人に与える負担を考慮して申し訳なさを表明しないのは自己中心的に見える。しかし,本来の患者の性格には,病理的な利己的心理がすぐに見て取れるようなpersonalityの偏奇を指摘することはできないように思う。患者は,率直で,洒落っけがなく,淡々と生活しているという風情の人柄であったり,多少凝り性だが生活を楽しむライフスタイルを持っていたり……と一定の傾向はなく,少なくとも,性格の病理のための不適応はなかった。自己中心的に見えるのは,診断者が暗に,うつ病患者は対他配慮性が強く,会社への忠誠心が強いという図式を人格判断の基準としてしまうからかもしれない。
受診の経緯についても,ぎりぎりまで頑張って過剰な適応努力をする「従来型うつ病」とは異なり,早々に退散したというような印象を受け,診断学的に症状が出そろわない段階で受診することが多い(不全型の発症)。訴えの中心は,「やる気がでない」「能率がさがってしまった」「疲れやすい」などの意欲減退であるが,ときに「腰が痛くて憂うつだ」「出社時に頭痛,吐き気,めまいがする」などの身体愁訴が加わる。抑うつ気分が訴えられないわけではないが,非常に憂うつそうなのではなく,現状を苦痛に感じてはいるか心中はむしろ当惑しているという印象がある。上司や同僚との衝突などをこれらの苦痛や困難が引き起こされた理由にあげることがあるが,しかし,発病以前には同種の困難をなんとか克服できていたという認識を持っている。この点で,発病という事態が不可解であると感じ困惑しているのである。
社会復帰については,早く復帰したがることの多い「従来型」と異なり,「現代型」はいつまでも復職時期を延ばしたり,復帰後の制限勤務の延長を求めたりすることが多い。復帰交渉の時,あるいは復帰時に決断して出社する際に,パニック発作様の症状が起こったり,会社の社屋の前まで行ってどうしても中に入ることができず帰ってくる,などの恐怖症的行動が出現することがある。このような恐怖症的行動自体は,従来型の遷延化例に見られたものと同質のものであるが,初発の病相に現れることが「現代型」の特徴である。
患者の自己同一性はむしろ仕事以外の領域で保たれており,提示症例のように長年にわたり趣味を続けていることがある。このことは,たとえ現実には会社人として職務をこなしていても,要請された役割アイデンティティを全面的には引き受けていないことを物語っている。この点も従来のうつ病理論とは異なるだろう。そして,この趣味領域での営み(提示症例のような純然とした趣味ではなく,たとえば20年間,土日は必ず1日中パチンコに行くなどの例もあった)は強迫的な反復性と持続を示す。患者はこの私的領域の反復的活動が創り出しているペースを自分本来のものとして,それを乱されることを嫌っているように見える。ただし,このような趣味領域の活動が同様の症例すべてに認められるわけではないのだが,その場合でも生活行動の中に気楽な過ごし方という領域を持っていて,その領域での活動を続けていることが多い。表2に,「現代型うつ病」と「従来型うつ病」とを比較した
表2現代型うつ病と従来型うつ病
現代型の特徴 従来型の特徴
①早期に受診→不全病型 完全に発病して受診
②選択的制止 全面的な制止
③自己中心的 対他配慮
④趣味を持つ 無趣味
⑤職場恐怖症的心理 遷延化例において見られる
Ⅲ 病態理解
1.逃避について:広瀬の「逃避型抑うつ」を参照して
「現代型うつ病」の病像は,制止主体の症状を示し,選択的制止があり,自己中心的に見え,恐怖症状を出すことがあるなど,多くの点でうつ病の病型研究として近年もっとも注目されてきた広瀬(1977)の「逃避型抑うつ」や松本(1990)が論じた中年層の逃避型抑うつに類似している。しかし,われわれは当初,これらの患者が「来るべき挫折が来てしまった」というような諦念を隠し持っているという印象を強く持ち,患者が疾病へ「逃避」しているとは思わなかった。また,趣味への逃避と見ることもできるが,趣味的活動は職場での苦境から逃避するために行われているというよりも,職場での苦境にも関わらずペースを変えることなく維持されているという印象をもった。
病態理解という点から見ると,「逃避型抑うつ」概念では,発症が「逃避的」に見えるのはヒステリー機制を含んだ甘えの病理によるという仮説が提示されているのに対し,「現代型うつ病」は恐怖症的心性によって病像が陰伏的に規定されている点に特徴があり,現代社会の一部に現れた局地的な心理傾向に関連するのではあるが,個人の性格の病理に依存するところは少ないように思う。
また一般に,「回避」や「逃避」の語を,症状構造を論じる理論語として用いるのと,現に患者の心理において働いている現象を記す観察語として用いるのとは次元(階梯)が異なることにも留意する必要がある。精神疾患の発症をストレス回避という意味で逃避だと構造的に解釈することは可能であるが,そのことと実際に患者に逃避の心理が見て取れることとは同一ではないのである。広瀬もこの点に対処しており,「逃避型抑うつ」における「逃避」に見える行動の実体は生体の反応としての擬死反射として理解できると論じている。これに対して,われわれは「現代型」の症状の性質と発症経緯は基本的に了解不能であることから,発病とストレスの間には「うつ病準備性」とでもいうべき素質的な身体性の病理が介在しており,この発症経緯は基本的に不可避な過程であると考えている。結局,われわれは現象の記述としても,症状構造上の仮説としてもこの病像を「逃避的」と言うことはできなかった。
2.恐怖症的心性について:レマネンツ恐怖
「現代型うつ病」に見られる恐怖症的心性は,すでに周知の(従来型うつ病の)遷延化例に見られる恐怖症状とほぼ同質のものと思われる。
(従来型うつ病の)遷延化例における恐怖症状は社会復帰に何度か挫折するうちに醸成されるものであって,患者は現実の職場状況を恐れているのではなく,職場に出社できなくなる際の,急かされ,追いつめられ,居所のなくなった状況(とそのときの自分の心理状態)についてのイメージを恐怖対象としている(元来,恐怖症とは具体的な対象というよりは対象のイメージヘの恐怖なのであろう)。つまり,遷延化例の恐怖症はいわば「前うつ状況」恐怖(インクルデンツ・レマネンツ恐怖)と言うことができる
とすると,「現代型」患者は初発病相の社会復帰の過程ですでに,遷延化例と類似した「前うつ状況」恐怖を抱いているのではないかという推論が可能である。
しかし,実際には,「前うつ状況」恐怖と言っても「従来型遷延例」と「現代型」とでは微妙に恐怖対象が異なるように思われる。「従来型うつ病」患者は秩序愛を行動面に明確かつ積極的に表わし,周囲から好ましいと評価されることによって会社組織に適応することに発病が準備されているのであった。秩序愛的行動によって過剰適応して発病する場合(「従来型I型」)でも,秩序愛的行動のために適応不全に陥って発病する場合(「従来型Ⅱ型」)でも,過剰な一体化に含まれている構造的矛盾が前うつ状況を招き寄せるのである(表3)。遷延化例に見られる恐怖は復職失敗を重ねる過程で,それまでの適応手段であった秩序愛的行動の適応性に信をおけなくなったところに,再三の復職という現実的課題に直面させられるために生じるものと思われる。この意味では,適応不全をきっかけに発病した従来型Ⅱ型の方が秩序愛の矛盾にある程度気づかされることになるので,その分,遷延化しやすいと言えるだろう。いずれにせよ,遷延化における恐怖は,秩序愛の矛盾がインクルデンツ的な挫折に至る道筋を(薄々とではあるが)意識したために生じるものなのである。
表3 従来型うつ病の二型
従来型I型:秩序的行動による過剰適応 Inkludenz-Remanenz的発病 秩序愛の矛盾に対して盲目
従来型Ⅱ型:秩序的行動の適応不全 Inkludenz的発病 発病後に秩序愛の矛盾に薄々気づく
現代型うつ病:秩序的行動を忌避 Remanenz恐怖による不全型発病 秩序愛の矛盾に気づいている
「現代型うつ病」患者はまさにこのインクルデンツ的挫折を予知しているかのように,緊密な会社組織へのコミットメントを忌避し回避しようとする対社会戦略を採っており,インクルデンツ的状況は回避できると考えている。
ところが,インクルデンツは秩序愛の空間的表現(「空間的」とは形として目に見えることと考えてよい。ここでは言動によって確認できる几帳面,律儀であることなどを指す)を抑制すればかろうじて回避できる可能性があるが,レマネンツは原理的に回避できない。このことが「現代型」にとっての深刻な脅威である。というのは,そもそも組織の中で役割を担って働く人間は,どのような働きぷりであろうと(几帳面であろうとなかろうと),職能の高まりに応じて割り当てられる仕事量が増えるという成り行きを拒否することはできないので,個人の能力と割り当てられる仕事量との臨界点がかならず到来するからである。「現代型うつ病」患者はこのレマネンツ的な臨界状況における疲弊を,社会に参入する当初から危険視しているのである。われわれはこの心理を「レマネンツ恐怖」と呼んだ(松浪ら,1998)。
留意しなければならないのは,「レマネンツ恐怖」という心理にはTellenbach(1974,0rig.1961)が「負債」という形で論じた倫理的性質があまり含まれていないという点である(実際,現代型うつ病では罪責感の表明が少ない)。これは端的に,患者が組織に一体化すること,組織の一員であることに価値を置いていないからであるが,「レマネンツ恐怖」が基本的には強迫的な機制によって成立しているので,「レマネンツ」に引き寄せられることはあっても,「レマネンツ」を恐れるがゆえに完全に「レマネンツ」に陥ることはないということも関与している。理論的には,次のように言うこともできる。そもそもレマネンツやインクルデンツはうつ病素質者が陥る自家撞着的運動における構造的矛盾を言い当てている(つまり,働けば働くほど遅れること,几帳面に働くために几帳面な仕事を完遂できないこと)のだが,この構造的矛盾には本来なんら倫理的性質は含まれていない。倫理的成分はメランコリー型性格の「几帳面さ」や「良心的」などの一見記述的な中立性を有するかに見える標識に密かに導き入れられている倫理性から由来するのである。言い換えれば,強迫性の空間的表現はこのような倫理的成分を含みこんでしまうのである。「現代型うつ病」は強迫性が外に形として現れることを忌避することによってこの倫理的意味合いを招き入れることを拒否しているのでインクルデンツに陥らないのであるし,レマネンツにおいて「負債」という倫理的責めが生じないのである。
IV 「現代型うつ病」と生活リズム
1.レマネンツ恐怖と生活リズム
「現代型うつ病」のレマネンツ恐怖の背景に確実に存在すると思われる忌避感は,「先端的なもの」「ペースを乱すもの」に向けられている。つまり,現代社会の多様性とめまぐるしい変化に向けられたものであり,これに自分のペースを乱されることを忌避ないし恐怖していると言えるだろう。われわれが「現代型うつ病」という変異型に見たうつ病の不変項とはこのような変化への忌避に関連している。
変化を忌避する心理は,「従来型うつ病」の患者にも確実に存在し,彼らの生活行動についての陳述に見え隠れしていた。たとえば,“今日も昨日と同じように過ぎでいくことが安心です”と述べる主婦や“つねに手順を確認して昨日と今日のできが違うなんてことのないようにします”と述べるパン屋を営む患者の陳述((従来型うつ病の例)を顧みれば,変化そのものが不安を惹起する心理がうかがえる(1991b)。
こうした変化の忌避,反復への依存あるいは反復愛好は強迫性の病理の動的,時間的側面であり,本来は「従来型」と「現代型」に共通に存在するはずである。しかし,「従来型」においては,強迫性のこの動的成分は,“几帳面”という静的な表現型によって空間化されてしまい見えづらくなっていたものと思われる。反対に,「現代型うつ病」では,うつ病患者の強迫性が,職場などの社会的・公的な領域においてあからさまに空間化されることが忌避されているため,職場外の私的領域の活動にその動的側面が(図らずも)露呈していると言うことができるだろう(「反復への依存」ということが含む「現代型」の依存の病理については,ここでは紙数を考慮して割愛する)。
このように見ると,「現代型」の患者に見られる(したがって,本来的には「うつ病患者」にも存在するはずの)生活行動の動的側面,とくに生活のリズム性が病理学的に重要な意味を持っているのではないかという視点が開けてくる。症例から導き出される限りにおいては,うつ病患者は職場や世間の多様に変化するリズムに翻弄されることを恐れ,私的生活におけるリズムに固執して自分の「ペース」を守っているとまずは言えるだろう。リズムを乱す因子が環境にあり患者は自分の固有のリズム性を保持しているという図式である。しかし,患者がこれほどまでに「マイペース」を固持する理由が環境からの多様な惑乱だけにあるとはとうてい思われない。むしろ,リズムの主要な惑乱因子は患者自身の側にあって,患者は自身の生活リズムの不安定性や被影響性を恐れており,趣味的領域における反復的な活動によってリズムを失うことをかろうじて防いでいるのではないだろうか。われわれはかつてこのような反復的活動を「硬化したリズム」と表現した(1991b;1998)が,「硬化した」リズムとは形容矛盾であって,これ自体はもはや「リズム」体験ではない。というのは,本来,「リズム」とは単純な反復ではなく,柔軟にゆっくりと変化していく躍動性を有しており,この躍動性が生む差異によって成立する意味体験だからである。したがって,「硬化したリズム」をもって営まれる趣味的行動は,リズムを喪失することから守られているという安らぎはあっても,それ自体が生み出す意味を持たない分,ある種の惰性的運動となる危険性を持っているのである。リズムの含む柔軟な揺れを快く感じるのでなく,この反復性に信を置く強迫性の心理こそ,「現代型」においてかすかに露呈した「うつ病」の病理の一側面であると思われる。
2.生活リズムとうつ病の病理
時間生物学や生理学の教えるところによると,人間の本能のデザインは生息のリズムという点においても自然と合致しておらず,人間をフリーランさせると24時間よりは長く(25時間という説がある)なる(Aschoff,1965)という
つまり,われわれは生理的には24時間+αの周期的な変化を営んでおり,地球の生活に馴化するためにはわれわれはみな,1日にα時間急がなければならない。この「ずれ」あるいは[遅れ]を解消するためには,光による脳内メラトニンの変化作用という生理学的なZeitgeber(同調因子)だけでは不十分であって,文化社会的なZeitgeberが不可欠である。われわれは朝起床してから夕刻就床するまで,三度の食事などの慣習的生活行動だけでなく,仕事に集中する時間と休息する時間の配分などのさまざまな個人的な行動様式によって,ともすれば遅れがちな内的時間感覚を修正し,1日のうちにαだけ時間を稼いでいるのである。
生活の実態に即して言えば,一般に,われわれは起床や就寝などの生理的リズムから,勤務の開始や終了などの社会的に設定されている制度的リズムに至るまで,外的に時間を区切られ,強いられた生活行動の切り替えの中で生活している。人間にとっての快適な生活リズムとはこれらの外的に与えられた生活行動の切り替えのタイミングを,いわば自分の習慣として内化し,自分が望んだものとして再規定することによって得られるものだと考えられる。この外的に強制されるリズム(というよりは反復性)を自分の習慣として捉え返す働きを担うのが個人の文化的Zeitgeberだと言うことができるだろう。
つまり,文化的Zeitgerberとは,外的な周期的「区切り」が有する無機的な反復性を人間の個人の行動様式の中に有機的に取り込むための慣習および個人的行動様式なのである。
うつ病の病理学にとっての問題はこれらの行動様式が個人の生きるスタイル,働くスタイルとして,個人のself-esteemを支えているという重要な価値を有するので,そのZeitgeberとしての機能的価値の方が認識されていないことである。うつ病の発病過程ではまさにこの個人のスタイルが喪失されるのだが,このことは,仕事上の失敗や対人関係における困難の中で自信を失い,self-esteemを低下させていくという心理学的文脈によってだけでは理解されない。
患者が自覚する個別的な失敗が起こる以前に,うつ病による生体のエネルギーや機能水準の低下によって,職業人・生活人としての自分なりの手順や流儀,つまり個人的な行動様式がしだいに維持されなくなるという生理学的事態が密かに進行し,このことが生み出すさまざまな小さな滞りや遅れが自信喪失を生むという生理-心理学的文脈も考慮されなければならない。そして,その個人の行動様式がZeitgeberとして機能していることを考慮すれば,この事態が生活リズムの失調に直接つながっていることは明白である。次々に外的に要請される時間的区切り(仕事の締め切りなど)から遅れがちになり,この「遅れ」を「挽回しようとして,できない」という焦燥感を伴った努力が続けられた後に,「体調」を崩すという形で事例化するうつ病は多い。このような観点から見れば,うつ病発症の素質は,外的リズムからの影響を受けやすく,またいったん被ったリズムの乱れすなわち遅れを解消して,自分の本来の生活リズムを取り戻す復元力か弱いこと(可塑性があること)にあるのではないかという推論も成立するだろう。
V 「現代型うつ病」の治療-うつ病のリズム論的治療論-
われわれは「現代型うつ病」という窓口を通してうつ病の病理を見直し,治療論に生かしていこうと考えている。現段階でわれわれが治療を行う際の基本的認識としているのは,①生活リズムという視点からすれば,うつ病素質者の病理の中心は(生活)リズムの可塑性である,②うつ病発病によるもっとも重大な損失は,個人の文化的様式すなわち生活人,職業人,趣味人としてのスタイルの喪失である,の2点である。
生活リズムという視点から見れば,うつ病の回復とは個々の生活行動がスムーズに営まれ,リズムを形成する要素となり,最終的には,患者固有の生活リズムが組織化されていくことである。入院治療を例にとると,患者は当初,病棟のタイムスケジュールやルールそして薬物療法などによって,いわば生理機能のレベルでの強制的リズムの中に置かれるのだが,病棟での生活行動に患者なりの趣向やスタイルが備わってくるにつれて,今度は,それらが睡眠や食事のあり方すなわち生理的レベルのリズム的規則性を再規定していくようになる。いわば生理的リズムと生活文化や様式によるリズムとの間の関係が逆転して,文化様式的リズムが生理的リズムを支配するようになる。これがうつ病の生活リズムという面での治癒過程である。そこで,この過程を促すための治療的アプローチを工夫していくことが課題となる。以下の治療法の工夫は別所ですでに論じた(1998)ことだが,簡単にまとめて解説する。
1.気分状態よりも体調を問題にする
うつ病発病直後の治療初期には,うつ病に陥ったことを認めて現実生活での挽回の努力を断念し,身体的心理的疲弊を解消することが基本となることは言うまでもない。しかし,従来のように,うつ病の治療全体を通じて「休養」を促し続けることは本来のリズムの回復のためにはむしろ不利であって,身体的休息がとれたら速やかにリズムの形成を治療目標に設定する方がよいと思われる。そこで,われわれは「休養」を「体を休める」ことに限定せず,疲弊状態を解消した後はむしろ病前の日常生活で日中行われていた「快適な」活動を(探し出して)推奨するようにしている。このことによって昼と夜,活動と休息のリズムの形成を促し「体調」の好転を期すのである。
われわれは一つひとつの生活行動がスムーズに,抵抗なく生活の一部として遂行される度合いを評価するために,「気分はどうですか」と聞くのでなく漠然と「体調はどうですか?」と尋ね,その次に個々の生活行動のどれが楽しめたか,スムーズに行えたかを聞くようにしている。とくに,「体調」という言葉で問う理由は第1に,うつ病からの回復時に,「気分状態が爽快である」と端的に気分状態に言及する患者は案外少なく,それよりも「体調がよくなった」という表現のほうが多少実感に近いのかもしれないこと,第2に,多かれ少なかれ強迫性の成分をもつうつ病患者に自分の気分状態をつまり自分の心理をチェックしようとする習慣を促さないですむこと,第3に,「体調」という言葉には,円滑な生活行動に含まれているリズム性,すなわち毎日の生活行動の反復性がリズムに乗っているように感じられることが含意されていること,第四に,生活行動レベルに含まれる快適な体験を発掘するきっかけとなること,などによる。
治療においては焦りの感情を生みだしがちな「遅れを取り戻そう」という意識を避け,「気持ちのいい活動を選び出して,それらが創り出すリズムで生活すること」に強調点を置く。そして,1日の中でそのような一連の活動がどの程度順調に継起的に生じているかを見る指標として「体調」を用いるわけである。
2.「小さな」楽しみを重要視する
一般に,うつ病患者にはなんらかの一領域に価値を限定し,その他の領域の価値を省みない傾向がある。つまり,人生を豊かにする,生き甲斐になる,人のためになるなどの大きな価値を追求し,多くは自分が行うべき責任を果たす活動に固執するあまり,その他の領域におけるもろもろの小さな価値には注目しない。そこで,治療的アドバイスとして,生きがいや充実を与えてくれるような大きな快楽を目指すのではないことを強調し,日常生活の中に織り込まれている「小さな快」に焦点をあてて,それらを享受できているかどうかに注目することを促す。
食事を例にとれば,朝食,昼食,夕食のそれぞれに違った様式,季節によって次々に移り変わる食材の季節感などに含まれている快に気づくように促すのである。このような「小さな快」は病前の患者さんの生活の中に含まれていたはずの快体験であるから,自分がどのような生活行動に楽しみを感じていたのかを改めて再確認してもらうのである。
3.その他の試行段階の治療的工夫
上述したように,われわれはみな自然の営みや社会的制度が要請するリズムから遅れているのであるが,うつ病素質者はこの「遅れ」を修正するのにより多くのエネルギーを要するものと思われる。彼らは常に社会のリズムに遅れ,リズムを喪失してしまう傾向が強い。「マイペース」は,社会的リズムとは一致しなくても,リズム自体を喪失してしまうことへの防衛となっている。したがって,われわれは,現段階では,彼らなりのペースをつかもうとする習慣的行動は,それがたとえ「硬化したリズム」であっても,基本的には容認する方がよいのではないかと考えている。しかし,この習慣的行動には反復-依存という依存の病理が関わっているので,ある程度の牽制が必要である。反復依存の色彩の濃い習慣的行動は本来的に無時間的な性質を有し,これはこれでリズムの喪失に至るからである。
また,発症年齢という点から見ると,マイベースを乱されても復元する力が十分に備わっている青年期には社会的リズムに合わせて生きることがかろうじて可能であったものが,次第にリズムの復元力が衰退して,うつ病を発症するのではないかという仮説も成立する。多くの職業人において,社会のリズムに遅れながら働いていても,ある程度の年齢に達し,そのような自分なりの働き方が周囲に許容されるようになれば,発病の危機を乗り越えて生活していくのであろう。いわば,私的リズムが社会的リズムに越境することがある程度許容されることで「遅れ」の解消という課題が不問に付されるのである。中年期以降の発病例では,患者の職場での個人的行動様式がある程度,周囲から容認されており,治療目標をこの個人的行動様式を取り戻すことに設定するのがよいと思われる。
しかし,「現代型うつ病」のように若くして発病した場合には,まだまだ働く個人的スタイルが周囲から容認されていないことが社会復帰にとっての大きな困難である。この意味で,社会復帰時には少なくとも制限勤務などの措置が必須となる。
おわりに
「現代型うつ病」は記述学的には制止主体が前景に立ち抑うつ気分が明瞭ではない病像であるが,このことは抑うつ気分が症状論的に二次的なものであることを意味しない。たしかに,制止症状によって日常のあらゆる行動が重い課題となってしまい,憂鬱になるというような反応性の成分をも抑うつ気分として採用するなら,二次的ということになるだろう。しかし,伝統的な精神医学における「生気性」(Schneider,1962,0rig.1946)という視点を参照すれば明らかなように,(生気的)制止と(生気的)悲哀感は本来一体のものである。とすると,「現代型うつ病」に見られる感情的成分は症状論的にどのように位置づけられるのであろうか。その手がかりは「生気性」概念に含まれている「身体性」の病理にあると思われる。治療論で触れたように,うつ病を一貫して「からだの病気」と捉えて症状を説明することには,それなりの説得力がある。われわれは「現代型うつ病」の病像を通じてうつ病の身体性について論じることが次の課題だと考えているが,本稿では論じられなかった。他日を期したい。
文献
Aschoff J(1965)Circadianrhythms in man.Science148;1427-1432.
平井静也・鹿子木敏範(1957)臨床精神病理学.文光堂.
広瀬徹也(1977)「逃避型抑うつ」について.(宮本忠雄編)躁うつ病の精神病理2.pp.61-86,弘文堂.
松本雅彦・大森和宏(1990)感情障害とその周辺-「逃避型抑うつ・中年型」について-.精神医学,32;829-838.
松浪克文・山下喜弘(1991a)社会変動とうつ病.社会精神医学,14;193-200.
松浪克文(1991b)秩序志向性と反復.イマーゴ,2(11);67-75.
松浪克文・大前晋・飯田真(1998)気分障害の病態・心理.(広瀬徹也・他編)臨床精神.医学講座4気分障害.pp.61-87,中山書店.
Schneider,K(1962,0rig.1946)Klinische Psychopathologie,sechste,verbesserte Auflage.Thieme,Stuttgart.
Tellenbach,H(1976/orig.1961)Melancholie,dritte,erweiterte Auflage.Springer.Berlin,Heidelberg.(木村敏訳(1978)メランコリー.みすず書房)
気分変調症について 黒木俊秀
大変すばらしい論述で、参考になります。
*****
精神療法第32巻第3号
うつ病態の精神療法気分変調症
-精神療法が無効な慢性“軽症”うつ病?-
黒木俊秀
I 気分変調症という病名は馴染みにくい
正直、そう思います。
本号の特集「うつ病態の精神療法」では,「逃避型」「未熟型」「若年性」「恐怖症型」など,現代の日本社会におけるさまざまなうつ病のサブタイプをとりあげているが,これらの病態はいずれも重症化しないものの慢性的な経過をたどりやすい点で,世界標準の診断名である「気分変調症」と重複する。しかし,気分変調症という診断名は,DSM-Ⅲ(APA,1980)において感情(気分)障害のカテゴリーに位置づけられて以来,四半世紀以上を経た今もわが国の精神科臨床にはいまだ定着していないのではないかと思われる。それは,同じくDSM-Ⅲにおいて新たに登場し,いまや広く人口に膾炙するようになった「パニック障害」や「外傷後ストレス障害(PTSD)」,あるいは「社会不安性障害(社会恐怖)」などの病名と比べると対照的である。精神医学の専門誌でも,うつ病の特集は頻繁にあっても,気分変調症にスポットを当てた特集は稀ではないだろうか(欧米においても chronic depression の特集号で扱われることが多いようである)。
定着・浸透しないのには理由があるだろうということで、次のような話に展開します。
必ずしも操作的な診断基準に厳密であることを要請されない臨床の現場では,とりあえず「うつ病」という包括的な病名をつけておけば事足りるという事情もあろう。しかし一方では,「うつ状態」ではあっても「うつ病」と診断をつけるにはどうかと思う,とはいえ「軽症うつ病」というほどには治りやすくはなく,年余に及ぶ経過をたどっており,治療者にしてみればむしろ重い症例をみた際,いまだ旧来の「抑うつ神経症(depressive neurosis)」や「抑うつ性人格(depressive personality)」の診断のほうが患者の見立てに適していると考えながら,あえてカルテの保険病名欄には「気分変調症」と表向きの診断名を記す精神科医も少なくないのではないだろうか。
そう思います。
よく知られているように,DSM-Ⅲの作成にあたっては,1970年代までの力動精神医学の語法から身体医学的(いわゆる生物学的精神医学の)語法への転換が意図されたが,いくつかの妥協も余儀なくされた。結果的には,病因論を一旦棚上げにして,従来の精神疾患の分類カテゴリーに変更を加えることで,その生物学的基盤を示唆するに止める,すなわち薬物療法の対象となることを示すという方針がとられた。気分変調症(性障害)においては,慢性に経過し,しかし「大うつ病」の診断基準を満たすほど重症ではない抑うつ症候群をすべて包含しながらも,「いわゆる抑うつ神経症」という但し書きを付けるという,いわぱ場当たり的な処置がとられたようにみえる。これに対しては,「心因性あるいは神経症性の感情障害あるいは感情障害の神経症的部分については,わずかにDysthymiaという軽症型の記述概念で暗示するに止めている」と笠原(1991)が批判した通りであろう(気分変調症の概念確立に貢献したAkiskal(2001)自身は,笠原による日本のうつ病患者の記述にも注目していた)。その後,DSM-Ⅲ-R(APA,1987),DSM-IV(APA,1994)と改訂を経るに従い慢性化,あるいは部分寛解した大うつ病や双極性障害は含まれないようになったが,最初にDSM-Ⅲにおいて大うつ病の除外診断かのような曖昧な診断基準が提示されたおかげで,日本の精神科医にとって気分変調症の概念がいささか馴染みにくいものになってしまったことは否めない。
そうです。
そもそも,なぜdysthymiaの邦訳が「気分変調症」なのであろうか。dysthymiaとは,語源的にはギリシャ語で「機嫌が悪い・気持ちがふさぐ」ことを意味し(Hippocratesによるメランコリー気質の記載にまで遡るらしい),1863年にKahlbaumがメランコリーの慢性型として記述したのが最初であるという(Freeman,1994)。ならば,「気分変調」の字義が「気分が乱れている」というニュアンスを与えるよりは,気分循環症cyclothymiaと対照をなすために「気分低調症」や「気分不調症」,あるいは「うつ停滞症」としても良かったのではないだろうか。邦訳にあたってどのような経緯があったかは不明だが,Schneiderの高弟,Weitbrechtが1950年代に提唱したendoreaktive Dysthymie に対してすでに「内因反応性気分変調症」の訳語があてられていた(「気分失調症」!とも訳された)ことを受け継いだのではないかと推測する。
気分低調症は分かりやすいですね。
夭逝した精神病理学者,樽味(2005)は,今日の青年期うつ病にみてとれる不全感と倦怠,回避と他罰的な感情が,従来の執着気質を病前性格とする中高年層の「メランコリー親和型」うつ病とは異質の精神病理より構成されることを指摘し,「ディスチミア親和型」うつ病と命名した(気分変調症に併発したdouble depressionのことではない)。これは,同様の非典型的なうつ病に対して提唱された「逃避型」あるいは「未熟型」うつ病の概念とも重なるが,うつ病患者に対するより洗練された臨床上の要請として(それらの患者に休養と服薬を勧めるだけではしばしば慢性化し,それこそ気分変調症へと「くすんでゆく」ことを樽味は看破した),従来の「メランコリー」に対比させて,DSMのdysthymiaという用語を利用したものである。樽昧の命名にはわが国の精神科医がdysthymiaという言葉によって喚起するいメージ(ある種の「弱力性」を示唆する)がよく反映されている。それは,前述したような,「うつ病」よりもいまだに「抑うつ神経症」や「抑うつ性人格」の診断名のほうがしっくりとくると感じる臨床現場の感覚にも通じている。
そうかな?
本稿では,まずDSM体系の枠組み,すなわち標準的な精神医学の範疇において,dysthymia概念の登場以降,明らかになった病態の輪郭とその治療選択について概説する。そのうえで,われわれの日常臨床の現場に視点を据えてdysthymiaに対する精神療法の在り方を論じたいと思う。著者自身は,dysthymjaは「ディスチミア」と英語読みするほうが適切と考えるが,ここでは教科書的に「気分変調症」の呼称で統一しておく。結論を先に述べると,現在の操作的診断基準に従って臨床の現場より抽出される気分変調症は大うつ病やパーソナリティ障害と明瞭な境界線を描き得ず,さまざまな異種の障害や問題を背景にした症候群に違いない。しかしながら,その中核群は,恐らくは内因性感情障害と生物学的に共通する素因を有すると考えられ,決して「軽症」の抑うつ状態ではない。このことをまずは肝に銘じて患者と対峙すべきであろう。
「dysthymiaの中核群は,恐らくは内因性感情障害と生物学的に共通する素因を有すると考えられ,決して「軽症」の抑うつ状態ではない。」ということで、考えてみましょうということになります。
Ⅱ 気分変調症の概念はいかに生じたか-Akiskalの研究より-
やっぱり、アキスカル先生。
Akiska1(2001)によれば,気分変調症の概念は決して目新しいものではなく,すでにKraepelinが生涯続く抑うつ的な気質が躁うつ病と関連することを認めていたという。その気質は,躁うつ病患者家系の非発症者にみられ,また躁うつ病患者の病前にも観察されることを指摘していた。しかし,その後,そのような持続性の非精神病性うつ状態は,抑うつ神経症あるいは抑うつ性人格と呼称され,神経症もしくはパーソナリティ障害圏内の病態に長く位置づけられてきたことは周知の通りである。これに対して,Akiskalら(1978)が,1970年代にテネシー州メンフィスにおいて抑うつ神経症と診断された患者の詳細な追跡研究を行った結果,従来の抑うつ神経症の疾病概念を覆す注目すべき結果が得られた(といっても,当時,大抵の臨床医は薄々感づいていたことであったが)。すなわち,3~4年後の再評価時には36%がメランコリー型うつ病を発症し,さらにその半数(全体の18%)が双極性障害へ診断が変わっていた。一方,性格的な特徴が引き続き認められた者(すなわち抑うつ神経症)は24%に過ぎなかった。それゆえ,「神経症性うつ病の概念を診断として用いることは臨床的にはもはや意味がない」と断じた。この他にも抗うつ薬に対する反応性,感情障害の家族歴,REM睡眠潜時などの生物学的指標等において内因性の感情障害と同様の傾向を示すことを明らかにし,それまでの内因性うつ病対神経症性(心因性)うつ病という二項対立的な診断分類に異議を唱えた。以上のように,Akiskalは,慢性軽症うつ状態と内因性感情障害が生物学的に連続している可能性を主張したのである(彼-内戦が勃発する前にレバノンから米国に移住した精神科医である-はKraepelinismの継承者であると自認している)。一方,DSM-Ⅲでは,Akiskalらの研究成果を受けて,慢性軽症うつ状態に対して気分変調症性障害の診断名を冠し,感情障害のカテゴリーに含めたものの,前述したようにかなり包括的な診断基準を提示してしまった。そのため,気分変調症にはさまざまな異種の疾患が含まれてしまうことが指摘された(古川,1998)。
「慢性軽症うつ状態と内因性感情障害が生物学的に連続している可能性」です。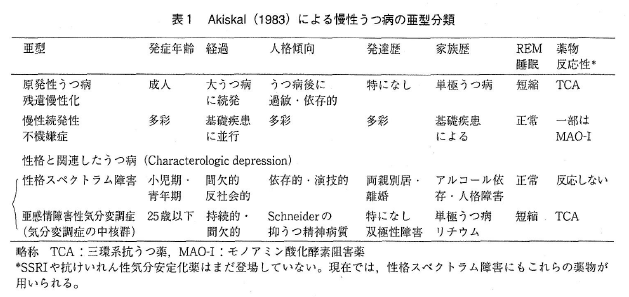
そうした批判に答えるために,Akiskal(1983)は,慢性うつ病の亜型分類を提唱し,そのなかで彼の考える(狭義の)気分変調症の概念を改めて強調した(表1)。それによると,慢性軽症うつ状態のうち,原発性の大うつ病や感情障害以外の精神障害,あるいは難治性の身体疾患に続発したうつ病態を除外した一群であり,典型的には思春期から青年期早期かけて徐々に発症し,数年の経過を経た後,大うつ病エピソードが重複する。しかし,大うつ病が軽快しても,病前の抑うつ状態に戻るだけである。こうした患者の大部分(慣習的に‘characterologic depression’と呼称している)は薬物療法に反応しにくいと指摘されてきたが,Akiskalは薬物反応性の相違からさらに2つの亜型に分類した。そのひとつは,性格スペクトラム障害(character-spectrum disorders)であり,この群の患者は薬物療法によって目ぼしい効果が得られず,うつ病エピソードが併発してもメランコリー型の特徴を示さない。むしろ,依存性,演技性,反社会性,あるいはシゾイドなどのパーソナリティ障害の傾向が認められ,薬物やアルコールに依存する傾向もあり,家族内にも同様の傾向がみられる。他方は,亜感情障害性気分変調症性障害(subaffective dysthymic disorders)と呼ぶー群であり,抗うつ薬や気分安定化薬に反応するが,時に軽躁状態が誘発される。双極性障害の家族歴もしばしば認めることから,この群の一部は双極性障害と生物学的背景を共有するとAkiskaiは考えた。Akiskalの主張を受け入れてDSM-Ⅲ-R(APA,1987)およびDSM-Ⅳ(APA,1994)では,早発性(early onset)と晩発性(late onset)の2つの亜型分類を設けたが,代わりにペシミズム,失快楽,罪悪感といった認知的症状,すなわち神経症的な表現は弱くなった。DSMⅣでは付録に診断基準の代案(表2)を収載し,代案の表現のほうが「気分変調症の特徴を表しているようである」として,議論が紛糾したことを匂わせている。
そうです。
表2
Akiskal(1983)による慢性うつ病の亜型分類
DSM-Ⅳ(APA,1994)の付録に収載された気分変調症性障害の診断基準Bの代案。
本文の診断基準よりも「気分変調症性障害の特徴を表わしているようである。しかしながら,これらの項目が気分変調性障害の公的な定義に採用されるためには,それを裏付ける証拠がさらに必要である」とコメントされており,症状によって気分変調症を特徴づけることの難しさを物語っている。
2年間の抑うつ期問中に以下の3つ,またはそれ以上が存在する。
1)低い自尊心または自信,または不適格であるという感覚
2)ペシミズム,絶望,または希望を失っている
3)全般的に興昧や喜びを失っている
4)社会的なひきこもり
5)慢性的な倦怠感,または疲労感
6)罪悪感,過去をくよくよ考える
7)苛立ちの自覚,または過度の怒り
8)低下した活動性,効率,生産性
9)思考の困難か集中力低下,記憶力低下,または決断困難に反映される
Ⅲ 気分変調症は,性格か,病気か
その後の気分変調症の研究の成果は,おおむねAkiskalの見解を支持している(The WPA Dysthymia Working Group,1995;古川,1998;Akiskal,2001)。操作的診断基準を用いた疫学調査では,一般人口における有病率は約3%であり,大うつ病と同様,女性に多い。大うつ病の併発はきわめて高率であり,実に90%を越える患者がいずれかの時点で大うつ病を重複するという。この傾向は,早発性の気分変調症患者に強い。身体症状を訴えて,プライマリケアを受診する患者の中にも気分変調症は多く紛れており,慢性疲労症候群や筋線維症のような機能的身体症状群(心身症)を併発するものが多いことも明らかになった。一方,パーソナリティ障害も高率に併発しやすく,その率は大うつ病よりも高いと報告されている。注目すべきは,気分変調症が決して「軽症うつ病」ではなく,重大な社会機能の障害を生じるという点であろう。それは大うつ病単独の患者よりも重いとする報告もあるし,double depressionの患者の回復は大うつ病単独の患者よりも芳しくないことが指摘されている。無論,予後は良いとはいえず,大部分の患者の症状が自然軽快することはないとされる。
予後は良いとはいえず、ということです。
以上のように,抑うつ神経症や抑うつ性人格に代わる疾患概念として登場した気分変調症であったが,現在に至るも,大うつ病およびパーソナリティ障害との境界は明確にはなっていない。とくに後者は早発性気分変調症との鑑別が実際上は困難であり,そもそも両者を区別することに意味があるのかという議論も生じた(古川,1998)。DSM-IV(APA,1994)では付録に抑うつ性人格障害の研究用基準案も掲載し,一応の区別を示唆しているが,「(気分変調症の)人格障害の特徴を評価することが困難である」と認めざるを得ない。結局のところ,気分変調症とは異種の病態を背景にした慢性抑うつ症候群としか語れないことになるが,このようなことは操作的診断基準に依拠する限りは常に起こりうるものであろう。
「気分変調症とは異種の病態を背景にした慢性抑うつ症候群としか語れないことになるが」ということで、ここからまた議論が始まるわけです。
Akiskalも,そのようなジレンマを強く感じているのであろうか,さらに多くの生物学的指標を取り込んで,気分変調症をより生物学的な感情障害のスベクトラムのなかに位置付けようとしている(Niculescu&Akiska1,2001)。とくに近年の彼は,‘soft bipolar spectrum’の概念によって,躁うつ混合状態や抗うつ薬による躁転,あるいは非定型うつ病のみならず,情緒の不安定性で特徴付けられる境界性パーソナリティ障害までも双極性障害と生物学的に連続する広範なスペクトラムに包含しようとしており(Akiskal,2005),うつ病親和的な性格(character)も生物学的な気質(temperament)に起因するとみなすことで「性格か病気か」の命題を乗り越えようとしているようにみえる(他方,幼小児期の喪失体験や養育環境の影響を無視しているわけではない)。それには,1990年代以降,パーソナリティ障害の治療にも選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)や抗けいれん性気分安定化薬が広く用いられるようになったことが影響しているのかもしれない(したがって,薬物反応性の有無による気分変調症の亜型分類は修正された)。
どのように理解したらいいかも、難しい。
いずれにせよ,Akiskal(2001)が再三強調する典型的な気分変調症(先に亜感情障害性気分変調症と呼んだ亜型を最近ぱ‘lethargic’もしくぱ‘anergic’typeと呼んでいる)とは,Schneider(1934)が抑うつ精神病質depressive Psychopathieとして記述した常に陰うつで,悲観的に考え,自分を責め,何事も楽しむことのできない厭世的・懐疑的な人物像と等しく,生物学的にはKraepelinが着目したようにメランコリー型大うつ病や双極I型障害と共通する素因がパーソナリティ的特性として表現されたものである。彼らは,堅苦しく,生真面目で,融通が利かず,抑制の強い人たちであり(Schneider(1934)は,同時に易刺激的で不機嫌なタイプや邪推深く関係妄想を抱きやすい夕イプもあることを指摘しているが),自我の発達が未成熟なパーソナリティ障害とは本来区別されるという。なお,Akiskal(2001)は,Tellenbachのメランコリー親和型性格や下田の執着気質にも無私のごとく仕事に没頭する点において気分変調症と共通する要素を認めているふしがあるが,この点についてはわが国の精神科医とは見解が異なる(最近,津田(2005)がうつ病とパーソナリティの関連についてAkiskalのsoft bipolar概念に言及している)。
なるほど。
IV 気分変調症に対する精神療法は無効か
無効ということはないだろうけれど。
その概念には不明瞭さがいまだ残るとはいえ,DSMⅢにおいて気分変調症が感情障害のカテゴリーに位置付けられて以来,その治療は,三環系抗うつ薬,モノアミン酸化酵素(MAO)阻害薬,およびSSRIなどの抗うつ薬による薬物療法が主流である。その有用性は統制された無作為化試験(RCT:randomized controlled trial)の結果からも支持され,ガイドラインは長期間の投与に耐容しうるSSRIを第1選択薬として推奨している(古川,1998;Akiskal,2001)。しかも,気分変調症も大うつ病の場合と同じ程度の十分な用量を投与する必要がある。興味深いことに,benzamide系化合物,amisulpride(欧州で認可されている非定型抗精神病薬)の有効性も報告されており(抗うつ薬と比較して効果の発現が速いらしい),わが国の抑うつ神経症の臨床では同じ化合物に属するsulpirideがお馴染みであったことが思い起こされる(Akiska1,2001)。
効く薬もあるということ。
一方,気分変調症に対する精神療法単独の有効性については,否定的な研究結果が多く,とくに薬物療法と比較した場合に劣性は明らかである。しかし,それは必ずしも心理社会的介入を否定するものではない。実際,薬物療法が有効とはいっても,抗うつ薬による気分変調症の寛解率はせいぜい50~60%であることを考えると,とくに治療抵抗性症例において心理社会的な支持は不可欠である。1995年に世界精神医学会のワーキンググループが発表した論文では,そのことを踏まえて,気分変調症に対する心理社会的治療は単独よりも抗うつ薬と併用しながら用いるべきであると提言している(The WPA Dysthymia Working Group,1995)。
抗うつ薬と併用しながら、ですね。もともとが長期に渡る疾患ですから、簡単にはいきません。
ところが,薬物療法と精神療法の併用が薬物療法単独よりも果たして本当に有効なのかについて,近年の研究は懐疑的なデータを示している。AmowとConsantino(2003)は,気分変調症に対する薬物療法と精神療法の併用効果について検討した4つの研究を紹介しているが,なかでももっとも規模が大きい研究は,Browneら(2002)が報告した700名を超える気分変調症患者に対するsertraline(日本は未認可のSSRI),12週間の対人関係療法,および両者の併用療法のRCTである。対象患者はプライマリケアを受診した者から組み込まれ,1/3がdouble depressionであった。治療は6ヵ月間実施され,以後,18ヵ月間の自然経過が評価された結果,治療終了の6ヵ月の時点で反応率は対人関係療法単独が47%,sertraline単独が60%,両者の併用が58%であり,2年の時点でも同様の傾向を認めた。この他に比較的小規模な研究結果(併用されたのは,対人関係療法,グループ認知行動療法,認知対人関係グループ療法など)とも併せて,ArnowとConsantino(2003)は,抑うつ症状の軽減に併用療法が確かに優れているとはいえないけれども,脱落率や機能的改善,あるいは治療抵抗性症例に関しては,なお併用療法の有用性を示唆している。
厳しいですね。
気分変調症の精神療法研究の第一人者であるMarkowitzら(2005)も,大うつ病を重複していない‘pure’な気分変調症患者に対する対人関係療法,短期支持的精神療法,sertraline,およびsertralineと対人関係療法の併用療法の効果を比較したが,やはりsertrahe単独と対人関係療法との併用療法との間に有意の差は認められなかった(反応率は56~57%)。ただ併用療法のほうが薬物単独と比較して寛解率がわずかに高いことと対人的機能に改善がみられたことから,「薬物が気分変調症治療の第一段階,精神療法はなお重要な補助的な治療である」と結論している。
こうなると、精神療法とは何か、となりますね。
以上のような,主に北米より報告された研究は,薬物を処方する医師と精神療法を実施する臨床心理士が完全にスプリットした状況下で行われたものであることに注意しておきたい。米国では,大部分の精神療法の担い手がすでに精神科医から臨床心理士,看護師,あるいはソーシャルワーカーヘと移っていることを反映しているのだが,スプリットした治療構造下に薬物療法と精神療法を並行して行っても真の意味での併用療法といえるのだろうかという疑問が起こる。そもそも慢性の経過をたどり社会的機能の低下も深刻な気分変調症に対して期間限定の短期精神療法である対人関係療法や認知行動療法の効果を計ること自体に無理があるのではないか。実は,これらの研究デザインは,米国の医療を支配しているマネジッドケアの現況と深く関わっており,精神療法の併用に関して否定的なデータであるにもかかわらず,なお著者がその有効性にこだわっているあたりに,彼らの苦衷がうかがえる。「マネジッドケアは患者の話をただ傾聴するという精神療法の基本すら認めない」と米国の精神療法家の嘆きは深い(Clements et al,2001)。
期間限定の短期精神療法は当然、dysthymiaとは相性がよくないわけです。
V われわれは気分変調症にいかに対応すべきか
できることも限られていますが。
幸いわが国の精神科医は,まだ薬物療法と精神療法とを一個人の中で統合できる立場にある。佐藤ら(1998)は,気分変調症に対して精神療法が必要な理由について,①高率に併発するパーソナリティ障害への対応,②抗うつ薬の効果が必ずしも十分ではないこと,③病因論的に異種の病態であることを挙げているが,これに加えて気分変調症が決して「軽症」とはいえないことを考慮すると,実際の治療の現場においては薬物療法と精神療法とを切り離して考えるわけにはゆかないであろう。
そうです。
ここでいう精神療法とは,広義のそれを意味し,治療全体の土台をなす非特異的な治療促進因子として機能しうる要素である。とくに強調したいのは,薬物療法を支える基本的な精神療法的態度の重要性であり,現実には治療者-患者関係のありよう(ラポール)が薬物のプラセボ効果として反映される(黒木,2005)。故樽味(2005)は,慢性うつ状態に対する薬物処方が,しばしばさまざまな抗うつ薬と抗不安薬による多剤併用へと発展し,必然的にいわゆる薬理学的彷徨の様相を呈しはじめると,それが患者の心的弾力性の風化を促してしまう(結果として彼らの認知的症状をさらに強化してしまう)危険性を指摘した。それを予防するのが,彷徨の途中に差し挾まれる「精神療法的補完作業」(たとえば,「主役は抗うつ薬ではなく,あくまで受療者自身であること」を躁り返し確認することなど)であると樽味は説いたが,プラセボ効果が精神療法的補完作業を担うと願うことは無理だろうか。いずれにせよ,初診時の処方をめぐる患者との対話において薬物療法が彼らの自尊心をさらに貶めないという処置と確認をしておくことが,その後の薬理学的彷徨の弊害を最小限に食い止めるコツかもしれない。すでに薬理学的彷徨の末に荒野より立ち現われたような患者の場合はどうするか(大学病院では,その種の紹介患者が少なくない)。その場合は彷徨の終結準備,すなわちとりあえず減薬を提案することができるであろう。しかし同時に,これまでの彷徨の遍歴をただの徒労であったと要約せぬこと,薬理学的履歴の調査を患者との共同作業として行うこと,さらに抗うつ薬の減薬・中止に伴う離脱症候群を予防することなどの配慮が必要である(慢性うつ状態に対する薬物療法では,向精神薬の耐性や依存,離脱症状に関する知識を身に付けておきたい)。
まあ、あまり勇ましいことは言えないという現状です。
気分変調症が異種の病態を背景とした症候群であることは,前述した通りであるが,その推定される病因・病態別の治療的対応はまだ確立していない。著者は,意外と先に述べたAkiskalの生物学的な見解が役立つのではないかと考えている。まずは彼が提唱するsoft bipolar spectrumに該当するような症例の存在に注意しておくと良い。その診断と治療に関しては,これまた図らずも,最近,神田橋(2005)が達人の極意を教示しており,是非参考にされたい。氏によれば,双極性障害の患者は「気分屋的に生きれば,気分は安定する」のであり,自己の感情を言語化するような内省行為は不得手である。一方,Akiskalのいう気分変調症の中核群へはどう対応したら良いのだろうか。患者は,下田の執着気質やTellenbachのメランコリー親和型性格に通じる極めて堅苦しい頑固さをパーソナリティ的特性として表現しており,他人との情緒的な交流が苦手である。しばしば過度の責任感を担い,自責的になる。彼らとの面接は重苦しく,治療者に耐え難い閉塞感をもたらすが,そういう場合は「貧乏性ねえ」とやさしく揶揄して一息つく。しかし対話によって喜びや楽しみの感情を誘発しようとしても成功することはなく,事実,彼らは自身の生活においても休息や娯楽,気分転換に馴染まない。ならば,仕事に没頭させ,他には目もくれず,罪悪感を内向させないですむような厳格な生活スタイルを維持できるように環境を整えることが次善の策ではないかと思う。無私・忘我の生活である。しかし,それでは先々なんらかの心身症(仮面うつ病)を起こしてくるのではないかという懸念もある。dysthymiaからalexthymiaへの移行では洒落にもならない。したがって,理念的にはその中間を狙って,自分の心身の状態よりも仕事そのものの意義や価値を彼らが夢中で語り,かつ体への労わりも忘れないという状態を治療目標に描いてみてはどうだろうか。
なかなか。
中核群の患者がSSRIを服用していると,時に職場でのテンションが高くなりすぎて,周囲の人々との衝突が増えることがある。薬物誘発性の軽躁状態であるが,放っておくと自己の地位や既得権に異様に執着しはじめ,被害的,他罰的な言動が目立つようになるので,牽制する必要が出てくる。患者自身も,大抵はその状態を心地良くはないと感じている。自分が怖いという者もいる。自覚的には「躁うつ混合状態」という表現がしっくりとくる様子なのは,SSRIによって心身がバランス悪く駆動されている感覚があるからであろう。これもあらかじめ副作用として生じてくる可能性を言及しておくと,予防しうる。最後に,Akiskalが示唆したように気分変調症は生物学的には内因性感情障害と連続性を有している可能性があるという点を改めて強調しておきたい。したがって,面接の場面でも患者の身体的表現型の評価が重要である。それは,目の輝き,皮膚の色つや,口唇の乾き具合,声の高さ,手掌の発汗,歩き方や立ち居振る舞いなどに現われるので,見逃してはいけない。これらの「生物学的指標」は回復の指標となる。認知的症状や社会的機能の程度ではなく,意識的努力によって変化させがたい指標をもって,病の回復の度合いを測定すべきであると神田橋(1986)も教えている。謝辞:神庭重信教授(九州大学大学院医学研究院)のご助言とご指導に深謝致します。
本当なら樽味先生が書くはずの原稿だったのだろうなあ。
文献
Akiskal HS(1983)Dysthymic disorder:psychopathology of proposed chronic depressive subtype.Am J Psychiatry 140;11-20. Akiskal HS(2001)Dysthymia and cyclothymia in psychiatric practice a century after Kraepelin.J Affect Disord 62;17-31.
AkiskalHS(2005)The dark side of bipolarity:detecting bipolar depression in its pleomorphic expressions.J Affect Disord 84;107-115.
Akiskal HS,Bitar AH,PuzantianvRetal(1978)The nosological status of neurotic depression:a prospective three-to four-year follw-up examination in light for the primary-secondary and unipolar-bipolar dichotomies.ArchGenPsychiatry35;756-766. AmericanPsychiatricAssociation(1980)Diag-nosticandStatistical Manual of Mental Disorders third edition.American Psycatric Press,Washington DC.
American Psychiatric Association(1987)Diag-nosticandStatisticalManuaLofMental Disrders third edition revision.American PsycatricPress,Washington DC. American Psychiatric Association(1994)Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders fourth edition.American Psycatric Press,Washington DC.(橋三郎・大野裕一染矢俊幸訳(1996)DSM-Ⅳ精神疾患の診断・統計マニュアル.医学書院)
ArnowBA,ConsantinoMJ(2003)Effectiveness of psychotherapy and combination treatment for chronic depression.J Clin Psycho 159:893-905. Browne G,Steiner M,Roberts J et al(2002)Sertraline and/or interpersonal psychotherapy for 325 patients with dysthymic disorder in primary care:6 month comparison with longitudina 12-year follow-up of effectiveness and costs.J Affect Disord 68;317-330.
Clements NA,MacKenzie KR,Griffith JL et al(2001)Psychotherapy by psychiatrists in a man-aged care environment:must it be anoxymoron?J Psychother Pract Res 10;53-62. FreemanHL(1994)Historical and nosological aspects of dysthymia.Acta Psychiatr Scand 89(supp1383);7-11.
古川壽亮(1998)気分変調症.(松下正明・浅井昌弘・牛島定信,他編)臨床精神医学講座4気分障害.pp.257-272,中山書店.
神田橋條治(1986)うつ病の回復過程の指標.精神科治療学,3;355-360.
神田橋條治(2005)双極性障害の診断と治療一臨床医の質問に答える一.臨床精神医学,34(4);471-486.
笠原嘉(1991)外来精神医学から.みすず書房.
黒木俊秀(2005)薬物療法における精神療法的態度の基本一処方の礼儀作法-.臨床精神医学,34(12);1663-1669,
MarkowitzJC,KocsisJH,BleibergKLeta1(2005)A comparative trial of psychotherapy and pharmacotherapy for “pure” dysthymic patients.J Affect Disord 89;167-175.
Niculescu AB,Akiskal HS(2001)Proposed endophenotype of dysthymia:evolutionary,chnical and pharmacological considerations.Mol Psychiatry6;363-366.
佐藤哲哉・成田智拓・平野茂樹,他(1998)気分変調症の精神療法.臨床精神医学,27(6);653-663.
SchneiderK(1934)Psychiatrische vorlensungen fur Arzte,Georg Thiemeverlag,Leipzig.(西丸四方訳(1977)臨床精神病理学序説.みすず書房)
樽昧伸(2005)現代社会が生む’‘ディスチミア親和型’・.臨床精神医学,34(5);687-694.
津田均(2005)うつとパーソナリティー.精神神経学雑誌,107(12);1268-1285.
The WPA Dysthymia Working Group(1995)Dysthymia indinical practice.Br J Psychiatry166;174-183.
The Medical Management of Depression NEJM2005 REVIEW ARTICLE-2
※MOOD STABILIZERS
※気分安定薬
Lithium is an antimanic agent and, as a mood stabilizer, prevents the recurrence of mania or depression. It may be superior to placebo for bipolar depression but not for major depression.
翻訳 リチウムは抗躁薬であるが、気分安定薬として躁状態・うつ状態の再発を予防する。また、双極性障害(躁うつ病)に対して偽薬に比べて優れているが、大うつ病には効果が無い。
(6-1)気分安定薬は双極性には有効、しかし大うつ病再発防止には効果がないという意味。わたたしはあると思っているけれど、どうなんでしょう。
Lithium is an effective augmenting agent, and the condition of roughly half the patients who do not have a response to a single antidepressant improves when lithium is added.
翻訳 リチウムは附活剤として効果が高い。単独の抗うつ薬を服用しても反応が無い患者に対して、抗うつ薬にリチウムを加えるとおよそ半数の患者に改善が見られる。
The anticonvulsant lamorrigine reduces glutamatergic activity and has been used as an augmenting agent in major depressive disorder and for treating and preventing depressive relapse in bipolar disorder.
翻訳 抗けいれん薬lamorrigineは、グルタミン酸の作用を低減させるため、大うつ病の治療附活剤として、また両極性障害(躁うつ病)のうつ状態の再燃予防に使用されている。
Lamouigine can induce severe skin reactions, including the Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis, although gradual dose titration appears to reduce the risk.
翻訳 Lamouigine はスティーブンス・ジョンソン症候群(皮膚粘膜眼症候群)、表皮壊死といった重大な皮膚の反応を誘発することがある。しかし、投与量を次第に増やしていくことで、リスクを低減できるようだ。
(6-2)漸増法です。
Other mood stabilizers, including the anticonvulsants valproic acid, divalproex, and carbamazepine, are used to treat mania in bipolar disorder.
翻訳 その他の気分安定薬として、抗けいれん薬のバルプロ酸、divalproex やcarbamazepineが双極性障害(躁うつ病)の躁病治療薬として使用されている。
(6-3)躁病にブレーキをかけるには、薬がとても有効です。
Divalproex or valproate may prevent a recurrence of bipolar depression.
翻訳 Divalproxあるいはvalproateは、双極性障害(躁うつ病)の再発を予防する。
(6-4)予防的服用が大切だと、最近は強調されています。躁病は社会生活も人間関係も破壊するからです。
※ANTIPSYCHOTIC AGENTS
※抗精神病薬
Typical antipsychotic agents (e.g.,chlorpromazine,fluphenazine, and haloperidol) block the dopa-mine D2 receptor, whereas "atypical" antipsychotic agents (e.g., clozapine, olanzapine,risperidone,quetiapine, ziprasidone, and aripiprazole), like nefazodone, act as 5HT2A antagonists.
翻訳 定型的な抗精神病薬(例:chlorpromazine、fluphenazine、haloperidol)は、ドーパミンD2受容体を阻害し、一方、非定型抗精神病薬(例:clozapine,、olanzapine、risperidone、 quetiapine、 ziprasidone、aripiprazole)は、nefazodoneと同じように5HT2A拮抗薬として作用する。
Antipsychotic drugs are combined with antidepressants to treat depression with psychotic features.
翻訳 抗精神病薬が抗うつ薬と併用されるのは、精神病性の症状を伴ううつ病を治療するためである。
(6-5)精神病性の特徴とは、多くの場合、現実把握の低下症状を指しています。たとえば、幻覚や妄想です。
Atypical antipsychotic drugs are also used for treatment-resistant major depression and bipolar depression.
非定型抗精神病薬もまた、治療抵抗性の大うつ病と双極性障害(躁うつ病)に利用されている。
Although atypical antipsychotic drugs have a more favorable side-effect profile with respect to parkinsonism, akathisia, and tardive dyskinesia,some pose other risks, such as drug-induced arrhythmia, diabetes, weight gain, and hyperlipidemia.
しかし、非定型抗精神病薬の方が、パーキソニスム、アカシジア、遅発性ジスキネジア、その他薬剤誘発性不整脈、糖尿病、体重増加、高脂血症等の副作用のリスクは低めである。
(6-6)非定型薬は第二世代とも呼ばれ、副作用が少ない。
================
OVERALL THERAPEUTIC STRATEGY
================
治療の総合的戦略
Patients who present with the complex, variable clinical picture of major depressive disorder and bipolar disorder may require a multimodal approach that includes pharmacotherapy, education, and psychotherapy.
翻訳 患者が、大うつ病と両極性障害(繰うつ病)の入り組んだ様々な臨床像を示す場合、薬物療法、教育的指導、そして精神療法を含む多方面の方法が必要となるだろう。
Treatment requires the monitoring of clinical responses, including suicidal ideation or behavior and side effects.
翻訳 治療に際しては、自殺念慮や自殺に及ぶ行動、そして副作用を含む臨床的反応を観察する必要がある。
To encourage adherence to therapy, education of both patients and their families must emphasize the fact that the effects of antidepressant medication take time.
翻訳 治療への専念を促すため、患者の両親と家族に対して、抗うつ薬治療の効果が現れるまでには時間を要することを特に啓発すべきである。
The average treatment duration for an episode is six months, and there is a high risk of future episodes; thus, both patients and their families must be made aware of these facts.
1つのエピソードについては平均で治療期間6ヶ月を要し、将来エピソードが再発するリスクも高い。そこで、両親および家族はこうした事実を認識する必要がある。
The treatment plan should take into account the patient's previous treatment outcomes,the mood-disorder subtype, the severity of the current episode of depression, the risk of suicide,coexisting psychiatric and somatic conditions, non-psychiatiic medications, and psychosocial stressors.
翻訳 治療計画立案については、以前の治療経過、気分障害のサブタイプ(亜型)、現在発生しているエピソードの深刻さの程度、自殺のリスク、付帯する心身両面の状態、他に服用している精神病薬以外の薬、そして心理社会的ストレスなどの側面を考慮すべきである。
(6-7)stressor ストレス原因 ですが、日本語としては上記でよい。
There are three phases of treatment: the acute, continuation, and maintenance phases.
翻訳 治療には急性期、継続期、維持期の3相がある。
()いつもの図です。
※ACUTE PHASE
※急性期治療
The treatment goal in the acute phase is remission--- the induction of a state with minimal symptoms ---in which the criteria for a major depressive episode have abated and marked improvement in psychosocial functioning has occurred, on the basis of reports from the patient and the patient's family.
翻訳 急性期治療の目的は、寛解である。寛解とは、症状が最小限にとどまり、大うつ病エピソードの診断基準に挙げられた症状が緩和され、社会心理的機能に顕著な改善が見られ、それが患者自身と家族の報告に裏付けられることである。
(7-1)remission 寛解:一時的部分的改善 recovery 回復:完全改善
Figure 2 presents a basic algorithm for the acute phase of treatment of a major depressive episode in a patient with major depressive disorder, on the basis of the current literature and treatment models, which were developed as part of several large-scale studies of treatment algorithms.
翻訳 図2に、大うつ病エピソードの急性期における基本的な治療アルゴリズムを示す。これは、既存の文献および治療モデルを土台にしており、治療アルゴリズムに関する大規模な研究活動数種の一部として開発されたものである。
Hospitalization is needed if symptoms are severe (dehydration, delusion and psychomotor agitation) and there is a risk of suicide (previous suicide attempts or current plan for suicide).
翻訳 重症例では入院治療を要し、脱水症、妄想、精神運動性激越といった症状の場合があげられる。また自殺の可能性を有する(前回自殺未遂にとどまったか、現在自殺を計画している)場合も入院が必要である。
Antidepressants are the treatment of choice of moderate-to-severe episodes of depression.
翻訳 抗うつ薬は、中等度~重篤なうつエピソードの治療選択肢である。
Since most antidepressants that are used for major depressive disorder have similar effectiveness, the choice of medication depends on depressive symptoms (psychotic or suicidal), the history of responses to medication (including that of first-degree relatives), medication tolerability, adverse effects, and the likelihood of adherence.
翻訳 大うつ病に用いられる治療薬のほとんどが同等程度の効果を持っているので、うつの症状(精神病性または自殺に直結する症状)、治療への反応履歴(第一親等の家族を含む)、薬物治療への耐性、有害副作用、そして治療方針を遵守するかどうか、といった患者の状況と傾向に応じて選択の余地がある。
Other considerations are concurrent medical conditions, use of nonpsychiatric drugs, and cost of medication. Table 3 lists suggested first-line medications.
その他考慮すべき点は、合併症の有無、非精神病薬使用の有無、医療費などである。表3は、第一選択薬の推奨リストである。
SSRIs and other newer antidepressant drugs with a greater safety margin constitute first-line medications for moderate-to-severe depression,particularly for outpatients, for patients treated by primary care physicians, and for patients with cardiovascular disease.
翻訳 SSRIおよびその他の新規抗うつ薬は、安全域が非常に広く、中等度~重篤なうつ病の治療手段としては優先度が最も高い。特に、外来患者、プライマリー・ケアの医師から治療を受ける患者、心血管系疾患が併存している患者に第一選択である。
Depression in persons 65 years of age or older generally requires relatively Iow doses of antidepressants, and SSRIs appear to be preferable to nonselective norepinephrine-reuptake inhibitors, such as tricyclic antidepres-sants, because of the lower risk of anticholinergic and cardiovascular side effects.
65歳以上のうつ病患者に対しては、通常比較的低用量の抗うつ剤を投与する。たとえば三環系抗うつ薬のような非選択性NRI(ノルエピネフリン再取り込み阻害薬)よりもSSRIが適するようだ。抗コリン作用と、心血管系疾患への副作用のリスクが低いからである。
The acute treatment phase usually lasts 6 to 10 weeks (Table 1).
急性期の治療期間は通常6~10週間である。(図2)
The patient should be evaluated weekly or twice monthly by the treating physician until substantial improvement is achieved.
症状が十分に改善するまで、患者は毎週あるいは隔週ごとに治療者の診察を受けるべきである。
The decision to increase the dose, change the medication, or add another mediations is modeled in Figure 2.
翻訳 薬の用量増加、種類変更、種類追加の判断については、図2に示す。
Outpatients at risk for suicide should not be given large supplies of antidepressant drugs that could not be lethal in the case of an overdose (Talbe1.)
翻訳 自殺のリスクがある外来患者には、大量の抗うつ薬を処方すべきではない。飲み過ぎた場合にも死に至らないようにするためである。(表1)
表2
図2
表3
※MONITORING TREATMENT RESPONSE
※うつ病薬物治療に対する反応のモニタリング
The response of patients to treatment requires systematic monitoring.
うつ病の薬物治療に対する患者の反応については、系統的なモニタリングを要する。
A practical set of criteria include nonresponse, a decrease in baseline severity of 25 percent or Iess; partial response, a 26 to 49 percent decrease in baseline severity; partial remission, a 50 percent or greater decrease in baseline severity (residual symptoms); and remission, an absence of symptoms.
翻訳 実践的なモニタリング指標としては、「無反応」(基準となる重篤な症状の減少率が25%以下)、「部分的反応」(基準となる重篤な症状の減少率が26~49%)、「部分的寛解」(基準となる重篤な症状の減少率が50%以上、これを残遺症状と呼ぶ)、そして症状が見られなくなる「寛解」が含まれる。
Options for the evaluation of the response include rating scales (Table 4) and the global judgment of the treating clinician on the basis of patient and family reports.
その他の評価基準としては、表4に示す評価尺度や、患者とその家族の申告に基づき治療者が下す総括的判断基準がある。
The best predictors of outcome are improvements in anhedonia (loss of pleasure), psychomotor retardation, and loss of interest, which are assessed by asking questions that go beyond "depressed mood."
翻訳 予後の最重要因子は、無快感症(喜びの喪失)、精神運動抑制、興味の喪失である。これらを普通の「抑うつ感」のインタビューよりも細かく質問して評価する。
Suicidal ideation or risk of suicide, pessimism, guilt, and other changes in cognition may take Ionger to improve than vegetative symptoms, such as alterations in sleep or appetite.
翻訳 自殺念慮あるいは自殺のリスク、悲観的な考え方、罪悪感その他の認知症状の改善が認められるのは、睡眠パターンや食欲の変化といった自律神経的症状に比べやや時間を要するだろう。
If initial treatment is not tolerated or the response is unsatisfactory (< 50 percent improvement), a change in medication or approach is indicated.
初期治療に耐性が無いか反応が不十分(改善率50%未満)であれば、薬剤または治療方法の変更を要する。
Thirty to 50 percent of patients have substantial residual symptoms after adequate first-line treatment (Table 3).
30~50%の患者は、適切な第一選択薬(表3)による治療を受けた後でも、症状は残存する。
If there has been no improvement after four weeks of treatment with an adequate dose of a given medication, the ultimate response is almost certainly going to be inadequate.
いずれかの薬剤を4週間適量服用した後、何の症状改善も認められない場合には、患者の最終的な反応が思わしくないことはほぼ確実と見てよい。
Among patients receiving the same dose of a given drug, blood levels may vary by as much as a factor of 20 because of individual variations in drugmetabolism.
ある薬剤を同量服用しても、患者によっては血中濃度に20倍の差が生じることもある。これは、薬剤の代謝に個人差があるためである。
Such variations are caused by genetic differences, the effects of drugs on liver enzymes,and the effects of aging.
こうした差は、個人間の遺伝子的差異、薬剤が肝酵素に与える影響、年齢などによって生じる。
Before medications are switched, consideration should be given to the diagnosis, the medication dose, and adherence to the drug regimen.
投与する薬剤を変更する前に、下された診断、投与量、そして服用方法・用量を遵守したかどうかを検証しなければならない。
Coexisting medical conditions, alcoholism, substance-use disorder, or the use of nonpsychianic medications such as beta-blockers may also underlie treatment failures.
合併症、アルコール依存症、薬物乱用、あるいはβブロッカーといった非精神病薬の使用も、うつ病薬物治療の失敗につながるおそれがある。
Nonresponse to medication requires a treatment change (Fig. 2).
薬物治療に対し無反応の場合は、治療方法を変更する必要がある(図2)。
Switching to an antidepressant from a different pharmacologic class minimizes polypharmacy and reduces the risk of adverse drug interactions and side effects seen with combinations of similar drugs.
薬理学的分類を異にする抗うつ薬への変更は、多剤併用を避け、類似の薬剤による好ましくない相互作用と副作用のリスクを最小限にする。
The disadvantage of switching agents may be the loss of a possible partial response from the initial drug and a delay in the onset of antidepressant action from the second.
薬剤変更のデメリットを挙げるなら、最初に投与した薬剤の部分的な効果が失われること、そして変更後の抗うつ薬の効果が出るまでに時間がかかることだろう。
The initial medication may need to be tapered to avoid symptoms of discontinuation, such as nausea, headache, and sensory changes.
最初の薬剤の投与量は漸減する必要がある。これは、吐き気、頭痛、知覚変化といった中断症状を避けるためである。
()薬は急に増やしたり急に止めたりしないで、だんだん増やす、だんだん減らすようにしましょう。例外もありますが。
Switching from irreversible MAOIs to most other agents requires a minimum drug-free period of two weeks.
不可逆的MAOI(モノアミン酸化酵素阻害薬)から、他の薬剤へ変更する際には最低2週間の断薬期間を要する。
Switching to a new antidepressant from the same pharmacologic class is one option.
薬理学的分類が同じグループの中の新しい抗うつ薬に変更するのもひとつの方法である。
Patients who do not have a response to one SSRI have a 40 to 70 percent chance of having a response to a second SSRI.
あるSSRIに無反応だった患者のうち、40~70%は、2番目に採用するSSRIに反応を示す可能性がある。
Another approach is the use of two antidepressants from different classes with complementary mechanisms of action to avoid loss of a partial response to the first medication.
もう一つのアプローチは、相互補完的な作用機序を持つ2番目の抗うつ剤を異なる薬理学的分類から選び、初めに服用した薬の部分的な効果を無駄にしないことである。
This approach increases the risk of drug interactions and new side effects, as well as the cost of treatment.
ただし、このアプローチの場合、薬物間相互作用、新たな副作用、治療費の増加といったリスクも伴う。
Augmenting antidepressant medication with other agents, so-called augmenting agents, that may enhance antidepressant efficacy avoids the transition from the first to the second antidepressant and builds on partial remission.
いわゆる附活薬剤によって、抗うつ薬の効果を補う方法であれば、1番目から2番目の薬剤への移行に際して効果が失われるのを防ぎ、部分的な寛解の足がかりともなる。
Lithium is a first-line augmenting agent.
リチウムは、附活薬剤の第一選択薬である。
Two to four weeks of lithium treatment are needed before the response can be assessed.
リチウムの効果を評価するには2~4週間を要する。
Lamotrigine is an effective augmenting agent for patients who do not have an adequate response to fluoxetine.
Lamotrigineはfluoxetineに十分反応しない患者にとって効果のある附活薬剤である。
Antipsychotic agents may augment the response in nonpsychotic major depression.
非精神病性の大うつ病に関しては、抗精神病薬が附活薬剤としての効果を発揮するかも知れない。
Thyroid supplements have been advocated even in the absence of clinical hypothyroidism for the purpose of enhancing antidepressant action.
甲状腺サプリメントは甲状腺機能低下症ではない場合にも、抗うつ作用を増進させるものとして推奨されてきた。
Modafinil is a stimulant and as an adjunct may alleviate residual sleepiness and fatigue.
Modafinilは興奮誘発剤であるが、残存する眠気と倦怠感を軽減する補助薬剤としても機能する。
Mood disorders with delusions or hallucinations respond better to an antidepressant-antipsychotic combination than to either alone.
妄想や幻覚を伴う気分障害については、単一のどの薬剤よりも、抗うつ薬と抗精神病薬の組み合わせが良い反応を示す。
Some patients with this constellation of symptoms will require electroconvulsive therapy (ECT), and almost all must be treated initially as inpatients.
翻訳 妄想や幻覚を伴う気分障害の場合、ECT(電気けいれん療法)が必要となる人もいて、その場合にはほぼ必ず入院で治療を開始する必要がある。
Benzodiazepines are used as an adjunct for anxiety and insomnia in 30 to 60 percent of cases, and in that group improve response and reduce the frequency of treatment discontinuation.
Benzodiazepinesは不安と不眠の治療に際して30~60%の割合で補助薬剤として用いられている。そして、この治療を受けるグループでは、反応が改善し、治療中断が少なくなる。
However, the drugs cause sedation, psychomotor and cognitive impairment, memory loss, and dependence and withdrawal syndromes and are associated with increased rates of falls, fractures, traffic accidents, and death among the elderly.
しかしながら、この薬剤に起因して鎮静作用、精神運動および認知機能障害、記憶障害、依存、退薬症候群が起こり、転倒、骨折、交通事故、高齢者の死亡の増加につながる。
The adjunctive use of benzodiazepines should be of limited duration to avoid dependence, and these drugs should be used with caution in the elderly and those with a history of alcohol or drug abuse or dependency.
benzodiazepinesの補助薬剤としての使用は、依存症を回避するため使用期間を制限すべきである。また高齢者やアルコール症や薬物乱用・依存症の病歴を持つに患者については使用に注意すべきである。
表4
CONTINUATION PHASE
うつ病の継続期治療
The continuation phase of treatment, generally lasting six to nine months after the induction of remission, aims to eliminate residual symptoms,
restore the prior level of functioning, and prevent recurrence or early relapse.
継続期の治療は通常、寛解状態に入った後6~9ヶ月をかけ、残存症状の除去、以前のレベルまでの機能回復、そして再発あるいは早期の再燃を防止する目的で実施される。
Residual symptoms (partial remission) are strong predictors of recurrence, early relapse, or a more chronic future course.
翻訳 残存症状(部分的寛解)は、再発、早期再燃、あるいは将来にわたる慢性化の予後を予測する大きな手がかりとなる。
Treatment should continue until such symptoms have resolved.
治療はこれらの症状が解消されるまで継続すべきである。
Episodes lasting more than 6 months and psychotic depression require a longer continuation phase, up to 12 months.
6ヶ月以上続くうつエピソード、そして精神病的うつ状態の際には継続期は12ヶ月まで長期化する。
The same medications and doses used to achieve relief in the acute phase are used during the continuation phase.
継続期においても、急性期に用いられたのと同じ治療薬・同じ投与量が用いられる。
DISCONTINUATION OF TREATMENT
治療の中断
If there is no recurrence or relapse during continuation therapy, gradual discontinuation may be planned for most patients after at least six months of treatment.
継続期の治療中に再発や再燃が起こらない場合、大抵の患者については最短で治療の6ヶ月後から徐々に減薬することを計画できる可能性がある。
Early discontinuation is associated with a 77 percent higher risk of relapse as compared with continuation treatment.
継続期の治療を継続していた場合と比較して、早すぎる治療中断をすると、再燃のリスクが77%高くなる。
The tapering of medication over several weeks also permits detection of returning symptoms that require reinstitution of a fuII medication dose for another three to six months.
数週間にかけて治療薬を漸減していくと、一部の症状がぶり返すことがあり、その場合には薬剤を急性期用量のままでその後3~6ヶ月投与することが必要となる。
It also minimizes the discontinuation syndrome, which otherwise may last days or longer and consists of physical symptoms of imbalance, gastrointestinal and influenza-like symptoms,and sensory and sleep disturbances, as well as psychological symptoms such as anxiety, agitation, crying spells, and irritability.
また、この方法は断薬症候群を最小限に抑える。さもなければ、断薬症候群は数日あるいはそれ以上続く可能性があり、不均衡症候群や消化器系疾患、およびインフルエンザのような症状が起こり、さらに知覚障害と睡眠障害、不安・興奮・号泣・過敏性といった精神病的症状が起こることもある。
The discontinuation syndrome is sometimes called the withdrawal syndrome, erroneously implying drug dependence.
この断薬症候群はときに離脱症候群とも呼ばれ、薬物依存に関して誤って使用される用語でもある。
(14-1)焦ってやめていいことは何もないということです。6~12ヶ月を維持療法にあてるのが安全ということになります。再燃、再発の苦しさに比較すれば、慎重が得策です。
(14-3)continuation phase 継続期 再燃を防ぎつつ好調を継続している時期
meintenance phase 維持期 再発を防ぎつつ好調を継続している時期
MAINTENANCE PHASE
うつ病の維持期治療
Maintenance treatment for 12 to 36 months reduces the risk of recurrence by two thirds.
うつ病の維持期治療を12~36ヶ月行えば、再発のリスクは3分の2に減少する。
This approach is indicated for patients with episodes that occur yearly, who have impairment because of mild residual symptoms, who have chronic major depression or dysthymia, or who have extremely severe episodes with a high risk of suicide.
このアプローチがすすめられるのは、毎年のようにうつエピソードを発生する患者で、弱い残遺症状を伴う機能障害を持つ患者、あるいは慢性大うつ病や気分変調症の患者、または自殺のリスクが高く非常に深刻なエピソードを伴う患者の場合である。
The duration of maintenance treatment will depend on the natural history of the illness and may be prolonged or indefinite in the case of recurrent illness.
維持期の治療期間は病状そのものの自然経過によってきまり、延長されることもありし、再発した場合にははっきりと決められないことになる。
The first choice of medication for the maintenance phase is the antidepressant that brought about remission.
維持期治療における第一の選択肢は、寛解をもたした抗うつ薬である。
Lithium has no advantage over antidepressants for prophylaxis but may reduce the risk of suicide independently of its effect on mood.
リチウムは抗うつ薬を超える予防力を持たないが、気分に対する効果とは無関係に、自殺のリスクを減少させる。
Tricyclic antidepressants, SSRIs, MAOIs,and the newer antidepressants (mirtazepine and venlafaxine) all help to prevent recurrence.
三環系の抗うつ薬、SSRI、MAOIまた新規抗うつ薬(mirtazepine と venlafaxine)などはすべて再発防止の効果がある。
Medication tolerability is particularly important during the maintenance phase, because it affects patients' adherence to treatment.
維持期において特に大切なのは治療耐性である。なぜなら、患者の治療に対する忠実さに大きな影響をもたらすからである。
Stable patients should see a psychopharmacologist at intervals of three to six months while they are receiving medication.
安定している患者は精神薬理学者に3~6ヶ月に1回の割合で面会し、治療を受けるべきである。
It is important to monitor adherence and breakthrough symptoms so that problems are detected early.
大切なのは治療に対する忠実さを確認し「突破口症状」を監視することである。突破口症状を見張ることで問題を素早く発見する。
Patient and family education reduces treatment attrition and improves the outcome.
患者とその家族に対する啓蒙は投薬量低減に役立ち、よい治療結果につながる。
The Medical Management of Depression NEJM2005 REVIEW ARTICLE-1
以前勉強会で使ったものが出てきましたので、
ここに収録。
図は、どこにあるか、まだ分かりません。
*****
The New England Journal of Medicine
October 2005
掲載の論文
DRUG THERAPY:The Medical Management of Depression
を英語読解講座みたいに読んでいきます。
The New England Journal of Medicine は医学の世界では
トップジャーナル中のトップジャーナルです。
自然科学のネイチャーみたいなものでしょう。
精神医学や脳科学専門ではないので、最先端の発表というよりは、
かなり事実として確定された、確実で、学ぶべきことを
提供している感じがあります。
医学全般の雑誌なので、精神科関係が取り上げられる時は、
一般医に向けての啓蒙といった色彩になります。
本文
翻訳
解説
の順に並べます。
では試しに啓蒙されてみましょう。
REVIEW ARTICLE
翻訳 総説
(1-1)この論文は、2005年の時点で、124の重要な論文を点検し、主要な論点を網羅的にまとめたものです。従って、解説そのものは素っ気なく、詳しいことを知りたい人は原論文にあたってくださいということになります。
DRUG THERAPY
薬物療法
The Medical Management of Depression
うつ病の医学的治療
J.John Mann M.D.
From the Department of Neuroscience,
New York State Psychiatric Institute-
Columbia University College of Physicians
and Surgeons, New York.
この人が著者。そして所属。
RECCURENT EPISODES OF MAJOR DEPRESSION, WHICH IS A COMMON and
serious illness, are called major depressive disorder;depressive episodes that occur in conjunction with manic episodes are called bipolar disorder.
大うつ病は普通に見られる(common)と言ってよいほど頻度の高い疾患で、しかも時に重症になる。大うつ病エピソードを反復する場合に大うつ病と呼ぶ。うつ病エピソードに躁病エピソードを伴う場合には双極性障害(躁うつ病)と呼ぶ。
(1-2)
depression うつ病
major depression 大うつ病
episodes of major depression 大うつ病エピソード
depressive episodes うつ病エピソード
bipolar disorder 双極性障害(つまり躁うつ病のこと)
(1-3)日本語では「大うつ病」という言葉は耳慣れないものだろう。まあ当然、「本格的なうつ病」といった程度の意味である。depression(うつ)の内訳としては、major depression(長く深いうつ)、dysthymia(長いけどあまり深くないうつ)、normal depressive reaction(病気とは言えない落ち込み、短くて浅い)とひとまず簡単に考えておきましょう。「短くて深いうつ」もありそうですね。
(1-4)まず大枠から説明する。
精神病の分類については、アメリカの診断基準であるDSMやWHOの診断基準であるICDが有名である。(1)先天性のもの、たとえば先天性知能発達遅滞、(2)器質性のもの、たとえば脳血管障害、(3)中毒性のもの、たとえばアルコール症、(4)気分障害 mood disorder、たとえばうつ病 depression、(5)認知の障害、たとえば統合失調症 schizophrenia、などなどと分類される。
(1-5)ここですでに気づくように、異なったレベルの病因が混在している。原因によりまとめたもの、症状によりまとめたもの、など。
すっきりさせたいならば、もちろん、原因で分類したい。DNAが原因、外的物質が原因、後天性器質性疾患が原因、外傷が原因、老化が原因、などと押し切りたいところだが、ここでもすでに原因が混在してしまっている。外傷が老化を促進したりする。また、DNAに老化が重なり、さらに外的要因が重なって起こる場合などもあり、原因では分類しきれない。また、そもそも、原因不明の疾患の方が多い。DSMは原因を今後明らかにするために、統計資料を蓄積するための分類である。
(1-6)では方針を変えて、症状で分類できないかと考える。まず精神活動を分類して、思考、感情、知能、記憶、意識、知覚、意欲、さらには集団機能、行動統制、衝動制御なども考えることができる。そしてそれぞれの障害として病気を考えることができる。しかしすぐに行き詰まるのだが、何が人間の精神活動の構成要素であるのか、分解し尽くす方法がない。要素 element と見えたものが、他の要素の複合体であったりする。たとえば、感情がうつになると、記憶もはっきりしないし、意欲もなくなり、知覚も変化したりする。論理的に構成するには無理がある。
(1-7)行き詰まりを打開しようと、ある学者(クレペリン)は、原因でも症状でもなく、経過で分類しようと提案した。長期の経過で次第にレベルダウンするものと、すっかり元に戻るものとにまず分けようというわけだ。それは病気の本質を考える上でとても良い観点であったけれど、その人を死ぬまで観察しないと診断が確定しないというのでは、診断学とは言えないではないかと批判された。それもそうだ。
(1-8)そこで、ある程度寛容の精神を発揮して、現状で、多数決みたいに、まずまず合意できる線で暫定的に決めて、あとで少しずつ見直そうということになった。たとえば、同性愛という項目は、かつて病気であったが、現在は病気ではないとされている。
(1-8)そんなのがDSMなどの疾病分類、診断基準である。現在観察される症状で、分類できるだけ分類して、記録しておこうという精神である。たとえば、神経症は、ない。それは原因に言及しているから、不採用である。
(1-9)その中で、うつ病はどういう扱いかみてみよう。昔は躁うつ病、そのあとで感情病 affective disorder と呼ばれ、現在は気分障害 mood disorder と呼ばれている。
昔からメランコリーとかうつ病とか躁病は知られていた。ひとりの人が躁病になったり、うつ病になったりすることも知られていた。そこで躁うつ病と呼ばれた。躁うつ病のタイプとして、うつだけ繰り返すものをうつ病、性格傾向とも言える程度のものをメランコリーと呼んだ。しかし考えてみれば、それは感情の病気だろうということで感情病と呼ばれた。しかしながら感情というものはかなり高級で、もっと基底にある気分が問題なのだろうとの意見があって、現在では気分障害と呼んでいる。
(1-10)気分障害の下位分類としては、双極性障害 bipolar disorder 、大うつ病 major depression 、躁病 mania 、気分変調症 dysthymia などがある。双極性障害というなら単極性障害・うつ型、単極性障害・躁型と呼ぶべきなのだろうが、面倒なのでうつ病 depression 、躁病 mania と呼んでいる。躁病の軽いものを軽躁病 hypomania と呼ぶ。うつ病を大別して、重いものを大うつ病、軽くて長く続くものを気分変調症としている。軽くて短いものは病気ではない。短くて重いものはたいてい治ってしまっている。
(1-11)ここでやっと大うつ病の説明である。depression という言葉は英語では景気変動の言葉でもあるし、日常語の中で、 depressed などの形で使う。失恋したり、愛犬が死んだりすれば、depressed である。しかしそのことと、病気としての depression をどのように分けたらよいのだろう。昔ドイツでは生機的(Vitale)抑うつの概念などが言われた。哲学的すぎてアメリカ人には分からないらしい。現在では、DSMの診断基準に従って分類すれば、病気と、ライフイベントに対する反応を区別できるとしている。まず持続期間が違う点。さらには気分だけではなく、自律神経症状などの身体症状、たとえば、睡眠、食欲、性欲の異常がある点。また、認知症状、たとえば悲観的思考や注意集中困難などを伴う点。
長くなって大変なので次に行きます。
Major depressive disorder accounts for 4.4 percent of the total overall global disease
burden, a contribution similar to that of ischemic heart disease or diarrheal diseases.
大うつ病は、世界疾病負担(Global Burden of Disease:GBD)全体の4.4%を占めており、これは虚血性心疾患あるいは下痢疾患とほぼ同じ割合である。
(1-12)the total overall global disease burden の部分が分かりにくいと思います。これは、WHOによる“Global Burden of Disease(病気のグローバルな損失)”という報告に含まれるもので、社会全体に対する各疾患の「経済的損失」を推定したものです。
-----
各疾患における「疾患によってもたらされた損失」(DALYsを用いて測定 単位:100万) と「トータルに対する割合」
虚血性心疾患 8.9 9.0%
うつ病 6.7 6.8%
循環器疾患 5.0 5.0%
飲酒 4.7 4.7%
交通事故 4.3 4.4%
肺癌&上気道の癌 3.0 3.0%
痴呆&中枢神経系の変性疾患 2.9 2.9%
変形性関節症 2.7 2.7%
糖尿病 2.4 2.4%
慢性閉塞性肺疾患 2.3 2.3%
-----
年度が違うようで数字に差がありますが、この統計では、うつ病による社会全体に対する経済的損失は全疾患の6.8%です。虚血性心疾患についで第2位。うつ病が社会全体にもたらす経済的損失はかなり大きなものと分かります。ついでですが、飲酒、交通事故が大きな負担になっているのも分かります。
ここでDALYs (障害調整余命年数)とは、世界疾病負担(Global Burden of Disease:GBD)研究の中で採用された考え方。世界銀行(WB) と世界保健機関(WHO)が関与した。GBD研究の目的は、1)集団の疾病および障害の負担を定量評価、 2)資源配分のための優先順位付け、とのこと。国ごとの疾病負担研究、環境起因の疾病負担研究など、研究は拡大。
経済的損失とは、まず、医療費。働けなくなった場合、家計の損失。労働力としての社会の損失。また、教育投資ができなくなり、次の世代に影響が及ぶ。栄養不全になり病気にかかりやすくなる。家族の医療費を負担できくなり、家族は重病になる。年金を払わない。医療保険に加入しない。さらに社会の悪習に染まる、など。
The prevalence of major depressive disorder in the United States is 5.4 to 8.9 percent and of bipolar disorder, 1.7 to 3.7 percent.
米国における大うつ病患者の割合は5.4~8.9%、双極性障害(躁うつ病)は1.7%~3.7%と見込まれる。
(1-13)ここでは、ある瞬間に、米国の全人口の中で、大うつ病と診断される人の割合と思えばいいです。5%という数字はとても大きなものです。20人に一人です。疾病統計には、生涯有病率、発生率、罹病率などの表現があります。生涯有病率は、ある時点で全国民を調べ、過去または現在に大うつ病と診断される状態があったかどうかを調べ、そうした人の割合を計算します。
Major depression affects 5 to 13 percent of medical outpatients, yet is often undiagnosed and untreated.
医療機関での外来患者に占める大うつ病の割合は5~13%であるが、未診断・未治療のケースがしばしば見受けられる。
(1-14)大うつ病で通院している人、プラス、他の病気、たとえば胃潰瘍や狭心症で通院している人が、実はうつ病にかかっていた場合、の合計で、5~13%というわけです。20人に一人から10人に一人と推定されています。大変な数です。
Moreover, it is often undertreated when correctly diagnosed.
更に、的確な診断はされたものの、不十分な治療しか受けていない患者も多い。
(1-15)大うつ病患者全体の1/3しか治療を受けていないといわれています。これは自分がうつ病であることを、自分の精神的堕落、恥ずべきこと、やる気のなさ、最近ではマイナス思考のせい、などと思ってしまうからでしょう。やる気のなさとマイナス思考は大うつ病の結果です。治療すれば改善します。
The demographics of depression are impressive.
うつ病患者の統計には驚かされる。
(1-16)辞書には demography 人口統計学 demographics 人口動勢 などとあります。まあ、統計数字ですね。単数で学問の名前、形容詞にして複数にすると、研究の結果の統計数字のこととなるようです。impressive はここでは、あまりいい意味ではないですから、そのような日本語をあてたいですね。
Among persons both with major depressive disorder and bipolar disorder, 75 to 85 percent have recurrent episodes.
大うつ病並びに双極性障害(躁うつ病)患者の75~85%が再発エピソードを体験しているのである。
(1-17)これは皆さんの印象と一致していますか、それとも、意外ですか。意外ですよね。あんなに苦しんだのに、こんなにも多くの人が再発しているなんて。実際、患者さんは、寛解した直後は、二度となりたくないと思っています。しかし年月がたつと、やはり再発しているのです。
一応よくなったのは寛解 remission 、寛解期に悪化すれば再燃 relapse 。
本当に治ったのは回復 recovery 、回復後に悪化すれば再発 recurrence 。
recurrent episodes=recurrent episodes of major depression or mania
In addition, 10 to 30 percent of persons with a major depressive episode recover incompletely and have persistent, residual depressive symptoms, or dysthymia, a disorder with symptoms that are similar to those of major depression but last longer and are milder.
更に、患者の10~30%は大うつエピソードが完治せず継続したり、うつの症状が残ったり、「気分変調性障害」になったりしている。気分変調性障害は、大うつ病と類似の症状が長期かつ穏やかに続く疾患である。
(1-18)完全回復は難しいということです。これは性格傾向が関係しているだろうと推定されます。また、環境因子が関係していると推定されます。性格と環境が変わらなければ、再発しそうですよね。
Patients who have diabetes, epilepsy, or ischemic heart disease with concomitant major depression have poorer outcomes than do those without depression.
糖尿病、てんかん、あるいは虚血性心疾患患者が大うつ病を合併症として有する場合、その予後は合併症のない場合に比べ思わしくない。
(1-19)その点でも、大うつ病治療は大切です。たとえば虚血性心疾患患者はある種の喪失体験をしているわけですから。
The risk of death from suicide, accidents, heart disease, respiratory disorders, and stroke is higher among the depressed.
うつ病では自殺、事故、心臓疾患、呼吸器系疾患、脳血管障害が死因となるリスクが高い。
(1-20)うつ病で自殺に注意するのは当然としても、事故、その他の身体疾患でも数多く死亡します。免疫系が不活発となり、身体の回復力が衰退することも一因でしょう。うつ病のときに免疫系が充分に働かないことはよく議論されます。
Effective treatment of depression may reduce mortality or improve the outcome after acute myocardial infraction or stroke and lower
the risk of suicide.
効果的なうつ病治療は死亡者を減らし、急性心筋梗塞ならびに脳血管障害の予後を改善し、自殺のリスクを低減させる。
(1-21)そういうわけで、効果的うつ病治療を工夫しています。
Although no specific abnormalities in genes that control neurotransmitter or hormonal synthesis or release have been identified with certainty, both major depressive disorder and bipolar disorder are clearly heritable.19
どの遺伝子が神経伝達物質やホルモン合成・放出を調整しているか明らかにされていないものの、大うつ病も双極性障害も、明白に遺伝性がある。
(2-5)そうですね。やはり部分的にはDNAの問題だと思います。
How a genetic predisposition interacts with adverse early-life experience to alter brain development and lead to major depression remains unclear.
幼少期のつらい体験は脳の発達に影響し、大うつ病をひき起こすだろうと推定されるが、遺伝的傾向と幼少期のつらい体験はどのように相互作用しているのか、明らかにされていない。
(2-6)たとえば、PTSDやアダルトチルドレン、性的虐待の問題など。発育過程では、遺伝子と環境が密接に絡み合っているので、難しい。
Genes and srress are hypothesized to alter neuron size and the extent of neuronal processes, the production of new neurons,'and neural repair in major depression.
仮説によれば、遺伝子とストレスによって、神経細胞のサイズが変わり、神経突起の伸び具合が変化し、新しい神経細胞の産生が制御され、大うつ病に際しての神経修復が支配される。
(2-7)具体的なイメージとしてはそうなるわけです。
Elevated cortisol levels, which characterize some moderate-to-severe depressive states, may be associated with a reduction in hippocampal volume,which appears to be proportional to the duration of untreated depression.20
直訳 副腎皮質ホルモン濃度が上昇すると、中等度から重症のうつ状態になるのだが、副腎皮質ホルモン濃度は海馬の体積の減少に関係している。海馬体積はうつ病の未治療期間に比例するように見える。
翻訳 うつ病未治療期間が長いと海馬体積は減少し、それに応じて副腎皮質ホルモン濃度は上昇する。その結果、中等度から重症のうつ状態が生じる。
(2-8)海馬体積の減少は、いい話題です。海馬という構造の、体積くらいしか測定できないのですから、研究が進まないのも無理はないと納得できますね。
たとえば、鶏肉と牛肉を比較する時に、重さや体積をはかるって、あまりにも原始的だと思います。
This process has been likened to a loss of neurons similar to that mediated by corticosteroids in animal models of stress 21 and as suggested by magnetic-resonance-imaging studies that have reported lower levels of N-acetylaspartate, a neuronal marker, in depression.22
翻訳 このプロセスは動物のストレスモデルにおける副腎皮質ホルモンによって制御されるプロセスでもある。その類推で、このプロセスは神経細胞の消失と関係づけて考えられてきた。また、うつ病では神経マーカーのひとつであるN-acetylaspartateの濃度が低くなると報告しているMRI研究があり、そのような研究によってもこのプロセスと神経細胞の消失の関連が示唆されている。
(2-9)ストレス→副腎皮質ホルモン→問題部分の神経細胞消失または機能停止。
これは分かりやすいストーリーですね。副腎皮質ホルモンはストレスホルモンと呼ばれることもありました。
ここでの反論としては、ストレスにさらされた場合、神経細胞消失という不可逆性の変化を刻印してしまうのは、生体にとってとても不利ではないかということ。一時的退却のために機能停止するというのなら合理的と考えられる。たとえば、「死んだふり」。
Major depression in response to stressful situations has been reported as more common among persons harboring a variant in the proximal 5' regulatory region of the gene encoding the serotonin transporter protein (5-HTT) (the target of selectiveserotonin-reuptake inhibitors [SSRIs]) that modifies promoter activity.
直訳 セロトニン運搬蛋白(5-HTT)を制御している遺伝子の近位5'制御部位に変異が生じている人には、高ストレスに反応して生じる大うつ病がより多くみられると報告されている。
翻訳 セロトニン運搬蛋白(5-HTT)を制御している遺伝子に近位5'制御部位がある。ここに変異が生じている人には、高ストレスに反応して生じる大うつ病がより多くみられると報告されている。
(2-10)こんな報告もありますか。5HTとは、セロトニンのことです。
This variant, in the 5-HTT gene--linked promoter region (5-HTTLPR), modifies promoter activity and is associated with lower transcriptional effciency of the 5-H7T gene, ultimately leading to fewer copies ofthe messenger RNA encoding the serotonin-transporter protein.23
翻訳 この変異は、5-HTT 遺伝子関連促進部位(5-HTTZJIR)で起こっており、促進活動を制御する。そして、5-HTT遺伝子の転写効率の低下と関係している。最終的にはセロトニン輸送蛋白のエンコードをしているメッセンジャーRNAの複写を少なくしてしまう。
(2-11)このレベルの研究になっています。
This lower-expressing variant may be associated with the amygdala-mediated hyperresponsiveness of young children to frightened or frightening faces that can facilitate encoding of painfu1 memories, leading to stress sensitivity in adulthood.24
翻訳 このようなセロトニン関係物質の産生低下は、驚かせられた顔あるいは驚かせようとする顔に扁桃体内側部過剰反応性を有する幼少児に見られ、そういった過剰反応性は苦痛な記憶のエンコードを促進する。そして成人後のストレス過敏性につながる。そのような可能性がある。
(2-12)そういう仮説だということです。may be associated with てすから、全然決定ではありません。
This variantis also associated with a reduction of serotonin function in response to maternal deprivation in non-human primates, an effect that persists into adulthood.25
翻訳 こうした変異体はまた、非ヒト霊長類における母親剥奪への反応としてみられるセロトニン機能の低下に関係している。その低下は成人しても続く。
(2-13)ライフ・イベントと脳機能の関連をなんとかして突き止めたいわけです。将来は、恋人に振られた時の脳損傷部位が写真に写るでしょうか。
An induced functional deficiency of the 5-HTT protein that is confined to the early postmatal period in mice results in altered behavior when they are grown, indicating possible changes in brain development that affect adult behavior. 26
翻訳 マウスで出生早期に限定される5-HTTの、誘導された機能的欠損は、結果として、成長した時の行動変化をもたらす。これは脳の発達における変化の可能性を示しており、それは大人の行動に影響する。
(2-14)ライフ・イベントが脳の発達を変えてしまう可能性。逆に、「にもかかわらず」変わらない部分もあるはずだ。個人的にはそこに期待している。
Brain imaging has identified numerous regions of altered structure or activity in the brain during major depression, suggesting disordered neurocir-cuitry in a variety ofstructures, such as the anterior and posterior cingulate cortex; the ventral, medial,and dorsolateral prefrontal cortex; the insula; the ventral striatum; the hippocampus; the medial thalamus; the amygdala; and the brain stem.17
翻訳 脳画像研究は大うつ病の場合の多くの領域の構造変化や活動変化を明らかにした。たとえば、前部および後部帯状回、腹側、内側、背側前頭前野、島葉、腹側線条体、海馬、内側視床、扁桃体、脳幹。
(2-15)まだまだ検討段階とみています。
These brain areas regulate emotional, cognitive, autonomic, sleep, and stress-response behaviors that are impaired in mood disorders.
翻訳 こうした脳の領域が制御しているのは、情緒、認知、自律神経、睡眠、ストレス反応行動であり、気分障害の際には障害される。
(2-16)脳の各領域について、機能分担がいわれるわけですが、それほど簡単ではないと思う。現在我々の考えているモデルとしては、普段つかっているPCのCPUとかメモリーとかだろうと思うが、あやしい。
Studies with the use of positron-emission tomography indicate a decrease in serotonin transporters as well as altered postsynaptic serotonin-receptor binding in many of the same brain regions, suggesting altered circuitry congruent with serotonin-system abnormalities.27
翻訳 PETを使った研究によれば、セロトニン運搬体は減少しており、同時に、脳の多くの部分でシナプス後セロトニン-レセプター吸着が変化しており、このことは、セロトニンシステムの先天性奇形と一致する回路変化を示唆している。
(2-17)まだまだ不確かな話です。
Pathophysiolosical features of depression
翻訳 うつ病の病態生理学的な特徴
(2-0)うつ病の病因論の場合には、精神病理学と言われる学問が活躍してきました。普通の医学に比較すると哲学的です。決定的に違うのは、病理標本がなくて、顕微鏡も使わずに議論してきたこと。
従来、医学というのは、症状と顕微鏡所見を関係づけることがメインストリームでした。だから、精神病理学などは机上の空論扱いもされたのです。
ここで Pathophysiological 病態生理学的という言葉で取り上げているのは、医学の世界で標準的な、症状の成り立ちを病態生理学的に、つまり物質の原理で説明しようという意思であって、大変よい方向です。
しかしそれがどんなにはるかな道であるか、以下の解説で分かると思います。
The clinical picture of depression varies from one major depressive episode to another in any given patient.
翻訳 どんなうつ病患者の場合にも、臨床症状は、大うつエピソードから次の大うつエピソードへと経過する。
This suggests that major depression, despite it's various symptom profiles, may have a common underlying cause.
直訳 このことから分かるように、大うつ病には、症状は様々であるにもかかわらず、一つの根本原因があるのだろう。
翻訳 大うつ病にはさまざまな症状があるものの、上記のことからは、大うつ病の根底には同じ一つの原因があるのだろうと推定される。
(2-1)そうでしょうね。
If so, the clinically evident symptom profiles may result from differing patterns of neurotransmitter abnormalities in various brain regions.17
直訳 もしそうならば、臨床的に明かな症状の特徴は、さまざまな脳領域における神経伝達物質の奇形のパターン変異が原因だろう。
翻訳 もしそうならば、臨床症状の差は、さまざまな脳領域における神経伝達物質変異のパターンの違いが原因だろう。
(2-2)たぶんそうでしょう。
Consonant with such hypotheses, a host of deficiencies --- in serotonin, norepinephrine, dopamine, y-aminobutyric acid (GABA), and peptide neurorransmitters or trophic factors such as brain-derived neurotrophic factor, somatostatin, and thyroid-related hormones --- have been proposed as contributing to depression.18
直訳 この仮説によれば、うつ病に関係する欠損は、セロトニン、ノルエピネフリン、ドーパミン、GABA、さらには脳由来向神経因子、ソマトスタチン、甲状腺関連ホルモンのような、ペプチド神経伝達物質あるいは成長促進因子で起こっているのだろうと考えられた。
翻訳 この仮説によれば、うつ病の原因として、セロトニン、ノルエピネフリン、ドーパミン、GABA、さらには、ペプチド神経伝達物質あるいは成長促進因子(たとえば脳由来神経栄養因子、ソマトスタチン、甲状腺関連ホルモン)の異常が考えられてきた。
(2-3)このようないろいろな物質が検討されています。まだまだいろいろ発展しそうです。決定版はないようです。
Furthermore, overactivity in still other neurotransmitter systems involving acetylcholine,corticotropin- releasing factor, and substance P are thought to be implicated in depression.18
直訳 さらに、他の神経伝達物質系(アセチルコリン、副腎皮質ホルモン放出因子、サブスタンスPに関係するもの)の過剰活動がうつ病に関係していると推定されている。
翻訳 さらに、アセチルコリン、副腎皮質ホルモン放出因子、サブスタンスP、に関係する神経伝達物質系の過剰活動がうつ病に関係していると推定されている。
(2-4)活動低下と活動過剰があるわけです。でも、それが原因なのか、結果なのか、いつも不明です。
たとえば、うつになり始めた瞬間をきちんと検査できれば、物質的変化として「始まりに何があったか」を検証できます。でも、そんなことはできません。そこを突破する何かのアイディアが必要なようです。
DIAGNOSIS OF A MAJOR DEPRESSIVE EPISODE
翻訳 大うつ病エピソードの診断
Diagnosis of major depression is based on standard clinical criteria such as those published by the American Psychiatric Association.
翻訳 大うつ病の診断に用いられる標準的臨床診断基準としては、たとえばAPA(米国精神医学会)の診断基準がある。
(3-1)those= criteria
The criteria for the diagnosis of an episode include at least two weeks of depressed mood, loss of interest, or diminished sense of pleasure plus four of seven other features that are sufficient to cause clinically important psychological or physical distress or functional impairment.
翻訳 うつエピソードの診断基準としては、「抑うつ気分」または「興味の喪失・喜びの感覚の減退」、さらに他の7項目のなかで4項目、これらが二週間以上続くことがあげられる。7項目は臨床的に重要な心身両面の疲弊あるいは機能障害を引き起こすもので、次の7つからなる。
(3-2)that= seven other features
ここでは、DSM-4-TRの診断基準を参照して、訳文を補っていくこととする。
大うつ病性障害(大うつ病エピソード)
A 以下の症状のうち 5 つ (またはそれ以上) が同じ 2 週間の間に存在し、病前の機能からの変化を起こしている。これらの症状のうち少なくとも 1 つは、(1) 抑うつ気分または (2) 興味または喜びの喪失である。
注:明らかに、一般身体疾患、または気分に一致しない妄想または幻覚による症状は含まない。
1.その人自身の言明 (例:悲しみまたは、空虚感を感じる) か、他者の観察 (例:涙を流しているように見える) によって示される、ほとんど1日中、ほとんど毎日の抑うつ気分。
注:小児や青年ではいらだたしい気分もありうる。
2.ほとんど 1 日中、ほとんど毎日の、すべて、またはほとんどすべての活動における興味、喜びの著しい減退 (その人の言明、または他者の観察によって示される)。
3.食事療法をしていないのに、著しい体重減少、あるいは体重増加 (例:1 カ月で体重の 5%以上の変化)、またはほとんど毎日の、食欲の減退または増加。
注:小児の場合、期待される体重増加が見られないことも考慮せよ。
4.ほとんど毎日の不眠または睡眠過多。
5.ほとんど毎日の精神運動性の焦燥または制止 (他者によって観察可能で、ただ単に落ち着きがないとか、のろくなったという主観的感覚ではないもの)。
6.ほとんど毎日の易疲労性、または気力の減退。
7.ほとんど毎日の無価値観、または過剰であるか不適切な罪責感 (妄想的であることもある。単に自分をとがめたり、病気になったことに対する罪の意識ではない)。
8.思考力や集中力の減退、または決断困難がほとんど毎日認められる (その人自信の言明による、または、他者によって観察される)。
9.死についての反復思考 (死の恐怖だけではない)、特別な計画はないが反復的な自殺念慮、自殺企図、または自殺するためのはっきりとした計画。
B 症状は混合性エピソード(つまり双極性障害・躁うつ病のこと)の基準を満たさない。
C 症状は、臨床的に著しい苦痛、または、社会的、職業的、または他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている。
D 症状は、物質 (例:乱用薬物、投薬) の直接的な生理学的作用、または一般身体疾患 (例:甲状腺機能低下症) によるものではない。
E 症状は死別反応ではうまく説明されない。すなわち、愛する者を失った後、症状が 2ヵ月を超えて続くか、または、著明な機能不全、無価値観への病的なとらわれ、自殺念慮、精神病性の症状、精神運動抑止があることで特徴づけられる。
本文ではAの内容を伝えているようなのですが、微妙に違いがありますね。たとえば、Aの中の、1、2,5、8、9の5つの症状があったとすると、上記引用のDSM-4-TRでは診断該当となりますが、本文の説明では、診断に該当しないことになります。引用文献のリストをみると、著者はDSM-4を参照しているようです。しかしDSM-4も特に変わりはないようです。
DSM-4
大うつ病性障害(大うつ病エピソード)
A 以下の症状のうち5つ(またはそれ以上)が同じ2週間の間に存在し、病前の機能からの変化を起こしている。(これらの症状のうち少なくとも1つは抑うつ気分または興味・喜びの喪失である)
1 その人自身の訴えか、家族などの他者の観察によってしめされる。ほぼ1日中の抑うつの気分。
2 ほとんど1日中またほとんど毎日のすべて、またすべての活動への興味、喜びの著しい減退。
3 食事療法をしていないのに、著しい体重減少、あるいは体重増加、または毎日の食欲の減退または増加。
4 ほとんど毎日の不眠または睡眠過多。
5 ほとんど毎日の精神運動性の焦燥または制止。
6 ほとんど毎日の易疲労性、または気力の減退。
7 ほとんど毎日の無価値感、または過剰であるか不適切な罪責感。
8 思考力や集中力の減退、または決断困難がほぼ毎日認められる。
9 死についての反復思考、特別な計画はないが反復的な自殺念虜、自殺企図または自殺するためのはっきりとした計画。
B 症状は混合性エピソード(つまり双極性障害・躁うつ病のこと)の基準を満たさない。
C 症状の臨床的著しい苦痛また社会的、職業的、または他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている。
D 症状は、物質(薬物乱用など)によるものではない。
E 症状は死別反応ではうまく説明されない。すなわち愛する者を失った後症状が2ヶ月を超えて続くか、または著明な機能不全。無価値への病的なとらわれ、自殺念虜、精神病性の症状、精神運動制止があることが特徴。
著者と同じ意味の診断基準をみたような覚えもあるので、思い出したら報告します。
These features include a weight change of 5 percent or more in one month or a persistent change in appetite, insomnia or hypersomnia on most days, changes in psychomotor state, fatigue, feelings of guilt and worthlessness, diminished concentration and decisiveness, and suicidal ideation or a suicide attempt.
翻訳 一ヶ月で5%以上の体重変化または継続する食欲変化、おおむね毎日の不眠または過眠、精神運動状態の変化、倦怠感、罪責感と無価値感、集中力低下および決断力低下、そして自殺念慮と自殺未遂の7項目である。
(3-3)7つのはずなので7つにまとめる。これはDSM4、4-TRの内容と一致している。
First or "early" depressive episodes are often milder than are episodes of returning depression, and an earlier age at onset generally predicts a more severe course.
翻訳 第1回目の、あるいは「初期段階」のうつエピソードは、再発時に比べるとたいがい穏やかなものである。また、発症が早ければ早いほど、一般的に、より重篤な予後が予測される。
(3-4)発症が早いほど、環境ストレスよりは遺伝子が関係していると推定されます。
It is thought that early diagnosis and treatment may mitigate adverse effects of depression on education, career, and relationships.
翻訳 早期診断と早期治療が教育・職歴・人間関係上、うつ病のもたらす悪影響を緩和すると考えられている。
(3-5)放置しておくと社会適応が次第に低下しますから。
It is important to note that secondary depression that is similar to a primary mood disorder may be triggered by serious physical illness such as cancer, stroke, demyelinating diseases, epilepsy, or even marked anemia.
翻訳 ここでひとつ重要な指摘がある。原発性気分障害に類似する二次性うつ病の引き金としては、重篤な身体的疾患、例えばガン、脳血管障害、demyelinating diseases(脱髄性疾患)、てんかん、更には顕著な貧血があげられる。
(3-6)Primary一次性、原発性
secondary 二次性、続発性
Conversely, major depression may be missed when patients present to primary care physicians with predominantly somatic symptoms, including pain.
翻訳 一方、プライマリー・ケア医師が痛みなど身体的症状の治療に重点を置いた場合には、大うつ病が見落とされるおそれもある。
(3-7)その可能性は常に念頭に置くべきです。
Typically, symptoms such as anorexia, weight loss, constipation, disturbed sleep, anergia, loss of libido, vague aches and pains, and deficiencies in memory and concentration may result in a missed diagnosis, particularly if the patient does not spontaneously report low mood or other psychological symptoms, such as guilt, hopelessness, anxiety, suicidal ideation, or prior suicide attempts.
翻訳 拒食症、体重減少、便秘、睡眠障害、免疫力低下、性欲の減退、自律神経性疼痛、記憶喪失、集中困難のような場合には、うつ病の診断を見のがす結果になることも多い。特に罪悪感、無力感、不安感、自殺念慮、過去の自殺未遂について自発的に報告しない場合には見のがされやすい。
(3-8)Anergia 免疫系反応が減弱すること →免疫不全 で分かりやすいが、エイズを連想してしまうだろうか。免疫力低下とした。
Delusions of guilt and somatic illness complicate up to 14 percent of major depressive episodes, especially postpartum depression.
翻訳 罪責妄想と身体的疾患がある場合、患者は内面について自己申告しない傾向が強まり、大うつエピソードのうち14%にのぼると考えられる。とりわけ、産後うつ病で起こりやすい。
(3-9)補いすぎかもしれませんが、意味はこういうことだと思います。
Depressive episodes in bipolar disorder may be similar to those in major depressive disorder or may present as part of a mixed state characterized by distressing combinations of depression and mania or hypomania (irritability, racing thoughts, anxiety, suicidal thoughts, and aggressive impulses).
翻訳 双極性障害(躁うつ病)のうつ病エピソードは、大うつ病のうつ病エピソードに類似していることがあり、躁うつ混合状態の一部としてうつ病エピソードを呈していることもある。躁うつ混合状態の特徴は、うつ病と躁病またはうつ病と軽躁病といった、困難な混合であり、焦燥感、観念競合、不安、自殺念慮、攻撃衝動などを呈する。
(3-10)distressing combinations 悲惨な組み合わせ
Patients with bipolar disorder who present with a depressive episode may be misdiagnosed as having major depressive disorder because they may often underreport hypomanic and manic symptoms, perceiving such features to be closer to well-being than illness.
翻訳 両極性障害(躁うつ病)患者は軽躁状態や躁状態を病気ではなく普通の状態だと見なして過少申告することがしばしば見受けられるため、両極性障害(躁うつ病)の患者がうつ病エピソードを有する際には、大うつ病と誤診される可能性もある。
A family history of bipolar disorder can assist making the correct diagnosis.
翻訳 家族に双極性障害の人がいれば、診断の参考になる。
(3-11)訳しすぎ。でも、分かりやすくしましょう。
ANTIDEPRESSANT MEDICATIONS
翻訳 うつ病の薬物治療
(4-1)抗うつ剤薬物療法、ですね。
About half of moderate-to-severe episodes of depression will improve with antidepressant treatment.
翻訳 中等度~重篤なうつ病エピソードの約半分が薬物療法によって改善されると期待できる。
(4-2)たった半分?もっと治ると思いますが。
CIasses of antidepressant agents are defined by their mechanism of action (Table 1).
抗うつ薬は表1に示すとおり、その作用機序に従って分類されている。
(4-3)表1はこちら。役に立ちます。→アメリカで使用されている抗うつ剤の特性と副作用一覧
Many agents with effective antidepressant action amplify serotonin or norepinephrine signaling by inhibiting reuptake at the synaptic cleft (Fig. IA and IB).
翻訳 抗うつ薬の多くは、シナプス間隙で(神経伝達物質である)セロトニンまたはノルエピネフリンの再取り込みを阻害することで、神経信号伝達を増幅させる効果を持つ。(図1A・1B)
(4-4)神経と神経の間にはシナプス間隙があります。神経細胞の一方の端から他方の端までは電気信号で伝えられます。シナプス前部分で神経伝達物質が形成され、放出されます。ドーパミン、セロトニン、ノルアドレナリンなどが神経伝達物質です。それがシナプス後部分の受容体(レセプター)にくっついて、電気信号に変換され、さらに先に伝達されます。シナプス部分での伝達が終わると、使用された神経伝達物質は、シナプス前部分に回収されて、次回の放出に備えます。この回収される過程を再取り込み(reuptake)と呼んでいます。再取り込みが阻害されると、神経伝達物質がシナプス間隙に「溜まり」、信号が増幅されることになります。
ここでは触れられていませんが、レセプターの側の、ダウンレギュレーション、アップレギュレーションなども大切です。
The several classes of drugs include SSRIs, norepinephrine-reuptake inhibitors, and dual-action agents that inhibit uptake of serotonin and norepinephrine.
翻訳 薬の分類としては数種のSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)、ノルエピネフリン再取り込み阻害薬、および、セロトニンとノルエピネフリン両者の再取り込みを阻害する、二方面に作用する薬がある。
(4-5)dual-action agentsをどう訳せばいいでしょうか。「二方作動薬」などでもかっちりしていいかも。二股作動薬でもいいかも。
Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) inhibit monoamine degradation by monoamine oxidase A or B.
MAOI(モノアミン酸化酵素阻害薬)は、モノアミン酸化酵素AまたはBの分解作用を阻害する。
Other antidepressant agents antagonize a2-adrenergic autoreceptors with a resultant increase in the release of norepinephrine, antagonize 5-hydroxytryptamine2A (5-HT2A) receptors,or both.
その他の抗うつ薬としては、(1)α2-アドレナリン自己受容体に拮抗し、その結果ノルエピネフリンの放出を増加させるもの、(2)5-HT2A受容体に拮抗作用を及ぼすもの、(3)この両者に作用する拮抗薬がある。
(4-7)α2-アドレナリン自己受容体というものがあります。説明は難しいので、またこのつぎ。5-HT2A受容体とは、5-HTがセロトニンのこと、そのレセプターがいくつもあるのですが、その中のひとつです。
*SSRIs
Clinical trials have shown little difference in efficacy or tolerability among various available SSRIs. or between SSRIs and other classes of ntidepressants.
臨床試験において、現在利用できる様々なSSRIの間で、またはSSRIと他の抗うつ薬との間で、効果と不耐性にはほとんど差がなかった。
(4-8)efficacy or tolerabilityは薬剤の用語です。薬剤は少なすぎると効果がありません。多すぎると毒性が強くなります。使用量をだんだん増やすと効果が始まり、さらに増やすと毒性が現れるので、その間で、薬剤使用量を調整します。
However, some specific differences should be noted.
とはいえ、いくつかの点については留意すべきである。
The active metabolite of fluoxetine has a half life that is longer than that of other SSRIs, which permits once-daily dosing and thereby reduces the effect of missed doses and mitigates the SSRI discontinuation syndrome (described below).
Fluoxetineの活性代謝物の活性の半減期は他のSSRIに比べ長く、1日1回服用すればよい。それによって、服用を忘れた場合の影響も減り、SSRI断薬症候群(後述)も緩和される。
(4-10)a half life 半減期。薬剤服用後、血中濃度が最高になったあと、半分の濃度になるまでに要する時間。半減期が長ければ、つまり、作用が長いことになります。
However, fluoxetine should be used with caution in patients with bipolar disorder or a family history of bipolar disorder, because an active metabolite persists for weeks and may aggravate the manic state in the event of a switch from depression to mania.
翻訳 しかし、fluoxietineの使用は双極性障害(躁うつ病)患者、また患者の家族に双極性障害の病歴がある場合には注意を要する。なぜなら、活性代謝物の効果は数週間持続するため、患者がうつ状態から躁状態へと移行した際、更に躁状態が悪化する可能性があるためである。
(4-11)細かいけれど、分かりやすくした。
At higher doses, paroxetine and sertraline also block dopamine reuptake, which may contribute to their antidepressant action.
翻訳 paroxetineとsertralineも服用量が多ければドーパミンの再取り込みを阻害する。(本来うつ病はセロトニン系との関係が想定されるものの)ドーパミン再取り込み阻害が抗うつ作用を強めている可能性がある。
SSRIs can be helpful in patients who do not have a response to tricyclic antidepressants, an older class of drugs, and appear to be better tolerated with lower rates of discontinuation and fewer cardiovascular effects.
翻訳 SSRIは、古い世代の抗うつ薬である三環系抗うつ薬を服用しても効果がない患者に役立つだろう。また、毒性が少なく、断薬症状は多くなく、心血管系への影響もほとんどないと思われる。
(4-13)要するにどういう意味なのかを日本語にしましょう。
Although tricyclic antidepressants may have greater efficacy than SSRIs in severe major depressive disorder or depression with melancholic features, they are Iess effective than SSRIs for bipolar depression, since they can trigger mania or hypomania.
翻訳 重篤な大うつ病、あるいはメランコリー親和型のうつ病患者には三環系抗うつ薬の方が、SSRIよりも優れた効果を発揮することがある。しかし、双極性障害(躁うつ病)患者にとっては、三環系抗うつ薬は躁状態・軽躁状態発症のきっかけになる恐れがあるので、SSRIを選択したほうがよいだろう。
(4-14)躁転と言います。
The SSRI fluoxetine is the only antidepressant that has consistently been shown to be effective in children and adolescents, and SSRIs may be superior to selective norepinephrine-reuptake inhibitors in young adults (18 to 24 years of age), although they are more likely to trigger mania in children.
幼児期~思春期の子どもに確実な効果を発揮するSSRIは、flioxcetine のみである。青年期(18~24歳)の患者には、選択的ノルエピネフリン再取り込み阻害薬の採用がより望ましいようであるが、躁状態を誘発する傾向も強いようである。
(4-15)日本ではまだ使えません。
*NOREPINEPHRINE-REUPTAKEINHIBITORS
Nortriptyline, maprotiline, and desipramine are tricyclic norepinephrine-reuptake inhibitors with anticholinergic effects.
翻訳 *ノルエピネフリン再取り込み阻害薬Nortriptyline、maprotiline、desipramineは、三環系のノルエピネフリン再取り込み阻害薬であるが、抗コリン作用がある。
(4-16)抗コリン作用とは。神経伝達物質であるアセチルコリンの作用を遮断する薬が原因で起こります。アセチルコリンは、心臓や気道などの細胞運動を刺激します。一般的に使われている多くの薬に抗コリン作用があります。抗コリン作用としてはたとえば、眼がかすむ、便秘、口の渇き、ふらつき、排尿困難、などがあります。一方で、たとえばふるえの軽減や吐き気の軽減など、有用な作用もあります。
Reboxetine is a selective norepinephrine-reuptake inhibitor with an effectiveness similar to that of tricyclic antidepressants and SSRIs, though it is unavailable in the United States.
Reboxetineは、選択的ノルエピネフリン再取り込み阻害薬であり、三環系抗うつ薬とSSRIに類似した効果を持つ。しかし、米国では認可されていない。
(4-17)日本でもまだ。
*DUAL-ACTION ANTIDEPRESSANTS
Serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors such as venlaflixine, duloxetine, and milnacipran block monoamine transporters more selectively than tricyclic antidepressants and without the cardiacconduction effects that can occur with triicyclic agents.
翻訳 *二方面の作用をもつ抗うつ薬
venlaflixine, duloxetine, and milnacipranといったセロトニン・ノルエピネフリン再取り込み阻害薬は、モノアミン輸送体を三環系抗うつ薬よりも選択的に阻害し、三環系抗うつ薬で発生する心臓伝導への悪影響もない。
(4-18)dual-action は流行です。しかし、批判もあります。原因がひとつなら、その部分だけを訂正すればよいはずです。本質的な原因療法ならば、dualでなくてもよいはず。原因が分からず、しかも、dual action の方が効果的だとの結果なので、現在での薬剤選択はdualになります。
Some tricyclics (imipramine and amitriptyline) inhibit both serotonin and norepinephrine reuptake.
三環系抗うつの薬の中には、imipramineとamitriptylineのように、セロトニンとノルエピネフリン両方の再取り込みを阻害するものがある。
The dual-action antidepressant venlafacine appears to demonstrate superior efficacy and higher rates of remission in severe depression as compared with either SSRIs such as fluoxetine or tricyclic antidepressants.
翻訳 二方面の作用を持つ抗うつ薬、venlafacineは、fluoxetine などのSSRIまたは三環系抗うつ薬と比較してより優れた効果を示し、重篤なうつ病の寛解率も高い。
(4-20)dual の開発競争になります。
The efficacy of duloxetine is similar to that of the SSRI paroxetine.
duloxetineの効果は、SSRIのparoxetineと同等である。
Venlafaxine and duloxetine are effective for the treatment of chronic pain and diabetic neuropathicpain, respectively,as well as pain occurring as part of primary or secondary depression.
Venlafaxineとduloxetineは、一次性・二次性うつ病による痛みと同様に、慢性疼痛や糖尿病による神経因性疼痛の治療にもそれぞれ効果がある。
(4-22)抗うつ剤は慢性疼痛に使われることがあります。
Bupropion, which inhibits both norepinephrine and dopamine reuptake, has no direct action on the serotonin system and is generally similar in efficacy to tricyclic antidepressants and SSRIs.
翻訳 Bupropionは、ノルエピネフリンとドーパミンの再取り込みを阻害するが、セロトニン系には直接作用せず、おおむね三環系抗うつ薬やSSRIと同様の効果がある。
(4-23)いろいろなうつがあるということになるのか。あるいは、ノルエピネフリン、ドーパミン、セロトニン系はそれぞれ独立ではないので、こういうことになるのか。
Bupropion is associated with less nausea, diarrhea, somnolence, and sexual dysfunction than are SSRIs and constitutes an effective alternative, or adjunctive therapy, for patients who do not have a response to SSRIs.
翻訳 Bupropionは吐き気・下痢・眠気・性的機能障害の発生がSSRIより少なく、SSRIでは症状の改善しなかった患者にとって、薬物治療の主剤ともなり、また補助薬剤ともなる。
(4-24)つまりはこういう意味だろうと思う。
アメリカで使用されている抗うつ剤の特性と副作用一覧
表のpdfファイルは下記。コピーしてアドレスに入れて、ジャンプして下さい。
http://www.geocities.jp/ssn837555/table1.pdf
現在日本で使用可能なものだけでもかなりなんとかなります。
Figure 1 と解説
Figure 1 Targets of Antidepressant Action on Noradrenergic and Serotonergic Neurons
翻訳 図1:ノルアドレナリン系神経細胞とセロトニン系神経細胞において抗うつ剤はどこに作用しているか
In Panel A, targets of action for antidepressants in the noradrenergic system can enhance activity by blockade of α2 adrenergic autoreceptor, blockade of norepinephrine(NE) reuptake at the synaptic cleft, simulation of α2-adregergic and β2-adrenergic postsynaptic receptors, activation of signal transduction and second messenger pathways, and blockade of monoamine oxidase (MAO), the enzyme involved in NE breakdown.
翻訳 パネルAでは、抗うつ薬のノルアドレナリン系システムにおける作用を説明している。α2アドレナリン自己受容体の働きを抑制する。シナプス間隙におけるノルエピネフリン(NE)の再取り込みを抑制する。α1アドレナリンおよびβ1アドレナリン後シナプス受容体の刺激物質として作用する。神経信号伝達と二次伝達物質経路を活性化する。ノルエピネフリンの分解に関係するモノアミン酸化酵素(MAO)を阻害する。(結果としてシナプス間隙でのノルアドレナリンを増やし、それ以降の神経信号伝達を促進する。)
(f1-1)ぶつ切りにしました。図の各部分を説明しています。
In Panel B, targets of action for antidepressants in the sertonergic system can enhance activity by blockade 5-HT2A,5-HT2B1, and 5-HT2D autoreceptors; blockade of serotonin reuptake at the synaptic cleft; activation 5-HT1A postsynaptic receptor; activation of signal transduction and second-messenger pathways ;and blockade of the 5-HT2A postsynaptic receptor.Monoamine oxides inhibitors (MAOI) function by blockade of MAO, the enzyme involved in serotonin breakdown.
翻訳 パネルBでは,抗うつ薬のセロトニン系システムにおける作用を説明している。5-HT2A,5-HT2B1および5-HT2D自己受容体の活性を阻害する。シナプス間隙におけるセロトニンの再取り込みを阻害する。また、5-HT1A後シナプス受容体を活性化する。神経信号伝達と二次伝達物質経路を活性化する。そして5-HT2A後シナプス受容体を阻害する。モノアミン酸化酵素阻害薬(MAOI)は、セロトニンの分解に関与する酵素であるMAOの働きを阻害する。(結果として、シナプス間隙におけるセロトニンを増やし、それ以降の神経信号伝達を促進する。)
(f1-2)セロトニン(5-HT)に関係するレセプターがたくさんあるということです。
MAOls
MAOIs
Older, irreversible MAOIs nonselectively block MAO A and B isoenzymes and have an antidepressant efficacy similar to that of tricyclic antidepressants.
翻訳 古い世代の不可逆的MAOI(モノアミン酸化酵素阻害薬)は、モノアミンA,Bを非選択的に阻害し、三環系抗うつ薬と同等の抗うつ効果がある。
(5-1)MAOIは日本では使いません。
However, MAOIs are not first-line drugs because
patients who receive them must adhere to a low-
tyramine diet to prevent hypertensive crisis
and because MAOIs carry greater drug-interaction risks than do other medications.
翻訳 しかし、MAOIは第一選択薬にはならない。というのも、患者は服用に際して低チラミン食を必ず摂取して高血圧発作を予防しなければならないからだ。また、MAOIは薬物間相互作用リスクが他の薬に比べて著しく高いからである。
(5-2)チラミンが高血圧誘発物質となります。チーズ、ワイン、ビール、大量のコーヒー、カジキ、ニシン、タラコ、スジコ、そら豆、鶏レバー、イチジクなどに含まれます。
MAOIs appear to be superior to tricyclic agents for people with depression characterized by extreme fatigue or extreme psychological sensitivity to rejection or failed relationships.
翻訳 MAOIが三環系抗うつ薬よりも優れた効果を発揮するのは、うつ病のなかでもだるさが強いもの、あるいは患者が心理的に過敏で拒薬する、または治療関係が築けない場合である。
(5-3)→rejection or failed relationships はこんな感じかなと思うが、どうかな?
MAOIs are also useful for treating patients who do not have a response to tricyclic antidepressants.
翻訳 また、MAOIは三環系抗うつ薬に反応を示さなかった患者にも有用である。
(5-4)うつ病治療におけるresponse 反応 とは、治療によって症状が少なくとも50%改善したものをいう。ハミルトンうつ病評価尺度などで評定する。臨床的全般改善度でいえば、著明にまたは明らかに改善した場合に相当する。
The reversible selective MAO A inhibitor moclobemide (which is not available in the United States but widely available in other countries) and the MAO B-selective inhibitor, selegiline, have a greater safety margin than do SSRIs but similar efficacy.
翻訳 可逆的かつ選択性MAO A阻害薬(モノアミン酸化酵素A阻害薬)であるmoclobemide(米国を除き各国で広く使用されている)、ならびにMAO B阻害薬(モノアミン酸化酵素B選択的阻害薬)であるselegilineは、SSRIに比べ効果は同様で、安全域が広い。
(5-5)SSRIよりもいいような書き方をしていますが、そんなことはないと思います。
A selegiline transmedical patch is under consideration by the Food and Drug Administration (FDA).
FDA(米国食品医薬品局)は、selegilineの経皮貼付剤について検討中である。
(5-6)皮膚貼付剤(パッチ)は、ニチコンパッチと女性ホルモンパッチをよく使います。
OTHER ANTIDEPRESSANTS AND NEW THERAPIES
その他の抗うつ剤および新治療法
Mirtazapine enhances the release of norepinephrine by blocking a2-adrenergic autorecepters as well as serotonin 5-HT2A and5-HT3 receptors and histarnine H1receptors.
Mirtazapineはノルエピネフリンの放出を促進させる。Mirtazapineがα2アドレナリン自己受容体、セロトニン5-HT2A、5-HT3受容体、ヒスタミンH1受容体を阻害することによる。
(5-7)as well as ですね。
Its efficacy is similar to the that of tricyclic antidepressants and SSRIs,and it is less likely to have sexual and sleep-related side effects.
翻訳 その効果は三環系抗うつ薬およびSSRIと同等、性的機能障害や眠気といった副作用も少ないようである。
(5-8)だいぶ宣伝していますね。
Nefazodone, which blocks the 5-HT2A serotonin receptor and serotonin reuptake, has an anti-depressant efficacy similar to that of SSRIs but with a lower likelihood of sexual-dysfunction and sleep-related side effects.
翻訳 Nefazodoneは5-HT2Aセロトニン受容体を阻害し、セロトニンの再取り込みを妨げ、SSRIと同様の効果を持ち、性的機能障害や眠気などの副作用も少ないものと思われる。
(5-9)新薬は性機能障害にターゲットがシフトしているのが読みとれると思います。
Nefazodone appears to be useful in postparrum depression, severe depression, and treatment-resistant major depression with anxiety.
翻訳 Nefazodoneは産後抑うつ症、重症うつ病、さらには不安を伴う治療抵抗性の大うつ病に有益と見られている。
(5-10)産後抑うつ症や重症うつ病では、妄想に近い、強い思いこみに対処する必要があります。そのあたりに効きそうです。
New antidepressive treatments currently being evaluated include vagal-nerve stimulation, rapid transcranial magnetic stimulation, mifepristone
(a glucocorticoid antagonist for treatment of delusional depression), and substance P antagonists.
翻訳 現在、新しいうつ病治療については、迷走神経への刺激療法、経頭蓋骨磁気刺激療法、mifepristone(グルココルチコイド拮抗薬:妄想を伴ううつ病の治療薬)そしてサブスタンス拮抗薬などが研究されている。
(5-11)Agonist あるレセプターに対して、本来くっつく物質と同じ効果を発揮する物質。Antagonist あるレセプターに対して、本来くっつく物質のかわりにレセプターを占拠して、物質のその情報伝達作用をなくしてしまう物質。
Other targets for future agents include neuropeptide Y, vasopressin V1b, N-methyl-D-aspartate, nicotinic cholinergic, delta-opiate, cannabinoid, dopamine Dl, cytokine, and corticotropinreleasing factor 1 receptors, as well as GABA, intracellular messenger systems, and transcription, neuroprotective, and neurogenic factors.
その他、未来の抗うつ薬として標的になっているのは神経ペプチドY、(下葉体後葉ホルモンである)バソプレッシンV1b、NメチルDアスパラギン酸、ニコチン様コリン作動性デルターオピエイト、カンナビノイド、ドーパミンD1、サイトカイン、副腎皮質ホルモン放出因子1受容体、GAVA(γ-アミノ酪酸)、細胞内伝達システム、転写因子、神経保護因子、神経原性因子などがある。
(5-12)→最後、,and--,andの連なりからは、a,b,c,as well as d,e,and (f,g,and h)といった構造と見える。a,b,c,d,e,そして (f,g,and h)。という意味だろう。
いろいろ調べているが、今のところ、空振りというわけです。
AUGMENTING AND ADJUNCTIVE MEDICATIONS
附活薬剤および補助薬療法
Various medications used in conjunction with other-antidepressants may help to augment the effect of antidepressants (Table 2).
様々な治療薬を他の抗うつ薬と併用すれば、抗うつ薬の効果を高める可能性がある。(表2)
They can also target different components of patients' symptoms (such as delusions) or help to prevent a switch in to mania.
併用する薬剤は患者により異なる症状(例えば妄想など)を治療の標的としたり、躁状態への転換を回避できる。
治療のために有効なお勉強
Tellenbachは常識としても、
Janzarikやその他を知って、理解して、自分のものとして使って、
果たして、治療効果に差が出るものか。
難しい言葉を使わなくても、
あっけなく、同じ結論を導く人はいる。
あるいは、精神分析的概念にもいろいろあって、
ラカンとか、そのようなものを知って理解している医者と、
そうでない医者で、治療効果として有意差が出るものか。
この点についての、統計的検定は難しい。
他は全部同じだけれど、ラカンを知っていると知らないだけが違うという二群の医者を、
用意することはできないだろう。
いくつもの要素を検定対象にすれば、
ラカンを理解している・いないよりも重要な要素が抽出され、
そちらの議論に、ラカンもJanzarikもかすんでしまうだろう。
副次的な要素に過ぎなくなるだろう。
しかしまた、すべては治療の有効性のためにと考えるのも狭い了見と言うもので、
知的好奇心のために探求することも、長い目でみれば意味がある。
いろんな学者を、精神病理学的な目で眺めるという、次元の違う見方も、
つまらないわけではない。
エコーがあれば、厳密な聴診技術は必要ないのかもしれないし、
適応範囲が広いSSRIがあれば、厳密な鑑別診断は必要ないのかもしれない。
一番強い抗生剤をつかっておけば、鑑別診断ができなくても、
とりあえずは、切り抜けられる。
診断に手間取っている暇に、患者さんを説得して、
薬を飲んでもらった方が早いのかも知れない。
しかし考えてみてほしい。
そうしたことの結果として、どこかの良心的なお医者さんが、
重症例を引き受けているのだということを。
*****
精神科病棟で、哲学的な精神病理学的文章を書いている人がいた。
ノートにぎっしり。
よく分からなかったが、ハイデガー、フッサール、木村敏などを書き写しているのかなと思った。
精神の現象学とかそんな感じ。
あとで聞いたら、その人が自分で書いたというものだった。
どれもよく分からないということが私には分かっただけだった。
ジプレキサで糖尿病
危険な場合には変薬、というのが推奨されている。
しかし、糖尿病の専門家の中には、統合失調症や躁うつ病で、
必要な場合には使ってください、血糖のコントロールは私に任せてくださいという、
頼もしい人もいるのである。
そのくらいのコントロールができなくて専門家とはいえないといった感じで、
とても頼もしい。
とはいえ、その人が自信があると言っても、何が起こるかわからないから、やはり怖い。
ジプレキサやセロクエルでなくても、何とかなる場合が多いのだから、
それでいいじゃないかと思ってしまう。
しかし、糖尿病の専門医の中には、そのような頼もしい先生もいるのだということで、
いいことだと思うし、そのような意見もあるのだと、
どうしても必要なときのために、頭の隅にとどめておいていいのではないかと思う。
(やっぱり、実際は、必要ないと思うけど。リスパダールでも、セレネースでもいいだろうな。)
シンバスタチン 不眠 プラバスタチン
先日、日本の薬剤売り上げランキングを見た。コレステロール関係は、リピトールがトップだ。全体では、武田のタケプロンがトップで、次がノルバスク、おおむね、高血圧の薬とコレステロールの薬が多い。これって本当にこれだけ必要なんだろうかなと思いつつ、久光の貼り薬がかなり上位に食い込んでいるのをみて、さすがに技術の高さが評価されていると思った。ジェネリックメーカーは、久光に及ばない。正味の薬効はまねできても、「貼り心地」が出せない。セロクエルは振るわないのに、ジプレキサはいい順位を確保していたりして、類似薬でこれだけ差が出ているのもおもしろく、興味は尽きない。